『コミュニケーション』カテゴリの記事
脳が求める情報の"心地よさ"って?

当社では、
特徴の1つは、社内広報を人のマインドの解決課題だと捉えて、
認知心理学的な要素を取り入れている点です。
たとえば、人はなぜコンテンツを見たくなるのでしょうか。
興味を惹きつける要素にはさまざまなタイプのものがありますが、
今日ご紹介したいのは、「感情報酬」という概念です。
新しい情報を見つけた瞬間、
その中心にいるのが、ドーパミン。
これは「快感」や「期待感」を司る神経伝達物質です。
たとえば、SNSのタイムラインをスクロールしているとき。
「お、これは知らない」「なんだろう?」
好奇心が働いた瞬間に脳が喜び、ドーパミンが分泌されて、
脳は「報酬」を受け取ったように感じます。
あなたがもし、
脳と神経伝達物質の働きを知ることで、
読者のどんな「期待のスイッチ」を押すのか、
ところで、SNSで自分の好奇心に従って、
タイムラインに似たようなネタばかり流れてくるようになった...
というご経験もあるのではないでしょうか?
私の例でいえば、最近は選挙が近いこともあって、
さまざまな候補者からの発信を見るうちに、
私のタイムラインはあっというまに政治のつぶやきが多くなってし
与党・野党、候補者・有権者に関わらず、
すると自分の信条に合っている声を目にした時は、
そうだ、そうだと思い、心地いい。
一応、私の場合はどんな対立構造になっているか興味があるので、
自分の信条と違う声も読んでいるため、
もし「心地良い」を基準に読む読まないを判断していたなら、
一気に「エコーチェンバー」の中に置かれることになります。
「エコーチェンバー」というのは、
自分と似た意見の人ばかりが集まって、
これもまた、脳にとっては心地よい状態なのです。
同じ考えに触れると、
安心感や一体感を感じるそうです。
つまり、意見の一致は脳に安心をもたらします。
でも、その「安心」が続くと、
私たちはいつの間にか「違う意見」
心地よさと引き換えに、視野が狭まっていく...。
そんなことが起きそうです。
しかも、脳は基本的に「自分が信じたい情報」
ドーパミンがくれる「ワクワク」やセロトニンがくれる「安心」
私たちはつい「自分の考えを裏付ける情報」
コンテンツの作り手としても、個人としても、
この「心地よさ」
ときには、あえて意外性のある視点を選ぶ。
ほんの少しだけ脳のクセを意識して、
そうすることで、情報との付き合い方が広くなる気がします。
「心地よい刺激」と「少しの違和感」
今週末は、選挙です。
有権者の1票が私たちの未来につながっていると信じ、
信用って何だろう?

衆議院が解散され、選挙戦が活発になっています。
選挙で重要とされているのは、マニフェストです。
日本の大きな方向転換が示された上での今回の選挙ですから、
有権者としてマニフェストをよく理解して選挙に臨みたいものです
そうだ! 選挙に行こう! ← JR東海風の美しいビジュアルで笑
さて、マニフェストは平たく言えば「約束」です。
ビジネスでも約束が大事なのは言うまでもありません。
社内での約束、社外との約束がいろいろある中で、
皆さんはどんな約束がもっとも基本的かつ重要度が高いと思います
やると言ったらやる...
しかし、大昔からそれ以上に大切にされてきたのは、
・決まった期日に、決まった金額を支払う
・約束した日までに、約束通りのものを納める
の2点ではないでしょうか。
この約束を守らない相手とは、2度と取引しない、
それが当然のこととして、
「信用とは、約束を守る習慣である。」と言ったのは、
「信用」の捉え方は国や地域によって異なります。
日本では、どちらかというと、最初は性善説で信用し、
一度壊れた信用は簡単に修復できないという暗黙の了解があります
しかも、相手を信用するのは必ずしも「契約書があるから」
そこが、良くも悪くも日本社会の特徴です。
「あの人は裏切らない(誠実)」と「あの人ならやってくれる(
の掛け合わせで信用をとらえていて、
信用できる人が大勢いる会社が、
信用できる企業になっているとも考えられます。
私たちは、あまり自覚していませんが、
「約束」や「信用」に対し、なぜ、
一説には、時間に対する価値観は、
田植えや水の管理は、
周囲に歩調を合わせなければ、当然、後ろ指を刺されますよね。
空気を読むことにも通じる恥の文化と関係があるのかもしれません
でも、
そこは異なっているのではないでしょうか。
私は、日本人の「信用」に対する価値観は
「お天道様が見ている」
このワードは、年初のメルマガ「おみくじ、引きましたか?」
日本人のアイデンティティの根っこにあるものの一つではないかと
これは、誰に見られていなくても、
「自律的な道徳観」です。
なんと素晴らしいじゃありませんか!
「お天道様が見ている」の起源がどこにあるかというと、
『古事記』や『日本書紀』に登場する天照大神(
というのが有力な説です。
日本では、古くから太陽を神と捉え、太陽=
「すべてを照らす存在」イコール「人の行いを見通す神」
2024年のNHK大河ドラマ『光る君へ』の中で、
疫病が起きると祈祷で解決しようとするシーンがありましたが、
平安時代の祈祷での中心神格は天照大神だったそうです。
だとすると、当時の人々にとって、
しかし、私たちの日常生活に目を向けると...?
現代では、日常の中で天照大神を意識したり、
「お天道様」という言葉を口にする機会は滅多にありません。
若い人たちの間では、この言葉は最早死語かもしれない。
それでも、その精神は社会的な良心として、
ゴミのポイ捨ては少なく、
日本社会の特徴です。
あ、今、思い出しました。
「Don't Be Evil(邪悪になるな)」はGoogleの有名な価値観です。
この思想は、まさに「デジタル時代のお天道様」
AIの時代になり、多様性との共生が叫ばれる中で、
個人にとっても、企業にとっても、
「信用」はますます重要になっていくような気がするのですが、
皆さんはどう思いますか?
1月最終週です。寒さに負けずに元気に参りましょう!
言いにくいことを伝える

Xを見ていたら、タイムラインに中野信子さんの著書「
広告らしきものが流れて来て、
私は、別に「毒の吐き方」には興味はありませんでしたが、
「脳科学と京都人に学ぶ『言いにくいことを賢く伝える』技術」
「エレガントに伝える」「京都人」に興味を持ち、
いえ、読んだのは本書ではなく、記事の方です。
発売は、2023年5月なので、
読者はどこに惹かれて読むのだろう?
もし「毒の吐き方」だとしたら、いやな世の中ですね。
でも、「言いにくいことを伝える」は、
私にも、月に何度かは言いにくいことを伝えるシーンがあります。
プライベートと仕事の両方を合わせてです。
そこで、今回は、人はなぜ「言いにくいことを伝える」
どうしたら少しでも悩まなくて済むのか、
我が身を振り返りながら考えてみたいと思います。
人が「言いにくいことを伝える」には、
大別すると、次の2つではないでしょうか。
第一は、そもそも思っていることを伝えるべきなのかどうか。
第二は、伝えた方が良いと思っても、
でも、自分が当事者で悩んでいるときは、
ちなみに私自身は、伝えるべきかどうかについては、
大抵は野生的本能で「伝えるべき」「伝える必要はない」
でも、伝えるべき理由については、結構考えます。
さて、まず葛藤の第一。
思っていることを伝えるべきかどうかで、
原因はいろいろ考えられます。
【結果が不安】それを言って、相手が分かってくれるかどうか、
→理解されないと、相手の気分を害するだけで、
【目的が不安】こんなことを思う自分は、
→伝える目的はエゴなのか、関係維持のためなのか、何なのか、
【感情と理性の線引き(目的の揺れ)】
→
感情が混じってしまい、考えが整理できない。
ほかにもあるかもしれません。
ここでは私の経験から自分の心理を分析して整理してみましたが、
実際に何かに直面したときに、
どうでしょう? 案外難しいような気がします。
第二に、伝えた方が良いと思ってもどう伝えたらいいかで、
これについて、私は、
が、それを含め、次の2つに注目したいと思います。
1つは、【目的の不明瞭さ】からくるものです。
そりゃそうですよね、何のために伝えるのかによって、
伝えるときのスタンスが変わり、
そもそもなぜ自分は伝えたいのかで揺れているにも関わらず、
どう伝えようと考え出すから、分からなくなるのは当然です。
もう1つの原因は、仮に目的が明瞭だったとしても、
【伝えるスタンス】が定まらないと、
仮にですよ、
コテンパンにやり込めたいというスタンスでいくのか、
分かってくれれば良いというスタンスでいくのかによって、
伝え方は大きく変わります。
一刀両断には言えませんが、多くの場合、
どう伝えたら良いか、悩むのだと思います。
さて、私自身は「言いにくいことを伝える」
伝えるというのは、とても面倒で、エネルギーのいる行為です。
ということは、関係を維持したり、向上させたり、
何らかの共通目的を達成したりするというような、
そこにエネルギーを使うことは人生の無駄遣いに思えます。
どうでもいいことのために、
もっといえば、どうでもいいことであるなら、
反対に、目的を関係の維持・向上だと思ったら、
相手をやり込める必要はないと分かります。
思いを伝え合うときに私が大切にしたいのは、
まず自分の発言に責任を持つことです。
そのためには、自分の感じたことを感じたこととしていうこと。
感じたことは私の主観であって、客観的事実ではないのですから、
「あなたはこうだ」とあたかも事実であるような評価・
自分の発言が主観であることを表現するには、
あなたのここが良くないではなく、自分はこう感じたよ、と。
そのスタンスを持つことで、
すると、自分の気持ちもラクになります。
そして、相手も人間ですから、自覚していることもあれば、
たまたまその日の気分で起きてしまったこともある。
感じた私の心だって、日々揺れているはずです。
そして、お互いを尊重する気持ちが根底にあれば、
言いにくいことを言ったあとも、お互いに「
「そういうこともあるよね」と受け入れられる気がします。
便利なことわざ「物は考えよう」

当社では、現在採用活動を行っています。
そのことで、先日、
自己客観視ができて素直であることは、
重視していることのひとつだと答えたところ、
「自己客観視か...。私は自己肯定感が高すぎて、全然ダメ」。
要するに自分のことを否定的に見ることができない、
ということのようです。
本来、自己肯定感と自己客観視は両立するものだと思いますが、
この友人は、
と捉えているようでした。
ところで、最近は自己啓発系のコンテンツの影響からか、
「自己肯定感が高い/低い」とか
「承認欲求が強い/弱い」など、
自己認識して言語化するような風潮が強まっているように感じます
自己肯定感で言えば、
まあ、もちろん、そうなのでしょうが、
あまり、それに振り回されるのはよくないとも思います。
というのは、自己開発のための知識を増やした結果が、
必ずしも良いものになるとは限らないからです。
言葉にはプラスのパワーもあれば、
マイナスのパワーもあるため、
たとえば、「自己肯定感が低い」と自認してしまうと場合、
その言葉に縛られて自己像が作られがちです。
そんな必要はないのに、
ですので、
少々の違和感があります。
ネガティブな自己認識はそんなに悪いことでしょうか。
たとえば、「自分はダメな人間だな」と思ったとして、
そんな自分をどう捉えるかは考えようです。
ある一面から見たら、謙虚さの現れだし、
また別の一面から見たら、
こうありたいと願うのは、まさに美意識そのものですから。
どんなものにも表と裏の二面性があります。
そのどちらに目を向けるのかは、自分で決定できます。
物は考えよう。
なんと便利なことわざではありませんか!
いつにも増して暑い夏です。
熱中症に気をつけて、健やかにお過ごしください。
出会いたい人と出会うために
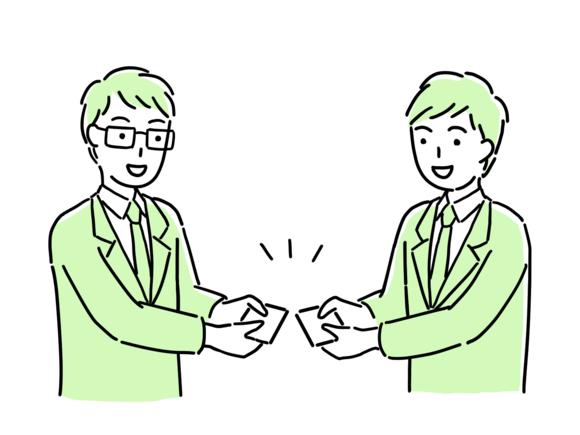
何をするかよりも、誰とするかだ...という表現、
一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
けれど組織では、仕事は上からのアサインありきだから、
誰とするかなど、自分の意思で決まるものではない。
そう思っている方も多いのではないでしょうか。
一方で、やりたいことを見つけてそれに打ち込む人生が良い...
多少弱まってきた気がしますが、
そして、そのような考え方は、「やりたいことが見つからない」と
思っている人たちに、
私自身がどうかというと、「人生は波乗り」
「やりたいことをやる」は、それはまあ幸せかもしれないけれど、
一度コレと決めたら変えられないような呪縛になりそうだ、と。
なぜなら、人間のやりたいことなんて、どんどん変わるからです。
だから、やりたいことが何かを見定めて、
実は強そうでいて、案外脆いのではないかと思ったりします。
人生は波乗りで良いと思う私が何を得たいと思ってきたかというと
1.やりたくないことをしない。
2.出会いたい人と出会えるようにする。
3.物事をより良くすることを楽しみたい。
ざっとこんな感じです。
やりたいことありきで人生を考えるというよりも、
この3つが満たされたら、十分幸せだという考え方です。
(もちろん、やりたいこともやっていますが、
仕事では、「インターナル・コミュニケーション」という領域で
専門サービスの提供に努めていますが、
私の中では、
そして、出会いたい人はどんな人かというと、
物事をより良くしたいと思っている面白い人たちです。
やりたくないことが何かというと、
物事をより良くしようと思っていない人と仕事をすることです。
さて、上の3項目の中で、一番難しいのが、
2番の「出会いたい人と出会えるようにする」かもしれません。
仕事に置き換えると、「何をするかではなく、誰と働くか」。
では、どうしたら出会いたい人と出会えるのでしょうか。
「出会えるようにする」などということが、
私は、ブランディングという考え方に立ち、実践すれば、
個人であっても実現可能なことだと思っています。
たとえば私自身を例に挙げると、
出会いたい方たちからご連絡をいただく機会が増えたと思います。
では、パーソナルブランディングという観点から考えたときに、
どうすると出会いたい人、
私は、そのコツは、第一に「意思表示」
たとえば...
・私は、こういうことを大切にしている人間です。
・私は、こういうことに関心のある人間です。
・私は、こういう人と仕事をしたい人間です。
ただの自己紹介ではなく、自分の意思を示すこと。
それを、十人に話すと、一人ぐらいが覚えてくれて、
求めることに近い話をもたらしてくれる可能性が高まります。
別に、そのように計算して生きてきたわけではありませんが、
意思表示には力があるなと感じています。
パーソナルブランディングなどと難しいことを言わずとも、
自分という人間について、相手にどう覚えてもらうか。
それによって、出会いが広がり、人生が広がるのだろうな...。
信じる者は救われますよ笑
答えは相手の中にある

皆さんは、「コンサルタント」
どのようなイメージがありますか?
調べてみると、
今どきは、結構人気のある職業だそうです。
また、ひと昔前はコンサルタントといえば、
イメージされませんでしたが、今の時代は違います。
キャリアコンサルタントもあればお掃除コンサルタントもあると、
多くの人が認識するようになりました。
さて、仕事のイメージは時代とともに変わるのが常ですが、
「コンサルタント」という仕事に対しては、
ネガティブなイメージを抱く人が多かった時期があったように思い
具体的にはこんなイメージです。
・内部のことを知りもしないのに、
・しかし、責任は取らない存在
・上から目線でモノを言う存在、
もし、こんなイメージを抱いたなら、そりゃ、
当社は、
初めてメニューに入れたのは、
サービス自体は1995年頃から行なっていましたが、
社員に「コンサルをサイトで謳う」「もっと力を入れる」
その頃でした。
しかし...
当時社員の反応はどうだったかというと、
若手からキャリア層まで賛同する空気がない。
では、その時の反応の本質は何だったのでしょうか?
おそらくクリエイティブ業務とコンサルティング業務は
全く別のことに見えたのだと思います。
今でも、多くの人にとって、
少なからずそのような感覚はあることでしょう。
しかし、たとえば、佐藤可士和さん。
彼は、アートディレクターでありながら、
クリエイティブ業務とコンサルティング業務は別の業務ではないの
ゴチャゴチャした状況をすっきりと整理し、
道筋をつけること。
これは、クリエイティブのディレクション業務そのものであり、
コンサル業務でもあるわけです。
だからこそ、彼は、「佐藤可士和の超整理術」を書き、
その本はベストセラーになっています。
片付けコンサルタントである近藤麻理恵さんもしかり。
価値観の整理から片付けに取り組むことを勧めるコンサルタントで
何を整理するのかはそれぞれが得意とする領域になりますが、
一方的な「べき論」を押し付けたりしていないはずです。
何をどう整理したいのか、その答えは本来相手が持っています。
ただ、いろいろな考えが邪魔をして、
私たちは、
それについても、基本は同じです。
その答えは相手が持っている。
答えを与えてしまうと、大抵の人はやらされ感になります。
あ、これはコンサル業務に限らず、
人は自分で考えたい生き物だってことなのかな?
さ、ゴールデンウィークが近づいてきました。
素敵な1週間をお過ごしください!
お節介にも三分の理
先週金曜日、11月29日に当社は創立40周年を迎えました。
メルマガを読んでくださっているみなさまには、
日頃のご愛顧に対し、心から感謝申し上げます。
営業職がいないのに、
唯一無二の理由があるわけではありませんが、
敢えて大きかった要因があるとするなら、
それは当社が少なからず「お節介体質」
お節介という言葉自体、最近、あまり耳にしなくなっていますね。
Z世代に通じるかしら?
頼まれてもいないのに、世話を焼くことです。
・でしゃばり
・余計なお世話
・口出し
こう聞くと、なんだか悪いイメージですよね。
・進言する
・参謀的な役割を果たす
・忠信である
こう聞くと、少しイメージが良くなったかもしれません。
でも、頼まれてもいないのにする、という意味は変わりません。
悪目立ちという言葉があるように、
頼まれていないことをするのは、でしゃばりであって、
あまり良くないと考える人は少なくない気がします。
十何年か前、若手の社員からこんなことを言われました。
ーーウチの会社ではお客様にとっての参謀という存在を目指せ。
そのためには意見を言えるようになれと言われるが、一方では、
お客様に寄り添えとも言われる。
同時に別のことを求められている気がする。
進言するのか、寄り添うのか、
もっと簡単にいうなら、進言するか、しないか、
この2択でご自分がどうありたいか、
進言や意見を述べることは、お客様との関係だけではなく、
上司部下間でも同僚間でも「する人」「しない人」に
分かれるのではないでしょうか。
私は、
「参謀のような価値」を提供できる会社にしたかったからです。
「参謀」という言葉と出会ったときには、「これだ!」
ただ役に立つ存在ではなく、頼れる参謀という存在になるには、
イエスマンもNGだし、我を通すために主張するのもNGで、
相手の立場を自分ごととして考え、
信念に従って率直かつフェアでいること。
これが、
40代の頃にこんな出来事がありました。
ある高級美容室チェーンを経営する会社の社長が、私に
「某雑誌からとても良い条件でタイアップのオファーがあった。
どう思う? いい話でしょ?」とおっしゃいました。
背中を押されたくて、出た話であることは十分に分かりましたが、
私は無料だったとしても止めた方がいいと反対意見を唱えました。
というのは、
その雑誌の読者層が高年齢層だったからです。
予想通りでしたが、当然その社長の気分を害すこととなりました。
論破するためにボコボコにされたと言っても過言ではありません。
(少々ワンマンな方だったこともあったかと思います)
しかし、それから数日後、社長直々にお電話をくださり、
「あの話は止めることにした」とおっしゃいました。
進言したことが正しかったのかは誰にもわかりません。
でも、信頼してくださったことは間違いありませんでした。
「お節介体質」
お節介にも三分の理。
そういえば、このメルマガ自体も少々お節介の傾向がありますね笑
お節介体質を受け入れて、読んでくださり、
いよいよ師走です。
2024年をいい形でフィニッシュできますように!
「ポジティブ VS ネガティブ」論
車のラジオを聴いていたら、ゲストにアンミカさんが出てきて、
彼女監修の「ポジティブ手帳2025」
ああ、もう手帳が話題の季節なんだな...
その手帳には、週次でポジティブワードが紹介されていたり、
心と体を元気にするハウツーが書いてあったりするらしいです。
手帳の内容自体は真っ当で良いものに思えました。
でも、一抹の違和感があって、何だろう?と考えてみたので、
シェアさせてください。
まず、ネーミング。「ポジティブ手帳」...。
Positiveは、積極的、前向き、
ポジティブな姿勢、ポジティブな考え方、
どう転んだって、良いことに違いありません。
しかし、私には、若干「煽り」
多分「ポジティブ」
社会では鬱などに悩まされている人が増え、
経済環境も良いとはいえないので生きにくい時代です。
夏目漱石ではありませんが、
だからこそ、この「ポジティブ」
そう、先導であって、扇動ではないのかもしれませんね。
でも、本当に心が豊かで健康的な状態というのは、
ポジティブであろうと努力することではないと思います。
たとえば、ネガティブ・ケイパビリティという言葉があります。
どうにも答えの出ない、どっちつかずの状況にあっても、
その不安定な状態、懐疑的な気持ちや違和感を抱えた状態に
留まって耐える力を意味します。
決してポジティブであろうと努力するのとは違います。
それは、
なので、ネガティブ感情から抜け出したいがために、
ポジティブであろうとすることは、
自分にとっては偽りの状態なので、健康的ではないと思うのです。
ネガティブな自分に気づいたら、それも素直に受け入れて留まる。
一番良くないのは、
というわでけ、ポジティブであろうなどと意識せずに、
普通に暮らしていて満ち足りているのが一番なのではないか、
その状態に呼び名はないのだろうか?...と思って調べてみたら、
「中庸」(ちゅうよう)と呼ぶらしいです。
この概念はギリシャ哲学や
中国の自然哲学「陰陽道」(おんみょうどう)から生まれ、
日本文化は後者から影響を受けています。
NHK大河ドラマ「光る君へ」に、ユースケ・
陰陽師・安倍晴明公が登場していました。
彼が礎にしていた思想が陰陽道です。
いったい「陰陽道」とは何でしょうか?
天地の間には、互いに対立し依存し合いながら、
万物を形成している陰・陽の2種類の気があるとされています。
積極的なものを陽、消極的なものを陰と呼びますが、
陰と陽には、善悪も優劣もありません。
「中庸」というのは、陰にも陽にも偏りすぎず、
何事においても過不足がなく、
勝手な解釈ですが、そうであるなら、
ちょっとしたポジティブは中庸にとって普通のこと。
そんな中庸の状態が私は健康的だと思います。
努力しなくても、
あ、でもポジティブ手帳を買うことで、
良い1年を送れそうな気がするならそれもアリですよね。
自分をコントロールできるのは自分だけですから。
いよいよ11月に入ってしまいました。
中庸な1カ月にしたいものですね(笑
脱「ついて型」のススメ

例えば、「~について取り上げよう」
あるいは、会議のアジェンダに書かれた「~について」の項目。
日常業務のいろいろなところで、
「~について」という言葉を使って会話がされています。
会議もコンテンツの一種であると考えた場合、
コンテンツの質はコンテンツを作る人のイニシアチブにかかってき
多くの物事で「~について」
本当にそれでいいのかな?とも思います。
というのは、1つの仮説として、この「ついて型」アプローチが、
アウトプットの質や生産性、
そこで、今日は、私が「ついて型」
その「ついて型」にはどんな問題があるのか、
問題があるなら、どうしたらいいのか、考えてみたいと思います。
実際、「~について取り上げよう」
コンテンツは作れますし、会議のアジェンダに「~について」
それなりに会議は成立してしまうものです。
それらのコンテンツでは何かしら言葉的なものが成果物になるので
「はい、これが本日のアウトプットです」
でも、
会議の成果に対し、参加者の納得感はあるでしょうか?
もう一度、たとえば「企画会議」。
当社が提供している企画力養成講座では、
ついて型でもコンテンツは作れるが、
とお伝えしています。
ーーーーーーーーー
~について取り上げよう
↓
だとしたら、誰に出てもらおうかな?
↓
どんなことを聞こうかな?
↓
聞いた話をうまく原稿にまとめなきゃ...
ーーーーーーーーー
確かに、この流れでもコンテンツらしきものは完成しますよね。
ですが、このアプローチはただ「聞いた話をまとめる」
「~について取り上げよう」から始まる企画プロセスでは、
大抵の場合、何をメッセージとするのか、とか、
読み終わった時に、
なので「~について取り上げよう」
「伝えたいこと→伝わること」に執着するなら、
気をつけないといけないなと思います。
会議のあり方もそうです。
日常的に行われる会議こそ、質や生産性、
でも、もしその会議のリーダーがアジェンダを考えるときに、
「1.○○について 2.○○について」というような感じで出していたとします。
そうしたら、
誰にもわかりませんよね。
もちろん、アジェンダと会議設計は別物ですから、
場のリーダーの頭の中に会議設計があるなら、
アジェンダ自体は「1.○○について 2.○○について」で済む場合もあります。
でも、私が一番おすすめしたいことは何かというと、
疑問文でアジェンダを組み立てることです。
(これは企画を立てる時もほぼ同じです)
ところが、
つまり、何を議論する必要があるのか、
場の作り手が「問い」
ですが、慣れていないと、
え? ほんと?と思うかもしれませんが、
考える必要のあることを漏れなく「問い」の形で出せる人は
実はそれほど多くないと思います。
私自身も「問いを立てる」を意識していますが、「漏れなく」
はなはだ心許ないです。
なので、「疑問文として書いてみる」
さて、今年もあっというまに6月。
終われば2024年も半分過ぎてしまいます。トホホ...
と、一瞬背中が丸まってしまいましたが、
その前に、今週を乗り切らないとですね!
「好意」の持つパワー

うちの会社では、
発表者が好きなテーマで30分程度説明し、
毎回、終了まで40~50分程度でしょうか。
たとえば、私が扱ってきたテーマの例を挙げてみますね。
・論点コンシャスになろう
・「Fast Worker」になるための秘訣
・今日は心理学、です!
・自分主導の説明と意思表示
・カテゴライズのすすめ
・自分ブランディング
オープン社内報など、
さて、昨日は、たまたま私の番で、今回は題して「意味付けの話」
ここでの「意味付け」
いろいろな事柄に対して、意義や価値、理由や教訓などの形で、
人が自分なりにしている「解釈」のことです。
たとえば、人が最も頻繁に行なっている意味付けは、
他人を評価判断することではないでしょうか。
あの人は、~だ。
あの人には、~なところがある。
あの人は、いつも~する。
自分の解釈で人を決めつけると、
人と人は、お互いに相手の人柄や性格、
その解釈があたかも本当の姿であるかのように決めつけをし合って
しかも、その評価判断はポジティブなことばかりではなく、
むしろネガティブなことの方が記憶に刷り込まれやすいと言えるか
ネガティブな評価判断をしてしまう顕著な例は、
誰にでも苦手な人の一人や二人はいるもの。
私はどちらかといえば、
たとえば、自分の話ばかり機関銃のような速さでする人、
しかも、声が大きく、感情の起伏が激しい相手は、
そのような人と話していると、30分を超えたあたりから、
気が遠のくような感じになって、まったく集中できなくなります。
実際に、一回り近く年上の方で、そのような人がいました。
前記の「自分の話ばかり機関銃のような速さでする」
事実と言っても良いと思いますが、
私はその人を「幼稚な人」「子どもっぽく、わがままな人」
こちらは明らかに私の解釈です。
前置きが長くなりましたが、実はここからが今日の本題です。
この人との間で、あるとき不思議なことが起きました。
人が人に抱く気持ちに「好意、好感」というポジティブな感情、
「反感、悪意、敵意」などのネガティブな感情、
さらに「普通、どちらとも言えない」という感情があるとすると、
この人の私に対する気持ちに「好意」
そうしたら、何とあれだけ苦手意識があったその人に対し、
この人の良いところを見つけようという気持ちが湧いてきました。
おそらく、「子どもっぽく、わがままな人」
心の中で被害に遭いたくないという深層心理が働いていたのですが
「好意」を感じ取ったことで、(敵対する相手ではないのだから)
寛大に捉えても大丈夫だと無意識ながらに思ったのだと思います。
ロバート・チャルディーニの著書「影響力の武器」の中で、
「好意の返報性」について書かれていますが、
職場での悩みとして、各種調査でしばしば「人間関係」
「あの人は~だ」は必ずしも事実ではなく、
見え方が変わるような気もします。
さらに必ず関係が変わるとは言えないまでも、「好意」
関係が変わる場合もあることは、
桜の便りが楽しみになってきました。
どうぞ良い週末をお過ごしください。





