「させていただく」の根っこにあるのは?

東京都知事選が終わりました。
感想はいろいろありますが、
今回は、過去最多の立候補者数だったこともあり、
出馬会見や政見放送、街頭演説動画など、
知事を目指す人たちの声を聞く機会がたくさんありました。
それらを通じて、
「立候補させていただく」に代表されるように、
「させていただく」という謙譲表現です。
もちろん尊敬語、謙譲語は難しいし、
私自身も含めて誰でも多少おかしな言葉を使っているので、
完璧であらねばならぬ...などと思ってはいません。
なのですが、「させていただく」という謙譲表現、
政治家の皆さんがやたらに多用するという印象、ありませんか?
そして、
では、なぜ「立候補させていただく」
早速、Google先生に「させていただく 謙譲語」で尋ねてみたところ、
マイナビさんのコンテンツから次のような説明がトップに上がって
ーー以下引用ーー
「させていただく」は「させてもらう」の謙譲語であり、
「相手からの許可」「恩恵を受ける」という意味が含まれます。
相手の許可を得ていない、得る必要がない、
使用しません。
ーーーーーーーー
なるほどと合点がいきました。
立候補は自分の意思で決めることであり、
「立候補させていただく」に違和感を感じたのだと思います。
では、「させていただく」の正しい使い方例には
どのようなものがあるのでしょうか?
以下の5例は、許可と恩恵という観点から正しいと言えそうです。
「〇日の〇時に訪問させていただきます」
「日程の変更をさせていただきます」
「この忘れ物は1カ月後に処分させていただきます」
「(イベント会場で)荷物の中身を点検させていただきます」
「ご提供いただいた写真を使わせていただきます」
しかし、実際に世の中では許可と恩恵とは無関係に
「させていただきます」が使われています。たとえば...
「資料は当日、配布させていただきます」
「(パートナー企業に)明日はお休みさせていただきます」
「報告書は予定通り明日提出させていただきます」
「写真を添付させていただきます」
「私が担当させていただきます」
いやー 使っていますよね。
これは多分、許可・恩恵以外に、意思表示を丁寧に伝える場合に、
「します」→「させてもらいます」→「させていただきます」
になっているのでしょうね。
だとしたら、言葉は生き物だし、
それはそれで別にいいんじゃないのという気にもなってきます(笑
話を戻して、政治家のスピーチの違和感の本質。
許可・恩恵でないことで使われているという以外に、
実はもう一つあって、それは「多用されすぎ」
多用されるがあまり、大臣が「指示させていただいた」
「お示しさせていただきます」と言ったりするのも、
「させていただきます」を多用している人にとっては、
「丁寧に、謙虚に...」という気持ちからなのかもしれませんが、
少し皮肉な見方をすると(すみません、天邪鬼で)、
「丁寧な言葉を使っておく方が、突っ込まれないだろう」とか、
「へりくだっておけば、人は信用してくれるだろう」などと
思っているようにも見えます。
何となく受ける印象として、言葉は上辺だけのもので、
実際には尊大であったり不誠実なのではないか?とか
防衛的な面が現れているだけなのではないか?
「検討させていただく」がその典型ですよね。
そう言ったなら、
「させていただく」という表現を、
「させていただく症候群」というのだそうです。
夏休みシーズンを迎えます。
「お休みさせていただく」ではなく、
「休みます」と言うのが普通なことになってほしいですね。
常識という「刷り込み」のコワさ
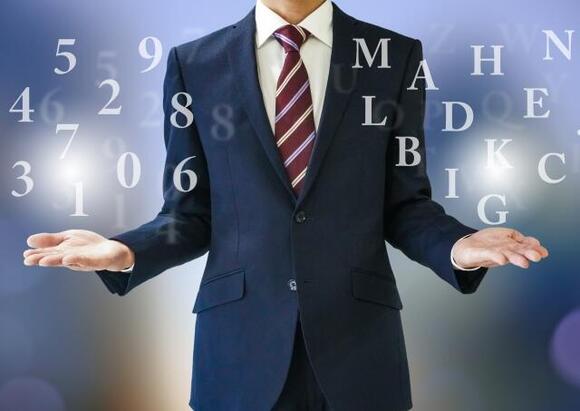
ヤフー知恵袋にこんな書き込みがあるのを見つけました。
ーーー
皆さんが常識を疑うことって、どんなことですか?
夏休みの宿題で「常識を疑う」
このお題が私には難しすぎて全然わかりません。
だから普段、
ぜひ、協力お願いします!!
ーーー
「夏休み」と書かれているので、
これを読んで、最初は、「常識を疑う」
愕然としたものの、よくよく考えてみると、
むしろその感覚の方が健全なのかもしれないなと思い直しました。
というのは、「常識を疑う」
たとえば今週、私の中で1つの常識が覆されました。
何だと思いますか?
実は、私、日本という国は「極東アジアの小さな国」
国土面積が小さい国という意味です。ところが...
日本は意外にも大きかったのです。
知ったきっかけは、「The True Size.com」というサイトを訪れたことでした。
これは、
実際の面積を体感できるサイトです。
たとえば、「Japan」で検索してみてください。
日本がアクティブになり、
日本の国土サイズが感覚的にわかります。
私が最初に驚いたのは、
日本がイギリスやイタリアよりだいぶ大きいのはもちろん、
ドイツよりも大きそうだったこと。
えー!びっくり!という感じでした。
で、さらに調べてみると...
日本の国土面積は377,945,210平方kmです。
東南アジアの中では、
中国 9,600,000
インドネシア 1,910,931
タイ 513,140
に次いで第4位。(単位はいずれも平方kmです)
それどころか、ヨーロッパのこれらの国々よりも大きい。
イギリス 242,495
イタリア 302,068
ノルウェー 323,772
ドイツ 357,581
フィンランド 336,884
ヨーロッパの国は国土面積が狭い国が多いんですね。
では、なぜ私は(もしかしたら、皆さんも)
日本はちっぽけな国だと思い込んでいたのでしょうか?
ここからは推測です。理由は2つあります。
その1。
この地図の特徴は高緯度に向かうにつれ距離や面積が拡大されるこ
日本は、赤道直下ではないにしろ、中緯度にあるので、
地図上の形は実際よりも小さく表示されます。
それが「ちっぽけ日本」
その2。考えられるもう一つの原因は、「日本は小さい島国」
幕末に国内で定着したこと。
どこからどうして定着したのかはわかりませんが、
黒船到来で軍事力のギャップをまざまざと認識させられ、
以来、自国を卑下する意味もあり、
つまり黒船あたりから、「日本は小さい島国」
そのような言語的表現は定着し、
そして、もっともアタマにくることは、(←これ、自分にです)
「日本は小さい島国」という気持ちで生きていなければ、
もっと気持ちも大きくなったような気がすること!
今回、改めて常識は疑わないと、見えてくるものも、
来週は6月も最終週。今年も半分が終わってしまいますね。
暑さに負けずに元気に過ごしましょう!
脱「ついて型」のススメ

例えば、「~について取り上げよう」
あるいは、会議のアジェンダに書かれた「~について」の項目。
日常業務のいろいろなところで、
「~について」という言葉を使って会話がされています。
会議もコンテンツの一種であると考えた場合、
コンテンツの質はコンテンツを作る人のイニシアチブにかかってき
多くの物事で「~について」
本当にそれでいいのかな?とも思います。
というのは、1つの仮説として、この「ついて型」アプローチが、
アウトプットの質や生産性、
そこで、今日は、私が「ついて型」
その「ついて型」にはどんな問題があるのか、
問題があるなら、どうしたらいいのか、考えてみたいと思います。
実際、「~について取り上げよう」
コンテンツは作れますし、会議のアジェンダに「~について」
それなりに会議は成立してしまうものです。
それらのコンテンツでは何かしら言葉的なものが成果物になるので
「はい、これが本日のアウトプットです」
でも、
会議の成果に対し、参加者の納得感はあるでしょうか?
もう一度、たとえば「企画会議」。
当社が提供している企画力養成講座では、
ついて型でもコンテンツは作れるが、
とお伝えしています。
ーーーーーーーーー
~について取り上げよう
↓
だとしたら、誰に出てもらおうかな?
↓
どんなことを聞こうかな?
↓
聞いた話をうまく原稿にまとめなきゃ...
ーーーーーーーーー
確かに、この流れでもコンテンツらしきものは完成しますよね。
ですが、このアプローチはただ「聞いた話をまとめる」
「~について取り上げよう」から始まる企画プロセスでは、
大抵の場合、何をメッセージとするのか、とか、
読み終わった時に、
なので「~について取り上げよう」
「伝えたいこと→伝わること」に執着するなら、
気をつけないといけないなと思います。
会議のあり方もそうです。
日常的に行われる会議こそ、質や生産性、
でも、もしその会議のリーダーがアジェンダを考えるときに、
「1.○○について 2.○○について」というような感じで出していたとします。
そうしたら、
誰にもわかりませんよね。
もちろん、アジェンダと会議設計は別物ですから、
場のリーダーの頭の中に会議設計があるなら、
アジェンダ自体は「1.○○について 2.○○について」で済む場合もあります。
でも、私が一番おすすめしたいことは何かというと、
疑問文でアジェンダを組み立てることです。
(これは企画を立てる時もほぼ同じです)
ところが、
つまり、何を議論する必要があるのか、
場の作り手が「問い」
ですが、慣れていないと、
え? ほんと?と思うかもしれませんが、
考える必要のあることを漏れなく「問い」の形で出せる人は
実はそれほど多くないと思います。
私自身も「問いを立てる」を意識していますが、「漏れなく」
はなはだ心許ないです。
なので、「疑問文として書いてみる」
さて、今年もあっというまに6月。
終われば2024年も半分過ぎてしまいます。トホホ...
と、一瞬背中が丸まってしまいましたが、
その前に、今週を乗り切らないとですね!
「善」という縛り

昨日、届いたコンサル向けメルマガで「謙虚という罠」という
タイトルを目にしました。
謙虚さというのは、心の中の問題ではなく、
態度の問題だというのがその内容でしたが、
内容よりもタイトルにインスパイアされて、
私も含め、多くの人は「謙虚」は美徳だと思っています。
今の自分に奢ることなく、控えめでいる、素直に学ぼうとする、
偉そうに振る舞わない...。
美徳であり、善であることに間違いありません。
でも、「謙虚という罠」という文字を読んで、
どんな罠があるのか考えてみました。
謙虚は善だという価値観を持っていると、
聞かれてもいないのに、
誉められても、「いえいえ、滅相もない」と応えたくなる、
自分が悪いわけではなくても、謝ってしまう...。
こんなことが起きたなら、それは確かに「謙虚という罠だな」
そして、そう考えてみると、一般に美徳であったり、
捉われすぎて歪んでくると、善ではなくなりますね。たとえば...
「協調性」が度を越すと → 主体性がなくなる
「真面目」が度を越すと → 融通がきかなくなる
「責任感」が度を越すと → ルール偏重になる 等
ちなみに、今年9月に映画化される辻村深月による恋愛小説『
私自身は読んでいませんが、代官山蔦屋書店コンシェルジュである
間室道子さんはブログで「傲慢と善良は表裏一体」だとして、
主人公の真美について次のように書いています。
ーーー
なぜなら、どちらも根底にあるのは「未熟」と「無知」だからだ。
たとえば厳格な母親にひたすら「いい子」に育てられた真実は
新卒採用の面接で「この会社は第一志望ではありません」と答えた。
嘘がつけない彼女は善良。
しかしこんなことを言われた相手はどう思うかまったく想像しないのは傲慢。
就職試験でこうなのだから、真実のさまざまはうまくいかない。
ーーー
善 VS 悪
もちろん善であるべきなのはその通りなのですが、
人は自分が絶対視していることに対し、
「協調性」が「善」という考え方も、
その結果、会議では(たとえ疑問があっても)
これが、災害時などに作用して、判断を間違えると、
大変なことになったりする場合もありますから、
人が善だと思っていることは、その人にとっては「その人らしさ」
自分らしいことを選んでいる方が、誰にとっても心地よい。
けれど、
もしかしたら「自分らしくない」と思い込んでいることの方へ、
気持ちをストレッチしてみるのもいいかもしれません。
「コツ」を身につける「コツ」って?

私事で恐縮ですが、ここ最近、
なかなかコツが習得できません。いえ、
進捗感や成長実感は仕事でも大切ですよね。
今回、真剣に考えてみたら、原因らしきものが浮かんできました。
そこで、今日のテーマはコツを身につけるコツはあるのか?です。
●コツというのは「やり方」か?
今さらですが、コツ(骨)の辞書的意味は「 物事をうまく処理する要領」のこと。
骨は、体の中心で体を支えていることから、物事の本質を見抜き、
技能として体得することを「コツをつかむ」
さて、コツと聞いて、ぱっと浮かんでくるのは「やり方」
似た言葉に「ノウハウ」がありますが、その違いは何でしょう?
私独自の整理だと、コツは体得を前提にした暗黙知ですが、
ノウハウは、やり方に関する暗黙知を体系的に整理した形式知。
なので、ノウハウを知っているからといって、
共通認識に立つために、ここでの暗黙知とは?を書いておきます。
暗黙知:言葉で説明するのが難しい経験的な知識(
経験知と身体知の両方を含む概念。
ということは、コツを掴むには、
①知識(考え方や理論など)を知っていること
②経験・体験が不可欠で、体で覚え、感じること
③上の2項目の間を行き来しながら、
...が、重要だということになります。
考えてみれば、当然ですよね。
でも「先生についてやり方を教えてもらえばコツは身に付くもの」
といった感覚で取り組んできた今の私は、
●実践の「量」か「質」か?
経験知・身体知を高めるために、
仕事では業務経験を重ねることが重要になるわけですが、
では、その経験の「量」と「質」なら、
両論あるようですが、ここではまず
「質が変化するまで量をこなすことが重要」
こんな書籍があります。
『アーティストのためのハンドブック~
(デイヴィッド・ベイルズ、テッド・オーランド著)
その中で陶芸の授業における実験的なエピソードが語られています教室の左半分の学生は作品の「量」によって、
量のグループは、制作した作品の総重量で評価され、
質のグループは、自分で最高だと思う作品を一つ提出し、
最後に全体を「質」で比較すると、「質」
どれも「量」によって評価されるグループによるものでした。
なぜ、こうした結果になったのでしょう?
量のグループは、試行錯誤を重ねながら作品を作ったことで、
粘土の扱いもうまくなっていきましたが、
質のグループの方は、完璧な作品を作ろうとするあまり、
考えることに時間をかけすぎてしまったからのようです。
経験知と身体知は、実践しないことには身につかないわけですね。
●実践における「質」で大切なことは?
コツを掴むには実践の「量」が大切だとはいえ、実践の「質」
ジョンズ・ホプキンズ大学の研究に関する記事(Jeff Haden/「Inc.」)によると、
同じことを反復練習するよりも、
トレーニングを繰り返す方が習得が早いと分かったそうです。
例えば、新しいプレゼンテーションをマスターしたいなら、
最初の数回は全体を同じ方法で練習し、
あるセクションに集中したり、プロジェクターを変えたり...
そして、結果を評価し、機能しないものを破棄し、
機能するものに改良を加えるということを繰り返します。
注意点は、条件を変えすぎてはいけないということ。
この方法で習得が早くなる原因の詳細は書かれていませんでしたが
既存記憶が蘇りやすい上、
2つの記憶が再統合され、定着しやすいということのようです。
つまり、反復練習では練習方法の「質」(工夫)
●オノがトレーニングでコツが掴めなかったワケ
私がコツを習得できなかった原因は、こんなことだと思います。
・(コツ=やり方という思い込みから)
・(結果から検証していただけで)
・圧倒的に量が足りない
・教われば何とかなるという他力本願(笑 ←多分1番の原因はこれ!
新しいことが始まる機会の多い4月です。
コツを身につける際の参考になれば幸いです。
よい週末をお過ごしください!
「お久しぶり!」はステキ!

今日は「お久しぶり!」という関係についての話です。
というのも、ここ最近、そのような出来事が多かったからです。
ですが、人との関係や間合いの作り方について、
私の考え方は少数派すぎてあまり参考にならないかも...
たとえば、ある人と初めて会ってからもう何年も経っていて、
しかもご無沙汰している場合、
私はあまり気にせずにコンタクトする方なのですが、
ある時ようやく、
そう気づいたのは、ある人からこんなことを言われたからです。
具体的には30年ぐらい前、
意気投合したので1度飲みに行き。。。で、
何年かしたある時、
楽しく飲んだその日、Fさんがこう言いました。
「あなたは変わってるね。
そう言われて初めて、自分が「時間経過」
この経験から私は「人を久しぶりに誘うと相手は困惑する」
遅ればせながら学んだ次第です。
ここでいう「困惑」とは「意外なことに出会った驚き」のこと。
本来の「困って、どうしてよいかわからないこと」
「困惑」の「困」の反応は、ある程度関係が築けているせいか、
ましてSNSの時代ではなおさらだと思います。
さて、最近の私の「お久しぶり!」の例を挙げると...
3月1日付の本メルマガ「出張シェフの一言に脱帽!」
「私以外の3人は全員お互いが『はじめまして』の関係だった」
あの時のメンバーの1人Yさんも実は10年以上前に当社にいた元
一方、今月は別の元社員の方からも「お久しぶりです」
自分から連絡した場合も、された場合も、「お久しぶり」
会いたいから会う、
考えてみれば、自然なことですよね。
昔よりも「お久しぶり!」がしやすくなったのは、
だけど、、、
いくらSNSがあったとしても、
久々だとコンタクトしにくい理由。
「相手は自分を覚えているか?」
「誰?と反応されるのではないか?」
そう思うと怖いですよね。
「会いに行くもっともらしい理由が見つからない」
と思ったら、自己制限がかかりますよね。
話がズレますが、
「書いたらどう思われるかな?」
時々いただく感想やご意見、ほんの数行のメッセージ...
これらはうれしい以外の何物でもありません!
(いえ、まるで催促しているようですが笑)、本当にうれしくて「
話を戻します。
「お久しぶり! お元気ですか?」と意思表示するだけなのに、
なぜか必要だったりする小さな勇気。
そんな時、役立つのは「覚えていないかもしれませんが...」
実際にそのように言葉にして接すれば、
お互いに気まずさがなくなります。
「覚えていないかもしれませんが...」と言って
「ごめんなさい、思い出せないのですが...」と言われたら
「ですよね~」と言えば済みますもの笑
人と人の関係にはいろいろな局面があります。
最近は「人間関係の断捨離」という言葉もあるそうですし、
今の人間関係を手放さないと、
そういう考え方もあってもいいし、
今はそう考える時期と判断するのもあっていいと思います。
だけど、しばらくコンタクトしていなかった相手に、
ちょっとだけ勇気を出してコンタクトしてみると、
新しい関係が始まるかもしれませんよ。
最近私が思い出した人は、うふふ... ヒミツ。
春ですし、
いかがでしょうか? 笑
「好意」の持つパワー

うちの会社では、
発表者が好きなテーマで30分程度説明し、
毎回、終了まで40~50分程度でしょうか。
たとえば、私が扱ってきたテーマの例を挙げてみますね。
・論点コンシャスになろう
・「Fast Worker」になるための秘訣
・今日は心理学、です!
・自分主導の説明と意思表示
・カテゴライズのすすめ
・自分ブランディング
オープン社内報など、
さて、昨日は、たまたま私の番で、今回は題して「意味付けの話」
ここでの「意味付け」
いろいろな事柄に対して、意義や価値、理由や教訓などの形で、
人が自分なりにしている「解釈」のことです。
たとえば、人が最も頻繁に行なっている意味付けは、
他人を評価判断することではないでしょうか。
あの人は、~だ。
あの人には、~なところがある。
あの人は、いつも~する。
自分の解釈で人を決めつけると、
人と人は、お互いに相手の人柄や性格、
その解釈があたかも本当の姿であるかのように決めつけをし合って
しかも、その評価判断はポジティブなことばかりではなく、
むしろネガティブなことの方が記憶に刷り込まれやすいと言えるか
ネガティブな評価判断をしてしまう顕著な例は、
誰にでも苦手な人の一人や二人はいるもの。
私はどちらかといえば、
たとえば、自分の話ばかり機関銃のような速さでする人、
しかも、声が大きく、感情の起伏が激しい相手は、
そのような人と話していると、30分を超えたあたりから、
気が遠のくような感じになって、まったく集中できなくなります。
実際に、一回り近く年上の方で、そのような人がいました。
前記の「自分の話ばかり機関銃のような速さでする」
事実と言っても良いと思いますが、
私はその人を「幼稚な人」「子どもっぽく、わがままな人」
こちらは明らかに私の解釈です。
前置きが長くなりましたが、実はここからが今日の本題です。
この人との間で、あるとき不思議なことが起きました。
人が人に抱く気持ちに「好意、好感」というポジティブな感情、
「反感、悪意、敵意」などのネガティブな感情、
さらに「普通、どちらとも言えない」という感情があるとすると、
この人の私に対する気持ちに「好意」
そうしたら、何とあれだけ苦手意識があったその人に対し、
この人の良いところを見つけようという気持ちが湧いてきました。
おそらく、「子どもっぽく、わがままな人」
心の中で被害に遭いたくないという深層心理が働いていたのですが
「好意」を感じ取ったことで、(敵対する相手ではないのだから)
寛大に捉えても大丈夫だと無意識ながらに思ったのだと思います。
ロバート・チャルディーニの著書「影響力の武器」の中で、
「好意の返報性」について書かれていますが、
職場での悩みとして、各種調査でしばしば「人間関係」
「あの人は~だ」は必ずしも事実ではなく、
見え方が変わるような気もします。
さらに必ず関係が変わるとは言えないまでも、「好意」
関係が変わる場合もあることは、
桜の便りが楽しみになってきました。
どうぞ良い週末をお過ごしください。
出張シェフの一言に脱帽!

先日の3連休の最後の日、
その際に出張シェフを利用しました。
実は、この会、私以外の3人は全員お互いが「はじめまして」
私が出張シェフを利用するのも初めてで、
Sharedineというサービスを利用したのですが、
調理器具や調味料は依頼主が用意し、
今回、私は買い物も含めてお願いしました。
結論からいうと、味、量、価格とも大満足です。
さて、そのようなしくみなので、
今回のシェフRyuさんにそんな時はどうするのかを尋ねたところ
「自分は、自分の方を状況に合わせます」と迷いのない回答が。
以前は、
所詮、レストランの厨房に家庭の厨房はかなわないので、
その環境でのベストを尽くせば良いと考えるようになったそうです
包丁の切れ味が悪いなと思ったら、たとえ砥石がなくても、
その場でできる工夫をしてしのぐのだとか。
この割り切りは簡単そうで簡単ではありませんよね。
「なんだ、○○○も揃っていないのか」
「思った料理ができないのは相手のせいだ」と
心の中で相手を責めることもできます。
こう思ってしまうのは、
人生言い訳が多くなりそうですね。
それに対して、Ryuさんのこの潔い考え方は素敵です。
だけど、、、
たとえば、私の場合、
限界の一歩手前で手を抜き、
「ベストを尽くした風」にやってしまうことがありますから。
心理学用語に「アカウンタビリティ」という言葉があります。
ビジネスでは説明責任の意ですが、心理学では「責任の概念」
自分に起きたことは自分自身の責任の結果である、
ちょっと聞くと厳しそうに感じますが、
なぜでしょう?
ほかの人のせいや何かのせいにしていると、
先ほどの私の筋トレの例でも、
だから、
昨年のウィンターシーズン、
しかも、ゲレンデに立つのは何十年かぶりのこと。
最後の最後の私のチャレンジは、しっかり前傾し、
スピードが出てしまうと怖いのですが、
そのときに得たのは、爽快感、満足感、達成感、充足感。。。。
Ryuさんの言葉をきっかけに考えてみたら、
結果の良し悪し以上に重要な気がしてきました。
私たちは、思いもかけない不運や想定外の出来事に見舞われると、
ついそのことを悔やんで、前を向けなくなります。
自分はベストを尽くしたか?
それを基準にすると、
今日から弥生です。桜も早そうですね! そして花粉も...
元気に参りましょう!
「考えろ」っていうけれど...?

企業から求められる人材像ですが、ここ20~30年、
「自ら考え、自ら行動する」と言われ続けているように思います。
「自考自行」「自考自走」「自考自創」
この点については、
実は、当社でも、昨日も若手向けに「考える」
「論点」と「サブ論点」というものをどう立てたらいいのか、
どこまで考えたら「タスク」に移っていいのかなど、
レクチャーとディスカッションを交えながら教えています。
私は、「会社は学校ではない」と思っていますが、
このような勉強会を行うのは、
その正論を最初から振り翳そうとは思わないからです。
なぜなら今の学校教育は「答えを教える教育」
「考える教育」が行われているように見えません。
しかし、学校教育がそうだからと言って、
まるっきり考えないという人はむしろ稀ではないでしょうか。
むしろ、みんな、何かしら考えているし、考えようとしています。
でも、だからといって、ただ「考えろ」と言われても、
何を考えることが求められているのか、わからないと思います。
なぜ、「考えろ」では不十分と思うかというと...
実は、私自身が「考える」ことを教えようとしても
どうやって教えたらいいのか、考え考えやっているからです。
つまり、自分自身がちゃんと言語化できていないのです。
人に、
私自身が「考える」
自分がその程度でしかないのに、社員にただ「考えろ」
いかがなものか、という気がします。
だから、社員と一緒に「考えるとは?」を考えています。
それは、結構、楽しいです。
なーんちゃって、結構「いい社長風」
ところで、いったいなぜ「考える」ことが、
「AIが~」という答えは聞き飽きているので、
私は、「考える」には大別すると、
2系統+ミックスの3つがあると思っています。
①好奇心を満たすために考える
②より良い結果を得る行動を決めるために考える
③上の2点のミックス
②は、ビジネスのみならず、私生活でもありえますが、
ビジネスで「考えろ」と言われる理由は、主に②
自分一人のための決断なら、考えず、
でも、組織であるからこそ、決めるには理由も必要ですし、
他の選択肢と比べて、どう違うのかの比較検討も必要になります。
で、②について、じっくり考えてみましょう。
「②より良い結果を得る行動を決めるために考える」
つまり、考える先には、行動があることがわかります。ところが、
そうすると人は往々にして考える前に、行動(タスク)
たとえば...
過去の当社のセミナーで、
Q1 あなたは飲食店を開業するために、
としたら、どのような場所に開こうと考えるか?
こう尋ねると、大半の参加者は「駅前」とか「人通りの多い場所」
無意識でも、有利な場所はどこか?を考えているわけです。
次に、こう尋ねました。
Q2 あなたは駅前で屋台を始めることにしました。
あなたの屋台の隣には同種の別の屋台があって、
でも、あなたの屋台は閑古鳥が鳴いている。
こう尋ねると、答えは2通りに分かれます。
1つは策を答えるもの。たとえば、
・メニューを変えてみる
・幟(のぼり)を立ててみる
・価格を見直す 等
もう1つは原因を探るための行動を答えるもの。たとえば、
・隣の屋台の客をつかまえて、どこが良いのか聞いてみる
・隣の屋台で食べさせてもらう 等
感覚値ですが、だいたい半数強の人は策(行動)
さて、では半数の人が策に向かうのはなぜでしょう?
私は、第1は、早く答えを見つけたいからなのだろうと思います。
要するに、この場合なら原因を考えるなんてじれったいのです。
第2は、
だとして、想像してみてください。
原因も分からずに、メニューを変えても多分成果は出ませんよね。
考えることが重要だと思う理由の1つは、
つまり、「急がば回れ」だからです。
焦って策を考えても、最終的には意味がなければ無駄ですよね。
さて、毎週見ているNHKドラマ「正直不動産2」に登場する
Z世代役の十影(とかげ)くんに興味を持っている今日この頃。
十影くんには、一見無駄でも、結局は考えた方がタイパいいよ、
と伝えたくなります。
ヤマピーこと山下智久さんが務める主人公・永瀬財地の、
ウソでも何でもアリだった人生が、正直アリキに変わって、
今では本音をぶちまける様がおもしろくて、
さ、今日は金曜日。
アレもコレもあると思いますが、乗り切りましょう!
今日もお付き合いいただき、ありがとうございました。
初めの一歩は「意思表示」

当社では、去年頃から、「リーダーシップ」「イニシアチブ」「
キーワードになっていて、
年初も、私は「
という話をしました。
リーダーシップというと集団をまとめて先導するとか、
統率するというイメージが強いですが、
その基本は、明確に「意思表示」することだと思います。
・自分はどうしたいのか
・自分は相手にどうしてほしいのか
・自分はどっちに向かって、どう進めようとしているのか
人を率いてまとめていくとなるとハードルは高いですが、
まず自分の意思を示すということであれば、
でも、この意思表示ができなければ、
集団をまとめて先導することなど絶対ムリです。
だから、リーダーシップの最初の一歩は「意思表示」
でも、
(もちろん、十把一絡げで断定することはしませんが)。
仮に日本人のコミュニケーションの特徴として、
意思表示を明確にしない傾向があるなら、
おそらく「相手の気持ちを察する」気遣いを「是」
でも、「察する」は、ある状況では美徳ですが、
仕事で推進担当者が周りに対して「察してほしい」
私はナシだと思います。
「意思表示」という行動を支えるのは、「主体性」です。
主体性とは、自分で考えて、自分の責任で決め、発言・
その対極にあるのは、指示待ち、受け身、思考停止など。
さらに、空気を読む、依存する、同調する、流される...
さて、「主体性が大事」などということは、
最早ビジネスパーソンなら耳タコではないでしょうか?
でも、なぜ主体性が大事なのか?と部下や後輩から聞かれたら、
何と答えますか?
私はこう答えます。
「私がラクできるから」です(笑)
指示しないとできない人より、
上司の私としては断然ラクです。
でも、上司をラクにさせるために、主体的であれ...と聞いたら、
「なんで、そんなことのために...?」と思いますよね。
だけど、「周りの人、みんなをラクにさせる」と聞いたら、
そんな人は、すごーく価値の高い人だと思いますよね?
図式的にはこうなります。
ーーー
主体的に動く人は、周りの人、みんなをラクにさせる
↓
周りが喜ぶだけでなく、知的労働比率が上がって、結果生産性も上がる?
↓
そこで生じた心理的余裕が、広い視野での思考を生む
↓
それが全社に広がると、会社の生産性も創造性も上がる
↓
生産性も創造性も上がれば、革新的なことも起きやすい
↓
実際に、イノベーションが起きる
ーーー
ちなみに「はたらくの語源は"傍を楽にする"」説、
うーん、あれはもっともらしいけど、疑わしいですね。
今回の話はそれとは関係ありません。
さて、
第三者の存在がなかったとしても、自分の意思で行動する方が、
やらされて行動するより、楽しいに決まっています。
と、考えると、なぜ主体性が大事なのか?
「自分の幸福のため」になるのかもしれません。
自分はどうしたいのか。
自分は相手にどうしてほしいのか。
まずは、そんな意思表示から取り組みたいものです。
(社長といえども、これは案外難しいです)
今月もわずか1週間ほど。
急に寒さが増しましたが、皆様、体調を崩されませんように!



