その準備は、本当に必要か?
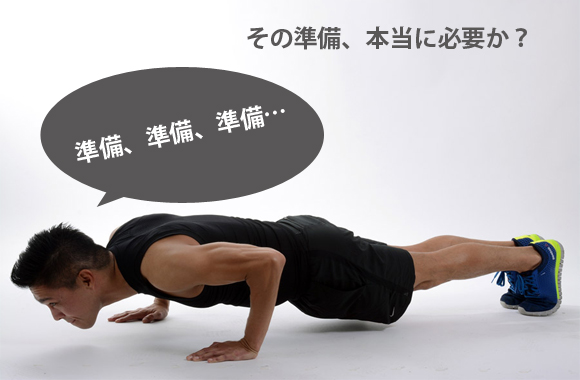
こんにちは。
今日は「準備」というものがもたらす、良いこと、悪いことを考えたいと思います。
実は今回初めて、ビデオも一緒に掲載します。
準備しないことも大切だなという思いから、
ビデオも一発撮りでやってみました。
うーーん。うーん。
ま、ね、やってみたら、いろいろ思いますが。。。
でも、もし準備したり、練習したりしたら、どうなるかは大体予想がつく。
だから、これでヨシとします。
鼻息とか、携帯の着信音まで撮れちゃっていますが(笑)
一般的にいうと、「準備」することは大切です。
私自身も準備をすることで乗り越えてきたことが多々あります。
でも、準備をすることが、むしろ「場の可能性」を縮めてしまうこともあります。
たとえば、セミナー。
私はセミナーを主催したり、講師に招かれたりします。
5−6時間のコンテンツを初めてリリースする場合には、
時間をオーバーしないか、わかりやすく説明できているかを事前に検証するために、
映像に撮りながら、タイムトライアルをします。
いわば、準備であり、事前のトレーニングです。
しかし、やればやるほど心の中でこんな声が聞こえてきます。
「これ、場がカチカチになって、なんだか面白くないんじゃない?」
で、実際に、練習したセミナーコンテンツは「滑らか」かもしれまえんが、
そのままやると、ほぼ面白みがありません。
Unexpectedなことが起きないからです。
そう、「予想しないこと」が起きない場というのは、面白くありません。
ですので、《教訓その1》は
《練習はほどほどにして、予想外のことに身を委ねるスペースを残すこと》です。
こんなこともあります。
たとえば、お客様の会議をファシリテーションするとき、
予想もしない意見が出てきてしまって、
当初の見積もりで想定している会議の回数で終われるだろうか...、
終わらなかったらどうしよう...と感じることがあります。
でも、想定している会議の回数で終わらせること自体は、
お客様にとって、目的ではありません。
それを理解した上で、ファシリテーターの私たちが、
なるようになると信じてそのライブ感に身を委ねていく。
そうすると、なぜか自然に収束したりします。
つまり、もし「終わらなかったらどうしよう」という心の声に支配されたら、
どうなったでしょうか...?
無理やりの結論は出るかもしれません。
でも、きっとそれは誰も納得していない結論、
参加者を置いてきぼりにした結論であるに違いありません。
良い場にするためには、ファシリテータは腹をくくる必要があるということですね。
つまり《教訓その2》は教訓その1とともに、
《その場の参加者の気持ちを置いていかないと腹をくくること》です。
他にもこんなことがあります。
当社ではアイデア会議という場があります。
準備をして臨むアイデア会議(アイデアを持ち寄る会議)もあれば、
準備しないで臨むアイデア会議もあります。
準備をして臨む会議の方が議論が活発になりそうですが、
実はそんなことはありません。
アイデアを持ち寄る会議ですと、
アイデアを「聞く人」「言う人」に分かれがちなのです。
そうなると、一つのアイデアが膨らんでいきません。
ところが、準備しなくても良いアイデア会議の場合、
誰かが出した一つのアイデアに、別の誰かがアイデアを乗っけます。
そうなると、アイデアが膨らんでいくんですね。
本当に不思議なことです。
つまり《教訓その3》は準備をせずに、
《その場からつくる方が活性化することがあるということ》です。
対話の場をどうつくるのか、
それはリーダーにとってとても重要です。
一般的に言われる「準備は大切、準備をしろ」ということ。
これはこれで真理であると同時に、
場づくりに対し、準備すればするほど、
「Unexpectedなことが起きない」ことによって、
参加者の意識が停滞してしまいやすいという弊害が起きるのも真実です。
ふと自分が属する場に「予定調和」が起きていて、
それが場に悪い影響を与えていないか、
「準備しすぎ」という切り口でチェックしてみると良いかもしれません。
3月の最終週です。
どうぞ良い1週間をお過ごしください!
「希望」は自分の中にある
 今日のテーマは「希望」です。
今日のテーマは「希望」です。
これを書こうと思った直接的なきっかけは、先日、ある人と話していたとき、
「『希望』は自分の中にある」ということが話題に上ったからです。
で、私のところにくる様々なご相談も「希望」という切り口で見ると、
いろいろあるなあと思いました。
と、同時に、これを読んでいる皆さんも、
ご自分の希望と絶望、部下や後輩の希望と絶望に
年に1度ぐらいは直面しているのではないかとも思ったからです。
私のところに来るご相談を「希望」という切り口で表現してみると、、、
・ある人からは、希望を失いそうになりながらも、
何とか壁を乗り越えたいという思いを感じます。
・別のある人からは、今はうまく行っていないけれど、
絶対にもっと良くできるという確信的希望を持っていると感じます。
・あるいは、なんだか話の最初は混沌としていて、
相談内容もよくわからなかったのに、
お帰りになるときには、希望を持った強い表情で帰る方もいます。
・さらに、人によっては現状を諦め、新天地に希望を持って、
退職の挨拶に来られる方もいます。
で、そういう方と接していて感じるのは、
結局希望がどこにあるかといえば、自分の中なのだなということです。
人にとって、「希望」は生きる糧。ですが、人は希望を失うこともあります。
「希望」の反対は「絶望」です。
あなたは、「絶望」したことはありますか?
私は、大中小取り混ぜていうと、これまでに何度か(も?)あります。
だって、30年以上やってると、そりゃ、ありますよ〜!
1週間ぐらいで回復できたものから、回復に数年を要したものまでいろいろね。
もっとも「懐かしい絶望」は、30代の前半から中盤の頃のものです。
バブルの影響もあって、毎週1本企画書を書くというような多忙な状況で、
時間が足りないから毎週週末にこぼれるわけです。
お金は結構稼いでいたのですが、毎週末仕事では幸せなわけがありません!
仕事三昧という八方塞がり。どうしていいかわかりませんでした。
忌野清志郎が「自分はうつ病で病院に行った。早めに病院に行くに限る」
という記事を読んで、「あれ? 私もうつ?」そう思いました。
それで実際、心療内科でカウンセリングを受けたことがあります。
ですが、、、これがなんというか、、、気が短い私には合わないんですぅ。
これを続けていても、ラチがあかん、と(笑
で、通院はやめて、ひたすらやりたかったこと、我慢していたことをやりました。
バイクの免許を取りに行くとか、小説を書くとか。
で、結局やってみたら、実はそれほどやりたいわけではないことがわかった。
それでようやく自分が他責で自分の人生を見ていたことに気づきました。
希望を持つか、絶望するかは、結局自分次第なんだな、と。
さて、、、、
希望の持ち方によって絶望的な状況でも人は生きられるという話が、
「ビジョナリーカンパニー(2)飛躍の法則」に出てきます。
それは、「ストックデールの逆説」です。
ストックデールは、ベトナム戦争で7年半の間、戦争捕虜を経験し、
生還したアメリカ軍パイロットです。
「ビジョナリーカンパニー(2)」でストックデールは次のように語っています。
20回以上の拷問を受けたにもかかわらず、希望を失わずに生き延びたのは;
「わたしは結末について確信を失うことはなかった。ここから出られるだけでなく、
最後にはかならず勝利を収めて、この経験を人生の決定的な出来事にし、
あれほど貴重な体験はなかったと言えるようにすると」
それに対し、希望を失っていった人々というのがどんな人たちだったかというと;
「楽観主義者だ。そう、クリスマスまでには出られると孝える人たちだ。
クリスマスが近づき、終わる。そうすると、復活祭までには出られると考える。
そして復活祭が近づき、終わる。つぎは感謝祭、そしてつぎはまたクリスマス。
失望が重なって死んでいく」
そう、失意が重なると、人は希望を失い、エネルギーを失い、
生きる気力がなくなりますよね。
だからこそ、そうなることを避けなければいけません。
で、「ストックデールの逆説」を端的に理解するのに良い言葉を紹介します。
私は、30代の頃、シュガーレディの創業社長/故・佐藤啓次郎氏の
社内報や社史に掲載するメッセージづくりを頼まれていたのですが、
インタビューをしたある日、ご自分の好きな言葉として、
こんな言葉を挙げられました。
「希望的観測は捨てよ。されど希望を忘れるな」
むむむ、これはまさにストックデールの逆説を端的に表した表現ですよね。
さて、、、
希望を失いそうになっている部下や後輩に寄り添う時は、
絶望を乗り越えた今の自分からというよりも、
希望を失いそうになった過去の自分の目線で言葉をかけたいものですね。
またある日、自分自身が希望を見失いそうになったなら、
「希望は自分の中にある」、
それを思い出したいものですね。
自分自身が「希望」とどう付き合っているか、
自分の周りの人が今希望を持てているか、
お互いに、一緒に、今日は「希望」という切り口で
セルフチェックをかけてみませんか?
そうすると、新しいエナジーが湧いてくる気がします!
もうすぐ桜の季節です。今週も、どうぞ良い1週間を!
「姿勢」は「姿の勢い」

「肩甲骨、意外に動くね」
週末、我が家に来て、「エゴスキュー」というエクササイズを教えてくれた
高校時代の友人が私の動きを見てそう言いました。
私は、辛さが自覚できないくらい慢性的に肩が凝っているのですが、
肩甲骨を動かすことと、正しい姿勢を保つことが重要と聞いたので、
ここ数週間、Youtubeで見た動画の運動を続けていたのです。
どうやら少しは成果が出ているらしいことがわかりました。
正しい姿勢についてネットで調べてみると、
正しい姿勢はラクな姿勢だそうですね。
背筋をピンと伸ばした姿勢は一見正しい姿勢に見えますが、
続かない姿勢で、正しい姿勢ではないそうです。
30代の頃、体の姿勢を意識した時期がありました。
自分らしく悠々としているには、体の姿勢が大切だと思っていました。
なぜか、悠々としていたり、堂々としていることが、
信頼を得る上でも重要だと思っていたのです。
で、特にその頃は、歩く姿勢を意識していた記憶があります。
ところが、慣れというのは恐ろしい。
いつのまにか意識しなくなり、気がつくと猫背気味です。
おそらくパソコンを使う時間が長いせいでしょうね。
で、もう一度初心にかえって、姿勢を良くしようかなと思う今日この頃です。
「姿勢」というのは、「姿」の「勢い」と書きますよね。
姿のパワーを表すのが姿勢。そう思うと、より一層重要な気がしてきます。
姿勢には、「体の構え方」という意味のほかに、
「心の構え方」という意味もあります。
カーネギーは、「心の構えは、声のトーン、顔の表情、体の姿勢に影響し、
その人が抱くあらゆる感情の性質を左右するとともに、
その人が話す言葉の印象を変える」と言ったそうです。
カーネギーに反論するのも憚られますが、
私は反対ではないかなあ...と思います。
武道も書道も踊りもスポーツも、基本はまずは体の姿勢。
それを整えることが心の構え方を整える上で不可欠というのが、
日本の伝統的な考え方です。
そういえば、「今でしょ!」の林修さんも
以前のテレビ番組「あすなろラボ」でこんな発言をしたようです。
ーーーーー
しつけの中で一番大事なことは「姿勢」。
集中力がないのは、集中できる姿勢ができてないからです。
宿題ができないのは、宿題をきちんと座ってできる姿勢ができてないからです。
「姿勢の良い不良」はいない。
姿勢の良い子に成績の良い子が多い。
ーーーーー
しかも、背中が曲がっていると、脳が発達しないのですって! へぇ〜
だから、カーネギーさん、
やっぱり体の構え方の方が先なのではないでしょうか。
体の構え方が体の使い方(行動習慣)につながり、
体の使い方が心の構え方になり、心の使い方になる。
これは、今流行りのルーチンをしっかりやろうという考え方にも通じますよね。
たとえばデスクでPCを立ち上げて仕事を始めるその一連の作業はルーティン。
ところがこれをルーティンだと思っている人は少ないし、
その作業をしているときの自分に興味を持っている人も少ないですよね。
これは自分の体の姿勢や動きに興味が持てないのと同じ感覚のことだと思います。
姿勢なんて、ルーティンなんて、それほど重要だと思っていないということです。
でも、実は姿勢やルーティンにこそその人の価値観や生き方が表れるのですよね。
それは、他のことにも影響するでしょうし、
もちろんパフォーマンスにも影響しないはずはありません。
体の姿勢が悪ければ、心の姿勢、生きる姿勢を整えることはできず、
反対に、体の姿勢を整えると、心の姿勢も生きる姿勢も整ってくる。
たかが姿勢、たかがルーティンなのですが...。
姿勢を整えるために、バンダイから出ている「猫背」というフィギュア(写真)を
机の上に飾ろうかな...と思って始まる月曜日です。
読んでいただきありがとうございました。どうぞ素敵な1週間を!
文章の基本は自分の視点で「これが大切」を伝えること

あなたは、文章を書くのは好きですか? 嫌いですか?
得意ですか? 苦手ですか?
今日のブログのテーマは、「文章を書くこと」についてです。
たとえばアマゾンで「文章力」で検索すると、相当たくさんの本が出てきます。
この検索結果の1ページ目を見たとき、私が読んだことのあるのは、池上彰さんの「伝える力」と山田ズーニーさんの「伝わる・揺さぶる!文章を書く」。いずれも評判のいい本ですね。この2冊を比較したとき、どちらがよりお勧めかと言うと、私は後者をお勧めします。
というのは、、、、文章力をテーマにした本は、テクニカルなティップスや必要な心がけが紹介されていることがとても多く、池上さんの本もそうした印象でした。しかし、人が知りたいのは、文章を書く時にいったい何が重要なのかという原理原則ではないでしょうか。そうした本がとても少ない中、山田ズーニーさんの本では原理原則に触れられており、お勧めできます。が、強いて難を言うと、ライターなどのプロにとってはピンとくる有益な内容だったとしても、文章を書く機会の少ない人にとっては、簡単に実行できるとは思えないという点です。
これだけ多くの本が出ているということは、もっと文章力を高めたいというニーズがあるからだと思いますが、学校教育では、作文を書かせることはあっても、文章の書き方の原理原則を教えてはくれません(思い込みだったら、すみません)。なぜそうなるのか。それは、そのぐらい文章を書くという行為の原理原則を紐解いて、体系的に教えることが難しいからです。多くの本が、文章の修辞技術の紹介に終始しているのもそのことと無関係ではないと思います。
原理原則がわからないという面では、私自身も例外ではありませんでした。たとえば、部下の書いた原稿に対し、何をもってOKを出し、どんなときはNGなのか。その基準は単に日本語としてわかりやすいかどうかだけではないはずです。基本となる考え方を持たないと、私の出したNGは個人の主観と言われても反論できません。そういう立場で文章教育を考える中で、見えてきたことがたくさんあります。
このページで全部は書けませんので、今日一番お伝えしたいことをここで明らかにしておきます。それは、文章を書く上で一番大切なのは、修辞ではなく、視点である...ということ。「文章はなるべく短く書きましょう」とか「言葉の重複は避けましょう」は修辞の話です。それよりも前に、自分はどんな視点から何を言いたいのかを決めることが、文章の命です。文章とは、そもそも何かを伝えるために書かれたものと定義づけた場合、それがない、あるいはよくわからない文章は、致命的な欠陥を持っていることになります。
こう聞いて、あなたはどう感じましたか?
「自分が書いているのは単なる報告書だし、別に大それたことを言いたいわけではない」とか、「自分の視点と言われても...」などと思われたでしょうか。
たとえば、「3月度支店別業績レポート」と「3月度支店別業績レポート〜目標クリアの支店の共通点とは?」というタイトルを比較して、どちらがより有益なレポートだと感じますか? 当然後者ですよね。何の視点もない情報発信ならあなたの仕事は誰がやっても同じだということになります。
ここで、「視点」というものをもう少し深堀りしてみましょう。先ほど文章の命は「自分はどんな視点から何を言いたいのかを決めること」だと書きました。これはどういうことかというと、「〜(について)は、〜が大切です」というフレームワークで自分の言いたいことを定めるのとほぼ等しいと思ってください。平たく言えば、意見や見解を持つということです。ですから、視点というのは「〜が大切」の部分です。たとえば、「チームワーク」をテーマに文章を書くとします。「チームワークでは、〜が大切です」とあなたの視点を入れて自分の考えをまとめるわけです。ブランクに入るのは何でしょうか?
・コミュニケーション
・各自の責任行動
・和
・団結
・全体最適
いろいろな視点からチームワークを語ることができます。でも、いろいろ語ってしまうと、読んだ人/聞いた人は「で、結局何が言いたいわけ?」と感じることになります。だからこそ、自分は何を語りたいのか、決める必要があるわけです。
もちろん、「チームワークでは、〜が大切です」を明確にしても、それで良い文章が書けるわけではありませんし、文章全体が完成するわけでもありません。しかし、それがあってこそ、あなたは文章で言いたいことを伝えたことになります。反対に、それが明らかでない文章は機能不全に陥っています。実は、世の中には機能不全に陥っている文章が何とたくさん存在していることか。
こういった傾向を考慮すると、文章力を養う場合に大切なのは、まずは70点の文章の姿と組み立てのプロセスを理解することです。つまり、70点の文章を書くプロセスには「自分はどんな視点から何を言いたいのかを決めること」が必要というわけです。
こういう内容をお伝えするのは、やっぱりブログではなく、体験型セミナーですよね。
はい! 当社の社内報担当者向けセミナーはしばらくお休みしていましたが、お問い合わせもいただいており、来月からほぼ毎月定期的に開催します。まだ告知のページができていませんが、4月20日(水)に企画セミナーを、22日(金)に文章構成セミナーを開催する予定です。さらに、今年度前半では社内広報から少し離れて、リーダー向けのコミュニケーションセミナーを開催する予定です。ご期待ください。(もしご関心がおありでしたら、問い合わせフォームからご一報ください。開催概要が決まりましたら、ご連絡いたします)
読んでいただき、ありがとうございました。どうぞ良い1週間を!



