ダイバーシティ? まず常識を疑おう!
週末、初対面の相手と
自分の命を何に使うか、何を生きる使命とするのか、
たとえ言葉にするのが難しくても、それを考えながら生きたいですね...
というような、初対面の割にはいきなりマジな話をしていました。
この問いかけへの答えについて、私は今もってシンプルに語ることができません。
たくさんの言葉が出てきてしまって、一言で言い切れないのです。
そのうちの一つが、人が抑圧されずに自分らしさを発せられる状況をつくる、
それに関わっていたい、というものがあります。
幸い、世の中は「ダイバーシティ」の掛け声の下、
個々の違いを認め合う社会に向かおうという理念が示され、
少しづつ動き出していると感じます。
と、同時に、それを阻むものが厳然として社会にはあります。
それは、何か?
「常識」です。
私たちは、社会から爪弾きにされると困るので、
されないようにするにはどうしたらいいか、
自分でも考え、また先輩や上司からも教えられます。
行動基準は「爪弾きにされないためにどうするか」でした。
「社会」と書きましたが、これは「社内」でも同様です。
その結果、暗黙の行動ルールがあなたの会社にもあるのではないでしょうか。
例えば、次のような考え方は社内の常識になっていませんか?
・営業職はハキハキ話すのが好ましい。
・大勢が賛成して決まりかけていることをひっくり返してはいけない。
・「わからない」時に堂々と「わからない」と言うヤツは困ったものだ。
・若輩者は意見を言わずに控えておれ。
・部下との関係を築くには誉めることから始めよ。
でも、こうした固定観念による常識に縛られていると、
人は自分らしくいられなくなり、本来の能力を発揮できません。
最初の3項目を例に、どんな常識が人を縛っているのか考えてみましょう。
営業職はハキハキ話すのが好ましい。
営業職がハキハキ話すのが好ましかった時代もあるでしょうね。
でも、今は「ハキハキ話す営業職」=「何かを売りつけたい営業職」
と見ている顧客の方が多いのではないでしょうか。
実は、営業される側は「ハキハキ話す営業職」なんて望んでいない場合も多い。
で、望みはシンプル。自分のことを親身に考えてくれる営業職を望んでいます。
なのに、会社はハキハキ話す営業職を育てようとする。
昭和的な金太郎飴営業職を育てようとするのは、ダイバーシティに反しませんか?
大勢が賛成して決まりかけていることをひっくり返してはいけない。
場のムードが賛成に偏っているときほど、反対意見は言いにくいものです。
でも、、、
CEOとしてゼネラル・エレクトリック(GE)を成功に導いたジャック・ウェルチは
当時、反対意見が出なければ、結論を出さなかったと言います。
反対意見を言う者は邪魔者と捉えるのとは大違いですよね。
反対意見を出せるムードのない状況はダイバーシティと言えるでしょうか?
「わからない」時に堂々と「わからない」と言うヤツは困ったものだ。
「わかりません」と発言することは、勇気がいること。
いまだ、そのような状況にあるのではないでしょうか。
でも、そこでわかったフリをしても、いいことはありません。
YESと言ったら、YES。NOと言ったら、NO。
わかったと言ったら、わかった。
グローバル化が進むと言うことは、
そう言うシンプルなコミュニケーションに向かうと言うことです。
それなのに、会社では「わかりません」と言いにくい状況がある。
この抑圧感、ダイバーシティとは対極にあるものですよね?
一人一人の心が感じている不自由を一度書き出してみて、
みんなでテーブルの上に出してみると、どうなるでしょうね?
みんなが「居心地が良い/悪い」を挙げて議論してみたら、
ダイバーシティは加速度的に進むと思います。
まずは自分の常識を疑うことから始めてみませんか?
今週も素敵な1週間でありますように!
「聞く」の本質
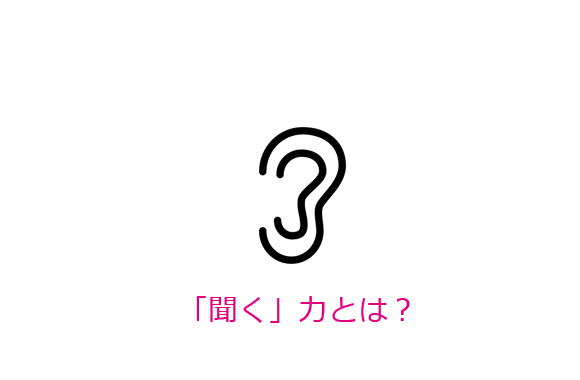
今日のメルマガで阿部が「書く」をテーマに書いています。
「書く」というトレーニングをせずに、レベルアップを図るコツについてです。
それに触発されたわけではありませんが、
ちょうど先週、私は「聞く」について、周りと意見交換する機会があり、
私自身も思うことがあったので、今日は「聞く」をテーマにしたいと思います。
あなたも、ヒアリングや打ち合わせで「聞く」ことはあるでしょうし、
仮に広報担当者であったなら、
記事を作成するために取材することもあるのではないでしょうか。
私たちも同様です。
さらに、会議ファシリテーションをする場合は、
参加者の議論がうまく運ぶように良い問いかけを行い、
参加者全員からバランス良く意見を「聞く」ことも仕事になります。
誰もが、「聞く」ことは仕事を進めるための重要事項であると認識していても、
「発問(質問)」でつまずくことや、
なんと聞いたらいいのかわからなくなることがありますよね。
これは、新人からベテランまで起きることです。
もちろん、そのつまずき度にはレベル差はあると思いますが。。。
これはなぜ起きるのでしょうか。
新人でもベテランでも共通するのは、
「聞く」ことの本質は理解することであるので、
耳で聞くだけでなく、自分の頭の中で、話を整理しながら聞こうとします。
話を聞いている間に、頭の中は情報でいっぱいになってきますが、
情報が入ってくるスピードに対し、整理するスピードが追いつかなくなると、
聞き手は次に何を聞くべきかがわからなくなっていきます。
私たちの取材セミナーでは、この状況を「迷子の状況」と呼んでいます。
話を整理しながら聞くというのはどういうことかというと、、、
これは、もうホントにすごいことをやっているわけですよ。
たとえば、、、重要度を区別しながら聞いていますし、
発した言葉の言外の意味も理解しようとして聞いています。
事実と推測も分けて聞いています。
さらには、話の要素同士の関係、たとえば因果関係や包含関係、
並列関係などを把握しながら聞いています。
またドラマ曲線や感情曲線をイメージしながら、
出来事や感情の高まりを理解しながら聞いています。
人間には本来そういう能力が備わっていますが、
誰もが最初から同じようにできるわけではありません。
また経験を積んでそのスキルが上がったとしても、
30分も話を聞くと、複雑な情報で頭はいっぱいいっぱいになっています。
いよいよ脳みそが追いつかなくなると、迷子になる。
ところが、この人は聞き上手だなと思う人を観察していると、
要所要所で「ちょっと整理させてください」と言って、
それまでに理解した内容を「つまり、こういうことですね」と
言語化していますね。
それは、お互いが迷子にならないためのコツなのだと思います。
見習いたいものですね。
一方で、若い時や経験の浅い時だから起きるつまずきもありますよね。
それは、問いを立てること自体が目的化してしまった場合に
起きがちなのではないでしょうか。
たとえば予め用意していた質問項目を上から順に聞いていったら、
あっというまに終わってしまい、時間が余ってしまって困ったとか、
質問をした直後に、相手の答えを聞く心の余裕もないまま、
次の質問をどうしよう...ということに意識が向かい、
結局質問の答えを聞くことに集中できなくなってしまったり。
話を「聞く」のは「理解するため」であるという本質を忘れて、
質問自体が目的化してしまうのには、
主に2つの理由があるような気がします。
1つは、そもそも「何を理解すべきか」がわかっていないということ。
わかっている必要があるという認識さえ持てていないこともあるかもしれません。
その認識がないと、自分が理解すべき事柄をわかっているかどうか、
セルフチェックさえできません。
もう1つは、聞き方に関する自分への評価を気にしてしまうということ。
うまく聞けなかったらどうしようという不安や、
話の間(沈黙)に対する恐怖、
良く思われたいという心理などが影響していると見られます。
理解することが求められているということを忘れてしまっている状態です。
でも、話を「聞く」のは「理解するため」です。
このシンプルな本質を忘れないこと、混乱したらそこに立ち戻ることが、
「聞く」ためのコツなのかもしれませんね。
どうぞ素敵な1週間をお過ごしください。
働いて笑おう! 〜コトをつくってヒトとつながるのがコツ?
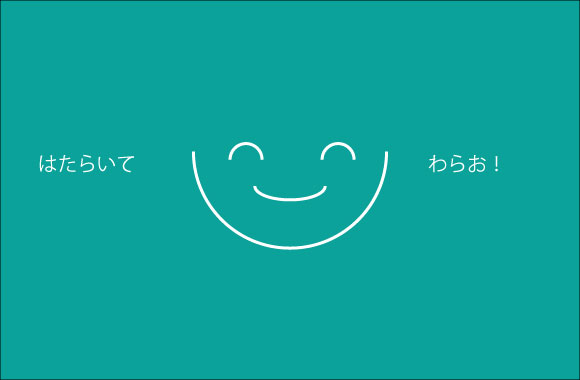
先日、表参道の駅構内で
PERSOLグループの広告「はたらいて笑おう。」というポスターを見かけました。
スティーブ・ジョブズとともにアップルを創業したエンジニア、
スティーブ・ウォズニアックと、
85歳の現役のファッションモデル、
カルメン・デロリフィチェが笑っている写真に、
「はたらいて笑おう。」というヘッドコピー。
とても素敵なコピーだし、魅力的な人選だと思いました。
働き方改革の必要性が叫ばれ、ブラック企業が問題視される中、
実際に、働いて笑っている人はどのくらいいるのでしょうか。
2013年のマイナビの記事によると、
仕事をしていて楽しいと感じている人は半分強(57.4%)でした。
1日8時間勤務とすれば、1日の3分の1以上を仕事に費やすのですから、
楽しみでありたいものです。
さて、仕事を楽しむということを少し脇に置いておくと、
人生を楽しむことについてはどうでしょう?
人生を「楽しもう」とするかしないかは、自分次第です。
私の周りには人生を楽しんでいるように見える人が多いです。
彼らの共通点は、ヒトとの関わりを大切にして、
コト(場といってもいい)をつくりだそうとしている点。
たとえば、ある友人は、ダンスサークルのような場をつくり、
サンバ、サルサと踊れるお店に定期的に繰り出しています。
また、ある友人はお互いにキッチンを解放しあって、
料理して食べるパーティーを始めました。
いずれの場にも、実は私も時々おじゃまを...笑
テーマやコンセプトを持って続けるような性格のものでない場合も、
口実を設けて、コト(場)をつくっている人が多いです。
気軽なところでは、ご飯のお誘いです。
「近メシ」という言葉があるように、
単なる社交辞令で使われる場合もあるようですが、
楽しんでいるように見える人は、必ず本当に連絡してくれます。
毎月1−2回誘われ、私も1−2回誘っているという感覚があります。
楽しむことに貪欲な彼ら彼女らは、コトに興味を持ったり、
コトでつながろうとしているように見えて、
実はヒトとつながろうとしているのかもしれません。
しかも、主体的に。
話を元に戻します。
私は、楽しんで働くためのヒントがそこにあるような気がするのです。
魅力的なヒトと仕事をすることは楽しいですし、
反対に、関係が良い状況にあると、自ずとヒトに魅力を感じたりもします。
たとえ協働して何かを達成し合う関係になかったとしても、です。
反対に、コトを面倒とか、敷居が高いと決めつけたり、
ヒトと距離を置いている方が楽だと決めつけていると、
もしかしたら自ら楽しむことを制限してしまっているかもしれません。
...と決めつけてかかるのも良くありませんし、
べき論を振りかざすつもりもありませんが。
人生を「楽しもう」とするかしないかは、自分次第であるように、
仕事を「楽しもう」とするかしないかも、自分次第ですね。
「はたらいて、笑おう。」
そんなふうに仕事と向き合えたらいいですね。
どうぞ素敵な1週間でありますように!
ダイバーシティの本質は「みんな同じをやめる」ということ

ゴールデンウィーク、みなさんはどうお過ごしでしたか?
私は、29日から7日までの9日間に、家飲みが4回あり.......
かなりアルコール度の高い休暇になりました(笑
せっかく減量してきたのに、1.5kgぐらい太った気がします(息
ほかにも、気になっていたキッチンの油汚れを落としたり、
両親と外食したり、
PLANプログラムで支援しているケニアの女の子に手紙を書いたり、
映画を見たり、、、とゆっくりしました。
さて、、、2週間ぶりのブログです。
だからこそ何を書こうかなと思ったのですが、
やっぱり連休の間に感じた話題について書こうかな。
それは、ちょっとマジメに言うと「多様性」についてです。
ゴールデンウィーク中に「TOKYO RAINBOW PRIDE(東京レインボープライド)」が開催されました。
これは、主催者のホームページによると、
「性的指向や性自認(SOGI=Sexual Orientation, Gender Identity)の
いかんにかかわらず、差別や偏見にさらされることなく、より自分らしく、
各個人が幸せを追求していくことができる社会の実現を目指すイベント」です。
因みにレインボーカラーは多様性を表すLGBTのシンボリックカラーです。
さらにおさらいしておくと、LGBTというのは、レズビアン(L)、ゲイ(G)、
バイセクシャル(B)、トランスジェンダー(T)などセクシュアリティのことです。
イベントの詳細について、私はそれほど詳しく知っているとは言えませんが、
昨日7日にはパレードが行われました。
私の知り合いの中にもパレードに参加している人たちがいます。
が、世間的にはどのくらいの人がそのイベントを知っているのでしょうか...?
でも、企業にいて、インターナルコミュニケーションや
HRやCSRに関わっている皆さんは、
その状況についてしっかりキャッチアップしておく必要がありますよね。
さらに、経営者はなおさらそこにアンテナを張っておかないと、
時代錯誤な経営になりかねません。
なぜなら、LGBTは特殊な人たちではない.....
これが世界的な認識になっているからです。
電通の調査結果(2015)によるとLGBTの人の割合は7.6%。
左利き、AB型の人と同じくらいの割合だそうです。
GWに我が家に来ていた友人の一人は高校教員ですが、
高校でもトランスジェンダーの生徒の対応で
(たとえばトイレをどうするかなどについて)議論が行われているそうです。
「今まで表に出ていなかったものが、表に出ているだけだ」と彼女は言います。
G7諸国のなかで同性婚、同性パートナーシップに関する法律を制定していないのは、
日本だけ。この遅れ、情報不足→認識不足→関心不足→政治の遅れなんでしょうね。
でも、キャッチアップして先行している企業もあります。
「TOKYO RAINBOW PRIDE(東京レインボープライド)」では、
そうそうたる大手企業が協賛し参加しています。
http://tokyorainbowpride.com
YAHOO!、NTT、アクセンチュア
ソニー、東急電鉄、ビームス
丸井、ジョンソン&ジョンソン、mixi
JT、GAP、LUSH.....他
また、配偶者がいる場合の制度を、
同性のパートナーがいる社員にも拡充した例も、
ゴールドマンサックス、日本IBM、日本マイクロソフト、
第一生命、ソニー、パナソニック、損保ジャパン日本興亜などで見られます。
こうした企業に対し、
特に若い消費者は「進んでいる」と見ますよね。
企業の方も、「遅れていると思われて、採用活動や販売に影響が出ては困る」
という計算もあるでしょうし、
経営の意思として、社員向けメッセージに使っている場合もあることでしょう。
さて、、、
私がここでお伝えしたいことは、LGBTを認めることも大切。
でも、それ以上に重要なのは、
「ダイバーシティ」は誰にとっても関係あるということです。
最近は「ダイバーシティ」という言葉が独り歩きしていますが、
本来は「Diversity & Inclusion」といって、「多様性の受容」を意味します。
「多様性の受容」という発想の中には、当然LGBTも含まれてきますが、
そもそも一人一人の人間は違う人間であり、
それを俯瞰してみたら「なんと、まぁ多様なことか、、、」と。
だからこそ、そこに目を向けてリスペクトし合い、
違いを超えて何かを生み出すことに価値があり、豊かさがある......
そんな考え方が「ダイバーシティ」の本質ではないでしょうか。
と同時に、企業が「ダイバーシティ」を語る場合は
それがグローバル戦略上不可欠だという視点があるのも当然です。
だから、逆にそれが、「会社が言っているだけ」と
思ってしまう状況を生み出している場合もあるかもしれません。
でも、実際には誰にとっても関係があります。
たとえば「多様性」の反対の概念にはどのようなものがあるでしょうか?
「同質性」「均質性」「画一性」という言葉もありますね。
他にも、「和」「集団行動」「あうんの呼吸」等も対極にある言葉かもしれません。
日本社会にある「人と同じように」「人との和を乱さないように」と
対極にある概念が「多様性の受容」です。
私は、「人と同じように」「人との和を乱さないように」という考え方が、
私たちを縛り、人の顔色を伺って、意見を言わない社会をつくっていると思うので、
むしろ人の和を乱すことを恐れずに、
自分の意見や気持ちを出せる人が大勢いる社会になってほしいです。
そして、そうでありながらも、お互いが相手を論破しようとするのではなく、
相互にalignmentを取ろうとするような社会になってほしいです。
それが実現できたとき、なんと自由で豊かな社会であることか!
抑圧から人を解放する、そんなダイバーシティが進んでほしいものです。
さて、今週は新緑を味わいながら、グリーンな気持ちでいきたいですね!
素敵な1週間をお過ごしください。



