言葉の壁(2)〜言葉を変えると「責任」への自覚が変わる
桜、きれいですね。
竹内まりやの「人生の扉」という曲に、こんな一節があります。
満開の桜や色づく山の紅葉を
この先いったい何度 見ることになるだろう
今日も、メルマガの内容を紹介します。
ーーーーーここからです!ーーーーー
NVCを考える本シリーズ「言葉の壁」の第1回だった前回は、
気持ちのいいコミュニケーションをするためには、
「評価」ではなく「観察」に基づく表現が大切だということをお伝えしました。
(※NVC=Nonviolent Communication by マーシャル・B・ローゼンバーグ)
今日は「責任逃れ」や「逃避」の意識がもたらす言葉表現が、
気持ちの悪いコミュニケーションを生み出す...というテーマで考えていきましょう。
「責任逃れ」とは、自分に責任が降り掛からないように、避けること。
「逃避」とは、しなくてはならない物事から意図的に注意や意識を逸らすこと。
本来なら、政治家の答弁のような言動を例に挙げるのが、
もっともわかりやすいのかもしれません。
けれど、、、
「それは私のせいじゃないから...」とか、
「何も私がやらなくてもいいんじゃない?」というような心の動きが
チラリと出てしまうシーン、実は身の回りにたくさんあるのではないでしょうか。
しかも、チラリだからこそ、そう伝えられると、すっきりしない気分になります。
たとえば、ここにAからHまで8つの台詞があります。
いずれも、自分の責任を回避したいニュアンスを感じますよね。
しかも、責任といったって、大きな責任問題ではない。
それぞれの台詞はいったい何のせい、誰のせいにしているのでしょう?
A「それをやるには、いろいろと無理が生じる」
B「誘われたので、行こうと思います」
C「上司に勧められて、参加しました」
D「これは就業規則違反だから、始末書を書きなさい」
E「管理職だから部下の査定をやらないわけにいかない」
F「衝動に負けて食べちゃった」
G「みんなが行くというので、断れなかった」
H「飲み会が嫌いなのは、シャイな性格だからです」
食事に行って、メニュー選びのときに、
「食べ物の好き嫌いはないから、合わせるよ」
なーんていうのも、ちょっとした責任回避かもしれませんね。
責任回避の言動にはいくつかのパターンがあるそうです。
上の例で考えると;
A:あいまいで、誰のものでもない力のせいにする。
B:他人の行動のせいにする。
C:権威からの命令や推薦のせいにする。
D:組織の方針や規則のせいにする。
E:役割のせいにする。(男として、母としてなども含む)
F:衝動のせいにして、抑制がきかないのはやむを得ないとする。
G:集団の圧力のせいにする。
H:自分の状態や診断、育った環境や病歴のせいにする。
ある、ある、と思いませんでしたか?
私たち人間は、自分の行動を誰かから咎められたくないという
防衛本能が無意識に働く動物のようです。
でも、本当はシンプルに自問すればいいはず。
やりたいの? やりたくないの?
行きたいの? 行きたくないの?
参加したいの? 参加したくないの?
もちろん、こういうことに目くじらを立てなくても、
日常生活は成り立つし、それほど他人との関係が悪くなるとは思えません。
でも、ローゼンバーグ氏はこう書いています。
「心の底からの訴えを遠ざけてしまうコミュニケーションを実践すると、
自分の思考や感情、行動の責任は、
ほかでもない自分自身になるのだという自覚があいまいになる。」
そうなんですよね。
言葉の使い方が思考のクセをつくりだすから放ってはおけないのです。
さ、今週は4月に突入! 桜も満開です。
どうぞ良い1週間を!
ソリューション業界はサービス業である...という話
今年の3月19日付け日経ビジネスに、蛯谷敏氏が「10年後に残る仕事、消える仕事〜働き方の未来についての身も蓋もない結論」と題して、記事を掲載していました。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20150317/278810/?P=1
その内容は、技術革新によって、雇用がどう変化するのかという大テーマの下、氏が属するマスメディア業界で10年後にも残るのは、2つのカテゴリー。すなわち、新しい企画を生み出し、それを自分の手で形にできる「クリエイティブ」という上流工程と、それを読者に手渡すための出口工程「営業」なのではないか、というものでした。この意見自体には「そうかもしれないなあ」という感覚で読んだのですが、何かこう収まりの悪い感覚が残ったのも事実でした。「クリエイティブ」工程は、「クリエイティブ」というだけの理由で、残れるのか?という疑問があったのです。
そんな折、偶然にもあるクライアントの案件で、その企業のお客様にインタビューする機会をいただきました。インタビューのテーマは、なぜコンペでその企業(私どものお客様企業)を採用したか、についてでした。具体的にどういう内容だったかは書きませんが、「クリエイティブ」工程という面でも、「ソリューション業界」という面でも、普遍的なことではないかと思える結論が出てきました。それは、提案内容が重要であることもさることながら、《問題解決に寄り添ってくれる姿勢があるかどうか》が重要だということ。どんなに素晴らしい提案であったとしても、相手からすると、《こうあるべき》というように正論を振りかざされたくない、ということだとも言えます。
これは、どのような問題を提起しているのでしょうか。私は、「サービス」という視点を直視せざるをえない、そんな視点が提示されたと考えています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
企業が提供する大多数の「サービス」は、
何らかの問題を解決する「ソリューション」である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これを逆説的に言うと、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
企業が提供する大多数の「ソリューション」は、
「サービス」である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ということになります。「ソリューション」すなわち「問題解決策」は、つまるところ「サービス」なのです。ところが、ソリューションを提供する側は、意外にこの点を忘れてしまいがちなのではないか、と私は感じます。それを忘れてしまうために、どういうことが起きるかというと、
・ソリューションを提供できる「権威者」であるように振る舞ってしまう。
・自分たちの考えを「べき論」で提案することが良いことだと錯覚する。
でも、お客様は必ずしもそういうことを望んでいるわけではないんですね。なのに、ソリューションを提供する側は、そのように振る舞うことで、自分たちの存在価値が上がるのではないかと勘違いする。その反対の行動をすることは「イエスマン」でしかないと思い込んでいるのかもしれません。
「サービスマン」としての自覚なくして、満足度の高い「ソリューション」は提供できない。そのことに、私たちは気づくべきだと思います。
そのような考えから、私は、初めてのお客様とはしっかり「会話する」ことを重んじています。具体的にどういうことかといえば、「効率」や「スピード」は二の次で良いと考えています。むしろ、「効率」や「スピード」を初期段階で追求するのは、「違う」と思っています。10頼んだのに、20考えてくれたという関係をつくること。思いに添うだけでなく、思いに着火させていくこと。もっとできる、もっと成果は出せるというイメージをクライアントと共有すること。そうしたことが、ソリューションプロバイダー(=サービスプロバイダー)の私たちにとっては、とても重要だと思っています。
グラスルーツでは、今、採用活動を行っていますが、スキル以上に、こういった価値観に共感してくれる方を求めています。ご興味がありましたら、こちらをご覧ください。
最後は採用の話になりましたが、当社の姿勢を知っていただきたくて書きました。サービス業という自覚で、グラスルーツは立っています。これからも、ずっと! 今後ともよろしくお願いします!
言葉の壁(1)〜言葉の暴力
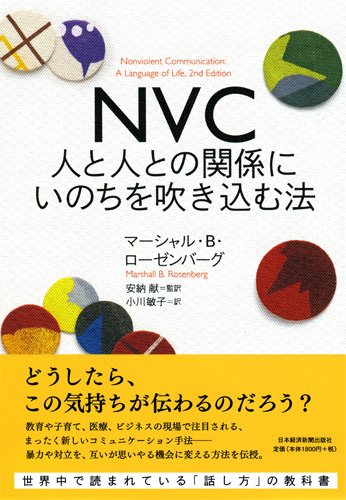
今日のブログは、今日配信のメルマガの内容を紹介します。
でも、その前に、メルマガの内容にあるNVC(Nonviolent Communication)に関する書籍を紹介しますね。アマゾンでの星の数は、4.5と好評です。
私たちは、とかく自分のネガティブな感情を隠そうとしたり、飲み込んでしまったりします。また、相手への願いや要求を素直に言えないことも多いのではないでしょうか。
この本をお勧めしたいのは、ここに書かれていることが、単なる小手先のテクニックではなく、人と人が良い関係をつくるための原理原則だからです。
タイトル:「NVC 人と人との関係にいのちを吹き込む法」
著者:マーシャル・B・ローゼンバーグ
http://www.amazon.co.jp/dp/4532318106
メルマガにも書きましたが、1対1の対面コミュニケーション(話し言葉)においても、1対Nのコミュニケーション(書き言葉)においても、有効な考え方だと思いますので、ご興味がありましたら、ぜひ読んでみてください。
ーーーーーーーーー↓メルマガここから↓ーーーーーーーーー
「言葉の暴力」と聞くと、まずパワハラやセクハラなどを思い出しますよね。
でも、マーシャル・B・ローゼンバーグは、
人の心を傷つけるコミュニケーションを暴力的ととらえ、
人を思いやるコミュニケーションを指して、
非暴力的コミュニケーションと呼んでいます。
つまり、パワハラやセクハラはもちろんですが、
他者への尊敬や愛を持たずに、
利己的で、偏見や疑いを抱いて接する
「イヤな感じ」のコミュニケーションは、
すべて暴力的だということになります。
NVC(Nonviolent Communication)と呼ばれるこの考え方、
私は、書き言葉でも話し言葉でも有効だと思っています。
そこで、今日から何回かにわたって、NVCという視点から
「言葉」と「コミュニケーション」というものについて考えていきましょう。
さて、次の5つの例で、AとBの2つの言葉を比べてください。
それぞれ、言われたら、どう感じると思いますか?
A同士、B同士は、ある共通点があります。何でしょう?
例1
A「あなたは、プロとしての知識欲に乏しい」
B「あなたは、専門書を読んだことがないと言った」
例2
A「あなたは、彼のお気に入りだ」
B「彼が『あなたに期待している』と言うのを聞いた」
例3
A「あなたは、働き過ぎだ」
B「あなたは、今週9時より前に帰ったことがない」
例4
A「彼は、会議の間、私を無視した」
B「彼は、会議の場で、私に意見を求めなかった」
例5
A「あなたの会議での発言は、いつも敵対的だ」
B「今日、あなたの発言の多くは『しかし』で始まっていた」
Aがしている行為は、すべて「評価」であるのに対し、
Bがしている行為は、「観察」です。
人は、「評価」を含んだ言葉を向けられると、
身構えてしまったり、防衛反応を示したり、反撃したくなったり...。
誰しも、心当たりがあるように、
関係が悪い方へ進む反応を生み出してしまうのですね。
共感されるコミュニケーションの大原則のその1は
評価判断を交えずに、観察に基づいて伝えることにあります。
確かに、人が、何かを評価判断するときって、
攻撃、嫉妬、非難、嫌悪、不満などの
ねじ曲がった感情が織り交ぜられていることが多いですよね。
しかも、そのことに無自覚なケースも少なくありません。
...と、自分のことを棚に上げて書いていますが、
いや〜、言うは容易く、行うは難し。
解説するのと、実践するのは大違いですが、
自分の言葉を聞きながら、チェックしてみる、
そんなトレーニングをして鍛えたいものです。
では、良い1週間をお過ごしください!
※読んでいただき、ありがとうございました。
よろしければ、「読んだよ!」クリックしてくださいね。
言葉は「窓」にもなれば、「壁」にもなるんですね。

「好奇心」が発揮できる組織とは?

「ヤフーの人事部はスゴいらしい!」。
ある人が「日本の人事部」に掲載されていたヤフーの執行役員・本間浩輔さんのインタビュー記事を教えてくれました。
前編 https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/1140/
後編 https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/1142/
本間さんは、2012年にヤフーの人事部のトップに就いて以降、社員がお互いにフィードバックする風土づくりや人事制度の改革などを、圧倒的なスピードで推進したことで知られています。今回読んだインタビュー記事を読みながら、人の活力やエネルギーはどうすると生まれてくるのか、そんなことを考えました。
興味深いことに、本間さんは元々は人事畑の方ではありません。インタビューの冒頭で、野村総研時代に「戦略で組織は動かない」ことを実感したことや、その後、心理学や経営学を学び直したとあり、その経験が組織観や人材観に影響を与えたことが窺われます。
とても面白かったのは、従来の目標管理制度に一石を投じ、「才能と情熱を解き放つ」組織に変えようとしたことです。こんな発言がありました。
以前の目標管理制度は、メディアでも紹介され、良いものであると評判でした。ただ、その運用を考えると、本当にそうだったのかどうかは疑問が残ります。社員は目標を見て、本当にその通りに動いているのか。逆に、組織に必要であっても、目標に入れていない仕事はしないということはなかったか。目標管理制度においては、活用の仕方を間違えると、フリーライダー(ただ乗りする人)が発生します。そういう運用面での弊害がたくさんありました。
(中略)
状況が変われば目標もそれに応じて変わります。その点からも、自分の目標ややるべき仕事を全て目標管理制度のシートに書き込むという概念が、そもそも間違っていると考えました。だから、いまやらなくてはならない重要な仕事を一つ、二つ書けばいいとしたのです。
戦略で組織は動かないとしたら、人はなぜ動くのか、どうすると動くのか、本間さんはそれを考え続けている。この記事にその答えは明確には書かれていませんでしたし、本間さんは、今なお、それを問い続けているのかもしれません。
ですから、ここから先は推測です。
本間さんは、好きかどうかもわからない仕事の中で目標を掲げても、必ずしも才能と情熱には直結しないと考えているのではないでしょうか。
というのは、先々週(2月23日)のブログで紹介した書籍「仕事は楽しいかね?」の中にも、「多くの人は、自分がどんな仕事が大好きか、わからない」というようなことが書かれていましたが、実際そうなのではないかと私も思います。つまり、この仕事がある程度好きという人は大勢いると思いますが、これこそが天職だと思えている人はむしろ多くないと思います。
そのような人にとって、目標は大切だけど、たとえば状況が変化して、何かプロジェクトが立ち上がりそうになったとき、すかさず「やりたい!」と手を挙げるには、むしろ目標が邪魔になったりすることがあります。ですから、目標にがんじがらめになるよりも、好奇心や意欲が湧いてくることに向かって行ける流動性を重んじる、そんな考え方があったのではないかと想像しました。
もちろん、想像したのには訳があって、本間さんのキャリアに関する考え方の基礎となったのは、「計画された偶発性理論(プランド ハップンスタンス セオリー/Planned Happenstance Theory)」だそうだからです。この理論は、1999年にスタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ教授によって発表されたもので、キャリアの8割が予期しない出来事や偶然の出会いによって決定されるとし、だからこそ、その偶然を意図的に生み出すような行動を取ることを考えるべきだ...というような理論です。そのためには、「好奇心」「持続性」「楽観性」「柔軟性」「冒険心」を持って行動することが大切だとされているのです。
つまり、自分の道を拓き、幸福になるためのキャリア形成には、これら5つの要素が必要だと考えるなら、「好奇心」や「柔軟性」「冒険心」を持って仕事をできるようにする制度が必要だと考えたのではないか。まあ、あくまで推測ですが、そのように想像してみることは楽しい体験でした。
会社の制度がどうであれ、仕事であれ、プライベートであれ、好奇心をもって暮らしたいものですね。3月も第2週目です。素敵な1週間でありますように!
安直な『ポジティブ・シンキング』はいらない
今日は、メルマガの紹介を兼ねて、今日配信のメルマガをそのまま掲載します。というのは、前回ブログで紹介した内容とも関わりが深いからです。
メルマガのコンセプトは「視点発見」。リーダーや社内のコミュニケーションをよくする立場にある方に対し、ご自身の考えを深める糸口を提供できればというスタンスで綴っています。そういう意味では、直接的なノウハウ提供という色合いは濃くありません。今日のメルマガは、題して「安直な『ポジティブ・シンキング』はいらない」。一見前向きに聞こえる振る舞いの中にも、単に安直な行動というのがあるのではないか、という問題提起です。「読んだよ!」クリックの先にあるコンテンツも、好評です!
お申し込みは、こちらからお願いします!
ー ー ー ー ここから ー ー ー ー
私はメルマガ以外に、ブログも毎週書いているのですが、
先週のブログで「仕事は楽しいかね?」という書籍を紹介しました。
https://www.grassroots.co.jp/blog/monolog/2015/02/150223.html
この書籍は、物事を成功させるために、目標から逆算して計画を立てるのではなく、
『遊び感覚でいろいろやって、成り行きを見守る』
『試してみることに失敗はない』
...を推奨するもので、それは私の人生観とも共通点があると書きました。
しかし、、、、
今日は一読すると真逆とも思われそうなことを書かせていただきます。
一般的な意味での「ポジティブ・シンキング」へのアンチテーゼとして。
言い換えると、「とにかく、やってみる」とか、
「今までこうやって乗り越えて来たから、きっと大丈夫...」など、
前向きな姿勢であるというだけで、美化するのは考えものだという視点からです。
「ポジティブシンキング」といっても、定義は曖昧ですが、
一般的な解釈としては、こんな感じ↓ではないでしょうか。
「難しい」「大変」「無理」「どうせ」とネガティブに考えずに、
前向きな姿勢で物事に取り組む、あるいは
逆境に直面しても、それはチャンスだと捉える...
「ポジティブシンキング」とは、そのように前向きに考える姿勢そのもの。
もちろん、行動しなければならない時に、
考えすぎてしまって、足がすくみ、一歩前に踏み出せない人に
「とにかく、やってみようよ」と励ますことは必要かもしれません。
また、何かを決断しなければならない時に、
「今までこうやって乗り越えて来たから、きっと大丈夫...」と
自己暗示をかければ、決断できることがあるのも事実だと思います。
でも、そういう発想を頼みにしている人に限って、
考えることを放棄していることが多いような気がするのです。
人間には想像力があり、
「どうしたら、より上手くできるか」を考える能力がある。なのに、
「とにかく、やってみよう」だけで始めてしまうのは、なぜなのでしょうか。
「どうしたら、より上手くできるか」というのは、仮説を持つとイコールですが、
「とにかく、やってみよう」で始める人には、仮説がありません。
言い換えると、「意図」もなく、行動しているにすぎません。
なのに、それを「行動力がある」といって賞賛するのは、
私は、違うなと思います。あなたは、どう思いますか?
また、新しいことを始める時や大きな選択をする時、
「今までこうやって乗り越えて来たから、きっと大丈夫...」だと思うことは、
私にもあります。自己暗示として有効だからです。
でも、それだけでなく「もっと良い方法はないか」とか
「今、変えるべきことがあるとしたら、それは何なのだろう?」
と考える方が、より良い方向へ変わって行けます。
もし、過去を否定する(=自分を否定する)のがイヤだから、
「今までこうやって乗り越えて来た」と肯定しているなら、
より良い方向に変えて行くことはできませんよね。
で、それが本当に成功体験だったとしても、
それにしがみついているだけだったとしたら、
それはポジティブシンキングでもなんでもないと思います。
どうせチャレンジするなら、ただ闇雲にするのではなく、
クレバーなチャレンジをしたいじゃないですか。
どうやったら上手くいくのか、
自分の思考が過去の経験にとらわれすぎていないか、
ちょっと考えてみる。ちょっとで、いい。
考えすぎる必要はない。
【Think】して【Try】する。
そのバランスが、実はとても重要な気がします。
※読んでいただきありがとうございました。
よろしければ、【読んだよ!】クリックしてくださいね。

成功しても、成功に甘んじることなく、「もっと」という感覚を持ち続けた
松下幸之助さんの言葉に学びませう。



