子どもたちに自分の仕事をどう語る?
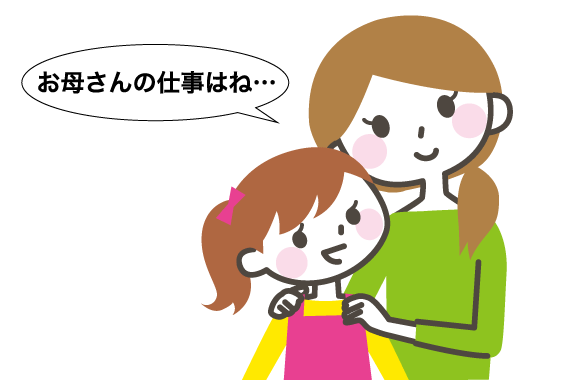
先月のことになりますが、
私たちグラスルーツは伝える仕事の面白さを届けたいという思いから
2つの小学校のサマースクールにエントリーし、
「お友だちをプロデュースしよう!」
「いろいろな題をつけて遊ぼう!」という子ども向け特別授業を開講しました。
当社のスタッフの子どもさんたちが通う小学校での開催です。
先生役は当社のスタッフ、子どもさんたちから見ればお父さん・お母さんです。
(詳細は、こちらをご覧ください)
参加した小学生たちの反応は上々で、友だちに質問するのが楽しかった、とか、
ほかの人は自分とは全然違うことを感じていることがわかって面白かった、など、
何かしら楽しい発見をしてくれたようです。
さて、先生役を担った二人との会話で、
普段、家で自分の仕事をどう子どもに説明しているか
ということが話題に登りました。
一人はわかりやすさ優先で「本を作っている」と語っているそうで、
もう一人は「働く人が元気になるための仕事をしている」と言っているそうです。
子どもにとって、前者は働く姿が目に浮かび、後者は大切な仕事なんだなと感じる、
そんな違いがある気がします。
いずれにしても、良くはわからないなりに、
子どもたちはちょっと誇らしいかもしれませんね(笑
私が小学生の頃、働く父親の姿を絵に描くという授業がありました。
ところが、どんな仕事をしているのか、父に聞けども聞けどもわからず。。。
当時、父は、国の地質系研究所のようなところに勤めていましたが、
何のための仕事なのかも、何をする仕事なのかも私にはわからず、
それでは絵が描けないので、
結局「周りにはこんなキカイがたくさんある」という絵を父に描いてもらって、
それを書き写したような記憶があります。
見たこともないので、私にはただの箱にしか見えませんでしたが(笑
自分の子どもに自分の仕事をどう説明するのかは、とても重要だと思いますが、
それは子どもに対してだけではありませんよね。
特に、自分自身のアイデンティティにとって最も重要である気がします。
その有名な例えが、レンガ職人の話ですよね。
「ここで何をしているのか」と問われて、
「レンガを積んでいる」と答えるのか、
「人々のために教会を作っている」と答えるのか。
では、実際の私たちは、自分の仕事をどんなふうに人に伝えているのでしょうか?
話す相手と状況によって、いやむしろ多くの場合、
「〜のために」の部分は語らなかったりしますよね。
たとえば学生時代の友だちから、「どんな仕事をしてるのか?」と聞かれたら、
「○○○の営業をやっている」とか、
「○○○会社の人事部にいる」と答えることの方が多いのではないでしょうか。
なぜならこの手の質問で相手が期待する答えはWhatであって、
Whyではないと思っているからです。
あるいは、下手にWhyを語ると、面倒くさいヤツだと思われる...と思っていたり(笑
でも、、、、ふとこんなことを思いました。
それは、自分の仕事へのこだわりをシンプルに語る言葉の準備が
不十分だということかもしれない、と。
たくさんの言葉を尽くせばWhatもWhyも話せますが、
シンプルに、子どもにもわかるような平易な言葉で、
ズバリ語ることは結構難しいものです。
そもそも自分の考えをそぎ落とすのが難しい上に、それができたとしても、
次は相手側の言葉で表現する必要があり、これまた難しいからです。
自分の仕事を人に(子どもにも!)わかりやすく、説明できるようになること。
それは、きっと自分の思考整理にもつながるのでしょうね。
あなたは、自分の仕事を子ども向けに説明するなら、どう説明しますか?
涼しくなってきましたね。どうぞ素敵な1週間を!
「場」は無言で物語る

私事で恐縮ですが、ここ最近、病院に入院していた母が退院後に入居する
介護付き老人ホームを探していました。
おかげさまで短期間で良いホームを見つけることができ、
既に本人は無事入居しています。
同時期に複数の施設を見学したり、いくつかの役所を訪ねたり、
病院の方たちと相談するという体験を通じて感じたことがあります。
それは、「場」というのは、無言でいろいろなことを物語るものだ、
ということです。
人と接する中で、何かを感じることはもちろんありますよね。
でも、面談などの形で人と接するよりも前に、
その場に醸し出されている空気を感じることはありませんか?
「カラー」と言ってもいいかもしれません。
なんとなくザワザワしていて落ち着かない感じの場。
静かできれいで、落ち着いているけれど、魂が感じられない場。
訪問している間に、自分の気持ちが滅入ってくるような場。
働く人たちが良いオーラを出している場。
反対に働く人たちの気が良くないと感じられる場。
どんなことからそう感じるのかを一言で言うことはできませんが、
多くの場合、そこに足を踏み入れてから、数分のうちに、
何かを感じ取っていたような気がします。
この行動、家のポストに入っていたDMやチラシを見て、
瞬時に読むか読まないかを判断するのと似ているかもしれません。
人間の感覚は本当に鋭いと思います。
私たちは、いったい何をどう判断しているんでしょう?
その場のインテリアや照明の影響もありますが、それだけではない。
私は、人の心の状態や人が刻んだ軌跡と関係があるような気がします。
最初は直感的に感じるだけですが、
その直感に基づいて、質問などを投げかけていくと、
やっぱり!と思うことも多々ありました。
たとえば、昨年完成したというある施設は、とても新しく、
建物もとてもきれいで、ハードウェア的には快適に過ごせそうな印象がありました。
でも、人影がまばら。よく言えば落ち着いている印象なのですが、
いまひとつ人の温もりや気配が感じられません。
もしかして、人で不足...?
「まあ、この業界はどこも人で不足ですから、その辺はご容赦ください」と
営業担当者。
では、どこもこんな感じなの...?
そこで、仲介会社の人に尋ねてみたら、
案の定、入居者3人に対し介護・看護職員が1人の割合の施設であるとのこと。
この数字自体は法律的には問題ありませんが、
入居者2.5人に対し1人の割合の施設に比べると違いがあるそうです。
やっぱり...。
結局、私が母の入居先に決めたのは、
見学している時にスタッフの方が挨拶や声がけをしてくれた施設です。
廊下にはスタッフ全員の顔写真が飾ってありました。
私がこの施設に決めたのは単に「挨拶をしてくれたから」ではなく、
働いている人たちから感じられるオーラが良かったからです。
その印象通り、施設の営業担当者から「正社員比率が高い」
「資格取得を奨励していて、半数が資格取得者である」
「定着率がよく、5年以上勤めている人が多い」という説明を聞き、
私が最初に感じたことは、こうした話と無関係ではないと思いました。
しかも、介護・看護職員の割合は、入居者2人に対し1人の施設でした。
あくまで解釈ですが、人を大切にする経営思想が根底にあり、
それがスタッフのエンゲージメントにつながり、
場に良い空気を生み出しているのだろうなと、そんな想像までしてしまいました。
実はこの体験、今回母が入院していた病院でも感じたことです。
こちらは、「場」というよりも、「人」の方かもしれませんが、
全体的にとても人当たりが良く、ハートが感じられる病院でした。
たくさんの具体的なエピソードがありますが、長くなるので省きますね。
84歳の母は、ここ10年ぐらいの間にいくつかの病院に入院しているのですが、
病院にもカラーがあるものだと痛感します。
中にはあまりに事務的で、ケンカしそうになった病院もあります(笑
今回の入院先の病院は、きっとしっかりした経営理念や経営思想があり、
それが末端まで浸透していたに違いありません。
「場」にもれ出る何か。
それは何なのでしょうか?
しかも、そこにいる当事者たちは無自覚なのに、相手は感じ取っている。
反対の立場に立ってみると、、、、きゃ〜 コワイ!
うちの会社に漏れ出ているのは、どんなことだろう?
そんなふうに外からの目線に立って、自社を振り返ってみるのも、
時には必要かもしれませんね。
あっという間に9月中旬です。
まずは今日を大切に過ごすことからですね! どうぞ素敵な1週間を〜



