ダメだよ、スパイダーマン!
アメリカンヒーロー映画、お好きですか?
私は、マニアではありませんが、あのお約束的な痛快さが好きで、
シルバーウィークには、まだ観ていなかった
「アイアンマン」「スパイダーマン」を堪能しました。
あの手の映画には、意外に名台詞があるんですよね。
たとえば、「一人の人間でも世の中を変えることができる」とか。
単純な私は、そっか〜!と思ってしまいます。
で、トビー・マグワイアが主人公ピーターに扮する「スパイダーマン3」。
本筋ではないのですが、あるシーンが妙に気になりました。
「ダメだよ、スパイダーマン!」と。
主人公ピーター・パーカーと、ヒロインのMJことメリージェーンが会話する
心のすれ違いのシーンです。
舞台女優になるという夢を叶えたMJは、
ある芝居で主役の座を獲得しますが、その演技を酷評されてしまいます。
辛い気持ちを聞いてほしくて、ピーターの部屋を訪れたMJですが、
ピーターからこんなことを言われます。
「ボクが言いたいのは、落ち込むなってこと。
自分を信じて、前向きになるんだよ!
君は少し、打たれ強くならないと・・・」
そう言われたMJは、
「気休めを言わないで! 私の気持ちもわかって!」と
言い返します。
ピーターの言葉は、MJを励まそうとして出てきたものです。
(ちょっと調子に乗ってしまっている面もありますけど)
でも、私はMJに共感しました。
そして、MJが言われたかったのは、そんなことじゃない、と思いました。
ただ、自分の気持ちを汲み取って、それを代弁してほしかったのではないか、と。
「好き勝手なことを言われては、辛いよね」とか、
「酷いことを言うな。気が休まらないね」とか。
さて、この映画を観た翌々日、
現実の世界で同じことが起きました。
私は友人と二人で、病気療養中の友だちのお見舞いに行ったのですが、
一緒にお見舞いに行った友だちが励ましの言葉を贈りました。
それは、今、必要だろうか。
私は、違和感を覚えましたが、
励ましたいと思ったその人の気持ちを咎めるのも違うなと思います。
その気持ちは私も一緒だったので。
世の中には、「励ましの言葉」を求める風潮もあります。
「励ましの言葉」を発信するTwitterもあれば、
相田みつをの言葉が必要とされていたり。
でも、「励ましの言葉」ほどタイミングが重要です。
心が下向きの時に言われると、わかってもらえないと感じます。
心が上向きになってきた時に聞いて、はじめて励ましが勇気づけになるんですよね。
心が下向きの時は、ただただ「わかってくれている」ことを感じたい、
それが真理なのではないでしょうか。
でも、、、
実は、私もよくやっちゃうのです。
まちがったタイミングでの、励まし、アドバイス、同調という名目での経験談語り。
相手が辛い状況にあると聞いた時、人が取る代表的な行動って、
次の4つではないでしょうか。
・「がんばれ」「大丈夫」と励ます
・「〜したら?」とアドバイスする
・「わかるよ」と言いながら、自分の経験を話してしまう
・どう反応していいかわからず、沈黙している
根拠ない私の推測では、8割ぐらいの人は
こんなふうに行動してしまうような気がします。
でも、実際に相手が望んでいるのは「辛いね」の一言だったりするのですよね。
アドバイスする人より、「辛いね」の一言を言える人になりたいもの。
スパイダーマンが「僕はまだダメだ」とメイ叔母さんに言った時、
彼女はこう言います。
「一番難しいことをしなさい。自分自身を許すの」。
できていないことに気づきながら、進歩していきたいものですね。
今週は、10月に突入しますね。
よい1週間をお送りください!
私たちはまだまだ成長できる...という脳科学の話
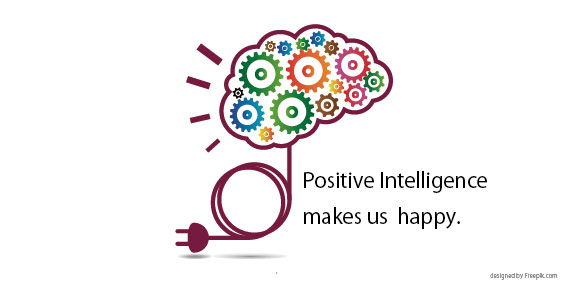
人の脳の成長は、12歳までに100%完了する...とよく聞きます。
だから、大人になったら、スキルや経験を重ねることによって成長するものだ、
と多くの人は思っているのではないでしょうか。
ところが、最近、成長に関する新たな知見に出会いました。
人の脳はまだまだ活性化できるし、それによって成長できるという脳科学の話です。
「ポジティブ・インテリジェンス」という脳の働きをご存知でしたか?
心の状態がポジティブなのか、ネガティブなのかで、
成果も成長も幸福度も変わりますが、
それは脳の働きと密接に関わっているそうです。
しかも、その脳の働きは大人になった今でも、簡単に活性化できるのだそう。
なんと、21日間で!
私がこう書いても、まったく説得力がないどころか、
なんだか怪しく、うさんくさい話に聞こえますよね。
大丈夫です、高価な教材を売りつけたりしませんから(笑)
情報源は次の本です。
「スタンフォード大学の超人気講座
〜実力を100%発揮する方法」
(シャザド・チャミン著/ダイヤモンド社)
同様の話は、7月頃にNHKで放映されていた「心と脳の白熱教室」で
オックスフォード大学の教授も解説していたので、
脳心理学の世界での定説になりつつあるようです。
-------------------------------------------------
◆ 心のポジ度を司るPQ脳
-------------------------------------------------
では、心の状態がポジティブなのか、ネガティブなのかは、
何によって決まるのでしょうか。
まず、私たちをネガティブにさせる脳の働きについて。
これは、「生存脳」が司っている領域で、リスクを察知して、
逃げる/戦うなどを瞬時に判断し、実行命令を出します。
それが、私たちの思考をネガティブに向かわせます。
たとえば「○○さんに会いたいとコンタクトしてみよう」と思った瞬間に、
「いや、○○さんはきっと忙しいはずだ、また別の時期にしよう」と思っている。
これは、断られる/迷惑がられることによって受ける
心のダメージを回避したいという脳の働きから来ています。
本書では、自分の中に妨害者がいるとして、10のタイプを紹介しています。
一方、ポジティブな思考を司っている脳もあります。
それが、ここで言う「ポジティブ・インテリジェンス」で、
具体的に言うと、脳の3つの部位を指しています。
(1)前頭前皮質内部(MPFC)、(2)共感回路、(3)右脳です。
IQやEQなどのように、
PQ(ポジティブ・インテリジェンス指数)を測ることも可能なことから、
本書では「PQ脳」とも呼ばれています。
自分の中に妨害者がいるのと同様、
内なる賢者がいるとして、賢者の5つの力が紹介されていました。
なるほど! 私たちが葛藤している時というのは、
「生存脳」と「PQ脳」が戦っているわけですね。
-------------------------------------------------
◆ 成長も、幸福もPQスコアのアップが鍵
-------------------------------------------------
無料のPQテストもあるので、やってみました。
(下にリンクを張っておきますね)
PQスコアというのは、1日の中でポジティブでいた時間の割合です。
75が劇的変化の境目で、それが維持されるようになると、
常時コントロールできるようになるようですね。
すると、半分よりは高いものの、75には及びません(涙)
このスコアはその日の気分を測定するようなものなので、日々変化します。
逆に言えば、この気分を高めに維持する力は身につけられるというのが、
この本のテーマでもあるのです。
起きていること、起きてしまったことはコントロールできないが、
どう影響を受けるかという思考習慣は、コントロールできる、と。
著者は、パフォーマンスは次のような式で表せるとし、
ーーーーーーーーーーーーーー
パフォーマンス=潜在能力×PQ
ーーーーーーーーーーーーーー
スキル、知識、経験、人脈などの潜在能力を引き上げるよりも、
思考習慣のPQを変える方が手っ取り早いと主張しています。
なぜなら、習慣は定着までに21日かかると言われており、
逆に言えば、21日で成果は上がるからだ、と。
思考の習慣を変える具体的な方法は紹介し切れませんが、要点は
・妨害者力を弱め、
・賢者の力を強め、
・五感の感度を高めるPQ運動でPQ脳を鍛える、の3点。
チームのPQを高める方法も紹介されています。
わかりやすい本なので、お時間があったら、ぜひ読んでみてください。
私も、21日間ぐらいなら、試してみようかなと思いました。
ダイエットも、簡単には続かない私ですけど(笑)
では、よい1週間をお送りください!
==========================
◆ ポジティブ・インテリジェンス無料テスト ◆
PQスコア無料テストを受けるには、下記のページの下の方にある
「TAKE IT NOW」のリンクボタンをクリックします。
http://positiveintelligence.com/assessments/
テストは日本語、結果は英語です。
大切なことはハンドボールが教えてくれた
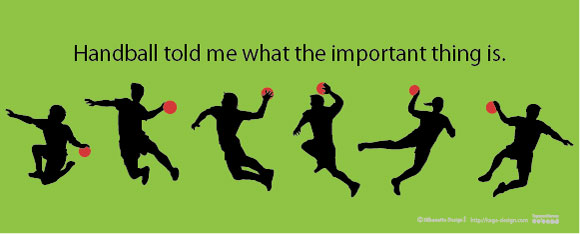
一昨日の土曜日、高校の部活(ハンドボール部)の4期合同OBOG会が開催されました。と、言っても言い出しっぺは私です。私は、神奈川県立多摩高校の出身。私たちが1年生だった時に2〜3年生だった先輩と、一つ下の学年の後輩たちに呼びかけたところ、35名が集まりました。全体の5割ぐらいの出席率です。よくまあ、縁が切れずに40年も繋がっていたものです。
多摩高の特徴は、同学年同士のつながりは強いのですが、縦のつながりは強いとは言えません。これをきっかけに期をまたいだOBOG会を創ろうという話になり、皆さん、とても楽しそうに帰って行ったので、開催して良かったなと思いました。
私が、今でもチームプレーっていいなと思う、その原点はこの高校時代の部活にあります。当時、私たちの代では神奈川県で2度優勝する程に強いチームでした。決して練習好きだったとは言えないのに、なぜ勝てたのでしょうか?
大きく分けると3つあり、それが私のチーム観の原点になっています。
1つ目は、絶対に勝つという気持ちが強かったこと。
2つ目は、厳しさと楽しさのメリハリがあったこと。
3つ目は、意志を示し合い、責任を果たし合うプレーをしたこと。
特に3つ目。あらゆる球技がそうだと思いますので、ある意味、当たり前すぎるのですが、つまりこういうことです。たとえばパス。
ボールをもらいたいときは、ボールを受けたい方向に向かって走ることで意志を示しますし、相手を走らせたかったら、走ってほしい方向にボールを投げて意志を伝えます。つまりパスとは、要求でもあるんですね。そして、両者の意志が一致しているとき、まさにあうんの呼吸のプレーになります。お互いに、意志を伝えた以上、その意志通りに責任を果たす。走ってほしいと要求するなら、当然相手の後ろにボールを投げてはいけないわけです。
ボールを貰った人は、またジャッジし、意志を示し、誰かと絡み合ってプレーをつくっていく。つまり、プレーの時間はコミュニケーションだらけなのです。そして、誰かと即興でいっしょにつくるプレーはとてもクリエイティブなものだとも言えます。
しかし、前半後半合わせて60分の試合時間の間、意志の示し合いと責任の果たし合いが、うまく機能し続けるというわけにはいきません。意思疎通が乱れ、要求通りに相手が動かないと、あるいは要求したのに、その意志とは裏腹のパスになってしまうと、パスミス、キャッチミスが生まれ、ボールは相手に移って行きます。
会社という組織でのチームプレーもまさに同じこと。意志を示したり、要求もしないうちから、「どうせ、わかってもらえないに決まっている...」と思い込んだり、「自分はこうします」「あなたにこうしてほしい」という意志を伴わないボールを投げてしまうのは、もはやチームプレーではありません。要求したのに、結果を見届けない態度も同様ですよね。あ〜大変。私はその何割ができているのだろうか?
意志を示し合い、責任を果たし合えるチーム。言うは容易く、行うは難しですが、そんなイケてるチームでありたいものですね。
9月も第2週に入りました。今週も良い1週間でありますように!



