『育成・成長』カテゴリの記事
ダメ出しはヘルシー

昨年の大河ドラマ「べらぼう」では、
蔦屋重三郎が、絵師・喜多川歌麿に
ダメ出しをするシーンが頻繁に描かれていました。
ダメ出しとは言っても、こうすると、
もっと良くなると思うという類のものですが、
それがだいたい無茶なオーダー。
歌麿は「しょうがないなあ、蔦重は」
という感じで引き受けるのですが、
無理をしてでも応えてみると、
明らかに作品が良くなり、
自分も納得する出来になる。
編集者と作家は、いつの時代も、
こうしてお互いを高めあって、
いい作品をつくっていくんだなあと
思いながら観ていました。
ところが、ドラマの中で歌麿は、
蔦重とのタッグを解消し、
他の本屋とのつきあいを始めます。
すでに有名な絵師であった歌麿に
他の本屋はまったくダメ出しをしません。
「すばらしい」
しか言われないことに歌麿は苛立ち、
「なんか、こうしてくれとかないのか」
と言うのですが、返ってくるのは
このままで十分といったコメントばかり。
そして、だんだん作品づくりに
迷いを感じるようになります。
電通若者研究部の調査によると、
高校生、大学生、1~3年目の社会人
計1,200人のうち、
「『本音』を誰かに話すことは、
相手が誰であってもリスクを伴うと感じる」
と回答した人が76.8%いました。
さらに、「仕事での成果よりも、
自分の心の安定を重視して働きたい」
と答えた社会人1~3年目は75.0%。
「職場で何かを成し遂げるよりも、
面倒ごとなく"うまくやる"ことが大事」
と答えた人も77.3%にのぼりました。
べらぼうで、本屋が
歌麿に何も言わなかったのは、
どうすれば良くなるのかという
アイデアが浮かばなかったからかも
しれませんが、
遠慮や忖度もあったのではないでしょうか。
この調査からは、
自分も少しも感情を乱したくないし、
相手の感情を乱すようなこともしたくない。
感情をぶつけ合うのは絶対に避けたい。
そんな若者の姿が見えました。
しかーし、仕事であれ、趣味であれ、
「成長」という視点で考えると、
ダメ出しは必須だと、私は思っています。
いいね!ばかりだと改善されない。
もうちょっとここをこうしたほうが...
という意見は、
成長していくためには必要です。
ダメ出しはたいてい目の前の仕事など、
コトに対して行われるもの。
本来は、人間性を否定するようなものではありません。
でも、人間性そのものを否定されたと思ってしまうので、
「ネガティブなお叱り」になってしまう。
そう捉えず、「ヘルシーなアドバイス」と捉えてみると
いいのではないでしょうか。
そうそう、「ヘルシー」。これです。
イチローが高校野球の練習に立ち会って、
こう言っていました。
今の時代、大人は厳しく指導できない。
子どもたちは、自分で自分に厳しくすることで
成長していくしかない。
それができる子はそういない。大変な時代だ、と。
ダメ出しは心を乱すもの、ではなく、ヘルシーなこと。
そう捉えて、するほうも、されるほうも、
もっと楽な気持ちでポジティブに
成長できる社会であればいいのになあと思います。
おまえの物はおれのもの

今回は「おまえの物はおれの物」は、
見方を変えると「共有」なのか?
という話です。
先日、外出から帰宅すると、
玄関に見慣れぬスニーカーがありました。
次男の友だちが遊びに来ているのだろうと
思っていましたが、夜になっても、
友だちが部屋から出てきません。
そのうちに、次男が「腹減った」と、
一人で出てきました。
聞くと、スニーカーは友だちの物だが、
友だちは来ていないとのこと。
しばらくスニーカーを借りているだけだと
言います。むむ? 靴って貸し借りするのか?
と思いました。
別の日。洗濯をしていたら、
これまた見慣れぬスウェットパンツが
出てきました。
次男に聞くと、
「ああ、それ○○の。借りてる」と。
もしかして、この子は、
「はい、借りるよー。これも借りるねー」
と友だちものをホイホイ持ってきてしまう
ジャイアン的なやつなのかもしれない。
これはマズイと思い、
人の物を簡単に借りるものではないと言い、
なぜ借りているのかを聞きました。
すると次男は
「自分は貸してと言ったことはない。
一緒に履こうと言われるのだ」
と言います。
え?
スウェットパンツに関しては
「なんか、普通のスウェットを
持っていなそうだから、貸してあげたい」
と別の友だちに持たされたのだとか。
ますます意味不明。
しかし、なんとなくわかってきました。
次男と次男の友人たちは古着が好きです。
友だちから借りているスニーカーも、
スウェットパンツも古着とのこと。
もしかしたら、彼らは
物を「所有」している感覚ではなく、
最初から「共有」している感覚なのではないか。
どこかの誰かが着たり、履いたりしたものを
最初から共有している感覚なので、
友だちとも気軽に共有するのではないか
と思いました。
我が家は、長男も次男も
Z世代と呼ばれる世代です。
この世代の特徴を表す消費行動の一つに
「リキッド消費」と呼ばれるものがあります。
リキッド消費とは、
その時々で欲しいものが変わる、
買わずともレンタルやシェアリングでOK、
モノよりも経験を大切にする、
この3要素を満たす消費生活のこと。
スマホから情報が大量に流れてきて、
いいなと思うものがコロコロ変わり、
それを所有することよりも、体験したい。
体験が終わったら、次。
といったところでしょうか。
うちの次男の古着も
そんな感じなのかもしれません。
使えるお金が多くない
ということが大きいとは思います。
私がイメージする、
お金をかけて狙ったアイテムを手に入れ、
大切に所有するような、
王道の古着好きな人々とは異なり、
高校生は、使えるお金が多くないから、
気軽にコーディネートし、
自己表現(体験)するアイテムとして
古着を利用している。
我が子を観察し、こうして消費行動を
整理するのはおもしろいですね・・・
さて、ここで、よく知られている
「おまえの物はおれの物」
というジャイアンのセリフについて。
このセリフ、この後に、
「おれの物もおれの物」と続きます。
つまり、
「おれの物はもちろんおれの物だし、
おまえの物もおれの物だ。
全部おれさまの物だ!」
という強い独占欲を表していますね。
しかし、実は、過去のアニメで
この言葉が「共有」を示すものとして
使われているエピソードがあります。
小学校の入学式で、
のび太にさまざまなハプニングが起き、
のび太自身も迷子になり、
さらにランドセルを無くしてしまい、
のび太とランドセルを
ジャイアンが必死に探して
上のセリフを言う場面があるのです。
ジャイアンは、
おまえが無くしたランドセルは
おれの物でもあるんだから、
取り返すのは当然。
おまえに起きた問題はおれの問題でもある、
って言ってるわけですね。
このエピソードを知ると、
最近のうちの次男の共有志向なんかもあり、
「おまえの物はおれの物」
が独占欲を表すセリフに見えなくなるから
不思議です。
「おまえの物はおれの物」と言われたら、
「なんてひどいやつだ」ではなく、
むしろ「シェア力が強い人」にうつる。
その後に、
「おれの物もおれの物」と続いたとしても、
「そりゃ基本、そうだよね。
でも、どんどんシェアしていきたいよね」
という意味にも捉えられる。
時代の流れと価値観が違うと、
同じ言葉や同じビジュアル、
同じ音楽を聞いても、真逆の印象を持つ、
なんてこともあるかもしれません。
コミュニケーションなどでは、
気をつけていないと
ちょっと怖いことが起こるかもなあ
とも思いますが、
現象としては、
とてもおもしろいなあと感じます。
そして次男は今日も友達の服を着ています。
シェアして楽しんでいるだけだといいのですが、、、
(注:次男の行動はZ世代を代表している
わけではないと思います。
お気をつけください。笑)
ホッキョクグマの子どもを見ながら 「成長」を考えてみた

今日は、ちょっと難しいことをやらないと
やっぱり成長しないよなあと思った、
という話です。
先日、近くの動物園にホッキョクグマの
子どもをようやく見に行きました。
昨年の秋に動物園内で生まれ、
5月から一般公開していたのですが、
混まない曜日や時間帯をねらって
平日に行きたいと思っていたら
なかなか行けるタイミングがなく
こんなに遅くなってしまったのです。
やっと生の姿を見られた
ホッキョクグマくんは、さすがに
赤ちゃんではありませんでしたが、
まだまだ子ども。
見た目はもちろんかわいいですが、
なんといっても、やっていることが
かわいい。そして賢い。
子グマが何をやっていたかというと、
飼育エリアの水辺に浮かんでいる
おもちゃ(色とりどりのポリタンクや、
ボールと思われるもの)を咥えては
水から上がる。
→ 次に岩の隙間や木の上などに
おもちゃを隠す。
→その後、せっかく一生懸命隠した
おもちゃをまた取り出して、水に放る。
→そのおもちゃを追って、水に飛び込み、
おもちゃをとらえる。
これを繰り返していました。
かわいいので、ボーッと見ていましたが、
ふと、これは本能的に狩りの練習を
しているのかもしれない、と思いました。
ホッキョクグマは、狩りをする生き物です。
野生のホッキョクグマは氷上にいる
アザラシにそっと近づいて捕えたり、
呼吸のために水上に顔を出すアザラシを
捕獲して暮らしています。
調べてみると、動物園での
ホッキョクグマのおもちゃ遊びは、
「探す・隠す・つかまえる」といった
連続動作や集中力、運動能力など、
野生での狩猟に必要となる要素を
自然と体験できるものと考えられる、
とのこと。
狩りで必要となる
「タイミング・忍耐力・すばやさ」なども
遊びの中で強化されるということです。
遊び方を見ていてさらに感心したのは、
自ら難易度を上げているところ。
好奇心や本能でやっていることだとは
思いますが、手を伸ばして
ギリギリ届く木の枝の上に
おもちゃを乗せたりするのです。
案の定、すぐには取れないので、
どうするのかと思ったら、
別ルートから木の後ろに回り込んで、
取っていました。
頭がいいなあと思いながら見ていました。
そんな子グマの様子を見ながら、
思ったことは、
ちょっとレベルが上のことに
チャレンジしないと、
ずっとレベルアップしないよなあ、
ということ。
問題なくこなせるレベルのことは、
安心感を与えてはくれますが、
そこにとどまっていると成長が止まる。
少しレベルが上のことにトライすると、
最初はうまくいかないことも多いですが、
そのうちできるようになる。
その、ちょっと上のレベルのことを
するかしないかは、本人次第だなあ、と。
ただ、ホッキョクグマの愛らしさを
堪能しに行ったのに、
なんだか大きな気づきを得て
帰ってきたこの日。
最近、ミシンで縫いかけている
超簡単ゴムパンツに
ポケットをつけよう!(レベルアップ)
と思ったのでした。
毎日とんでもなく暑いですが、
水分をとって、体調に気をつけて
まいりましょう。
「聞く」のは簡単ですか?
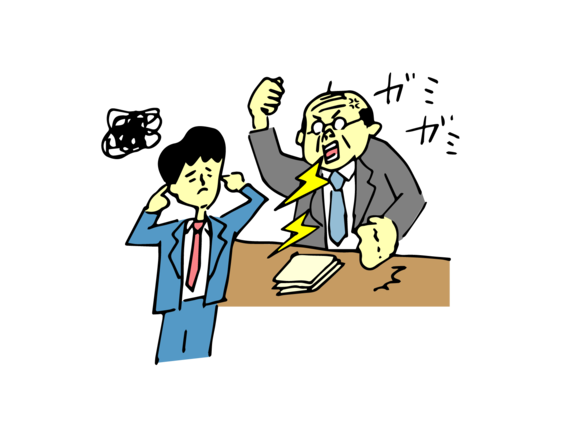
先日、高3の次男にお説教されました。
あるきっかけから、
次男が「今日は言わせてもらう」モードに入り、
過去のことも掘り出してきて、まあ、言う言う。
思春期の男子ですから、
普段はそれほど話さないですが、
よっぽど溜めていたんでしょう。
日頃、全然聞いていないのかと思っていたら、
結構覚えているんだなあと
変に感心してしまうくらいのしつこさ。
そう思ってたんだ、それは申し訳なかった、
と思うことも多かったのですが、
それとこれとは違うし、一緒にしないでほしい、
ということもあり...
「いや、ちょっと待って」
と言いそうになりましたが、
そもそも次男が言わせてもらうモードに入ったのは、
私が、「ただ、聞く」ということを
ちゃんとしてこなかったからだと、
説教されながら気づいたので、
ぐっと抑え、頑張って受け止めました。
でも、ですよ。
いつまで?
と思うくらい過去のことを掘る(笑)。
私は、頭の中で、
あとどのくらい続くのかなあと思うわけです。
仕事終わってないし、洗濯途中だし、
とかいろいろ思うわけです。
すると、すかさず、
「今、全然聞いてなかったよね。
そして今、時計見たよね。
俺には、時計見たよね?とか言うくせに、
自分でもやってるよね。反省してないよね」
と次男。
ああ、子どもってこういう気持ちなんだなあ、
そりゃ、くどくど言われると、
他のこと考えたくなるわ。
やっぱり、一つのことだけを短く言って
終わりにしないと意味ないんだなあ。
などと妙に納得したり、
いい学びだなあなんて思っていると、
「なんで、すっきりした顔してんの?」
とか言われ、神妙な顔をしてみたり。
言われた方としては、体感1時間。
実際は30分くらいだったかもしれないです。
いや、ちゃんと聞いていましたよ。
途中、他のことを考えそうにはなったけど...
大人って、人に怒られたりしないので、
私は息子にいろいろ言われて
すごくよかったと思っています。
ごもっとも、と思うこともたくさんありました。
息子の訴えを翻訳し、解釈すると
こういうことです。
・私は、人の話をただ「聞く」ことをしていない。
これは、自覚があります。
即、解決したいタイプなので、
すぐに、全体を見渡してしまって、
この人はこう思ってるかもよ、
そしてこの人はこう思ってるはず。
だったらこうしたらいいんじゃない?
とか言ってしまう。
でも、相手は、解決策を知りたいわけじゃない。
「そうなんだ」「大変だったね」だけでいい。
一度、受け止めなくちゃいけない。
・都合がいい
子どもには正論を言うくせに、
自分のことになると、できていないことに対して、
都合よく言い訳したりする。
こっちは仕事もして、家事もして、
忙しいんじゃい! と思いますが、
息子は自分の枠組みの中でしか考えないので、
そう受け止めますよね。
俺は学校も行って、予備校も行って、
忙しいんじゃい、って思っているでしょう。
こうして「大人はずるい」みたいな
印象を持つんだろうなあと思いました。
勉強になります。
さて、「聞く」について。
よく「人の話はただ聞くのではなくて、
しっかり聴こう」と言われますよね。
意識を集中して、耳を傾けて「聴こう」と。
当然、「聞く」よりも「聴く」の方が、
難しいと一般的には思われています。
でも、ただ「聞く」のほうが難しいのだと
心理士であり、心理学者の東畑開人さんは著書
「聞く技術、聞いてもらう技術」の中で、
言っています。
東畑さんによると、
「心理士としての僕なりに定義するならば、
「聞く」は語られていることを
言葉通りに受け止めること、
「聴く」は語られていることの
裏にある気持ちに触れること。」
だそうで、
この、「言葉通りに受け止める」
ということがきちんとされないと、
対話が成り立たない。
たとえば、何かに対して
「それは嫌だ」という声があがった時に、
背景にある問題にいきなりフォーカスが移ると、
「嫌だ」は聞かれなくなってしまう。
そういうことが
社会でたくさん起きているのではないか、と
東畑さんは言っています。
これ、読んだ時も納得したんですが、
次男大説教事件(?)の後、
ものすごく腹落ちしました。
確かにそうです。反省です。
「聞く」ことを、まずしっかりしないと、
根本の問題が解決されたとしても、
相手は「聞いてもらえなかった」
という感想になります。
不安、不満は消えない。
それは本当の解決ではないということですね。
思い起こすと、あちゃーと思うこともたくさん。
気をつけなくちゃいけないと思いました。
さて、GWも終わり、あっという間に5月も中旬。
気温が安定しませんが、
皆さん、体調に気をつけてお過ごしください!
モチベは大事

LIFEというコント番組があります。
NHKで2012年から放送されている長寿コント番組です。
この番組を率いているのがウッチャンこと内村光良氏。
今年61歳だそうです。
先日、LIFEにレギュラー出演しているタレントが
番組を語るインタビューを視聴しました。
出演していたのはココリコの田中氏とドランクドラゴンの塚地氏。
LIFE初回からずっと登場している2人はお笑い界ではベテラン
現在は、俳優としても活躍していますね。
インタビューで、2人はこう言っていました。
「13年もやっているのに、LIFEは毎回とても緊張する。
いいものをつくろうと毎回気合いが入る」
LIFEの現場は、スタッフとタレントが一つになり、
チーム全体でていねいにコントをつくっているそうで、
そのこだわりは他の番組とは比べものにならない。
そう語っていました。
LIFEには毎回、ゲスト出演者もいて、
ほとんどのゲストが、コント慣れしていないという理由で、
彼ら同様、とても緊張しているそうなのですが、
実は、出演者の中で、毎回一番緊張しているのは
ウッチャンだと言っていました。
「内村さんは、毎回、誰よりも緊張しているし、
誰よりも練習する。収録前に僕たちが立ち話をしている時も、
内村さんは、1人で壁に向かってセリフの練習をしている。
そんな内村さんの姿をみんながずっと見てきているので、
僕らは背筋が伸びるし、いいものをつくろうと真剣になる」
この話、とてもいい話だと思いました。
彼らが全力で取り組んでいるのはコント。
かつらをかぶったり、顔にシワをかいたり、青く塗ったり、
大きな髭をつけたりして芝居をしています。
たった数分のお笑いですが、彼らは真剣勝負。
50歳を超えたベテランコントマンたちが、
毎回、全力投球しているんだと思うと
胸が熱くなります。
このインタビューを視聴したあとに見た、
LIFEの新作コントで、ウッチャンは
卵黄を模した、丸くて大きな黄色い被り物をし、
ピコピコ音がなる靴で登場しましたが、
その姿を見てウルっときたほどです。
インタビュー番組では、
ウッチャンのコメントも流れていました。
「田中と塚地はLIFEの風神、雷神。
彼らがいなければなり立たないし、
こんなに長く続けてくることはできなかった」
スタジオにいた2人がグッと涙をこらえたのは
言うまでもありません。
背中を見て学ぶ。
最近はまったく聞かなくなったワードですし、
こんなこと言おうものなら「今は令和だぞ」とか
言われちゃうのでしょうが、
LIFEの現場では、きっと、上の人の背中を見て学ぶ
ということが繰り返されているのだろうなと思いました。
芸の世界だから特にそうなのかもしれません。
でも、学ぶ必要性を強く感じて、成長したいと思えば、
現場がどこであれ、自ずといろいろなところから
盗もうとするのかなと思います。
ところが、世の中、ていねいに教えないと学んでもらえない
ということになっていますよね。
特に会社なんかはそうです。
それは、会社にいる人たち全員が
「この仕事で成長したいんです」と、
強く思っているわけじゃないから。
会社のような場は、
いろいろな温度感の人がいるのが当然。
均一に学べるフォーマットやマニュアル化された
教育プランや教材がないと教えることも
学ぶことも難しいのだろうなと思いました。
でもですよ、こうも思いました。
そういうフォーマット的なものがあったところで、
やっぱり、学びたい欲が強くない時は刺さらない。
自分が学ぶ側に立った時を想像してみても、
興味や、学ぶモチベーションがなければ
意欲的に吸収する姿勢には
なかなかなれないと思います。
そんなわけで、いろいろ書いてきましたが、
結論として思ったことは、
学ぶには「モチベーション」が必要、ということ。
純粋な学習欲じゃなくても、
クリーンな成長欲じゃなくてもいいと思います。
お金を稼ぎたい、モテたい、でもいいと思う。
モチベーションがあれば、
マニュアルなんて逆になくても、
背中を見て、いろいろ盗んでいくのだと思いました。
モチベは大事。
あらためてそう思います。
さて、4月もすぐそこですね。
当社は引っ越しを終えたばかり。
私は花粉で毎日瀕死ですが、
あらたな気持ちでまいります!
何がしたかったの?

私の中で、第3次カメラブームがきています。
第1次は30年くらい前。
安いフィルムカメラを買って、モノクロフィルムで、
それっぽい写真をほぼ感覚で撮影して、
現像した写真のそれっぽさに満足していました。
次は20年前あたり。
子どもが生まれ、子どもの写真を
毎日大量にデジカメで撮影していました。
被写体は100%子ども。
今思うと、あの頃は、
写真を撮っているというよりも、記録していた、
というほうが近いかもしれません。
そして、数年前くらいから第3次に突入しています。
きっかけは、昔のカメラの取説をじっくり読んでみたこと。
読んだ理由は仕事で必要だったからですが、
あ、撮影ってそういうことだったの?ということを
初めて(遅い)、構造的に理解したのです。
そうなると、いろんなカメラをいじりたくなるもの。
家に眠っていたコンデジを引っ張り出してきて、
このカメラ、こんなにステキに撮れたんだ、と感動した話は
以前、このメルマガでも少し触れました。
で、先日、眠っていたカメラがもっとあったことを思い出し、
探してみると、ありました。昔のNikon。
昔といっても、20年前くらいのデジカメです。
しかも、一緒に保管されていたのは300mmの望遠レンズ。
どうやら、義父から譲り受け、子どもたちのサッカー撮影のために
しばらく使っていたようですが、記録メディアが古いし、
本体も重いので、引き出しに入れたままになっていたようでした。
カメラの数値をいろいろといじれるようになった(遅い)私。
せっかくなので、望遠レンズとともに持ち出して
外で撮影してみることに。
私が住んでいる地域は、計画的に緑が残されていて、
池や小川もあるので、鳥がたくさんいます。
望遠で撮りたいものは特になかったのですが、
まあ、鳥でしょうね、という感じで、
鳥にターゲットを絞りましたが、
普段動くものを撮り慣れていないので、
全然撮れない(笑)。
いや、シャッターは押すんですよ。
でも、そもそも、鳥を撮りたい!という
強い思いがないことと(生き物好きなので鳥は好きですが)、
こういう写真にしたいという
仕上がりイメージがないので、
構図が全然決まらないわけです。
これじゃない、もっとこうか?と試しているうちに
鳥は飛び立ってしまいます。
2時間近く緑道を歩いて、かなりの枚数を撮りましたが、
まったく撮れた感触がないまま帰宅。
メディアからデータを取り込んで撮影した写真を見て、
ひどすぎて笑いました。
だいたいは、まあ撮影できてはいるんですが、
とにかく、
「これ、何がしたかったの?」
という写真なんです。
写真には撮影者の意図がかなり出ることに
改めて気づきました(遅い)。
つまり、私の写真には意図がない。
まあ、望遠っぽく撮れてるけど...「で?」
と突っ込まれそうな仕上がり。
原稿もそうですし、デザインもそうですけど、
意図がないと、ぼんやりしたものになって、
何が言いたかったの?何を伝えたかったの?
というものになってしまいます。
最初に言いたいこと、伝えたいことを決め、
それができるように、全体をしっかり設計しないと、
なんとなくいい感じにしてみました、にしかならない。
写真の場合、偶然を切り取ってみました、
ということもあると思いますが、
偶然の切り取りがいい感じに成立するのは、
それなりの蓄積があるからですね。
というわけで、一人反省会を終えたので、
また、カメラジャーニーに出ようと思います。
望遠は...撮りたいものができてからにしようかな...
第3次カメラブーム、まだしばらく続きます。
「好き」のパワー

今日は、なんだかんだ熱意と愛は強いなあ、
という話です。
小学生の時にお笑いトリオのロバートにはまり、
ライブに通い詰め、
会場ではコント内容を必死にメモし、
ロバート目的で東京の大学に進学し、
学園祭の実行委員になって
ロバートに出演依頼をしてライブを成功させ、
さらに卒業後テレビ局に就職して
ディレクターとしてロバート秋山の特別番組を
企画制作したという人がいます。
「うそ、そんなことあるの?」。
これが、この話を何かで知った時の私の感想。
「ロバートが大好き」という熱い思いを
こんなにも長く持ち続けられることも
びっくりなのですが、
途中から「ロバートと一緒に仕事がしたい」
なんて野望を持ち、それに向かって
実際に行動を起こし、本当にロバートの番組を
企画するまでになるなんて。
怖くなるくらいの実行力です。
そしてなんと彼、
ここまでの話を本にまとめました。
この本、自分がどんな人間で
いかにロバートのファンであり続けたか、
どうやって番組をつくるまでになったのか、
というエピソードが細かく書いてあるのですが、
行間から滲み出ているのは
いかに「ロバートがすばらしいか」でした。
推しへの愛ってこういうことなんだなと理解。
意外だったのは、
彼が優秀なビジネスパーソンであること。
しかも小・中学生の頃から。
ただ熱意で進んできたわけではなく、
その都度、自分の状況を俯瞰し、
どうすれば目的が達成できるのか、
冷静に考えているのです。
ロバートの布教は完全に熱意で、
一方で自分が人生をどう歩んでいくのかは客観視。
熱さと愛だけではテレビ局でロバートの番組を
企画制作することなんてできなかったでしょうが、
それでも原動力は間違いなくとんでもない熱さと愛。
その上に冷静さが乗っかっているから
こうなれたんだろうなあ。
ちなみに、ロバート側は
ライブ会場で必死にメモをとるメガネの少年を
「メモ少年」と呼び、成長を見守ってきたよう。
いよいよ自分たちの業界に近づいてきた
メモ少年(青年)の行動力は恐怖だったようですが、
進路について本気でアドバイスをしたみたいです。
全力で応援してくれるファンの成長を見守る。
こういう世界があるんですねえ。
「好きなことを仕事にするほうがいいか、
しないほうがいいか」
という議論があります。
社会人1,000人を対象にした調査
(ミライトーチ調べ)では
「好きなことを仕事にした方がいい」
と答えた人は全体の47%、
「しない方がいい」と答えた人は12%、
「どちらとも言えない」が41%でした。
また、「子どもの頃や学生の頃になりたかった
職業につけているか」の問いに、
「つけている」と答えたのは14%、
「目指している途中」が5%、
「過去についていたが今はついていない」が5%、
「つけていない」「特別なりたかった職業はない」
と回答した人はいずれも38%でした。
子どもの頃か・・・。
中学生のとき、英国のロックバンド
「デュランデュラン」の
ジョン・テイラーというベーシストに
ロッキン・オンでインタビューするには
どうすればいいか、と英語の先生に聞いて
困惑させたことを思い出しました(笑)。
その後、ほとんど思い出さなかったくらいなので、
あの時、一瞬だけ好きだったのだと思います。
飽きっぽいと熱が保てませんね・・・。
「好きなことを仕事にするほうがいいか、
しないほうがいいか」。
いろいろな考え方がありますが、
「好き」の力はやはり強いと私は思います。
集中力も努力も、やっぱり「好き」な人には
叶わない。
「好き」が生み出すパワーはとてつもなく大きい。
あらためてそう感じます。
そろそろ花粉の季節がやってきます。体調に気をつけてまいりましょう。
正解のない問題には、意見があるだけ
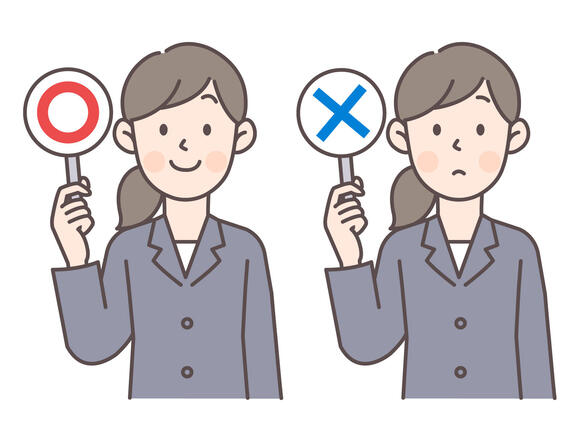
食卓に並ぶさまざまな料理を、
リアルなイラストで表現し、
SNSで発信している山田めしがさんという方がいます。
ただ完成形を描くのではなく、
一口、また一口と料理が少なくなっていき、
最後は皿だけになるプロセスを
描いているのがユニークで、
見ている私も
全部食べたような満足感が得られるという、
なんとも不思議なイラストです。
最近では、McDonaldの月見バーガーや月見パイと
コラボした動画が話題になりました。
この方、調理師でもあるそうで、
料理と描くこと、
どちらも好きでたまらないのだろうなと
想像します。
さて、そんな山田さんには、よく
「どうやったら絵がうまくなりますか?」とか
「料理がうまくなるコツはなんですか?」
という質問が来るようで、それに対し、
山田さんはXでこうコメントしていました。
「ハッキリ言って答えようがない。
それより、私はこんな画材を使って
こんな感じの絵を描きたくて、こう描いてみたけど
うまくいかないのでアドバイスください、
とかのほうが答えやすい。
とにかく描いてから聞いてほしい。
作ってから聞いてほしい」
こうも言っていました。
「例えば一つコツをいったところで、
なるほど参考になりますって、行動に移さんでしょ。
簡単に描ける方法探すよりも、
苦戦しながらジタバタもがいて描き上げた作品の方が
上手い下手関係なく美しいし、
間違いなく画力は上がると思う」
ごもっともです。
サッカーをほとんどしたことない子が
「サッカーがうまくなるコツを教えてください」
と言ってきたら、
「まず、たくさんボール蹴ってみてください」
と言いますし、
水泳したことない子が
「水泳がうまくなるにはどうすればいいですか?」
と聞いてきたら、「まず水に入ってみましょう」
となりますもんね。
大人だったら「AIをうまく使いこなすコツは何ですか?」
とかでしょうか。
やはり「まず使ってみましょう」ですよね。
私も含めてですけど、きっと、頭のどこかで
「正解があるはずだ」「最短ルートがあるはずだ」
と思っているから、
こういう思考になるんだろうなあと思います。
自分でやってみて、「ああ、こういう感じね」
をつかんでもいないのに、
万人に共通する正解があるはずだ、と思ってしまう。
実際、「~~のコツ」「~~の正解」系の
タイトルがついた本、多いですしね。
試しにAmazonで「正解」というワードが
タイトルに含まれている本を検索してみましたが、
想像以上に出てきました。
「投資の正解」
「間取りの正解」
「人生の正解」
「話し方の正解」
正解を求める人が多いから、
これが正解ですという情報が多いのか、
これが正解です情報が多いから、
正解を求める人が多くなったのかはわかりませんが、
とにかく「正解」がいっぱい。
先日、ブロガーのちきりんさんの
『自分の意見で生きていこう
「正解のない問題」に答えを出せる4つのステップ』
(https://amzn.asia/d/2icBKSI)
なるほど、これはいい整理だと思ったので、共有します。
ちきりんさんは、こう言っています。
世の中のあらゆる問題は、
「正解のある問題」と「正解のない問題」に分けられ、
「正解のある問題」には
「正解」と「誤答」のみがある。
対して「正解のない問題」には
「正解」や「誤答」はなく、あるのは
「自分の意見」「Aさんの意見」「Bさんの意見」など、
さまざまな人のさまざまな「意見」。
「間違った意見」も「正しい意見」もない。
「正解のある問題」とは、たとえば、
国連加盟国の数は?とか、
前回の選挙の投票率は?など。
これらには正解があるので、
もしわからなかったら調べればいい。
調べれば正解がわかる。
「正解のない問題」とは、たとえば、
自分は結婚すべきなのか?
引っ越しをすべきなのか?
などの個人の問題や、
消費税をもっと上げるべきなのか?
移民をより積極的に受け入れるべきなのか?
などの社会問題など。ほかにもたくさんある。
これらには「正解」はなく、「意見」があるだけ。
だからネットで調べても正解に行き着くことはない。
この本は、世の中、正解のないことばかりなんだから、
意見を持っていないと生きていけませんよ、
自分の意見を持って、
自分で選択していきましょうと言っているわけです。
あたり前のことなのですが、
あらためて、そうだよなあと思いました。
正解風な意見があちこちにあるから、
正解のない問題でも正解を探してしまい、
正解風な意見を見つけて、安心する。
そういうことが起こっているのだろうなと思います。
安心したい欲ですよね、きっと。
それだけ不安が多い世の中ということなのでしょう。
さて、そんなことを呟いているうちに、
今日が仕事納めです。
仕事納まるのか。家の掃除はどうするのか。
正解のない問題を抱えています。
皆さま、今年も1年、メルマガをお読みいただき、
ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
良いお年をお迎えください。
「守」を省いていませんか?
「遠くを見ています」
テレビのインタビュー番組に出演していた
草彅剛さんが、なぜそんなに目がいいのか、
何か特別にしていることがあるのか、と聞かれ、
そう答えていました。
インタビュアーが、
いやいや、そんな簡単なことであるわけがない、
もっと他に何かやっているでしょう、
というような反応をしたら、
草彅さんは、こんなことを言いました。
「だいたい、そういう反応されるんですよ。
そんなわけないって。でも、皆さん、
子どもの時から、遠くを見るのは目にいい、って
言われてきているのに、実際やっていないでしょう?
やってます? 僕はちゃんとやっているんですよ」
「ああ、そうだ。本当にそうだ」と私は思いました。
いいと言われていることを素直にやっているのか?
やったと言えるほど、続けたのか?と。
「よく噛んで食べなさい。30回噛みなさい」
なんて、言われたりします。
よく噛むと体にいいと
私も親や祖父母に言われました。
でも、私はやってこなかった。
どう体にいいのかわからんと思っていたのか、
面倒臭いと思っていたのか、
子どもの私がどう感じていたのかは覚えていませんが、
とにかくやってきませんでした。
昔から言われていたことに限らず、
「エスカレーターではなく階段を使うといい」
とか
「水をたくさん飲むといい」
など
健康にいいというジャンルに絞っても、
「こうするといい」という情報は山ほどあります。
これまた、私の場合、
素直に採用していることはほとんどありません。
無意識に、
「そのやり方は私に合っていない」とか
「いや、もっと効果がある方法があるはずだ」と、
やらない理由を考えているのかもしれない。
書きながら、そう自分自身の癖を分析したのですが、
いやこれは、まず自分でよく理解してから取り入れたい、
ということだと気づきました。
よく理解していないものに手をつけたくないというやつ。
でも、これ、理解するまでに時間がかかるわけなので、
なかなか手をつけないということになります。
「ちょっと待って、まだ理解していないから」
なんて言っていると、時間がどんどん過ぎる。
そして、なんだかんだ、
オリジナリティを加えようとする 笑。
そのままやりたくない。
厄介です。
仕事や勉強でもそうかもしれません。
「こうするといいよ」という情報やアドバイスを
もらっても、そのまま実行しない。
これもまた、
「待って、これから理解するところだから」
とか
「私なりのやり方があるはず」
みたいな理由ですね・・・
そうなると、いつまでたってもやらない。
まずは、言われたまま、素直にやってみる。
いろいろ工夫を加える前に、やってみる。
これ、とても大切だと気づきました。
なんでもかんでも片っ端からやったほうがいい
ということではもちろんありません。
でも、難しいことをいろいろ考えず、
まずは言われたまま、いくつか試してみる、
とにかく早く取り掛かることが大事だなと。
やりながら理解することもできるし、
やらないと理解できないこともある。
やらないと、自分に合っているかどうかもわからない。
守・破・離ですね、これは。
守を全然やっていないのに、破に行っちゃいかんよ、
まず、教えのままやってみて、
そこから自分のオリジナリティを加えなさい、
ってことですね。
まずはレシピ通りやってみよう、
つべこべ言わずにまずやってみなさい、私! 笑
というわけで、
書きながら、自分自身にツッコミを入れる、
リフレクション感満載のメルマガになりました。
さて、あっという間に8月も終わり。
暑すぎて、早く秋が来ればいいと思っていたのに、
ツクツクボウシの鳴き声が聞こえると
夏の終わりを感じて寂しくなってしまいます。
とはいえ、9月もまだまだ暑いでしょう。
台風も心配です。
体調に気をつけてまいりましょう。
脳のパワー、どこで使う?どこで休める?

昔から血液型や星座によるタイプ診断的なものに
興味がありません。
興味がないのは、一度も「当たってる」と
思ったことがないからだと思います。
私はA型で山羊座なのですが、
この組み合わせで目にする説明は
だいたい以下のような感じです。
「とても真面目。几帳面。慎重。コツコツ努力型」
ううむ。当たってない。
そんなわけで、血液型論は信じてこなかったのですが、
世の中、結構頻繁に人間関係と血液型が
一緒に語られますよね。
プライベートトーク、とくにママ同士のトークなどでは
よく出てきました。
「B型なんだ。やっぱりね」
「そうだよね、あの人AB型だもんね」
のような会話です。
私の場合は「A型っぽくない」と
言われ続けてきました。
A型は真面目で几帳面とか、AB型は変わっているなどの
なぜそう言えるのか?というような情報を
無意識に信じてしまって、バイアスになっていることを
確証バイアスと言いますよね。
血液型以外にも、
「女性はていねいだから、細かい仕事に向いている」
とか
「アウトドア派の人は明るく、コミュ力が高い」
とか(笑)、まだまだあると思います。
人事コンサルタントの曽和利光氏によると、
そもそも、人が確証バイアスにとらわれてしまうのは、
脳を「省力化」したいからだそうです。
日々接するさまざまな対象を
イチから認識・解釈していくと、
知的パワーを大幅に消費することになり、頭が疲れる。
すでに何度も直面した対象(物事)に、
毎回初めて出会ったかのように
イチから認識を始めていては、
知的パワーがいくらあっても足りないので、
思い込むことで省力化しているのだと言います。
なるほど。確かにそうかもしれません。
時間もパワーも有限です。
いちいち、「いや、本当にそうなんだろうか。
そうとは言い切れないんじゃないだろうか」
とならないやり方を脳が選んでいるのかもしれません。
しかし、確証バイアスにとらわれてしまうと、
フラットな判断ができなくなります。
曽和氏は、ジョブズやザッカーバーグが
毎日着る服に悩まないよう、
ユニフォーム化しているのは、
脳のパワーを使わない対象をつくることで、
それ以外の判断をクリアにできるようにしていると
説明しています。
そうか。やはりインプットでも「緩急」なんだ。
と、私は思いました。
なんのこっちゃってことですが、
私は、以前から度々このメルマガで
「緩急」「強弱」はとても大事
ということをお話ししています。
それは、主にアウトプットでの意味でした。
たとえばダンスや音楽だとわかりやすいですが、
全部を同じスピードで、強い力で表現しても
あまり良さが伝わらないけれど、
速くなるところ、遅くなるところ、
強いところ、弱いところが表現されていると、
ぐんとストーリー性が出て、見ている人、
聞いている人の感情に
アクセスしやすくなる。
これは、記事の執筆などでも同じです。
しかし、今回の話はインプットの話。
脳は、何かを理解する時、
いつも全力でパワーを使わないように、
確証バイアスで省力化している。
しかし、それだとフラットな判断ができなくなる。
そうならないように、
脳がパワーを使わない対象を決めて、
脳がきちんと休める状態もつくり、
逆にパワーを使わなくてはならないところに
使えるようにしよう。
ってことですもんね。
ああ、私がたまにボケボケなのはこのためなのか。
最近はしなくなりましたが、
缶切りを買いにいったのに、
栓抜きを買ってきてしまったのは
脳の省力化だったのね、
あれによって、
ほかの時間は冴えていたのかもしれない、
と妙に納得。
いやいや、結果として緩急がついちゃった、よりも、
ちゃんと意図して緩急をつけたほうがいいですね。
ここで脳を使わないようにしよう、
逆にこっちで使おう。
そんなふうに少しでも意識してコントロールできれば、
確証バイアスが働かないように
できるのかもしれません。
皆さんは脳のパワーをどこで使って、
どこで休めますか?
さて、本格的に暑くなってきましたね。
体調に気をつけてまいりましょう。


