『挑戦・やってみる』カテゴリの記事
脳のパワー、どこで使う?どこで休める?

昔から血液型や星座によるタイプ診断的なものに
興味がありません。
興味がないのは、一度も「当たってる」と
思ったことがないからだと思います。
私はA型で山羊座なのですが、
この組み合わせで目にする説明は
だいたい以下のような感じです。
「とても真面目。几帳面。慎重。コツコツ努力型」
ううむ。当たってない。
そんなわけで、血液型論は信じてこなかったのですが、
世の中、結構頻繁に人間関係と血液型が
一緒に語られますよね。
プライベートトーク、とくにママ同士のトークなどでは
よく出てきました。
「B型なんだ。やっぱりね」
「そうだよね、あの人AB型だもんね」
のような会話です。
私の場合は「A型っぽくない」と
言われ続けてきました。
A型は真面目で几帳面とか、AB型は変わっているなどの
なぜそう言えるのか?というような情報を
無意識に信じてしまって、バイアスになっていることを
確証バイアスと言いますよね。
血液型以外にも、
「女性はていねいだから、細かい仕事に向いている」
とか
「アウトドア派の人は明るく、コミュ力が高い」
とか(笑)、まだまだあると思います。
人事コンサルタントの曽和利光氏によると、
そもそも、人が確証バイアスにとらわれてしまうのは、
脳を「省力化」したいからだそうです。
日々接するさまざまな対象を
イチから認識・解釈していくと、
知的パワーを大幅に消費することになり、頭が疲れる。
すでに何度も直面した対象(物事)に、
毎回初めて出会ったかのように
イチから認識を始めていては、
知的パワーがいくらあっても足りないので、
思い込むことで省力化しているのだと言います。
なるほど。確かにそうかもしれません。
時間もパワーも有限です。
いちいち、「いや、本当にそうなんだろうか。
そうとは言い切れないんじゃないだろうか」
とならないやり方を脳が選んでいるのかもしれません。
しかし、確証バイアスにとらわれてしまうと、
フラットな判断ができなくなります。
曽和氏は、ジョブズやザッカーバーグが
毎日着る服に悩まないよう、
ユニフォーム化しているのは、
脳のパワーを使わない対象をつくることで、
それ以外の判断をクリアにできるようにしていると
説明しています。
そうか。やはりインプットでも「緩急」なんだ。
と、私は思いました。
なんのこっちゃってことですが、
私は、以前から度々このメルマガで
「緩急」「強弱」はとても大事
ということをお話ししています。
それは、主にアウトプットでの意味でした。
たとえばダンスや音楽だとわかりやすいですが、
全部を同じスピードで、強い力で表現しても
あまり良さが伝わらないけれど、
速くなるところ、遅くなるところ、
強いところ、弱いところが表現されていると、
ぐんとストーリー性が出て、見ている人、
聞いている人の感情に
アクセスしやすくなる。
これは、記事の執筆などでも同じです。
しかし、今回の話はインプットの話。
脳は、何かを理解する時、
いつも全力でパワーを使わないように、
確証バイアスで省力化している。
しかし、それだとフラットな判断ができなくなる。
そうならないように、
脳がパワーを使わない対象を決めて、
脳がきちんと休める状態もつくり、
逆にパワーを使わなくてはならないところに
使えるようにしよう。
ってことですもんね。
ああ、私がたまにボケボケなのはこのためなのか。
最近はしなくなりましたが、
缶切りを買いにいったのに、
栓抜きを買ってきてしまったのは
脳の省力化だったのね、
あれによって、
ほかの時間は冴えていたのかもしれない、
と妙に納得。
いやいや、結果として緩急がついちゃった、よりも、
ちゃんと意図して緩急をつけたほうがいいですね。
ここで脳を使わないようにしよう、
逆にこっちで使おう。
そんなふうに少しでも意識してコントロールできれば、
確証バイアスが働かないように
できるのかもしれません。
皆さんは脳のパワーをどこで使って、
どこで休めますか?
さて、本格的に暑くなってきましたね。
体調に気をつけてまいりましょう。
「忙しいから」なのか?
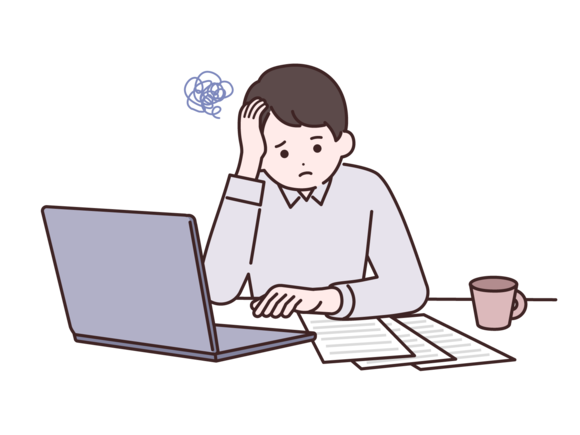
家の片付けをしていたら、20年ほど前に買った
コンパクトデジタルカメラが出てきました。
最後に使ったのはたぶん12~3年前くらい。
そこからずっと引き出しの奥で
眠っていました。
まだ使えるかどうかわかりませんでしたが、
充電してみたら動いたので、
早速何枚か撮ってみることにしました。
初期のコンデジなので
使い方はとてもシンプルですが、
いろいろと忘れてしまっていたので、
ネットで取扱説明書を探し、
あらためて機能を調べました。
少しずつ設定を変えながら撮っていて
気づきました。
とても優秀なカメラだったのだと。
当時は子育てでバタバタだったこともあり、
AUTOで撮るばかりで、
どこをどのくらい調整できるのかを
あまり見ておらず、
いたって普通の写真を撮っていました。
でも、あらためて触ってみると、
かなりいい感じで撮れるのです。
20年近く、気づいていなかった。
うう、購入時にちゃんと調べておけばよかった。
なんて後悔したものの、
「ま、普通に撮れればいいか」
くらいに思っていたのも事実。
でもやはり、もっと前にやる気になって
使いこなせるようになっていれば、
高いクオリティの子ども写真が
残せたはず・・・と反省しました。
考えてみると、こういうことはよくありますね。
「機能を知らなかったから、使ってこなかった」
ということもあると思いますが、
「なんとなく知ってはいたけど、
情報を得るのが面倒で使わなかった」
とか
「なんとなく知ってはいたけど、
難しそうだったので、使ってこなかった」
こっちのほうが多いのではないでしょうか。
たとえば、スマホ。
便利機能があるのは知っているけど、
調べるのも覚えるのも面倒で、
一瞬で終わるかもしれない作業に
何分もかけている。
とか
エクセルで何かの資料をつくるとき、
関数やマクロを使えば長い目で見ると
効率化につながるのに、
覚えるのも理解するのも大変そうだから、
非効率だと知っているけれど
今までのやり方でやっている。
など。
なぜ新しい情報を得たり、覚えたり、
試してみたりするのを避けるのか。
最初に出てくる理由はおそらく、「忙しいから」。
でもきっと、その奥には
こんな思いがあるのではと思います。
「今、特に困っていないから、今までと一緒でいい」
「下手に何か変えると、時間がかかってややこしい」
「何か新しいことをして、失敗するのがいやだ」
自分で書きながら、いろいろ思い出されて
反省モードに入ってきました(笑)。
はい、そうです。
「忙しいし、いろいろ調べたり、試す時間がない」
これですよね...
しかし、じゃあ忙しくないタイミングが
いつかやってくるのか?
というと、そんなことはない。
常に「忙しい」。
なので、これを続けていると、
「THE前例踏襲の人」になってしまいます。
世の中、リスキリングが叫ばれています。
ベネッセが2023年に
社会人4万人を対象に実施した
「リスキリングに関する生活者理解のためのインサイト調査」
社会人の約40%が、
直近1年間の学習経験も今後の学習意欲もない
「なんで学ぶの」層なのだそう。
調査では、人生に対して主体性が持てない、
自己肯定感が低い人が多く存在すること、
そして、リスキリング=押し付けられるだけの終わらないタスク
と捉える人が多いことも明らかになりました。
ううむ。
やはり学びは自発的でないといけないですよね。
自分では学ぶ意味がないと思っているのに、
外から「学べ!」と言われても、
本当の学びにつながるとは思えません。
では、どうしたら学ぶ意欲が高まるのか。
これは私の考えですが、
一つは学びのハードルを下げることかなと思います。
お金を払って何かの学校に行ったり
オンライン講座を受けるなどの学びもいいですが、
学びのイメージが学校や講座ありきだと
金銭的、時間的理由からなかなか始められない。
なので、今日、新しい機能を一つ使ってみる、
くらいでもいいのではないでしょうか。
昨日と違うことをしてみるくらいの気軽さで
トライしていると、1年経てば、
かなりの学び量になっていますよね。
あとは、未来を見るしかないんじゃないかな
と思います。
過去にうまくいかなかったから、やる意味がない。
など、過去の失敗経験に囚われると、前に進めません。
だから、未来を見る。
そして大袈裟なくらいポジティブなイメージを描く!
これを覚えたら、仕事がだいぶ効率化されて、
帰りにジムに寄る時間が増えて、
スーパーボディになるかも!
くらいのやつです。
自分自身が楽しむのが一番ですから。
なんて言ってますが、
実は私もいろいろとできていない...。
今回は自分自身に言い聞かせる感じになりました。
さて、もう6月も中旬です。
今年が半分終わりますね。
ジメジメしていますが、
体調に気をつけてまいりましょう!
細かく刻もう

以前どこかのインタビューで
YOASOBIのボーカル、幾多りらが
「歌うときは、なるべく細かい音符で
理解する」というようなことを
言っていました。
2019年に大ヒットした
『夜に駆ける』のレコーディングのことを
言っていたと記憶しています。
テンポが速い。言葉も多い。転調も多くて、
息継ぎのタイミングも難しい。
とにかく歌うのが難しい曲だったそう。
少しもずれられないので、
音符を細かく刻んで、
音を捉えたというようなことでした。
一拍の中の細かな音符を捉える。
たとえば、いーち、にーい、さーん、しーい
の中に、それぞれ4拍捉える。
いちにさんし、にいにさんし、
さんにさんし、しいにさんし
みたいなことだと思います
(文字で書くと難しいですね。
理解していたただけたでしょうか)。
これを読んだとき、すごく納得しました。
実は私、大昔にダンスをしていたのですが、
キレキレなダンサーは
すごく細かく音を捉えて、
その細かい音にも動きを合わせている。
大雑把に音を捉えると、
動きも大雑把になってしまい、
間延びしてしまうんですよね。
私はできませんでしたが、
キレッキレで緩急あるダンスをする人は
音を細かく捉えるのがうまいなあと
思っていました。
音楽では音ですが、この「細かく捉える」と
上達するというのは、いろいろなジャンルで
言えることだと思います。
たとえば、スポーツ。
テニスでラケットを構えるとき、
いちで体の正面でラケットを構え、
にで足とラケット引いて、
さんで打つという動きがありますよね。
あれを、いーち、にーい、さーん
とやるのか、
いちにっさん、にいにっさん、
さんにっさん で捉えるのかで、
やることが変わると思うのです。
細かく捉えると、
そのタイミングで体がどこにあるのか、
腕がどこにあるのか、
重心がどこにあるのかまで
意識することができる。
そうすると、修正していける
ということだと思います。
そしてこれ、仕事でも言えますね。
たとえば制作の仕事で言うと、
学生向けに
企業の採用パンフレットをつくる
と捉えるのか、
その企業をほとんど知らない
理系の学生向けに、
ストーリー仕立ての
採用パンフレットを
ウェブ閲覧用につくる
というところまで捉えるかでは、
やることが全然違ってきます。
細かく捉えようとすると、
疑問がわき、確認事項が発生する。
それを一つひとつ確認していくことで、
精度が高くなっていくのだと思います。
さて、あっという間にGW前半が終わりました。
お休みされている皆さんも
お仕事をしている皆さんも
どうぞ体調に気をつけてお過ごしください。
時には、しつこく

しつこい人。
どういう人でしょうか。
ネットでは、しつこい人の行動として、
こんなものが出てきます。
何度も同じことを聞いてくる。
こちらの温度感を考えない頻度で連絡してくる。
LINEの文章が長い。
とにかく細かい。
おせっかい。
心配性。
自分勝手。
思い込みが強い。
うーん、通常、嫌われてしまう行動ですよね。
エスカレートしてしまうこともありますし。
心理カウンセラーによる
しつこい人の対処法、なんかもあったりして、
しつこくされる人、困っている人が少なくないんだな
と思います。
では、しつこい人はなぜしつこくしちゃうのかを考えてみました。
心配性で気になると確認せずにいられない、とか、
私がやってあげなければという思い込み、
熱量が大きい、ということもありますね。おそらく。
がっと熱が入って、集中してしまう。
で、その熱をわりとずっと保って行動できる、
という人たちなのかと想像します。
しつこいと嫌われるけど、そんなしつこさを
持っていないといけない人たちもいますね。
それが、新しいものをつくりだす人、
大きな物を動かす人、推進していく人たち。
こういう人たちはあっさりするわけにはいきません。
たとえば、イーロン・マスク。
周囲がひいてしまうほどのしつこさでしょうね。
スティーブ・ジョブズもそうだったのではと思います。
『結局、「しつこい人」がすべてを手に入れる』
の著者、伊庭正康氏は、
「しつこさ」はスキルの一つだ、と言っています。
「しつこさというと、具体的な方法論が見えづらく、
根性だの気合いだのといった話になりがちですが、
そうではなくて、しつこさに必要なのは、
ちょっとしたコツを加えること、
いろいろと妄想を膨らませることです。
そして、いいしつこさを発揮するには、
最上位の目標を考えること。
ゴールをぶらさず、いろいろ試してみること。
一つ失敗して終わりではなく、新しいやり方を試して、
諦めずに最上位の目標に向かうこと」
TKKの法則。
これ、伊庭氏による、しつこさを身につける法則です。
T たのしくする
K かんたんにする
K こうかを確認する
確かに。何かを動かしていく人たちの共通点は
簡単に諦めないこと。楽しんで、楽に、
そして、とにかくやり続けることかもしれません。
ビジネスに限らず、ダイエットでも何でも
何かに取り掛かってうまくいかないとき、
足りていないのは「しつこさ」だなあと思いますね。
しつこさにはエネルギーが必要なので、そのエネルギーは
楽しくないと生まれないってことか、と納得しました。
最後に、
しつこい人が、しつこく思われないために、
伊庭氏は「自分軸で勢いよく話す前に、相手の話を聞くこと」
と言っています(笑)。
当たり前ですが、熱が高いと忘れがちなのかもしれませんね。
さあ、12月。今年も残り少ないです。
しつこさをうまくコントロールして行きましょう!
「負荷」、かけていますか?

急に寒くなってきましたね。
寒くなると増すのが食欲。
秋は何もかもおいしい。
あれもこれも食べたい。
好きなだけ食べても太らなかった
あの頃に戻りたい。
そう願っても戻れるわけはないので、
あれこれ食べたいなら、その分、
運動するしかありません。
そんなわけで、自宅でも無理なく続けられそうな
筋トレメニューをネットで眺めていたのですが、
そうこうしているうちに、気づきました。
この「無理なく」というのが、いかんのだと。
無理のない、ちっともつらくないエクササイズを
無理のない回数こなしたところで、
筋トレにはならないと知ったのです。
フィジカルトレーナーの
中野ジェームズ修一氏はこう言っています。
「筋肉は、同じ負荷を与え続けると
そのレベルに慣れてしまい、
それ以上成長しなくなるという特性があります。
常に、ややきついと感じる運動レベルが
筋力アップにつながるのです」
極端に言うと、楽ちんエクササイズを
100回やるよりも、きついと感じるメニューを
10回やるほうが筋トレにつながる。
つまり、負荷が必要だということです。
負荷・・・。
ですよね。そりゃ、そうだ。
きつさなくして成長なし。
これは筋トレに限った話じゃないですね。
ゲームでも、仕事でも、何でもそうですが、
最初は難しい、つらいと感じるレベルに
挑戦しているうちに、スキルが上がって、
クリアできるようになる。
自分にとって無理のない、
楽ちんと感じることを長く続けても、
成長にはつながらないんですよね・・・。
No pain, no gainってよく言いますしね。
と、こういうことを言うと、
「昭和の教育か!」
というツッコミをうちの次男なんかはしてきます。
苦労っぽいニュアンスが出てくると、
とたんに「はいはい、昭和」で片付けたがる。
まあ、おそらく、成長に負荷が必要なことは
本人もわかっているのだと思いますが、
直視したくないので、そういうリアクションに
なっているのだろうと思って、見ています(笑)。
さて、日本能率協会マネジメントセンターが行った
「イマドキ若手社員の仕事に対する意識調査2020」
(2019~2020年の新入社員、
その育成にかかわった上司、計1502人が対象)
を見ると、
若手社員の特徴は以下のようにまとめられています。
「自分のことを認めてくれる環境で、
無理なく、無駄なく成長したい」
なるほど。成長意欲はあるし、認められたい。
しかし無理や無駄はNGなんですね。
無理を避けるのは、慣れないことをして
失敗したくないからですよね。
無駄も、一見、失敗と関係ないようですが、
効率的にやりたいというのは
正解とわかっていることをやりたいということで、
やはり失敗するのがいやなのかなと思います。
失敗を避けるのは、他人からの評価が
気になるからでしょうか。
同調査では「他人からの評価が気になる」人が
8割に達しています。
ここが高いのは、彼らがSNS世代だからですね、
おそらく。
「いいね」がつくか、つかないか。
無意識かもしれませんが、
どこかでそんなことを気にするのかもしれません。
でも、やはり、誰からも何にも言われない、なんて
非現実的。
みんながみんないいことしか言わないのは
むしろ嘘っぽいですね。
漫画『ジョジョの奇妙な冒険』の作者、
荒木飛呂彦氏は、著書『荒木飛呂彦の漫画術』で
こんなことを言っています。
ぼくがデビューした頃は厳しい編集者が大勢いて、
彼らは、漫画を持ち込む新人に対して
「プライドを傷つけないようにしよう」とか
「気持ちを思いやる」なんてことは全く考えず、
プロに徹する仕事人として、厳しいことを
ズケズケ言ってきました。でも、好きというだけで
漫画を描いていたぼくが王道に目覚めたのは
彼らのおかげです。
編集者の厳しいフィードバックがあるから、
クリアしようと挑戦して、レベルアップする。
あのジョジョだって
そうして生まれてきているんですね。
そういえば、漫画の話ばかりで恐縮ですが、
『進撃の巨人』の作者、諫山創氏も、
最初は編集者から「線が汚い」と言われ、
デビューが決まってからも練習し続けた
という記事を読みました。
諫山氏は、売れっ子になってからも、
ポジティブなコメントはうれしいが、
参考にならないと言って、
自ら進んで否定的なコメントを
探しにいっているとか。ストイックですね・・・。
いずれにしても、負荷がかかり、
乗り越えるというプロセスがないと、
こうした大作は生まれないのだなということを
改めて感じますよね。
成長には負荷が必要。
筋肉の成長にも負荷が必要。
最近はエスカレーターではなく階段を使っていますよ!
(小さな負荷から始めております)
11月もあっという間に過ぎていきます。
健康に気をつけてまいりましょう。
ハッタリはセルフ・プロデュース
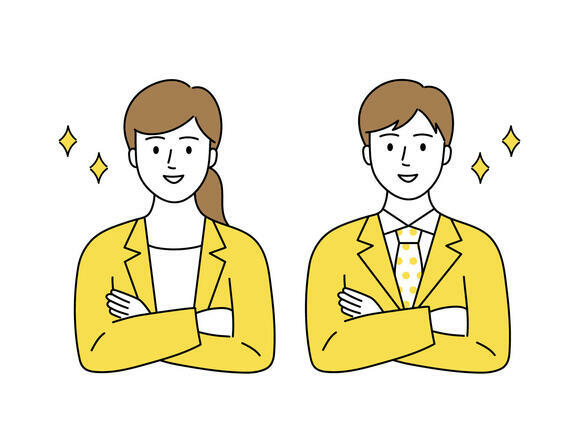
30年ほど前のこと。
勤めていた会社を辞めてNYに移り住んだ私は、
当時、その会社は受付スタッフも募集していて
毎日のように数人が面接に来ていました。
アメリカだからなのか、その会社の特徴だったのか、
だれかが、と言ったのは、
受付ブースに座る人がころころ変わっていたからです。
「あれ? 昨日は女の子じゃなかった?
今日は男性が座ってるね」
「あれ? 先週いた子は?」
という感じで、どんどん人が入れ替わる。
ある日、その理由を採用担当のマネージャーに聞いてみると、
例えば「パソコンの知識はエクセレントだ」と言ってくるが、
でもそんなことは日常茶飯事なようで、彼女は「困るわよねー」
びっくりしました。
だって、すぐにバレることじゃないですか。
実際できないんだから。
しかも、バレたときに「ウソつきましたね」となって、
しかし、それをアメリカ人の友達に言ったところ、
「私だって、エクセレント・オーガナイズ・スキルと書く」と。
彼女は、片付けがまったくできなかったので、
「ウソでしょ!」って思いましたが、
なるほど、そういうものなのかと思いました。
自分のスキルを正直に伝えるどころか、
「それほどでもないです」と
低めに言ってしまうことの多い日本人と、
少しでもできれば(ほとんどできなくても)
エクセレントだと表現し、自分を最大限に売り込むアメリカ人。
考えてみると、私たち日本人は、セルフ・
でも、これは「ハッタリ」ってことだろうなと思いました。
私の古くからの友人に、学生の頃、
彼女は、
「水泳コーチのバイトをする、背中が美しい女子大生」
になると決めていたらしいのです。
泳げないのになぜ採用されたかというと、
コーチたちが、
「私たちがあなたに泳ぎを教えます」となったのだとか(彼女談)
そんなバカな、と聞いた時は思いましたが、
実際に泳ぎを覚え、美しい背中になった彼女を見て、
彼女はその後も、ほとんどできないのに
何かに応募しては、面接で
「実はこれは今はあまりできないのですが、
こういうことならできます!」
などと自分を売り込み、いろいろなことを実現させてきました。
彼女のアクションはいつも
「なりたい自分をイメージ」、
次に「ハッタリ」、そして「実現」でした。
今思うと、実現に向かうために、
ハッタリで自分にプレッシャーをかけていたのだろうなと思います
そういえば、以前、
「
ハッタリをかまし続けると実績も後からついてきます」
カリスさんは韓国出身で、
「思い込みが大事なんです。自分は特別と思っていない人は、
とカリスさん。
なるほどなあ、と思うと同時に、今の日本、
「いやいや、そんな私なんてそれほどでもないです」
みたいな人ばかりだと勢いがなくなるばかり。
「ハッタリ」をかける人も必要だし、それを受ける側も「
それ、本当に苦手ですか?

「人間の行う仕事の約半分が機械に奪われる」
英オックスフォード大学のオズボーン准教授が
そんな内容の論文を発表して
世の中を騒がせたのが8年前。
AI時代を生き抜くために必要な力として
「創造力」が挙げられるようになりました。
アドビが2020年に日本の高校生1200人を対象に
行った調査によると、「自分には創造力がある」と
答えた生徒は55%。「創造力がない」(45%)を
少し上回っています。
創造力をどう捉えているかという問いでは、
「自分らしい個性を自由に表現する力」(63%)
「芸術性の高いものを生み出す力」(46%)
「何もないところから新しいものを生み出す力」(46%)
「育った環境や努力によって培われるもの」(45%)
という回答でした。
SNSで写真や動画を日常的にアップしている
彼らなので、自分には創造力があると
感じている人はもっと多いのかと思ったのですが、
それほどでもなく、
「自分には創造力がない」が45%かあ。
うーむ、「ある」と答えた人が半数を超えたとはいえ、
半数近くの高校生が「創造力がない」と
感じているとは、なんとも残念だなあと思います。
だって、まだ高校生ですよ。
さらに残念だと思ったのは、「ない」と答えた人が
創造力に対する自信を失ったきっかけが
小学校高学年の図画工作の時間や
中学校の美術の時間にあると答えていること。
とくに中学校の美術の時間に自信を失ったと
回答した人が多く、そう感じた理由として
「成績が悪かった」
「周りの人より下手だった」
「アイデアが浮かばなかった」
との声があがっています。
生徒の創造力を伸ばすべき美術の授業が
逆に創造力を失わせてしまっているのは、
悲しいなあと思います。
これは私の想像ですが、
小学校のとくに低学年くらいまでは、
どんな絵を描いても、先生が褒めてくれると思うのです。
「わあ、大胆でいいね」とか「個性的でいいね」とか。
でも、中学校になると内申点というものがあるので、
学校側がおおらかに成績をつけなくなります。
生徒も、おかしな絵を描いて成績を落としたくないから
自由に描かない。
お手本のように、すごくきれいに描ける人、
テストの点数が高い人が良い成績をとるので、
それができない人は自信を失うことに
なるのではないでしょうか。
さらに厄介なのは、
ここでいったん苦手意識が芽生えると、
それ以降もずっと苦手と思い込んでしまうこと。
芸術系のものはとくに苦手意識が
刷り込まれやすいように思います。
創造力は、単に絵をうまく描く力ではなく、
ビジネスのあらゆるところで
必要になってくる力。
創造力がないと思い込んでしまうのは
とてももったいないと思います。
なんて書きながら思ったことは、
小・中学校で感じた苦手は
実は苦手じゃないのかも?ということ。
成績や評価を気にして苦手と思い込んだり、
嫌いになったもの、案外あるのかもしれません。
伸び伸びと自由にやってみたら、
苦手と思っていたことでも案外楽しめたり、
むしろ好きと思える可能性もありますね。
2022年、スタートしたばかりです。
皆さんは今年、どんなことにトライしますか?
ガッツ!は時代遅れ?

先日、YouTubeで何気なく観た、
お笑いコンビ、ティモンディ 高岸さんの
ヤクルト始球式の動画で感動してしまいました。
昨年10月、神宮球場で行われた
ヤクルト-広島戦。
この日は、ヤクルトのキャンプ地である
松山市と交流を深める「松山DAY」で、
松山市の野球強豪校、済美高校の
野球部出身であるティモンディ高岸さんが
始球式のマウンドに立ちました。
キャッチャーはコンビの相方であり、
同じく済美高校野球部出身の前田さんです。
高岸さんは、芸能界最速と言われる
147kmの豪速球を投げることで知られています。
どれだけ速い、いい球を投げるのか。
観客の視線が高岸さんに注がれます。
しかし、高岸さんは一向に
投球モーションに入れません。
涙を流しているのです。
涙を拭いて、帽子をかぶりなおして、
モーションに入ろうとするのですが、
また涙が流れてくるから、まったく投球できない。
何度も、何度も涙を拭いて、
ようやく振りかぶって投げた球を
しっかりとキャッチした前田さん。
マスクを上げて、やっぱり涙を拭いて、
マウンドに駆け寄り、笑顔で高岸さんと
抱き合います。
球場全体から温かい拍手が巻き起こりました。
彼らは高校の野球部時代、
甲子園優勝を目指し、
その後はプロになることを夢見ていたと
雑誌の記事で知りました。
野球部のモットーは「心技体」ならぬ「体心技」。
まずは体を作ることから、というトレーニングは
相当キツかったと言います。
ところが、甲子園に出場できたのは
高1の一度きり。しかも応援席。
卒業後、高岸さんは大学で野球を続けましたが、
怪我でプロの道を断念。
前田さんもまた大学で野球をやることは
ありませんでした。
その後、高岸さんの誘いでお笑いの道に。
結成時、「始球式に出る」ということを
一つの目標にしていたそうなのです。
マウンドに立ったとたん、
野球に打ち込んだ高校時代の熱い思い、
そして怪我をしたときの絶望感、
お笑いの誘いを受けてくれた前田さんへの感謝、
いろいろが一気に押し寄せてきたのかも
しれません。
一生懸命打ち込んだ経験があるから、
感情が溢れ出してしまうのだと思いました。
そして、頑張っている人、頑張った人、
新たな夢を叶えた人の姿はやはり感動的だなあ、
ともらい泣きしながら感じました。
さて、ここ数年で「グリット GRIT」という
ワードを耳にするようになりました。
アメリカの心理学者、
アンジェラ・ダックワース氏の著書
「GRIT やり抜く力
人生のあらゆる成功を決める
『究極の能力』を身につける」
は、日本では2016年に発売され、
ベストセラーになりました。
GRITとは、
G Guts(闘志)
R Resilience(粘り強さ)
I Initiative(自発)
T Tenacity(執念)
の頭文字をとったもの。
GRIT、やり抜く力がある人は、
芯があり、それでいて変化への適応力が高いと
言われています。
グーグルではGRITがある人を
積極的に採用し始めており、
ビル・ゲイツやマーク・ザッカーバーグなど
多くのビジネスリーダーがこの力を
重視しているのだそうです。
書籍の中で、ダックワース氏は
成功した人の多くは「天才」だから、
また「才能」があったからと
言われることが多いが、そうではなく、
共通してあるのはGRITだと言っています。
「ガッツがない」とか「粘り強く」なんて
今の子どもたちに言うと、
「出た! 昭和!」とか言われがち。
うちの次男なんかは、必ずそう返してきますが、
でも、やはり、何かに打ち込んでいくためには、
こうした力が必要なんだなと改めて感じます。
ところで、GRIT、
大人になってからも伸ばせるそうなのです。
そのために必要なことは、
・興味があることに打ち込む
・失敗を恐れずにチャレンジし続ける
・小さな成功体験を積み重ねる
・GRITがある人たちの中に入る
もしくは近くにいく
どうでしょう。
最初の3つは、いやいやそれが難しいんですよと、
怠け癖がある私は思ってしまう感じですが(笑)、
4つ目はいいかもしれないと感じました。
GRITがある人たちの輪に入ると、
周りの価値観が自分のスタンダードに
なっていくからです。
ランニングのアプリで周りの人たちとつながり、
一緒に目標を達成していくというのは
まさにこれですよね。
秋も深まってまいりました。
運動するにも、芸術活動をするにもいい季節。
GRITを伸ばすためにはベストなシーズンかもしれません!
(しかし食べるにもいい季節なんですよね...)
今週もあと少し、がんばってまいりましょう!
小さな目標で習慣化
![AdobeStock_232461614-[更新済み]_resize.jpg](https://www.grassroots.co.jp/blog/abelog/images/c9c1aeca9cb5eb4ff561f1448411a73860be965a.jpg)
早いものでもうすぐ4月。
新しいことを始めるには、いいタイミングですね。
「実は、年初に始めたことがあるのですが、
続いていないんです」
とか
「最初の数日はがんばったのですが、
面倒になってきて」
など、年明けに何か始めてみたものの続かなかった、
という人にとっても、4月はリトライするいい機会。
と、常にいいタイミングを探してしまうこと、
続けられない人あるあるなのかも、と
最近気づきました。
続けられないということは、
ほかに原因があるはずなのに・・・。
そうです。私も数年前の年初、
「今年は、毎朝、近所をランニングする!」と決めて
しばらく走っていたのですが、
1ヶ月ほどで続かなくなってしまいました。
敵は花粉でした(と当時は思っていました)。
1月はわりと順調に走っていたのですが、
2月が近づいたあたりから、
くしゃみと目のかゆみで、走っているよりも、
立ち止まっているほうが長くなってしまい、
「なぜ私は外に出て、わざわざ花粉を
吸い込んでおるんだ?」
という気持ちになって、
花粉シーズンが終わるまでお休みすることに。
しかし、いざ花粉シーズンが終わったと思ったら、
今度はじわじわ暑くなり、
「なぜ私は朝からわざわざこんなに
汗だくになっておるんだ?」
という気持ちになって・・・
ということを、「走る走ると言って、なぜ走らない?」と
聞いてきた次男に、先日説明していたら、
完全に呆れられました。
さて、数年前に『小さな習慣』という本が
全米でベストセラーになりました。
自己啓発ストラテジーの調査と執筆を行う
スティーブン・ガイズ氏によって書かれた本です。
ガイズ氏が本の中で言っていることはいたってシンプル。
習慣化するためには、
目標をばかばかしいくらい小さくする
ということです。
ガイズ氏は、30分の運動を日課にしたくても
まったくできなかったという経験の持ち主。
ところが、当時読んでいた本からヒントを得て、
ばかばかしいと思いながらも、
「毎日腕立て伏せを1回する」ということに
チャレンジした結果、それが最終的に30分の運動に
つながったのだそうです。
ちなみに、この「腕立て伏せ1回チャレンジ」は、
筆者のブログの中で一番反響があった
投稿だったといいます。
そもそも、多くの人は、
自身の管理能力を過信しているのだそうで、
たとえば「毎日腕立て伏せ30回、腹筋30回する」
は無理な目標だと思わず、
十分可能だと思ってしまうのだそうです。
でも、始めてみると、なかなかハードだと気づき、
ストレスになり、続けられなくなる。
確かになあ、と思いました。
欲張っちゃうんですよね、なぜか。
調査によると、人間の行動の45%は習慣として
自動的に行われているといいます。
というのも、脳は省エネを好むから。
えいやと気合を入れないといけないような行動には
たくさんのエネルギーを必要とし、
脳にとってストレスが大きい。
でも、小さな行動は、脳にとって
「新しくて大変な行動がやってきた!」というほど、
ストレスをかけないので、
自動化しやすいということなんです。
そうか、確かに私の走る目標はハードル高めでした。
まず「朝」がハードルが高い、
「外」も高い。
そもそも「走る」も高かったのかも?
ひいい、ちょっと考え直してみます。
まだまだ花粉が舞う季節ですが、
今週もすてきな1週間をお過ごしください。
よしできた! リリース!

「札幌の女子高生2人組によるテクノバンド
LAUSBUB(ラウスバブ)が発表した曲が世界から注目を集めている」
という記事を目にしました。
よく読んでみると、
彼女たちが昨年の年末に
「SoundCloud」というドイツの音楽プラットフォームに公開した楽曲が、
今年に入ってSNSを通じて世界中に拡がったということ。
公開後、瞬く間にチャートを駆け上がり
あの世界的人気の韓国男性音楽グループBTSを抑えて
週間チャート1位になったのだそうです。
すごい。単純にすごいです、1位。
でも私がさらに、へえーと思ったのは、
彼女たちがドイツの音楽プラットフォームを選んで曲を公開したことです。
調べてみると、SoundCloudは、ベルリン発祥の音声ファイル共有サービスで、
今年1月の発表では世界190カ国で3,000万人のクリエイターが参加し、
2億5,000万以上の楽曲が聞かれている世界最大規模の音楽プラットフォームなんですね。
彼女たちがここを選んだのは、まさに、
「世界の人に聞いてもらいたいと思ったから」。
インタビューで理由をそう語っていてすごい時代だなあと思いました。
昔は、たとえば音楽であれば、世の中に出ていくためには、
ライブハウスで演奏できるくらいになって、
ファンを増やして、話題を作って、
それなりの人に見つけてもらって・・・と、
ハードルがたくさんあったと思います。
でも、今はダイレクトに世界の人に自分の曲を聞いてもらえる!
今できた曲を数分後に世界に流せる。
何を今さら。いつの時代の人?って言われそうですが、
「札幌の女子高生テクノバンド、
ドイツの音楽プラットフォームで週間チャート1位に」
なんて聞くと、やはりそこの違いを
感じずにはいられません。
このニュースを聞いて、もう一つ思ったことがあります。
それは、デジタルネイティブ世代は、
「よし、できた。出してみよう」に慣れてきているんだろうなあ、ということ。
本来、日本人は他の国の人たちよりも
完璧主義なんじゃないかと思います。
それが日本製品の質の高さにつながっている。
細かなところまでこだわり抜いて、最高レベルまでクオリティを高めるのが得意です。
でも、今の時代、グローバルで勝負しようと思ったら、
そのスピードじゃだめなんでしょうね。
じっくりじっくりこだわっている間に、ニーズがなくなってしまうくらいの速度で
世の中が変わっています。
インドがIT大国になったのは、
6割主義だからだと、どこかで読みました。
6割できたらリリース。
あとはクレームや意見を受け付けながら、修正を加えていく。
このスピード感だから、
世界中からお金が集まるのだそうです。
デジタルネイティブの若い世代も、このスピードに慣れています。
なので「よし、できた。出そう」ができる。
女子高生テクノバンド
LAUSBUB(ラウスバブ)も、
そんなスピード感で、年末というタイミングを見計らって
リリースしたんじゃないかなと想像します。
彼女たちの曲を実際聞きました。
こういうものを高校生が
打ち込みで作るんだなあと感心するレベル。
いや、高校生だからできるんですね、きっと。
作りたいから作るという
ピュアなモチベーションなんだろうなあ。
中学生のときにYMOに影響を受けた私としては、ちょっと衝撃でした。
そう考えると、
日本人の完璧主義には、
いろんな「~すべき」が入ってるのかも。
音楽にしても、
「打ち込みするなら、まず楽器に慣れるべき」
とか
「それを聞くなら、先にこっちを聞くべき」
とか。
しっかり土台を築いていくためには、
それでいいのかもしれませんが、
グローバルでの競争を考えると、やはり
そういうことから自由になることが必要なのかもしれません。
あっという間に3月。
今週もすてきな1週間をお過ごしください。

