『コミュニケーション』カテゴリの記事
3 ページ / 18 ページ
他人事ではない、森さんの問題
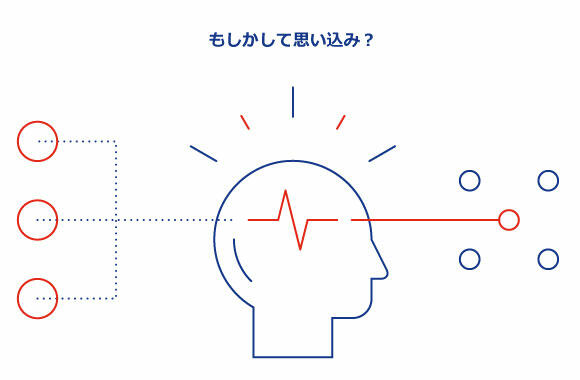
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の
森喜朗前会長の女性蔑視発言に端を発した
後任会長問題は、橋本聖子前五輪相が就任し決着しました。
橋本さんの人柄や実績についてはよく知りませんが、
当初は過去のスキャンダルなどを理由に固辞していたそうです。
にもかかわらず、火中の栗を拾うようなこの状況で、
よく逃げずに引き受けられたと思います。がんばってほしいですね。
さて、今日の本題は「偏見」についてです。
森さんの発言は「失言」と報じられていました。
あの失言の本質は、言葉の表現の問題ではなく、
心の「本音」が出てしまったということだと思います。
だから、本来はあの発言がなければ良しということではなく、
そういう価値観の人物が組織委員会の長にいること自体が、
世界から問題視されたわけですよね。
今回の森さんの、女性は話が長いという発言内容には、
根っこに「偏見」がありました。
女性に対するネガティブで偏った先入観です。
でも、考えてみると、女性への偏見は未だに社会全体にありますよね。
別に森さんの肩を持つつもりはありませんし、
女性は被害者、男性が加害者と言うつもりもありません。
でも、現に日本のジェンダー・ギャップ指数は153カ国中、121位です。
これは、世界経済フォーラムが毎年発表している
経済・教育・保健・政治分野の男女平等度を表す指数のこと。
あまりの低さにびっくりしてしまいますよね。
話を元に戻すと、ある対象に対して、
ネガティブで偏った思い込みを持つというのは、
人間の特性だとも言えます。
思い込みが怖いのは、思い込んでいるがゆえに、
信じて疑わず、気づけなくなることです。
今回、新会長に就任した橋本聖子さんは、
「参院議員に初当選したとき、
『経済がわからないオリンピック選手がなぜ政治家になるのか』と揶揄された」
とご自身のサイトで書いています。
当選は1995年のことですから、最早26年前ですね。
では、今回の会長就任に対する社会の目はどうなのでしょう?
正直に告白しますよ。
私自身、橋本さんのことをあまり良く知らないのに、
橋本さんで務まるんだろうかと一瞬ですが思ってしまいました。
理由は、やっぱり元オリンピック選手の橋本聖子さんの印象の方が強烈で、
政治手腕やリーダーシップに長けているという印象が薄かったからです。
しかし、だからと言って、26年も政治家として活動して来た橋本さんに対し、
「橋本さんで務まるんだろうか?」と考えるのは失礼だし、やっぱり偏見です。
なぜ、こういうネガティブな先入観が出てくるのでしょうか。
理由を思いつくままに出してみました。
・知らないものに対して、人はそれだけで不安を感じてしまうから。
・アスリートと政治家、それぞれに求められる資質に共通点が見つからず、
そう簡単に天は二物を与えないと思うから。
・客観的な判断材料がない時は、イメージの影響を受けやすいから。
・これまでに知っている限られた情報だけで、イメージを作り上げているから。
まあ、そんなところでしょうか。
こうして見ると、ほぼ全てにおいて誤解を招き寄せていますよね。
小さなことのようですが、
結局はその思い込みが差別意識とどこかでつながって行くのだと思います。
けれど、実際にはアメリカでは、俳優が大統領にも州知事にもなっています。
日本でも俳優だった森田健作さんは千葉県知事ですし、
東国原英夫さんも政治家でした。
アスリートだったから務まらないと思ってしまうのは、
まさに思い込み以外の何物でもありません。
芸能人によるSNSでの政治的社会的発言をバッシングする風潮にも、
同じような偏見を感じます。
私たちはどうしたら、思い込みを減らせるのでしょうか?
名案は浮かびませんが、
「思い込んでいない?」と自問する習慣をつけるしかありませんね。
コロナによって厳しい状況が続いているオリンピック/パラリンピック。
差別や偏見を乗り越えて来た歴史でもあるし、
ここまで大勢の人たちが努力してきたわけだから、
まさかの奇跡や素晴らしいアイデアによって、開催できるといいなぁと思います。
加えて、私は自分が女性なので、これを機にジェンダーギャップの大幅改善が進み、
国際社会での日本のイメージが変わるといいとも思います。
もしかしたら「オリンピックは無理」というのも、思い込みなのかな?
来週はもう3月です。春の足音が聞こえてきますね。
素敵な1週間をお過ごしください。
ポーズはバレる〜その謝罪ってどうよ!?
先日Twitterで「うちの会社は女性の比率が高くて、
『女性が活躍しやすい会社』であることを打ち出して採用活動をしているけれど、
管理職は男性ばかりで、結局ポーズにすぎない」
というような内容のつぶやきを目にしました。
ここでいう「ポーズ」というのは、写真を撮るときのポーズではなく、
見せかけの態度のことですよね。
言い換えると欺瞞的な態度だともいえますし、
自分/自社の行動や態度をよく見えるようにアピールする行為だとも言えます。
そう考えると、「ポーズ」だったとしても、
全部が全部悪いわけではありませんよね。
私も、時には「ポーズ」を取っているような気がします。
特に、アピール系。。。苦笑
で、少しだけ感度を高めて眺めてみると、
ポーズにすぎない振る舞いというのは、しばしば見かけます。
もっとも多いのは「謝罪」の時ではないでしょうか。
春頃、ある教育研修サービスを提供している会社の営業の人に、
私はクレームを言いました。
緊急事態宣言の最中、強引な営業をされたからです。
プログラム自体は良いものだと思っていましたが、
「環境変化の時期なので、こちらの気持ちになってほしい」と。
そうしたら言われたお詫びが、
「不快な気持ちにさせてしまって、申し訳ありませんでした」でした。
このお詫びの言い回し、とてもよく耳にしますし、
正しいお詫びの仕方として、専門家などからも紹介されています。
でも、個人的な感覚で言わせていただくなら、
この言い回しって謝罪にはなっていないと思うんですね。
あなたは、この表現にどう感じますか?
私が感じる違和感がどこにあるかというと、、、
この謝罪の意味は、
そういうつもりではなかったのですが、
私の言葉によって不快に思われたのであればお詫びします、
という意味だと思います。
言い換えると、不快に思われなかったなら、
謝らないよと言っているようなものです。
自分がとった行動とまったく向き合わずに、形式だけお詫びしているような感じ、
つまり「ポーズ」にしか思えなくて、違和感を感じてしまいました。
そうすると、ますます不愉快な気持ちになったりします。
私が言われたかったことは、
「あなたの気持ちを考えず、自分の都合で勧めてしまい、ごめんなさい」とか、
「私はあなたのことを考えて勧めたつもりでしたが、
ご意向に合っていないなら、適切な提案ではなかったと思います」です。
自分の非を認めて謝っていただくか、
謝らないまでも非を認めるというスタンスがあれば、私は納得できました。
さて、政治家を含め、なぜ多くのシーンで
「不快な気持ちにさせてしまって、申し訳ありませんでした」とか、
「誤解を招いたなら、お詫び申し上げます」が
使われているのでしょうか。
正解はわかりませんが、その理由として2つの可能性を感じます。
その1。クレーム対応的な発想で謝罪しているため。
ある教育研修会社のサイトのコラムで、適切な謝罪の仕方として、
こんなことが書かれていました。
「相手に不快な思いをさせたということに対してのみ謝ると良いです。
自分に非があることとないことの区別をしっかりつけることが大切になるからです」
モンスターからのクレームにさらされるうちに、
防衛的な謝り方が標準になってきたのかもしれません。
でも、モンスターではない私のような人間はむしろ不満が増すのですけど...。
その2。「迷惑をかけるな」という教育が影響しているため。
昔は、「悪いことをしてはいけない」という教えの方が強かったと思いますが、
今は「周りに迷惑をかけてはいけない」という教え方なのではないでしょうか。
子どもが公共の場で暴れているときに、
「おじちゃん(側にいた他人)に怒られるよ」と言ってしまい、
「なぜ、これが悪いことか分かるか?」という教え方が
されなくなっているからなんじゃないかなぁ。
まあ、両方ともあくまで推測にすぎませんが。
いずれにしても、ポーズの謝罪って、おもしろいほどにバレバレですよね。
なので、人のフリ見て我がフリを直さなければ。。。。
また、謝罪であれ、謝罪でない場合であれ、
リーダーや広報が、思っていないことをポーズとして語っても、
すぐにバレます。
本当の本音を実直に語るって、やっぱり大事ですよね。
今週も素敵な1週間でありますように!
求めるのはどんな「強さ」?
先週6日、ロックバンド「ヴァン・ヘイレン」を兄と共に率い、
ギタープレーで人々を魅了した、
エドワード・ヴァン・ヘイレン氏が亡くなりました。
彼のことを知らなくても、マイケル・ジャクソンの「Beat It」の
ギターソロを思い出せる人は多いのではないでしょうか。
私自身も、バンド「ヴァン・ヘイレン」については、
ヒット曲「Jump」とか、「You Really Got Me」ぐらいしか知りませんが、
彼らに限らず、ロックをこよなく愛します。
ロックのどこが好きなのかを考えてみたのですが、、、、
多分私は、ロックスピリットのコアにあるものを「意思の強さ」と捉えていて、
音楽的なこともさることながら、そういった精神性が好きなんですね。
だから、「なあなあ」なロックバンドとか、
ぶつかることを恐れてしまうロックバンドってありえない(笑)
さて、今、「意思の強さ」と書きました。
どんな強さかはともかく、あなたは自分に「強さ」を求めますか?
求めるとしたら、どんな「強さ」ですか?
自分が憧れる「強さ」を何かに例えると、どんなものになりますか?
私は、多くの人は、その人なりの価値観から、
何かしらの強さを自分に求めていると思いますし、
実際に何かしらの強さが人にはあるのだと思います。
でも、「強さ」にもいろいろなタイプがあります。
たとえば、、、
何があっても動じないハガネのような強さ
柳のようにしなやかで折れないという強さ
苦しくても9回裏で逆転するような粘れる強さ
謙虚に物を見られる強さ
毎日の小さな努力を積み重ねられる強さ
切れ味の良いナイフのような強さ
懐深い愛情で物事を受け入れる強さ
ネガティブなことをユーモアに変えてしまう強さ などなど....
自分が欲する強さがどんな強さなのか...のその答えの先には、
往々にして自分の強みがあったりするのかもしれません。
実は、私も去年、当社のDNAを探り出そうとして、
同じようなことを考えました。
企業DNAというのは、なぜ今日まで存続できたのか、
存続を可能にしてきた強み的な要素のことです。
企業の判断基準の元にある美意識や価値観だとも言えます。
その時に当社のDNAの一つとして整理されたのが、
「自然体でしなやかな、謙虚に自己変革できる強さ」でした。
もちろんいきなりこうした言葉が出て来たわけではありません。
当社が大切にしたい雑多な事柄が先にありました。たとえば...
自然体、しなやかな、謙虚、自己変革、前例にとらわれない、品、
やってみる、面白がる、気づける、発見する、最上志向、遊び、
損得以外の価値、プロとしての自負、利益主義、雑談、ムダが大事...など。
他にも様々な概念が出された中で、
これらの概念はある種の強さを志向していると考え、
それをまとめたのが「自然体でしなやかな、謙虚に自己変革できる強さ」でした。
反対に強さに関してありたくないワードを出してみると...。
根性、攻撃的、暴力的、高圧的、乱暴、横柄、批判、不安
びくびく、おずおず、ネガティブ、依存体質、他人軸、他責
プライドが高いだけ、プライドがない、評論家...など。
価値観や美意識に、正しいとか、間違っているということはありませんよね。
ただただ自分の価値観や美意識に背くと感じながら、
無理にほかの価値観に合わせようとすると、誰しも心が穏やかではなくなります。
だからこそ、採用活動/求職活動では、事業内容や職種だけでなく、
価値観が合っているかどうかを見極めることが大切ですよね。
なぜなら、心が穏やかではないということは、アンハッピーということだからです。
ってことは、自社の価値観を知るのも大切ですが、
自分の価値観を知るのが先決ということになるのでしょうか。
組織人である以上、1日8時間は働くわけですから、
価値観という切り口で自分の幸福を求めたり、
人と対話したり、社内メディアで話題にしたり、、、
時には必要かもしれませんね。
10月も中旬になってしまいました。
今週も素敵な1週間でありますように。
「自分のOS」のバージョンアップ
あなたは人の、あるいは自分の、「OS」について考えたことがありますか?
本来、OSとえば、Windowsの「Windows 10」、Macの「Catalina」のような
コンピュータのオペレーティングシステムですが、
それになぞらえて、今日は、人のOSとそのバージョンアップについて、
ヒントを探ってみたいと思います。
当社では、スタッフに対して成長には「スキル」より「OS」の方が大切だと
伝えています。
スキルというのは、OSの上で動くアプリケーションのようなものだからです。
といっても、では「人のOSとは何か?」と聞かれると、説明は簡単ではありません。
OSはパフォーマンスを左右するものだと考えると、
パフォーマンスを生み出すのは第一に思考と行動です。
思考が行動を作り、行動が思考を作ると言われるように、
パフォーマンスを高めるには、行動はもちろん重要ですが、
思考の質を高めることが必要です。
思考という言葉には「理」のイメージがありますが、
一方で、仕事でパフォーマンスの高い人は、
人間力のようなものを持っていることが多いのではないでしょうか。
これは、どちらかというと「感」のイメージですよね。
相手の気持ちを汲み取ったり、
場に起きていることを感じ取ったり、
人の気持ちに対してだけでなく、自分の気持ちにも素直であったり。。。
これらは、理屈というよりも、五感や感受性に寄るところが大きいですよね。
で、今、「理」と「感」を分けられるかのような書き方をしました。
一般に、しばしばこの二つはあたかも別のことのように扱われることが多いです。
でも、ふとこんな考えが浮かんできました。
本当にそうだろうか?と。
理的なこと、感的なことは確かに別々に存在しているような感じがしますが、
実は、その間はむしろ密接に連携し合っているもので、
明確には分かれていないのなのではないか、
むしろ人間の「理」の力と「感」の力は一体のもので、
1つのシステムとして、インプットとアウトプットを行なっているに違いない、と。
まあ、これ、専門家の誰それによれば...というような根拠もなく書いていますので、
真に受けないでくださいね。
ただ、こう考えると、まんざらウソでもないと思えるような...。
たとえば、目の前の誰かが、大笑いしながら、何かを話していたとします。
笑っているという表情の情報は目から入り、話す内容は耳から入ります。
この人が本当に楽しくて笑っているのか、
お愛想のためにウソっぽく笑っているのか、
あるいは、威圧するために笑っているのかは、
大抵の場合、人間の動物的感覚で何秒もかからずにわかります。
しかも、そこに至る過程の情報を理解していれば、
動物的感覚から得た情報に加え、分析的な思考が働き、笑いの真意がわかります。
「理」の力と「感」の力は一体的なもの...と思ったのは、そういうことからです。
そういう意味で、人のOSのバージョンアップを図るには、
思考の習慣を変える、思考の質を変える、
広い意味で感覚感度を高めるなどが役立ちそうですが、
抽象的にそんなことを言われても、何のヒントにもなりませんよね。
そこで、私の個人的な意見がお役に立つとも思いませんが、
OSを高めるためのアイデアをもう少し具体的に書いてみることにします。
私は「自分が『わかったか』どうかへの感度」を高めることは、
OSの質を高める上で効果があるのではないかと考えています。
自分自身の理解の状況さえ自覚できない時に、
他人のことなどわかるわけがない、というのがその理由です。
あなたは、自分の「わかった」と「わからない」の
その感覚をどのくらい意識していますか?
同じ「わからない」であっても、
経験を積むと、自分の抱く疑問点は明瞭になりますが、
若くて経験の浅い段階では、その感覚がぼんやりしがちです。
自分が、わかっているのか、わかっていないのか、わからないという感覚。
わからないことはわかっても、何がわからないのかわからないという感覚。
そんな状況に陥るのではないでしょうか。
「わかった」が成立する1つの基本パターンに、
こうだから、こうで、だからこう、なので、こう...というように、
前と後ろの関連がわかって、全体がわかるというものがあります。
ここで「わかった」感覚を支えるポイントは2つです。
・前後のつながりがわかる
・そのつながりに基づく全体像がわかる
そのパターンで「わかった」経験を重ねていくと、
段々自分がわかっている/いないに自覚的になれます。
さて、「自分が『わかったか』どうか」にアンテナを張ることも重要ですが、
「『わかったつもり』になっていないか」というアンテナを張ることは、
もっと重要だと思います。
「わかった」と思えた時、人はすっきりしています。
「わからない」と思う時、人はもやもやし、疑問が湧きます。
でも、その中間に「わかったつもり」というやっかいな状態が存在しています。
教育の専門家である西林克彦氏は、
その著書「わかったつもり〜読解力がつかない本当の原因」の中で、
「わかったつもり」というのは、
・わからない点はなかった
・自分のわかり方に、さして不満はない
・それほどはっきりした「よりわかりたいという欲求」はない
...と思っている時に起きると言います。
「わかったつもり」でいる時、その人はその状態に満足しているので、
それ以上に知りたいという欲求が起きません。
そのような状態の人に、さらにわかってもらうように上司として指導する場合、
上手な問いかけが必要ですが、そもそも本人が知りたいと思っていないので、
風穴を開けるのは簡単ではありません。
もちろん、これは上司の立場も同じです。
書いている私だって、「わかったつもり」に陥ることがあります。
でも、「わかった」「わからない」「わかったつもり」があることを、
みんなが知ってさえいれば、もう少しオープンに話せそうです。
2020年もあと3カ月。。。。
今週が素晴らしい1週間でありますように!
「待つ」で考える「人との関係」
あなたは、誰かが自分を待っていると感じることはありますか?
若い頃、実家の両親は私の訪問をいつも待っていたと思いますが、
親の言いなりになるのが嫌だったのか、
期待に添うような行動を取りませんでした。
当時、実家は30分ほどで行ける場所にあり、
帰ろうと思えばいつでも帰れたはずなのに、若気の至りです。
待ってくれる人がいる幸せに気づかなかったんですね。
別の例で、最近、こんなこともありました。
青山で30年以上にわたって、こだわり系の飲み屋さんをやっている人から、
「コロナで営業が大変だから、来てほしい」と電話がありました。
偶然にも同じ世代。口が悪く、個性的なオーナーです。
どうしようか?...と一瞬思ったけれど、結局行きましたよ(笑)
相手が待っているのは、私ではなく、お金を落とすことなのかもしれませんが、
やっぱり、そこには人間関係があります。
「待つ」は「期待」だと理解するようになって、
「待つ」にもいろいろな意味があることを知りました。
ある人の元気な姿を見たくて待っている人。
自分の気持ちや行動に気づいてほしいなと思って、待っている人。
与えた課題を部下がクリアしてくれることを待っている上司側の人。
提出した課題にOKが出るのを待っている部下側の人。
あなたは、誰を待っていますか?
誰が、あなたを待っていますか?
待つ=期待。
そう思うと、その人との関係も見え方が変わってきますよね。
ところで、世の中には「指示待ちはダメ」という考え方があります。
指示待ちが起きる主な要因は、2つあるのではないでしょうか。
1つは、その人の思考行動特性のような、内的要因。
もう1つは、その人と指示を出す側の人との間にある、関係的要因です。
今日のテーマで取り上げたいのは、後者です。
その昔、PR会社に転職した私の若い頃の経験を例に考えてみました。
ある時、制作部からマスコミ対応や取材誘致を行うPR部へと異動になりました。
上司は私が右も左もわからないだろうからと、
「自分の人脈を紹介するので、待ってて」と言いました。
知り合いの記者にアポを取って、連れて行くという意味です。
ところが、その後、何週間かして「記者さんの紹介の件ですが...」と聞いても、
「わかっているから、ちょっと待ってて」と。
私の異動と同じ頃、ある日、経験者が入って来ました。
彼女は、入社の翌日に「プレスを回りたいので、名刺をください」と。
それを聞いた上司の反応は、大絶賛でした。
「え? そういうこと?」
上司の「待ってて」は何だったのだろうと思いながら、
それをきっかけに、私は目的から考えればわかることを一人で始めました。
このことから何がわかるでしょうか?
この時の私の指示待ちの責任は上司にある、と言うつもりはありません。
私と上司との関係や私の認識から生まれたのだと思います。
その認識とは、次のようなものでした。
・自分は上司に心配されている。
・勝手に動いて、変なことをされては困ると思われている。
・上司は、部下の面倒を見るのが自分の仕事だと思っている。
概ね正しいと思いますが、でも、こう申し出ることもできたはずです。
「紹介していただけるのはありがたいので、ぜひお願いします。
でも、自分としては、わからないなりにやってみたいので、
注意事項があれば教えてください」。
そう言われた上司が私を止めたとは思えません。
それなのに、私がそう言わなかったのは、上司を不安にさせないようにとか、
上司を立てないと悪いなど、そんな遠慮があったからでした。
つまり、指示待ちにならないための前提として必要なことは、
あなたはきっとできると信頼され、期待されていると思える関係があること。
そんなふうに考えますが、いかがでしょうか。
自分の体験ばかり書いてしまいました。
読んでくださってありがとうございます。
「待つ」という行為から、あなたと周りの人との関係を考えたら、
何が見えてくるでしょう?
どうぞ素敵な1週間をお過ごしください!
「わかる」の壁
私は、仕事柄か、人や自分の頭と心の動きに対し、いつも興味を持っています。
仕事柄と書いたのは、一つにはクライアントの組織に何かを伝える仕事、
もう一つは自社の社員に何かを伝える仕事、という2つの視点からです。
どちらも相手に「わかってもらう」ことが重要なので、
人の心理や認知、わかるということについて、好奇心を持って眺めてきました。
特に、社員に何かを伝えるケースでは、反応を見ながら、いろいろと考えます。
当社は小さな会社なので、私が直接スタッフに教える機会も少なくありません。
そして、その過程で、ただ教えるだけなら簡単ですが、
「わかってもらう」をゴールにすると、途端に難しくなります。
まだまだ自分の技量が乏しいなーと思います。
たとえば、先日社内で「プロット」の本質について、話をしました。
プロットというのは、原稿を書いたり、コンテンツを立案する時に考える、
いわば話の筋道であり、構成のことです。
あなたもパワポでプレゼン資料を作ることがあると思いますが、
何かを伝える姿勢として、いきなり作り出すのではなく、
構成を先にすることはとても重要です。
でも、、、意外と世の中ではないがしろにされているような気もします。
プロット、すなわち話の流れというのは、
そのコンテンツでどんなメッセージを伝えたいかによって変わります。
ですが、今度はメッセージとは何かというその本質がわかっていないと、
プロットもわからないし、上手く組み立てることができません。
プロットもメッセージも抽象概念なので、
だからこそ教えたり、理解するのは、簡単ではありません。
そういうことを社員に伝えようとするたびに、「わかる」とは何か、
どうすると「わかる」のか?を考えます。
話は飛ぶようですが、最近養老孟司さんが書いた「バカの壁」を読みました。
平成のベストセラーであり、ロングセラーでもありますが、
私はずっとこのタイトルにある「バカ」という言葉が嫌いで、
読まずにきました。
でも、先日、TUTAYAに行ったら、帯にあった文字、
「445万部突破! 120刷超 驚異のロングセラー」が目に飛び込んできて、
いったいなぜこんなに売れたのかを知りたくなって、今更ながらに読んだ次第です。
編集者が聞き書きしているためか、1冊の本としては散漫な印象で、
良質な読み物とは言い難いと感じましたが、
それでも、その中に人の「わかる」が方程式として表されていて興味深かったです。
「わかる」の方程式と書きましたが、それは私の意訳で、正確には、
脳が入力された情報をアウトプットするまでの間を表した方程式です。
その式は、こうです。
ーーーーー
y=ax
ーーーーー
「y」は出力。情報を得てからの脳の反応。
私はこれを「わかる」の到達レベルと捉えました。
「x」は入力。人が得た情報です。
「a」はその人にとって、その事柄の重みや関心度。
当然ですが、「y」は「x」と「a」の乗算ですから、
「a」がゼロだと、「y」もゼロになって、「わかる」に到達しません。
「a」は、その人の経験や知識、志向などによって個々に差があります。
つまり、教える人は、相手の「a」(経験、知識、志向)に添って教えること
が大切だということですね。
ま、当たり前といえば、当たり前ですが。。。。
それができれば、「わかる」に近づけるということです。
だから、教えたい相手が、今、何をどこまでどう理解していて、
そう理解しているベースには何があるのかを聞き出すことは、
わかるために結構重要だってことになりますよね。
また、この式を見ていると、こんなことも言えるのではないでしょうか。
どんな方法で「x」(インプット情報)を得るかによって、
「わかる」「わからない」が変わるということです。
「認知特性」とか「優位感覚」と言う言葉を聞いたことがありますか?
人は、物事を理解する際に、五感を使っています。
どの五感が強いのかは人それぞれで異なり、それに合った教え方をされると、
スッと入ってくるけれど、合わない教え方をされると、迷子になる、、、
そんなことが認知心理学では言われています。
たとえば、親切心で図解して説明したら、
相手は図が苦手だった...というようなことは避けたいですよね。
どんなタイプがあるのか、その分類は学説によって若干異なりますが、
3つから6つのタイプがあるとされています。本質は一緒です。
(「認知特性」「優位感覚」で検索すると、出てきます)
1つのわかりやすい分類例としては、、、、
視覚優位、言語優位、聴覚優位という大分類と、
さらにそれぞれを二分し、合計6分類にしているものです。
ニコこどもクリニック院長の本田真美医師はテストなども公開しているので、
自分の優位感覚を知りたければやってみるといいかもしれません。
さて、、、「わかる」は教える側以上に、教わる側の意識のありようも重要です。
「わかる」に早く到達する人は、どんなことをしているのでしょうか。
私が見る限り、最低3つの点で共通しています。
①自分がわかっているのかどうか、アンテナを立てて、自己チェックしている。
②わからないときは、何がわからないのか、問いを立てながら、思考を深めている。
③インプット内容やアウトプット内容(考えたこと)をまとめ的に整理している。
つまり、「わかりたい」という欲求が根底に強くあります。
反対に「わかる」に到達しにくい人の特徴は、
①わかろうとせず、覚えようとする。
②まずは処理が大切で、処理したら完了とする(わかろうとしない)。
実は、「わかる」と「覚える」は別のことなのに、
その違いはあまり理解されていないような気がします。
「わかる」の最大のメリットは、次に応用が利くようになることです。
簡単だとは思いませんが、教える人も教わる人も「わかる」を大切にして、
そのメリットを享受したいものですね〜
今週も素敵な1週間でありますように!
意見の本質って?
メルマガもブログも、いつも今回は何を書こうかなと立ち止まる瞬間があります。
その答えがスッと出てくるときもあれば、七転八倒するときもあります。
今回は、どちらかというと、どれを切り捨てるかで悩みました。
最近読んだ、あの本にインスパイアされたことを書こうかなとか、
今、グラスルーツが開発に取り組んでいるDNAのサービスに絡めて、
私が感じている企業経営の問題意識を書こうかなとか...。
まあ、毎回、いろいろ思うわけですね。
でも、今回はそれらはやめにして、意見の本質って何だろう?ということについて、
皆さんと一緒に、考えていきたいと思います。
きっかけは、当社のDNAサービスを開発するプロセスで、
ありたい社会について考え、ありたい自社像について考えたからです。
誰もが自分の意見をフランクに言える社会がいいなーと。
さてさて、「考えることは大事...」。
これは、ビジネスパーソンなら多かれ少なかれ教えられ、認識していると思います。
でも、多くの人は、いつもいつも考える必要に迫られているわけではありません。
そんなに考えなくても、過ぎてしまう日常もある。
「考える」ことについて、必要に迫られる具体的なシーンとしては、
やっぱり意見を求められるときではないでしょうか。
なのですが、この「意見を言う」は結構くせ者で、
何を言うことが意見を言うことなのかを説明できる人は
あまり多くないような気がします。
いえ、もちろんこの問いに対して、
唯一無二の正解があるわけではなく、
各自各様の答えがあってしかるべきですし、
私も今回、この問いと向き合って、初めて自分の考えを整理しました。
昔から、「意見を述べよ」ということは、
イコール「自分の考えを述べよ」というくらいに理解していて、
それで対処できないわけではありませんが、
もっと明瞭に「意見を述べるとは何を述べることなのか」について
この機会に答えを見つけておきたいとそんなふうに思いました。
で、あーだこーだ考えてみて、あえてフレームワーク的に整理してみたのですが、
こんな形、どうでしょう?
ーーー意見を述べるフレームワークーーー
私は、(①ほにゃらら)には、(②ほにゃらら)が大切だと思う。
なぜならば、(③ほにゃらら)だからだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
分解すると、
①は視点
②は主張
③は理由
つまり、意見の発信者は物事をどのアングルから見て、どう思っている、
その理由は何かってことを言えれば、明快な意見になるわけです。
私は意見としてはこの程度で十分だと思っていて、
それを是とするなら、意見の構造って、結構シンプルですね。
難しいと思うのは、案外①番なんですけど。
え? そんなの当たり前じゃん、今さら何言っちゃってんの?と
思われた方もいるかもしれませんし、
全く違う別の視点からそれでは不十分だというご意見をお持ちの方も
いるかもしれません。
それは、それでいいですよね。むしろシェアしていただきたい。
意見の本質、
自分の考えをどうやって整理するか、
あなたは、どう思いますか?
私は、みんながいろんなことで、
いろんな意見を発せられる社会が健康だと思います。
だからこそ、各自が意見を持つということを大切にしたいですね。
2020年もまもなく半年が終わります。
毎日を大切に、毎日をいい時間にするぞ!と思って過ごしたいですね。
今週も、素敵な1週間でありますように!
こんな時だからこそ、「わかりやすく」
先週7日に政府が緊急事態宣言をしてから、今日が最初のブログになります。
今日は、社会に向けて出されている「新型コロナウイルス」に絡んだメッセージから、
「わかりやすさ」の共通点について考えたいと思います。
今、政治や業界のリーダー、スポーツ選手など、
いろいろな方がメッセージを出され、人々を励まし、道しるべを示しています。
特に、政界や業界のリーダーたちのメッセージは重要性を増し、
それがわかりやすいかどうかもポイントになってきていますよね。
私が共感した例を3つほど紹介します。
わかりやすさでダントツに光っているのは、小池百合子東京都知事です。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/governor/governor/kishakaiken/2020/04/10.html
わかりやすさの直接的な理由は「言葉」にありますが、
それ以上に大きいのが、都民が求めていることを話してくれることではないでしょうか。
また、言葉の源にある「考え方」もわかりやすいです。
たとえば、国は、状況に応じて段階的に制限を拡大する方針だったようですが、
小池さんは「最初に早く大きく制限をかけて、徐々に緩和していくのが、
危機管理の要諦(キッパリ!)」と言って、
自分の意思とその理由を示していました。
「大義」を明確にするのも、小池さんの特長です。
考え方がわかりやすく、伝える言葉がわかりやすい。
まあ、政治家ですから当然と思うかもしれませんが、
話がわかりにく政治家も大勢いますよね。
小池さんは、若者に人気のユーチューバーHIKAKINとも対談するなど、
できることは何でもするという意気込みが行動に現れていて、
それ自体もメッセージとして機能させている印象です。
イギリスではジョンソン首相が感染し、入院中ですが、
今、小池さんが入院することになったら、本当にたいへん!
ご自身の身を守りながら、指揮を取っていただきたいと思います。
2つ目は、東京都医師会の尾崎治夫会長と、そのメッセージです。
4月5日には「もしも6週間みんなで頑張れたら」というメッセージを、
4月8日には「専門家を大事にしよう。」というメッセージを
facebookに出されています。
前者は東京都医師会のHPにも掲載されています。
https://www.tokyo.med.or.jp/17934
こちら↓はFBにログインしていないと見られません。
https://www.facebook.com/haruo.ozaki
抜粋になりますが、たとえば5日のメッセージでは、
こんなふうに語りかけています。
「皆さん想像してみて下さい。
新型コロナウイルス感染症に、もしも今この瞬間から、
東京で誰一人も新しく感染しなかったら、
2週間後には、ほとんど新しい患者さんは増えなくなり、
その2週間後には、ほとんどの患者さんが治っていて、
その2週間後には、街にウイルスを持った患者さんがいなくなります。」
これを読んで私が思ったのは、緊急事態宣言で示された1カ月ではなく、
6週間なのだということ。
ただ感染拡大防止のために1カ月自宅で、と言われるよりも、
ゴールへの道筋がイメージできました。
実は、私、恥ずかしながら、医師会の会長というのは、もっと保守的で
長いものに巻かれるような人物ではないかという先入観を持っていました。
ところが尾崎さん、まったく違います。
リーダーとして明確な意思を示しています。
ちなみに、写真は会長室で飼っているアイボが撮ったものだそうです。
また「専門家を大事にしよう。」では、
西村経済再生相と思しき人物を名指しせずに批判しています。
その主張がもっともだと思うのは私だけではないでしょう。
でも、批判することが目的なのではなく、
専門家の意見にもっと耳を傾けてほしいというメッセージを
伝えたいのだということがよくわかります。
そして、そのメッセージを届けたい相手はおそらく安倍さんです(笑
3つ目は、自動車工業4団体によるメッセージ。
話されたのは自工会の豊田章男会長でした。
https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/32286491.html
冒頭で、こんな語りがあります。
「世の中にはコントロールできる話とコントロールできない話がある。
コントロールできないことに深刻になればネガティブになる。
自分がコントロールできることをしっかりやっていこう。
コントロールできないことを誰かがやってくれていたら感謝しよう」。
ニュースなどから不安な情報にどっぷり浸かっている私たちにとって、
自分がすべきことが何なのか、わかりやすくイメージできますよね。
安心感を与えてくれる始まりの言葉でした。
会見では、決定事項のみを発表するのが慣例だそうですが、
中盤では、これから考えていくことも紹介したり、
国内でのモノづくりにこだわってきて本当に良かったという思いを述べたり、
「我々の産業には、生き残るための粘り強いDNAがあるはずです。
なんとしても踏ん張って、生き残っていきましょう!」と
業界関係者を勇気付ける言葉もありました。
18分におよぶスピーチは内容が盛りだくさんでしたが、
4団体の意思と熱い思いの伝わる、素晴らしいメッセージだと思います。
3者に共通するのは、次の2点。意外にシンプルです。
1)聞く人・読む人の今の思いや疑問に添っていること。
2)「大義」を伝え、「意思」を伝え、「思い」も織り込んでいるということ。
それによって、相手の頭と心の両方にメッセージを届けることができ、
結果として共感を生み出しているのではないでしょうか。
さて、「わかりやすさ重視」という観点で、官邸広報にも変化があることを
ジャーナリスト江川紹子さんの執筆記事を読んで知りました。
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20200408-00172156/
7日に発表された緊急経済対策の会見で、質問に立った江川さんに対し、
翌日の8日に菅官房長官から電話があり、追加説明があったそうです。
「昨日の記者会見で、よくご理解いただけてなかったようなので」と。
発表の晩のラジオ番組で「よくわからなかった」と発言したことが
漏れ伝わったのではないかと江川さんは推測していますが、
これは相当に珍しいことのようです。
そのほかの変化についても紹介されているので、
ご興味があったら読んでみてください。
ニュースや会見、SNSでのコメントを
「わかりやすさ」という視点からチェックしてみると、
いろいろ学びがありますし、気も紛れます。
ありゃ、とても長文になってしまった!!!
今回のブログ、長いだけでわかりにくかったら、ごめんなさ〜い。
不自由な毎日ですが、くじけずに一緒にがんばりましょう!
『なぜ』がわからないと、やる気は起きない
心をいじられた感じの週末でしたね。
台風19号にそわそわしました。
映画でも観ながら、
家で過ごそう思っていたのですが、
スーパーの商品はなくなるし、
自分の生活圏への不安と、
TVで映し出されていく被害の状況。
いろんな人のことが気になって、
映画を観るような気分になりませんでした。
でも、台風の翌日は、
ラグビーW杯日本代表が大活躍。
様々なテンションが交錯したせいで、
少々疲れた感があるのは否めません。
でも、こんなことを言えるのは、
被災を免れたからです。
大したことができないにしても、
被災した方たちに
思いを馳せたいものです。
さて、今日は私たちにとって
「なぜ」を知ることの意義について
考えたいと思います。
きっかけは、今月の初めに私が受けた健康診断でした。
これまでは、健保組合の健診施設で
一通り受けていたのですが、
もういい歳だし、社長が突然余命宣告を受けたら、
周りに迷惑をかけるし、
いつもよりちょっと高度なオプション健診も受けようと思い、
病院での健診を受けました。
健保組合の提携先は東京高輪病院。
結論から言うと、
全般的にスタッフ教育が行き届いている印象で、
とてもいい病院だなと感じました。
さて、ここからが本題です。
胃のレントゲンで、素晴らしい技師の方に出会いました。
検査が終わって、部屋を出るとき、
「私のこれまでの人生で最高の検査でした。ありがとう」と言ったほどです。
胃のレントゲン、
いつもは健保組合の健診施設で撮ってもらっていて、
それが私にとって、ある意味標準でした。
別に特別な不満もなかったし、
これで当たり前だろうと思っていたのです。
ところが、今回の技師は本当に素晴らしく、感動ものでした!
私が感動したのは、次の4点です。
1)今からすることを説明してくれました。
「はい、では食道の写真を撮ります。
バリウムをごくりと飲んでください」
「今度は十二指腸の写真を撮ります」
目的意識が持てると、がんばろうと思えます。
2)しかも、都度都度状況説明をしてくれます。
「はい、いい写真が撮れました」
「きれいな写真が撮れました」
こう言われると、変な写真にならないように
さらにがんばろうと思えます。
3)なぜ、それをするかを説明してくれました。
「今から、胃を膨らませるために発泡剤を飲んでいただきますが、
ゲップをがまんしてください」
↑これは大抵言ってくれますよね。
でも、↓これはないのでは?
「今から、バリュームが胃の中で混ざるようにするために、3回回っていただきます」
こう言われると、「おお、そうか、
うまく混ざるように体を動かさないと」という気持ちになります。
4)進捗&現在地を教えてくれる。
「はい、あと2回です。申し訳ありませんが、がんばってください」とか
「あと2枚撮ったら終わりです」とか。
がんばって検査は受けているものの、
でもやっぱり終わりが見えないのは不安。
その絶妙なタイミングでこの声がけ。
出口が見えると、最後までしっかりやろう!そんな気分で続けられました。
この技師がしてくれたことを通じて、
私とその技師との間に協働関係が生まれたような
そんな気持ちさえ抱きました。
胃のレントゲンを撮る、ただそれだけのことなのに。
この体験、いろいろ素晴らしかったですが、中でも1番と3番。「なぜ」の説明。
私はこの大切さを痛感しました。
モチベーションや仕事観に影響を与えるなーと。
今さらな例ですが、
レンガを積む男の話を思い出します。
「ここで何をしているのですか?」と聞かれ、
「レンガを積んでいる」でもなく、
「壁を作っている」でもなく、
「人々が祈りを捧げる偉大な教会を作っている」と語るには、
この「なぜ」抜きではありえないでしょうね。
また、こんな話も思い出しました。
メルマガを共に書いている阿部、
前々職でこんな体験をしたそうです。
間違えの多いアルバイト学生に、
あなたの仕事の意味を伝え、
間違えるとどんな影響が出るかを伝え、
だから、とても重要な仕事なのだと伝えたら、
間違えなくなった、と。
人はみんな無駄なことより、
意義のあることに関わりたい。
だからこそ、
意義を伝えることは重要ですね。
社内コミュニケーションにおいて
重要なことが伝わっていない場合、
「なぜの説明が足りていない」
ということが一因の場合も少なくありません。
伝わっていないと感じたら、
「『なぜ』が伝わっているか」
という視点で検証してみるのも一考です。
今週も素敵な1週間でありますように。
ラグビー日本代表が力を出し切れますように。
では、また〜!
いろいろな考えに謙虚に耳を傾ける
個人的な話で恐縮ですが、私は去年から今年にかけて、
自分のマンションの管理組合の理事として、
2カ月に1度ぐらいの頻度で開催される理事会に出席しています。
マンションに住んだことのない方には、
そのしくみがイメージできないかもしれませんので、
簡単に紹介しますね。
基本、マンション(集合住宅)は住民の自治で成り立っています。
実際には、管理会社がかなりの面でサポートしてくれているので、
住民がゼロから考えるシーンは多くありませんが、
それでも「自治」という原則に基づいて、管理会社が出してくれた情報を判断し、
決断するのは住民...という構図です。
最高決定機関は、全住民が出席する「総会」で、
「理事会」は住民代表の執行機関のようなもの。
その人数はマンションの規模によって異なりますが、
私の住む今のマンションは73世帯あり、
6人が役員(理事5名、監事1名)として選出されるしくみになっています。
そして、理事5名の中から、理事長1名、副理事長1名、理事3名を選びます。
役員は立候補が優先されますが、
一般に多くのマンションでは輪番制で
みんなで交代交代で役割を担うというパターンが多いのではないでしょうか。
この週末、新旧交代の場、つまり現在の役員と
次の役員が集う場が設けられました。
本来は次の役員の役割を決める場、という意味もありました。
新しく輪番制で回ってきた6名のメンバーのうち、
参加は4名、欠席は2名です。
参加4名のうち、女性3名はマンション自治の原則について理解しており、
男性1名はこのようなことが初めてのようでした。
さて、このような状況で、役員を決めるということについて、
人がどう動くのか、私は興味深く観察しました。
その過程で感じることは多々あったのですが、中でも一番、
「ああ、人それぞれ違うものだなー」と思ったエピソードを
1つ紹介します。
それは、欠席している人を巡っての反応です。
いない場で、役割を決めてしまっていいかどうか。
仮にもし全員がここにいたら、なんらかの方法、すなわち
・話し合い
・じゃんけん/あみだくじ等
のいずれかによって、役割を決めただろうと思います。
しかし、欠席している人がいるという事態に直面し、
見方は別れました。
「いない場で決めるのはどうか」
「欠席裁判のようになるのは感じが悪いであろう」
これらの意見は、役割を決めるなら全員同席した上で決めるべきだ、
という考え方です。
ですが、、、私がどう感じたかというと、
出席していない人がいるからといって、決めないのではなく、
「理事会に一任」という委任状が形骸化されないためにも、
出席していない人の分も含めてアミダくじで決めるのもアリだと思いました。
...というのは、、、、
実は昨年、私自身が理事になる年、同様の会があったとき、
私も都合が悪くて欠席しました。
その際に、「理事会の選任の重要な時期に欠席してすみません、
結論はお任せします」というようなことを委任状に記して、
欠席表明した記憶があります。
これを書いた時、一応それなりに覚悟をしています。
どんな役割が回ってきても、受け入れよう、と。
で、そう書いたのに、欠席者がいたからもう一度会を設けると言われたら、
「二度手間にならないために、委任状を出したのに...
私が欠席したからまた場が設けられたのかな、申し訳ないな...」
と私は思うからです。
そもそも輪番制のメンバーは、全員がなにがしかの役割になります。
「私が理事長をやりますよ」という人が現れない限り、理事長は決まりません。
反対に理事長をやりたい人は、おそらくこの日に欠席しないでしょう。
だから、私の意見では、適任かどうかは別として、アミダくじで決めて、
万が一、適任に見えない、頼りなさそうな人が理事長になってしまったとしても、
それを周りが支える...それが現実的にあるべき姿なのではないか、
私はそんなふうに考えていました。
ですが、今回は「いない場で決めるのはどうか」が判断基準となり、
結論は持ち越されました。
私の考え方とは違うなーと感じましたが、
そのほかの無言の意見や、声ある意見にも、
謙虚に耳を傾けることの大切さを痛感しました。
そして、自分とは違ういろいろな考え方があること、
認識すべきですね。
3 ページ / 18 ページ



