AI時代に欠かせない「自問力」~chatGPTを使ってみた!
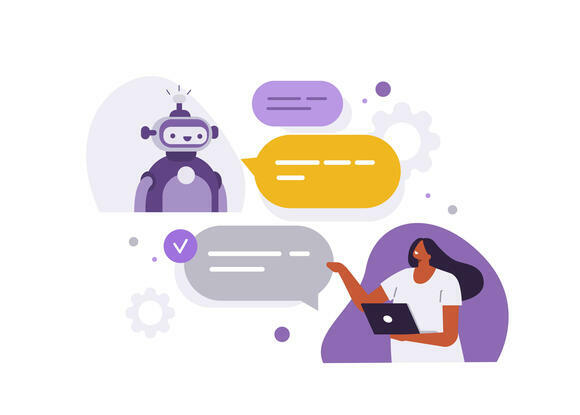
今日は今、世界的に話題になっている「chatGPT」
私なりに気づいたこと、感じたことをご紹介します。
この動き、人間とAIがどういう関係なるのかという意味で、
絶対押さえておいた方が良いと思います。
「chatGPT」は、
対話形式で質疑応答が出来るチャットボットです。
https://openai.com/blog/
と聞くと小難しく感じますが、ブラウザからログインし(
質問すると答えを返してくれるしくみです。
大学入試レベルの問題を解いてしまい話題となり、
すでに大学の宿題で利用禁止されるというぐらい「スゴすぎ」
OpenAI社の技術は、
同社は、イーロン・マスクやマイクロソフトなどによって、
数十億ドル単位か、
脚光を浴びる彼らが昨年2022年11月に公開したのが、この「
チャットボット自体はすでに使ったことのある方も多いと思います
私の経験では、なんとなくいつもイマイチでした。
このサービスはチャットボットの延長線にあるので、
正直「ほんとうにそんなにスゴいの?」
確かにそれは、既存のチャットボットをはるかに凌ぐ体験で、
驚きを感じざるを得ませんでした。
使い方の詳細は検索すれば出てくるのでお調べいただくとして、
ざっくり言えば、
①ユーザがテキストで質問する ②チャットボットがテキストで回答する
この繰り返しです。
実験結果を紹介しますね。
まず「社内報の文章を上手に書くコツは?」と尋ねたところ、
こんな答えです。
ーーー最初の回答① ここからーーー
社内報の文章を上手に書くコツは以下の通りです。
1. 読み手を意識する:
2. 簡潔かつ分かりやすく:社内報は情報量が多くなりがちなため、
3. 読みやすい体裁:見出しや段落の構成、フォントや文字サイズ、
4. 報道価値を意識する:社内報は社員に向けた情報伝達だけでなく、
5. フィードバックを受け入れる:
ーーーここまでーーー
なんか、スゴくありませんか?
でも、このアドバイスを受けて、メキメキ文章が上達する人は、
ここでは、試しに、「2番についてさらに質問です。
すると、「文章を簡潔にするためのコツは以下の通りです」
ーーー次の回答② ここからーーー
1. 要点を絞る:書きたい内容の中から、
2. 簡明な表現を心がける:読み手が理解しやすい、
3. 文字数を制限する:
4. 実例を使う:抽象的な概念やアイデアを説明する場合は、
5. リライトを繰り返す:一度書いた文章を、何度も読み直して、
ーーーここまでーーー
うーむ。まあ、スゴいですよ!
こんなにスラスラと回答できるんですからねー
さて、ここからは私の気づきです。
いろいろありますが、一番は、AIを使いこなそうと思ったら、
自分の疑問を持てるかどうかだなぁということ。
言い換えると、1つ目の質問への回答を読んで、
分かったような気分になってはダメだということ。
なのですが、おそらくこのしくみの問題は、
実は8割ぐらいの人は分かったような気になってしまうのではない
という点です。
分かったような気にならず、2つ目の疑問、3つ目の疑問と、
自分の疑問を出せるかによって、
AIを使いこなせるかどうかの分かれ道になるな、と思いました。
ところが、現実社会では、我々は自分の「理解」
ふわっとしたままでも過ぎていきます。
そのような現実に自分を合わせていると、
永久にAIを使いこなせるようにならないのではないかと
懸念を抱きます。
いえ、AIの方は、
私は、AI時代には、正しいとか正しくないとかではなく、
「自分」というものを持っているかどうかが、
AIに負けない価値を持つと思っています。
それには、多分ふわっとした自分でいてはダメなのでしょうね。
このことから、さらに「自分を持つって何なんだ?」
自問を持つことこそ人間の好奇心の表れです。
なので、今後の社会で重要視されるのは、
「自問力」「好奇心」かなと思いますが、
まずは、chatGPTを使ってみてください。
「抗えない」のウソ
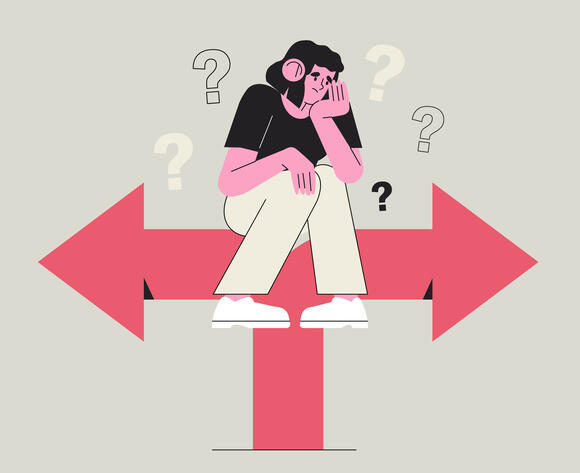
昨日の当社の定例ミーティングで、
ズバリ一言ですが、うちのメンバーにこんな話をしました。
仕事での様々な関係の中で、いろいろな会話がされているけれど、
そのとき社会では「目的」が忘れられがち。
もし「目的」
話が複雑になってしまうのは、「目的」
グラスルーツは「目的」思考の会社でありたいので、よろしく!
まあ、これ、正論ではありますが、
正論で解決できないことがあるから、
では、正論で解決できないこととは何でしょうか?
いろいろあるとは思いますが、
その1つに、組織の中で「抗えない」
こんなことを言ったら、周りから何か言われる...
これをやめると言ったら、角が立つ...
これを変えたいが、あちこちから反発を喰らいそう...
一度は婉曲的に伝えたけど、それ以上は言いにくい...
だから「抗えない」。
ある意味、想像に難くないですよね。
実際、三人寄れば公界(くがい)というくらいですから、
人が3人いると社会ができてしまうし、
3人いると銘々が別のことを考えています。
そして、誰もが生存本能から「人から嫌われたくない」
ちょっとしたことを発言する=モノ申した人=波風を立てた人=
そんな図式が生まれてしまうのだと思います。
アドラー心理学などでも、
ましてや組織になり、自分の発言が「所属部門」
そりゃ軽率にモノが言えない気分になるのもわかります。
ですが、こういう体験はありませんか?
「抗えない」と思ったから取った自分の行動で、
実は結果的に自分の評価が下がった、みたいな。
私はありますよ、若い時に。
まあ、正確に言えば「抗えない」というほど
突き詰めて考えて取った行動ではありませんでしたが、
「この人の言葉に従うべきだろう」
「この人の判断通りに行動していたら問題ないだろう」
自分が非難されたり、スベったりした経験。
2つ例を挙げますね。
1つ目は、ある上場企業の秘書室で業務を引き継いだ時、
前任の先輩から言われた通りにやったのに、
「○○さんなら、そんなやり方はしなかった」と
担当していた役員からお叱りを受けました。しかも、2度も!
自分で判断して行動したならまだしもでしたが、
納得できない気持ちが残りました。
2つ目は、PR会社に転職し、
上司は「連れて行くから、待っていてね」と、
よく言えば直々に教育指導してくださるつもりだったのでしょうけ
上司が動いてくれないと動けない状況に、
でも、同じ頃、隣の部に入社した新人が、
「プレスコンタクトに行ってきます」
「この新人はスゴイ!」と発言。
その時は「おいおい、あなたが私をステイさせたんだよね」
この体験には、いろいろな示唆が含まれています。
上の人から言われたことは、忠実に守らなくてはいけない...。
私は、そう思っていましたが、実はこれはウソだということです。
もう少し正確に言うと、忠実に守ろうとするのも、
その結果には誰も責任を持ってくれないし、
「自分は言うことを聞いただけです」
そう気づいてから以降、私は仕事であれ、恋愛であれ、
「自分が選択した」
「抗えない」「言われたことはやるしかない」と思うのは、
自分の思い込みであると。
その結果何が起きるかというと、「自己責任」
でも、それって潔くて快適です。
というわけで、今日のテーマは本当に抗えないのか、でした。
あなたはどう思いますか?
今週末は30年ぶりにスキーに行きます。
ケガなどせずに帰ってこられるよう、祈ってくださいまし。



