他人事ではない、森さんの問題
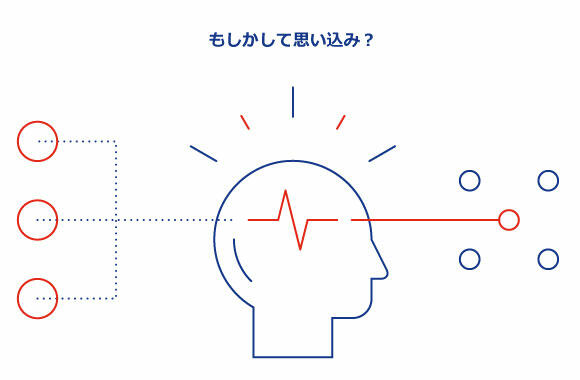
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の
森喜朗前会長の女性蔑視発言に端を発した
後任会長問題は、橋本聖子前五輪相が就任し決着しました。
橋本さんの人柄や実績についてはよく知りませんが、
当初は過去のスキャンダルなどを理由に固辞していたそうです。
にもかかわらず、火中の栗を拾うようなこの状況で、
よく逃げずに引き受けられたと思います。がんばってほしいですね。
さて、今日の本題は「偏見」についてです。
森さんの発言は「失言」と報じられていました。
あの失言の本質は、言葉の表現の問題ではなく、
心の「本音」が出てしまったということだと思います。
だから、本来はあの発言がなければ良しということではなく、
そういう価値観の人物が組織委員会の長にいること自体が、
世界から問題視されたわけですよね。
今回の森さんの、女性は話が長いという発言内容には、
根っこに「偏見」がありました。
女性に対するネガティブで偏った先入観です。
でも、考えてみると、女性への偏見は未だに社会全体にありますよね。
別に森さんの肩を持つつもりはありませんし、
女性は被害者、男性が加害者と言うつもりもありません。
でも、現に日本のジェンダー・ギャップ指数は153カ国中、121位です。
これは、世界経済フォーラムが毎年発表している
経済・教育・保健・政治分野の男女平等度を表す指数のこと。
あまりの低さにびっくりしてしまいますよね。
話を元に戻すと、ある対象に対して、
ネガティブで偏った思い込みを持つというのは、
人間の特性だとも言えます。
思い込みが怖いのは、思い込んでいるがゆえに、
信じて疑わず、気づけなくなることです。
今回、新会長に就任した橋本聖子さんは、
「参院議員に初当選したとき、
『経済がわからないオリンピック選手がなぜ政治家になるのか』と揶揄された」
とご自身のサイトで書いています。
当選は1995年のことですから、最早26年前ですね。
では、今回の会長就任に対する社会の目はどうなのでしょう?
正直に告白しますよ。
私自身、橋本さんのことをあまり良く知らないのに、
橋本さんで務まるんだろうかと一瞬ですが思ってしまいました。
理由は、やっぱり元オリンピック選手の橋本聖子さんの印象の方が強烈で、
政治手腕やリーダーシップに長けているという印象が薄かったからです。
しかし、だからと言って、26年も政治家として活動して来た橋本さんに対し、
「橋本さんで務まるんだろうか?」と考えるのは失礼だし、やっぱり偏見です。
なぜ、こういうネガティブな先入観が出てくるのでしょうか。
理由を思いつくままに出してみました。
・知らないものに対して、人はそれだけで不安を感じてしまうから。
・アスリートと政治家、それぞれに求められる資質に共通点が見つからず、
そう簡単に天は二物を与えないと思うから。
・客観的な判断材料がない時は、イメージの影響を受けやすいから。
・これまでに知っている限られた情報だけで、イメージを作り上げているから。
まあ、そんなところでしょうか。
こうして見ると、ほぼ全てにおいて誤解を招き寄せていますよね。
小さなことのようですが、
結局はその思い込みが差別意識とどこかでつながって行くのだと思います。
けれど、実際にはアメリカでは、俳優が大統領にも州知事にもなっています。
日本でも俳優だった森田健作さんは千葉県知事ですし、
東国原英夫さんも政治家でした。
アスリートだったから務まらないと思ってしまうのは、
まさに思い込み以外の何物でもありません。
芸能人によるSNSでの政治的社会的発言をバッシングする風潮にも、
同じような偏見を感じます。
私たちはどうしたら、思い込みを減らせるのでしょうか?
名案は浮かびませんが、
「思い込んでいない?」と自問する習慣をつけるしかありませんね。
コロナによって厳しい状況が続いているオリンピック/パラリンピック。
差別や偏見を乗り越えて来た歴史でもあるし、
ここまで大勢の人たちが努力してきたわけだから、
まさかの奇跡や素晴らしいアイデアによって、開催できるといいなぁと思います。
加えて、私は自分が女性なので、これを機にジェンダーギャップの大幅改善が進み、
国際社会での日本のイメージが変わるといいとも思います。
もしかしたら「オリンピックは無理」というのも、思い込みなのかな?
来週はもう3月です。春の足音が聞こえてきますね。
素敵な1週間をお過ごしください。
感謝の仕組み化、どう思う?

先週、社内でWEB社内報にあってほしい機能について議論をしていました。
その中で、巷によくある「Thanksボタン」「Thanksポイント」は必要か、
という話になったのですが、
あなたなら、その機能、ほしいと思いますか?
これらは、Thanksカードのデジタル版です。
私たちの結論としては「ほしくない」ということに。
その理由は、、、気難しいことを言うようですが、
こういった施策にちょっとしたあざとさを感じるからです。
どういうことかというと、この機能を導入する目的は、
感謝されたらモチベーション上がるよね、
お互いの感謝を見える化して、モチベーションを上げていこうよ!
...ということですよね。
その発想の奥には、なんというか、マウンティング感覚があるというか、
誰もが持っている承認欲求で人をコントロールしようとしているというか、、、
あざといという表現は適切でないかもしれませんが、自然体とは言えません。
しかも、感謝という、本来ならとても素敵な行為をチープなものにしてしまう。
そんなもんはほしくないよね、ということになりました。
というわけで、今日のテーマは感謝とご褒美、褒めるについてです。
ThanksボタンもThanksポイントも、根底にあるのは、
感謝を大切にしようという思想。そこには、まったく異論はありません。
でも、仕組み化した時点で暗黙の義務が発生するところに違和感を感じます。
義務的なリアクションは、望ましいコミュニケーションとはいえません。
まあ、仕組み化すると、ラクそうに思える気持ちはわかりますが。。。。
しかも、暗黙的義務的Thanksであっても、
それをもらうことは、承認欲求が高い人にはウケるかもしれないし。
でも、内発的な動機を原動力に行動する人にとっては、むしろやる気が削がれます。
「嫌われる勇気」で一躍有名になったアドラー心理学では、
褒めることを否定し、その代わりに感謝を示すことを勧めていますが、
褒めることを否定している理由は、
承認欲求を満たして行動させようとすることを否定しているからです。
人が、褒められるという「言葉のご褒美」ほしさに行動することは、
幸福の追求に反するという考えです。
感謝を見える化した時点で、それはもう「ご褒美」と同じに思えます。
コロナで印刷していた社内報をWEB化するという流れは、現在加速しています。
安易にThanksという「ご褒美」を導入してほしくないものです。
さて、Thanksのシステム的な見える化という話以前に、
子どもや部下を「褒めて育てよう!」という育成観も、どうなんだろうと思います。
私自身はアドラーが言うほど褒めることをストイックに否定はしませんが、
褒め方の指南書を頼りに、
上司が一生懸命がんばって部下を褒めるというのは、いかがなものかと思います。
例えば、否定的な指摘をする前には、3つほど褒めろなんていうのもその1つです。
いったいいつ頃から、「褒めて育てよう!」が主流になってきたのでしょうか。
東洋経済オンラインのインタビュー記事の中に答えが見つかりました。
「ほめると子どもはダメになる」の著者・榎本博明さんによれば、
「褒めて育てよう!」という教育観は1990年代頃からのもので、
学校教育がテスト結果より授業中の態度や関心で成績を評価する方向に
変わった頃と時期を同じくしているようです。
もともと褒めて育てる理由は、「自己肯定感が高まるから」だったようなのですが、
榎本さんは「頑張ってもいないのにただ褒められていい気持ちになっていたのでは、
本当の自己肯定感は育たない」
「日本は欧米流の『褒めて育てる』を歪んだ形で導入した」
と語っています。
ちなみに「アメリカは褒める社会」とはよく耳にすることですが、
日経ビジネスの中でかつてアブダビ政府の投資庁で働いていた林則行さんが
こんな面白いことを書いていました。
面談で英米人の上司は「がんばってるね。
私だけでなく周りのみんなが評価しているよ」など良いことしか言わず、
営業成績が低迷している人に対してさえ、
「今年の営業成績だけど、もう少し行けたはずだよね」と軽くお尻を叩き、
「これがあなたの本来の力でないことは知っている。
景気が悪かったのが最大の要因だよ」とフォローしたりするそうですが、
こう言われたアメリカ人の部下は「相当厳しいことを言われた」と思うのだそう。
もし日本であったなら、自分はまずまずの評価を受けたと勘違いしそうですよね。
ベースにある文化や意識が違うものをそのまま日本に持って来ると、
おかしなことになる例と言えるかもしれません。
マニュアル的に褒めるというアプローチには疑問を感じるものの、
「褒める」の影響は知っておきたいもの。
まず、スタンフォード大学キャロル・S・ドゥエック教授の実験結果を紹介します。
実験は400人の小学5年生を対象に行われました。
子どもたちをふたつのグループに分け、
簡単な問題を解かせます。
終わった時、片方のグループの子には「よくできたね」というひと言で褒めてやり、
もう一方のグループの子は褒めない。
その後、子どもたちに次に挑戦する問題を選ばせました。
簡単なものか、難しいものかの二択です。
すると、褒められたグループの子どもたちは、大半が簡単な方を選び、
褒められなかったグループの子どもたちは、9割以上が難しいほうを選んだそうです。
つまり、もう一度褒められるためには「解答できる」必要があり、
そのために、困難に挑戦する意欲が削がれたのだと見られています。
なんだか恐ろしい。
このほかにも、いろいろなところでいろんな人が実験を行っていて、
「頭がいいね」と地頭的な能力を褒められるとその後伸びなくなり、
「頑張ったね」と努力を褒められると伸びるなどがわかっています。
いずれにしても、褒めることの功罪を知るのは良いとして、
あまり詳しくハウツーを知りたくはありませんね。
なぜなら、人を成長させるためと考えれば、それも必要だとは思いますけど、
本来は計算づくで褒めるのではなく、心底褒めるのがいいですから!
感謝も同じで、やらなきゃ感覚の仕組みの中では言われたくないなー
と思っていても、案外うれしかったりするのでしょうか?
人間って、めんどくさい。でも、それが真実だという気がします。
長くなっちゃいました。今週も素敵な1週間を!
集中力が散漫だと思ったら...

あっというまに2月になってしまいましたね。
時の速さにため息が出ます。
さて、今日のテーマを単刀直入に言うと、
私たちは今、「集中力散漫社会」のネガティブスパイラルの中にいるのでは?
という話です。
実はこれ、先週の私の体験に基づいて考え、
調べた結果、わかったことです。
自分で言うのもなんですが、私の取り柄の一つに、
集中力が高く、しかも持続できる...というものがあります。
なのに、先週の私は、集中したいことにまったく集中できませんでした。
当然、パフォーマンスは下がります。
集中力という観点で自分を振り返ってみると、
もしかしたら、これは先週始まったわけではなく、
ここ最近の傾向であり、むしろ徐々に下がっているのではないかと思えてきました。
さらに考えていくと、このような私の感覚は、
ひょっとしたら私にだけ起きているのではなく、
日本中で起きているのではないか、、、と思ったんですね。
どういうことでしょうか?
生産性と人の集中力というのは正比例の関係にありますよね。
逆に言えば、気が散る時間が多いと生産性は下がる。
だから、気が散る要素を放置しておくと、当然、生産性は下がるわけです。
私の日常で言えば、Slackやメールを読んだり、
それに伴って指示や助言をすることが「気が散る要素」に当たりますが、
このような状況にあるのは、私だけではないと思います。
「通知」という親切な機能が、皮肉にも集中力を邪魔します。
PCだけではなく、スマホにはSNSなどからも通知が届きます。
(設定を変えろという話もありますが。。。)
通知が入るたびに、マルチタスクモードがオンになり、
内容を把握しようとし、必要に応じて応えようとする。
そうすると、本当は集中したかったことから、どんどん意識が離れていきます。
ニューヨーク大学のアダム・オルター教授の研究では、
興味深いことがわかっています。
人がメールをチェックするのに、使っている時間はたった6秒だそうですが、
メールチェックを終えて、元の集中状態に戻すのに、25分かかるというのです。
また、「マルチタスクは脳を疲れさせる」と語るのは、
精神科医であり禅僧でもある川野泰周さん。
Study Hackerのインタビューで次のようなことを述べています。
複数のことを同時に処理するマルチタスクのために、
脳の中のデフォルト・モード・ネットワークという部分が働くそうなのですが、
この部分、エネルギーの消費効率が悪く、
多くのエネルギーが使われる結果、脳を疲れさせてしまうというのです。
脳が消費するエネルギーの6割もがこの部分で使われているという報告も。
デフォルト・モード・ネットワーク? 初耳です。
どうやら、特定の対象に意識を向けず、いろんなことに意識を向けたり、
とりとめもない意識状態の時に活性化する脳の回路のことのようです。
クリエイティブな着想などを得る際にも活躍する部分なのだとか。
一方で、ある事柄について積極的に思考を駆使したり、
意識的に注意を払ったりする状態を司るのは、
セントラル・エグゼクティブ・ネットワークという部分。
集中しているときは、脳のこの部分が使われているようです。
メールも、Slackも、Teamsも、
コミュニケーションという面では大切ですが、
マルチタスクと上手に付き合わないことには、
脳は疲労し、集中力は下がるということです。
その結果、当然生産性も下がってしまいますよね。
ついでに言うと、脳が疲れていると、考えることをやめてしまったり、
感情や悩みにさえ鈍感になっていく気がします。
エネルギーが足りずに悲鳴を上げている脳にとっては、
なるべく省エネでいたいはずだからです。
この状態が社会に蔓延しているとしたら、いいことナシ!
まさにネガティブスパイラルです。
では、私たちはどうしたらいいのでしょうか?
目下の私はこのように考えることにしました。
8対2の「パレートの法則」というのがありますよね。
・売上の8割は全顧客の2割が生み出している
・売上の8割は、全商品銘柄のうちの2割で生み出している
・売上の8割は、全従業員のうちの2割で生み出している 等々
全体の数値の大部分は、全体を構成する要素の2割程度が生み出している
とする説です。
これは、仕事で費やした時間と成果の関係にも当てはまると言われていて、
成果の8割は、費やした時間全体の2割の時間で生み出されているというのです。
言われてみれば、そうかもしれません。
毎日毎日、8時間、集中を続けるなんてできませんからね。
8時間の2割ということは、1.6時間です。
まあ、少し欲張って1日のうちに2時間だけ集中しようと決めたら、
何となくできそうな気がしますよね。
あなたの脳は元気ですか?
今週も素敵な1週間でありますように!



