年賀状で思う、個人を尊重するとは?
年賀状シーズンがやってきました。
メールやメッセンジャーが発達しても、
今のところ年賀状を止めるという話は、
私の周りでは聞きません。
世代的なものもあるかもしれませんが...。
社員や元社員に年賀状を出すとき、
毎回、ふと自問することがあります。
それは、社内結婚した人たちに出すときです。
一般的には二人に1通出すのが普通だと思いますが、
私は一人ひとり別々に出しています。
自問の内容は、うざいと思われちゃうかな...?
銘々に返信しなくてはいけないような
負担な気持ちにさせちゃうかな...?
です。
といっても、それほど深く考えているわけではありません。
ただ、子どもの頃に両親二人の名前で届いた年賀はがきが、
父宛の年賀はがきに分類されているのを見て、
ちょっとした違和感があったこと。
ウチの母は自分一人の名前で(夫婦連名ではなく)
自分の年賀状を出していたことなどの
影響を受けているような気がします。
つまり、深くは考えていないなりに、
私は「個人」というものを尊重したくて、
夫婦であっても別々に年賀状を出してきたのだと思います。
そんなことを考えていたら、
いったい「個人」を尊重するとは、どういうことなのか、
ぐるぐると考え出してしまいました。
英単語の【individual】(個人)は、
もはやそれ以上【divide】(分割する)ことができない
ことに由来するそうです。
平野啓一郎さんの著作「私とは何か」では、
「個人」は分けられるという概念として
「分人」という言葉も出てきていますが、
物理的に分割できないという意味で、
個人はやっぱり最小単位だと思います。
そんな個人は、個人として存在しながら、
いろいろな役割を背負っていますよね。
たとえば、赤ちゃんは「オギャー」と生まれた瞬間は、
純粋な個人として存在できます。
なんの責任も抑圧もなく、
なんと自由な状態であることでしょう。
しかし、やがて親から「お兄ちゃん/お姉ちゃんなんだから...」
役割を持たされます。
社長、部長、課長...
父親、母親...
長男、長女...
地域の委員、マンションの理事...
宴会の幹事、介護する役割...
話の聞き役、ムードメーカー...
役割は、モチベーションを生むこともあれば、
抑圧を生むこともあります。
個人の上に乗っけられた役割なのに、
個人が役割に負けてしまうと、
人生の主人公が誰なのか、わからなくなりますよね。
だから、
まず自分自身が個人としての自分を尊重することが大切だと思いま
では、自分自身が個人であることを尊重するとは、
いったいどういうことなのでしょう?
それは、「オギャー」と生まれた瞬間の状態、
つまりそこに存在している自分自身をただそれだけで尊いものと思
自分の心を自分自身で束縛せず、
命を与えられたことに感謝することなのではないか...。
私は、そんなふうに受け止めています。
なので、最初の問題に立ち返って、
私が元社員の夫婦宛に個々に年賀状を書くのも、
そこに存在してくれていること自体への感謝を示したい、
役割に飲み込まれずに、個人の幸せを追求してほしい、
きっとそのような願いからなんだろうな...。
個人の人生の上に、役割の人生があるのだから、
役割の人生がすべてになってしまってはいけないんだろうな...。
年賀状からそんなことに考えが及びました。
今年もあとわずかです。
素敵な1週間をお過ごしください。
サラバ!「〜なんだから〜らしく」の時代
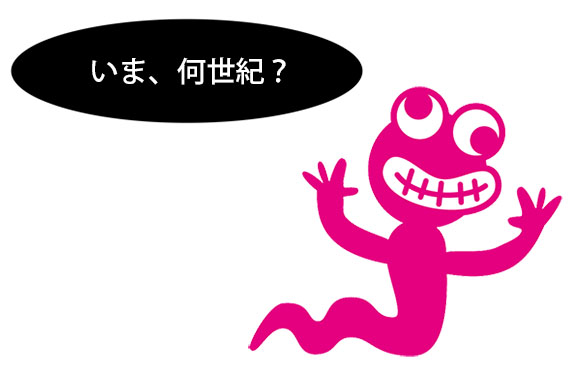 年末が近づいてきましたね。
年末が近づいてきましたね。
毎回、ブログを書く時に、何について書こうかなぁと思います。
今回もアレにしようか、コレにしようかと思いましたが、
大河ドラマ「女城主直虎」が最終回に近づいているのと、
facebookが、「過去の思い出を振り返ろう」というメッセージとともに、
2014年の12月10日に書いた私の投稿を見せてくれました。
それに刺激を受けて、今日は「〜は〜らしく」という価値観や強迫観念に対し、
アンチの視点で書こうと思います。
大河ドラマ「女城主直虎」は来週12月17日が最終回です。
今年も随分と楽しませてもらいましたが、
脚色はあるにせよ、現代への示唆に富んだドラマでした。
その一つが、「〜は〜らしく」は必要ないというメッセージです。
第4回、主人公である直虎は、南渓和尚に次郎法師と名づけられます。
形こそおなごであれ、あれは次郎。
蝶よ花よと育てるものではない。
...というように、「女だから」とは違う目線で物語が展開されます。
(ま、厳密に言うと、南渓和尚は女なら本来「蝶よ花よ」と育てるべきだろうが...
と思っているようなので、根底では「〜は〜らしく」という気持ちが
あるのだと思います)
で、ドラマとしては、そこから女城主が誕生するわけです。
直虎は「戦(いくさ)のない世にするための戦」に勝つために
行動して行きます。
史実として直虎が女性であったのかどうかを含め、
実際のところはわかりません。
でも、男性と女性とで、大勢としての感覚や発想に違いがあることに
異論がある人は少ないのではないでしょうか。
もっと言えば、男性だったとしても個々に異なり、
女性だったとしてもそれぞれが違う。
最後は、人は個々に違うと言う話になりますが、
やはり母性を負っている女性は血を流し命を落とすこと自体を嫌う傾向が
男性よりも圧倒的に強いと思います。DNA的に。
だからこそ、女性は戦いには向かない、
女性は家の中にいて家を守っていればいい、
そうやって家を守ってきた女性は社会について見識がない...
そんなふうな暗黙の合意が長い歴史の中でできてきてしまったんですよね。
でも20世紀(21世紀?)になって「女性だから」という決めつけ自体が
タブー視されるようになり、現代に至っています。
それでも、、、、
実際には小さい少女がこんな悲しい思いをしています。
それが、冒頭に書いた私の2014年のfacebook投稿です。
私が注目したのは、サッカーをやっているある少女の作文でした。
「女の子がサッカーをやっている」という大人の反応に彼女の心は傷つき、
そして彼女自身が自らそれを乗り越えていく姿に私は感動しました。
読んでいただても1分もかからないので、まずはこちらを見てください。
http://buzzmag.jp/archives/16462
これを読んで、どう感じましたか?
私は、こんなことが起きているなんて信じられない、ではなく、
ああ、やっぱりそうなんだな...と思いました。
まだまだ私たち大人の心の中に、いろんな決めつけや思い込みがあり、
それが社会の進化の妨げになっているんだな、と。
ここは女の子のいるところじゃない、
女の子(なんか)に男の子は負けるな!
これが少女の聞いた大人たちからの叫びだったのではないでしょうか。
しかも、その叫びの理由は試合に出ている自分の子どもが男の子だからです。
母親自身は女性なのに、自分の子どもが男の子だと
女性への視点を失ってしまうという悲しい構図。
とても痛い指摘だと思います。
私には子どもがいませんが、
この作文を書いた女の子の気持ちを想像することはできます。
だから、男の子がいるお母さんも、冷静になればもちろん想像できると思うんです。
「男なんだから女に負けるな」
これは20世紀の発想で、もうこういう時代ではないってことを。
女性が上司にいたとしても普通な時代に、
親が「男なんだから女に負けるな」と思っていたら、
男の子はむしろ傷つきますよね。
で、、、、私が今回書きたいのは、男性女性の話だけではなく、
「〜は〜らしく」という方程式でのその他諸々の思い込みや決めつけについてです。
私も「社長なんだから社長らしくしてくれ」と言われたり、
疲れているから欠席したいと言ったら「友だちなんだから出てよ」と言われたり、
ちょっとしたことでたくさんの困惑を感じてきました。
そして、最終的に出てきた答えは、
人の思惑のせいにするなってことです。
人が「〜なんだから〜らしくしてよ」と自分に期待していたとしても、
自分が快適でないなら、あるいは、やりたくないならやらなければいい。
自分の人生なんだから、それが第一であって当然だと今は思います。
で、これは、自分側の解決方法です。
でも、やっぱりそうは思えない時代があったわけで、
社会の価値観が変わってほしいと願っていたな。
具体的には、みんなが「〜は〜らしく」という方程式を捨てて、
決めつけなしのコミュニケーションが取れたらいいな、と。
私は、多様な価値観にアンテナを張ること、
これからの時代は必須だと思うんですよね。
「〜なんだから〜らしく」と自分が思っていることに気づいたら、
リセットする。そんなふうな素直さを持ち続けていたいものです。
さて、あなたはどう思いますか?
今年もあと半月。
今週も素敵な1週間をお過ごしください!
忖度(そんたく)〜それでもみんながやっている

先週金曜日に毎年恒例の流行語大賞が決まりました。
その1つが「忖度(そんたく)」です。
この言葉が広まったきっかけは、
今年3月の籠池泰典氏の発言、
「直接の口利きはなかったが、忖度があったと思う」だそうです。
検索ランキングの上位に上がったように、
一度は辞書検索をした方も多いのではないでしょうか。
私も、このメルマガを書くために、あらためて検索してみました。
デジタル大辞泉によれば、
[名](スル)他人の心をおしはかること。また、おしはかって相手に配慮すること。
つまり、この言葉は本来、悪い意味を持たない言葉でした。
でも、SNSや日常会話でも気軽に使われるようになったのは、
日本的な習慣や発想を揶揄したり、茶化したりしてのことだと思います。
言い換えると、良いも悪いもなかったものが、
忖度の中には、悪い忖度があると多くの人が気づいたとも言えます。
悪い忖度は、自分の心に背いてでも、相手が期待することに応えようとしたり、
相手が期待していることを与えることで、自分に見返りがくることを期待したり。
でも、これは、贈収賄などの不正に限りません。
企業では、自分の上役に対して、こうした気持ちを持つ人が多くなると、
決して健康な状態とは言えないのではないでしょうか。
いわゆる「顔色を伺って行動する」ということですから、
主体性も何もあったものではありません。
さて、、、
私たちの生活、実際にはどうでしょう?
自分も含め、周りの会話に目を向けると、忖度だらけだったりします(笑)
つまり、私たちは、良くも悪くも、
相手の心を推し量り、配慮するということをしていますよね。
そして、良い意味での忖度=心配りをしたつもりが、
実はまったく相手の気持ちを汲み取れていなかった、、、
などということもよく起きます。
たとえば、
・Aさんは、○○の役割を交代してほしいと思っているようだ。
・Aさんは、○○の役割を手伝ってほしいと思っているようだ。
どちらもAさんの気持ちを推し量っていますが、まったく見方が違います。
人の気持ちへの解釈がこんなふうに分かれるという経験、
あなたにもあるのではないでしょうか。
しかも、所詮解釈なのだから、どちらが正しいとも言えないはずなのに、
「いや、そんなはずはない」と主張して、
正しいのは自分だという論戦を繰り広げたり。
本当は、Aさんに聞いてみればいいのだと思いますが、
Aさんがその場にいない場合などは、こんなことが起きがちです。
私も最近あるコミュニティで、そんな場に居合わせました。
おそらく人は、自分の思い込みに基づき相手の気持ちを推し量り、
自分の都合のいいストーリーで相手を解釈する。
知らず識らずのうちに、そういうことをやっているのかもしれません。
もちろん悪気などありません。
せめて自分はどんな心がけがいるのかと自問してみると、
・解釈を正しいとは主張しない。
・想像するよりも直接聞いて言質を取る。
・自分の心に背かない。
そんなところでしょうか。
年末まで1カ月を切りました。
忙しい季節ですが、だからこそ心を亡くしたくないですね。
素敵な1週間をお過ごしください。



