イヤなことを避けるとコアコンピタンスはつくれない
今週、11月29日(水)は当社の33周年となる創立記念日です。
改めて当社の強みは何なのかと自問したり、再確認したりしながら、
強みを強みとして維持発展させるには、イヤなことも避けてはいけないな、、、
と、そんな確信にたどり着きました。
どんな会社にも、何かしら強みがあります。
創業者のこだわりが強みとなって受け継がれて行くケースも多いと思います。
では、「受け継がれる」というのは簡単なことなのかというと、
実はとても難しいことですね。
あなたの会社には、どんな強みがありますか?
上手く受け継がれていますか? 今日はそんなことを考えたいと思います。
当社を例に挙げると、、、
強みの一つに「企画」というものがあります。
「企画」に対して、とてもこだわりが強い会社です。
私自身がそこにこだわりを持ち、
他社よりもぶっちぎりで企画が強い会社でありたいと思ってきたからです。
そうです、ぶっちぎりでなければ、強みとは言えません。
あなたの会社の強みに関しても、同じことが言えるのではないでしょうか。
ぶっちぎりで他社より強くありたいと思ってきたことは何か?
強み=企画という当社の例に話を戻しますね。
ロジカルに物事を分析したり、
議論をし尽くしたり、
発想をジャンプさせたり。。。。
美しく一本筋の通った、明快なコンセプトの企画。
なるほど、それは効果がありそうだと思えるような企画。
お客様が喜んでくださる企画。
エクスタシーを感じるような企画。
そう言ったものにこだわりを持って取り組んできたので、
そのノウハウの上にコンサルティングなどの別のサービスを
展開することができました。
しかし、この「企画」という行為、
色々なスキルが求められ、
経験を積まないと、そう簡単に自律的にできるようにはなりません。
OJTで社員に企画を教えるたびに、
ダメ出しをしたり、注文をつけたりしないといけない。
実は、このフィードバック、どんなに言葉を選んだとしても、
する方も、される方も、
あまり気分のいいことではありません。
人は、誰しも受け入れられたい生き物ですからね(笑
諸手を挙げての「OK!」でない限り、
NGや注文出しなどのフィードバックは、
なるべくならされたくないのが人の本音です。
でも、コアコンピタンスを守るためには、
高い要求をしないとならない。
で、要求した結果、どうなるかというと、、、、
入門者は「やっぱりオノさんはオノさんの思う通りにやらないと
イエスとは言わない。自分はオノさんの金太郎飴にはなれない」という
反応を示します。
それは、時には反発となるし、
時にはやる気の低下を生んだりします。
しかし、そこから3年が経ち、5年が経つうちに、
その人自身が、何がOKで何がNGなのかを判断できるようになり、
グラスルーツらしいこだわりを受け継いで、
その目線から後輩の指導をするようになります。
その時点で、すでに目利きになっています。
不思議なことです。
もちろん、反発を感じて、やめてしまった人もいたことでしょう。
でも、おそらく今では私が私の金太郎飴を作りたかったわけではないこと、
わかってくれているような気がします。
企業が、強みを持つということは、
何かしらに半端ないこだわりを「集団として」持ち続けるということです。
では、半端ないこだわりを持ち続けるとはどういうことか?
私は、こう考えます。
・独りよがりでないか、自己満足でないか、シビアな目をみんなが持っている。
・ギリギリの合格ラインとぶっちぎりの判断基準を持っている。
・これは「ぶっちぎりか?」という自問を各自が持ち続けている。
・ぶっちぎりでなかった時に、エクスキューズをせず、潔くそれを認め、
どうしたら良かったのかを考え続けている。
結局、コアコンピタンスというのは、
風土と密接に繋がっているのだと思います。
OKなのか、NGなのかを、なあなあにしてしまう組織風土の中で、
コアコンピタンスが維持成長できるはずはないですからね。
つまり、OKはOK。NGはNG。
組織風土の中に、その明瞭さがなくなると、
強みだったものは、あっけなく消えていくと思います。
強みを築くのは大変ですが、
消えていくときは、本当にあっけなく、消えていくでしょうね。
あなたの会社は、どうですか?
守っていきたい強みは何ですか?
OK/NGが明らかで、強みを守れる風土がありますか?
というわけで、もうしばらくは私も自社のコアコンピタンスの維持のために、
NG出しを通じて貢献しましょうぞ!
短期的には気分のいい仕事ではないかもしれませんが、
長期的には絶対必要な仕事だと信じているので。
今週はもう12月に突入!
2017年のエンディングに向けて、素敵な1週間でありますように!
「自立」と「自律」はどう違うのか?
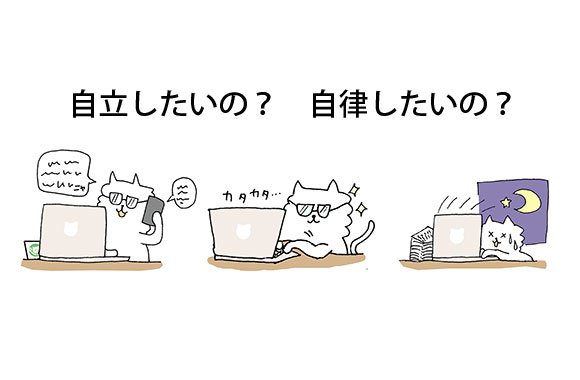 部下が伸びて行けるようにするには、自分はどう関わったらいいのか、
部下が伸びて行けるようにするには、自分はどう関わったらいいのか、
これは私でなくても、上の立場にある人なら、きっと誰もが考えていることです。
もちろん、私も考えます。
そこで、今回は「自立」という単語を入り口に、
育成や成長のあり方について考えたいと思います。
人の欲求の一つに「自立して仕事をしたい」というものがあります。
特に経験が浅ければ浅いほど、その欲求はとても強いのではないでしょうか。
自立して仕事をしたい。
↓
上司からの支援がなくても一人で仕事ができる自分でありたい。
↓
報告はするので、仕事を任せてほしい。
まず部下の立場に立つと、
こう思うのは、とっても自然なことですよね。
このとき、部下は、「自立」というのは、一人でできるようになること、
と思っている場合が多いような気がします。
そして、上司も、早く独り立ちしてほしいと思っているので、
自立心を持っていること自体を悪く評価する人はいないのではないでしょうか。
ところが、私の体験から言って、「一人でできる」という場合の
「できる」の目盛り合わせを十分していないと、
上司部下の双方にとって、あまりいい結果になりません。
似たような意味合いの言葉に「自立」と「自律」があります。
この2つの単語はどう違うのだろうと考えていたら、
キャリア・ポートレート コンサルティング 代表の村山 昇さんという方が、
「INSIGHT NOW」でとてもわかりやすい比喩を使っていました。
数式を投げかけて、答えを出させる3つの方法とその違いについてです。
https://www.insightnow.jp/article/20
村山さんはこんなふうに違いを説明しています。
・3+5=●は、自立レベル
・●+●=8は、半自律レベル
・●+●=○は、自律レベル
右辺は、ミッション・ゴール、たどり着く先。
左辺は、それを実現させるためのプロセスや実現方法です。
自立というのは、
英語で言えば、self-standing(自力で立つことのできる)。
「3+5」という与えられたやり方を一人で実行し、
一人で「8」以上のゴールにたどり着ける。(←私の解釈です)
他に依存しないで、自分でやっていける段階ということのようです。
自律レベルは、右辺(○)も、それを実現するための左辺(●+●)も
自分で考えて、実行できる段階です。
英語で言えば、self-directing(自分で方向付けできる)。
自力で立った後は、自分が決める方向に進んでいけるということだとしています。
さて、、、、
恐らく最初の段階で部下の気持ちにあるのは、
「自立(self-standing)」の方ではないかと思います。
要は、他者の力を借りずに、自分の力だけでやり遂げたいという気持ちです。
一人前だと自認でき、他者からも認められたい、そんな気持ちでもあります。
ところが、営業のようにゴールを定量的に定められる場合は、
「8」以上のゴールにたどり着けたのかどうか、
明瞭にわかりますが、サービス的なもの、ソフト的なものは、
一目瞭然にはわかりません。
そして、「8」の状態を体験したことがなければ、
自分が「8」の状態を生み出せているのか、
自ら見極めることができないし、できなくて当然です。
ですから、「8」の状態がどんなものであるのかを、
いかにして共有するかがとても重要だということになります。
上で述べた「一人でできる」という場合の
「できる」の目盛り合わせをしておくということです。
そして、あくまで「8」は合格ラインであり、
「8以上」を目指すのだと共有された状態をつくること、
それが大切なのではないでしょうか。
ところが、これが簡単ではない。
なぜなら、そもそも「8」の状態を体験したことがない部下は、
体験していない部分を想像で補うしかないわけですから。
しかも、往々にして部下はゴールのレベルを追求することよりも、
まずは「一人で進めたい」という欲求の方が強い場合が多いです。
スポーツに例えると、「勝ちたい」よりも「試合に出たい」という感じでしょうか。
これに対する最善の答えは私にもわかりません。
でも、こんな仮説を持っています。
仮に「自立的に仕事をしようとすること」よりも
「より良い仕事をしようとすること」の方に価値があるという
共通認識が持てていたなら、
与えられている仕事の現状認識を一致させることが
大切だと思えるのではないでしょうか。
あるいは、もっとより良くするためにはどうしたらいいかという観点で
「8」のあり方について、
自然に質の高いコミュニケーションを図るようになるのではないでしょうか。
それが、目下の私の仮説です。
村山さんの話に出てきた「自立」ではなく、「自律した状態」、
つまり、自分が決める方向に進んでいける状態というのも、
結局、より良い方向に向かって進んでいける状態ということだと思います。
自律的になると、「試合に出たい」を卒業し、「勝ちたい」となる。
私は、そんな気がしています。あなたは、どう思いますか?
どうぞ素敵な1週間をお過ごしください!
フレンドリーである/ないの違いとは?
 11月の3日から6日間ほど一人でベトナム/
11月の3日から6日間ほど一人でベトナム/
一人旅の面白さを語れるほど、
ですが、急にスケジュールが見通せて、行けそうだと思う時、
パッと行くことを決めるので、
で、
今日は、今回の旅行で得たたくさんのインプットの中から、
一つを拾い上げて紹介しますね。
それは、「フレンドリー」であることについてです。
ハノイは面白い街でしたが、信号もない中、
車とバイクが激しく行き交う道を体を張って横断するのに疲れてし
現地滞在の正味4日のうち、
具体的には、
1日はハロン湾へ、もう1日はホアルー&タムコックへ。
いずれも世界遺産です。
タムコックのツアーは現地ホテルで申し込んだためなのか、
20数名の参加者のほとんどは欧米から来ている人たちでした。
フランス人、カナダ人、オーストラリア人、スウェーデン人、
男女2人組もいれば、男性3人組もいるし、
女性3人組もいれば、夫婦とその友達の3人組もいました。
もちろん一人旅の人たちも。
バスで移動し、古都ホアルー観光や、
ツアーにありがちなお土産屋さんでの休憩、
最後のタムコック観光を通じて、
その時にフレンドリーな人とそうでない人がいることに気づきます
しかし、一見フレンドリーでないように見える人
(言い換えると自分からは話そうとしない人)も、
話しかけられれば、話すんですよね。
人間観察的にいうと、まずこの感じが面白い。
私自身は一人だったので、
どちらかというと自分から話しかけた方だと思います。
恥ずかしいほどのブロークンな英語で(笑泣)
そんな中、私に最も大きな刺激を与えてくれた人物は、
インドネシア/バリ島から一人で来ていた28歳の女性です。
彼女はいろいろな人にどんどん話しかけていき、
二人だけの世界にドップリ浸かっているように見えたカップルさえ
彼女が話しかけると、楽しそうに会話に参加していました。
敢えて表現を選ばずにいうなら、
日本ではきっとこれを「オバチャン力」というのかもしれません。
相手がどう思うかなんて、彼女は気にせず、
自分が思うままにどんどん話す。。。
でも、美しくチャーミングなバリニーズがこれをやっていると、
「オバチャン」どころか、
「素晴らしくフレンドリーな人」と表現したくなります。
私は、彼女のフレンドリーさに感化され、
さて、ツアーから戻ってハノイで一人で夕飯を食べていたら、
隣のテーブルの人たちから突然話しかけられました。
マレーシアからの旅行者で、きれいな英語を話す4人家族でした。
一言、二言話した後、言われた一言がショックでした。
「日本人は話したがらないからね...」と。
言葉の裏側で「あなたは違うね」と言われたと感じたので、
「いや、私だって英語で話すのは得意じゃないですよ」
「それは問題じゃないよ」と言い返され、これまた別の意味でガ~
どうやら私は「フレンドリー」な方に分類されている!?
私なんて、あのバリニーズに比べたら、遠く及ばないのに。
とても低い次元で、なのに褒められている。。。
複雑な心境になりました。
彼らと別れてから湧いてきた疑問、
それは、なぜ「日本人は話したがらない」と彼らは思ったのか、
ある時、日本人に話しかけたのに、
そもそも「話しかけないでくれ」
私の頭をよぎったのは、オリンピックのプレゼンです。
あれだけ「お・も・て・な・し」をアピールしちゃっているのに、
なんかこれヤバクない?と思いました。
「話したがらない日本人」であることは
「おもてなしする日本人」であることと矛盾している。
国際的にはそう映ると思いました。
日本人としては、それとこれは別なんだよと弁明したいけど、
多分、それは通用しない。。。
結局「フレンドリー」の本質って何なのでしょうか?
当社の社員に、やたら外国人に話しかけられやすいY君がいます。
私は、「フレンドリー」についてある仮説を持って、
「Y君は、外国人に微笑まれたら、微笑みを返すんじゃない?」
彼の答えは「イエス」でした。
私の感覚でのフレンドリーの基本は、
・まず目を合わせることを厭わないこと、
・そして目が合ったなら、微笑みを送ること、
...ではないかなと思っています。
私はベトナムで無意識のうちにそれをやっていたので、
あのマレーシア人の家族にフレンドリーだと思われたのだと思いま
実は、目を合わせたり、微笑みを送るというのは、
社内でも大切なことですよね。
ですが、これ、
で、これを社内から始めようとすると、
トレーニング的な意味での私のオススメは、
コンビニで買い物をする時に意識を持つことです。
店員さんとちゃんと目を合わせて、
そして、「ありがとう」とちゃんと言うこと。
店員さんも目を合わせる人が意外に少ないということに気づくかも
相手が目を合わせてくれないその時に感じる「
しっかり感じると、「フレンドリー」
私は、これを意識的にやっています。
そして、本当は、名札を見て名前を覚え、「ありがとう、○○
でも、やっぱり気恥ずかしくて、いまだにできていません。
よし、明日こそ、いや今日こそやってみます!
さて、、、
あなたのフレンドリー度は何点ぐらいですか?
私のフレンドリー度を10点満点で表すと、
多分6点ぐらいですね。
あのバリニーズが私の中での10点モデルです。
楽観的な私は、これ、自分の伸びしろだと思うことにします!
11月ももう後半。
どうぞ今週が素敵な1週間でありますように!



