「自己満足」見直し論

こんにちは。
今日のテーマである「自己満足」という言葉、
どちらかというと肯定的には使われず、
否定的なニュアンスを含んで使われることが多いと思いませんか。
「自己満足に終わる」
「自己満足でしかない」
こんな使われ方をよくします。
自分自身や自分の成したことに対して、
独りよがりで悦に浸っているけれど、
満足しているのは自分だけで、他人を満足させられるものではない...
というような意味合いでしょうか。
人に向けて使うときは、
他人への目線が欠けていることに対して揶揄する言葉になり、
自分に向けて使うときは、
謙ることで批判をかわす意図も見え隠れします。
でもね、先日、ふと思ったんですよ。
他人より先に自分が満足しないものが、他人を満足させることはありえないな...と。
他人から褒められたり、他人を満足させることができても、
自分が満足しなければ、全然ハッピーじゃないし、
反対に、自分が満足して幸せだと思えれば、それで十分幸せだよね、と。
実は、セドナから帰って以降、
私の中で変化したことがいくつもあるのですが、その一つがこれです。
向こうで過ごしている間に、
ネイティブインディアンの血を引く占い師のような女性に出会いました。
その彼女に、こんなことを言われたのです。
「あなたはもっと自分のことを第一に考えるべきだし、
もっと好きなことをやって人生を楽しめ」。
人生が楽しくないと思ったことなど一度もなかったので、
最初はぴんと来ませんでした。
でも、「子どもの頃から、自分のことを後回しにする傾向があったでしょ」
と言われて、むむ、、、んー、たしかに。
思い当たったんですよね。
子ども時代のことよりも、むしろ今の自分について。
たとえば社長をやっているので、
「社長なんだから、仕事を優先するのは当然...と
いつも最初から譲歩していたんじゃない? 私?」
そんな疑問が湧いてきたのです。
誤解されても困るので、補足しますが、
実際には仕事は楽しいし、大好きです。
特に未来のことを考えたり、戦略的なことを考えたりしているときは、
本当にワクワクします。
だけど、それはもしかして「アタマが楽しんでいる」状態であって、
「ココロが楽しんでいる」のとは違うのかも、と
そんなふうに思いました。
振り返ってみると、長い間、
学生時代のように「好きだからやる」をしていませんでした。
表現したり、創作したり、人に見せたり、
100円で買ってもらったり。。。
学生時代はそんなことをして、まったくの自己満足でしたが、
間違いなく満足していました。
もう一度自己満足のために、「好きだからやる」をしようかなと、
そんな気になりました。
ですが、ここであなたとシェアしたいことは、
何かをするとか、しないとかの話ではなく、
自分の満足を最初に考えるということ、そして
それに対して簡単に譲歩しないということが、
幸せのために不可欠だという発見についてです。
仕事だってそうだと思います。
上司を満足させることよりも、
自分が満足することを先に考えてちょうど良いのでしょうね。
そうしたとしても、揺り戻しはあるのが社会ですから(笑
自己満足について、あなたはどう思いますか?
さ、5月もあと2日で終了ですね。
どうぞ良い1週間をお過ごしください。
(picture by:Justine Furmanczyk)
人は変われるが変えられない
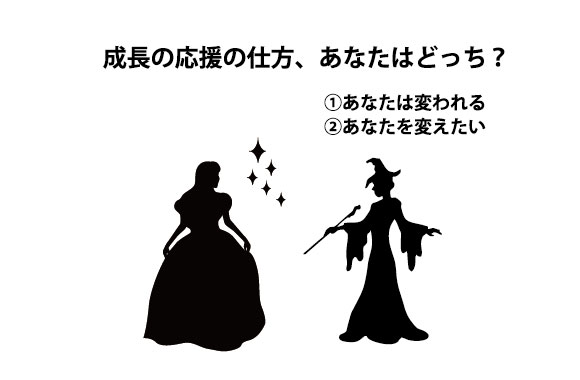
こんにちは。
今日は「人の成長をどう応援するか」という話です。
我が身を振り返り、ちょっと反省したりしながら、
最近考えたことをシェアさせてください。
私自身の成長に関する願望は、
何歳になっても成長していたい、ということ。
私にとって、成長とは「良い方向に変化していく」とほぼ同義です。
で、私も含めて、誰しも変われるし、生涯成長できると信じています。
けれど、人にとって成長と変化は意味が違います。
成長 = 良いこと、望むこと
変化 = 面倒で不安であり、必ずしも望まないこと
部下や後輩の成長支援の役割を担う上司や先輩は
相手を思うあまりに、こんなことを考える。
「どうやったら、もっと伸ばせるだろう?」
「どうやったら、次のステージに行かせることができるだろう?」
「そのためには、こんなことが必要だ。今、足りないのは何々だ」
「そう変われるように、手助けしよう!」
そして、変化を促すようにアプローチします。
しかし、これでうまく行くことは、まずありません。
いや、間違いなくうまく行くことはないでしょう。
人は自ら変わることはできるけれど、
人が人を変えることはできないという前提に立てていないからです。
もちろん、私の発言やあなたの発言を
相手が主体的に受け入れて、影響を受けることはありますよね。
でも、その発言の意図が、相手を変えさせようというものだったら、
それは相手にとって強要になるので、返ってくる反応は、、、
服従か反発です。
私自身、これはもう失敗の連続で...。
あなたは変われるし、成長できると信じることは良いことだったとしても、
こう変わる「べき」だと言ったり、
私がそうなれるように手助けしたいと思い始めると、
おかしな方向に向かっていきます。
これは、上司と部下の関係に限らず、
親子関係でもパートナー関係でもきっと同じです。
相手を変えさせるという発想は、
不遜で傲慢ってことですよね。
それがわかるまでに私は時間がかかりましたが、今はわかります。
自分がされたら、イヤですからね。
でも、その時は善意のつもりだから気付けない。
善意という名の暴力を意図せず振るっているから怖いですね。
成長を「願う」と「強要する」の間にある違いは、何でしょうか?
それは、成長を促し、手助けをしようとした自分の行動を
相手が受け入れてくれない時に、どう感じて、どう行動したかで判断できます。
批判したり責めたくなっていたら、それはもはや強要ですよね。
「なんでアイツは反発するんだ!?」と感じたら、
それは多分思いやりという名の強要になっている可能性があります。
厄介なのは、相手が一見受け入れているように見えて、
実は服従している時。
特に上司部下などヒエラルキーのある関係では、起きがちですよね。
服従は負のエネルギーを内側に蓄えてしまい、
最後には巨大地震を引き起こすので、早めに気づき向き合いたいものです。
人を応援するのは良いこと。
「変えさせよう」とはしないこと。
それを知っているからといって、即実践できるわけではありませんが、
知っていれば、できなかった時に反省できます!
それを肝に銘じて、今週を良い1週間にしたいと思います。
ビデオも観てくださいね〜!
Have a nice week!
メッセージ下手で損をしていませんか?〜画一的フレーズに要注意
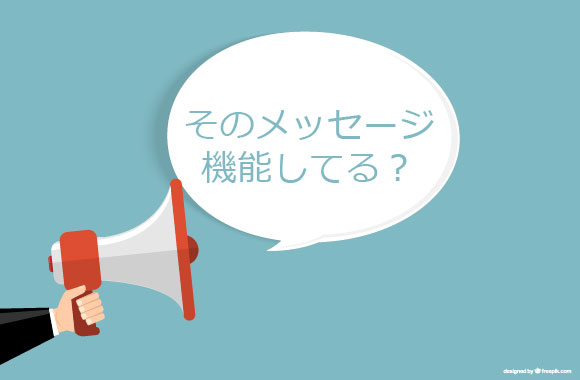
こんにちは。
さて、突然ですが、当社のサイトの中で、もっとも流入を得ているのは、
どのページだと思いますか?
ページ単位でいうと、
第1位 社長就任時、社員の心をつかむスピーチ・原稿の作成のポイント
https://www.grassroots.co.jp/blog/monolog/2014/03/140331.html
第3位 社長就任時や新年度、社長メッセージでやってはいけない5つのこと
https://www.grassroots.co.jp/blog/monolog/2012/04/120423.html
いずれも大分以前のブログ記事なのに、いまだに多くの閲覧者が訪れています。
それだけトップのメッセージ発信の重要性を感じているからこそ、
わざわざ検索して当社サイトに来てくださるのだと思いますが、
その割に社会では「メッセージ」というものをうまく扱えていないと感じます。
というのは、メッセージとしての言葉を大切に扱っている企業が、
少なく見えるからです。
そこで、今日は、「ありきたりで、もっともらしい言葉を使うのではなく、
独自のこだわりの言葉を使うことの大切さ」についてお伝えしたいと思います。
たとえば、以下はIRレポートや中期経営計画、サイトにおけるトップメッセージ等で
よく見かけるフレーズの例です。
・リーディングカンパニー
・最高のお客様満足の提供
・アジアナンバーワン
・新価値創造
・健康で心豊かな社会に貢献
「あるある...」と思われたのではないでしょうか?
世の中で頻出している単語やフレーズというのは、
言ってみれば手垢にまみれた言葉であって、
その言葉で人を魅了することはまず無理です。
しかし、実際には、そうした単語を使わなくてはいけないこともあります。
その場合、その言葉に魂を吹き込む作業、
すなわち、個人の思いを乗せる作業が必要です。
しかし、それを実践している企業はとても少ない。
なぜなのでしょうか。
これは、まったくの私見ですが、
7割は下記の3点のいずれかに該当するのではないか、というのが私の肌感覚です。
1)そもそも、企業にとって、トップメッセージが重要であるという認識がなく、
メッセージには魂を吹き込む必要があるという認識もない。
そのために、メッセージ作成に手間暇かける必要性も感じていない。
2)魅力ある独自のメッセージが重要という認識があっても、
スタッフが社長に代わって書いている場合は、
その思いを吸い上げきれていない。
または、社長が発した言葉を上手に構成して作文すべきと思い込んでいる。
3)重要性は認識していても、書く人に技量や知識がなく、
自社のメッセージを作成するときに、他社の文言を参考にしてしまう。
メッセージはただの作文ではありません。
まあ、普通は社内にメッセージの専門家などいませんから、
無理もないかと思いますが、
言葉は、刺さってなんぼ、振り向かれてなんぼ、です。
メッセージが上手に発信できたら、投資家を引きつけ株価が上がり、
優秀な人材を引き寄せることもできます。
もっとメッセージへ関心を持つ企業が増えてほしいですね。
5月ももう半分が過ぎましたね。
今週も良い1週間でありますように!
「言葉の共通認識がある」は落とし穴
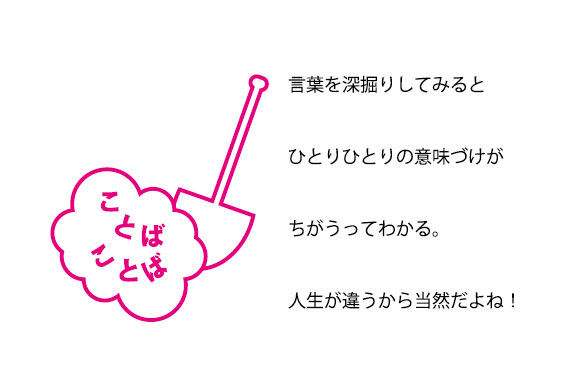
こんにちは。
あっと言う間に終わってしまったゴールデンウィーク。
いかがお過ごしでしたか?
私のテーマは少しストイックでした。
早起きして瞑想したり、パーソナルトレーナー選びの面談したり。
生活習慣を見直したいと思っています。有言実行!
さて、本題。
今日は「言葉の深掘り」の大切さについてです。
当社では、定期的に「うきうきランチ」という食事会を催しています。
このランチは持ち回りで誰かがネタプロバイダーになります。
ネタプロバイダーが出したお題について、
みんなで語り合うというのが唯一のルールです。
ネタはどんなネタでもOK!
前回は「苦労とは何か? これまでに最も苦労したことは?」。
前々回は「(GR外で)最も尊敬する人は誰?」
小さい会社だからこそ持てる機会だと思います。
普段の生活で「苦労とは何か?」なんて考えませんから、
結構、脳みそを活性化させてもらっています。
しかも、そこにネタプロバイダーのその人らしさが出ます。
そこがとってもおもしろいです。
「苦労」の回では、ネタプロバイダーはこう話しました。
ーーーー
自分にとって苦労とは、何が起きたのか理解不能で
どう対処していいかわからないことが起きることだと思っている。
仕事をがんばって、でも思うようにできなくても、
できないからこそまた努力したとしても、それは苦労とは呼べないのではないか?
他の人は苦労についてどう思っているのか、聞きたい...。
ーーーー
こんなような話だったと思います。
で、その回のネタプロバイダーは、自分にとっての苦労の象徴として、
スポーツをやっていたとき、重要な大会の前に突然スランプに陥って、
今までできていたことが突然できなくなり、とても苦しかったという
体験を紹介してくれました。
「苦労」というお題を受けて、ある人は「『苦労は買ってでもしろ』は嘘だと思う。
やりたくないことでの苦労はしないに越したことはない」と主張。
そして「買ってでもした方がいい苦労は、自分がやりたいことのときだけ。
でも、自分がやりたいことなら大変でも苦労とは感じないはずだ」とも。
さらに、別の人は「(ネタプロバイダーと同様に)
自分も今、対処法がわからなくて苦労していることがあるのだけれど、
その過程で自分が成長していると思えるので、苦労と呼ぶのは違うかな」と。
その後、私にも発言の番が回ってきました。
悩む、、、苦労って何だろう?
大変だったことはたくさんあるけど、それって苦労だったのかな?
たとえばリーマンショックの時、大変だったけれど、あれを苦労と呼ぶのかな?
なんか苦労って言葉はしっくり来ないな、、、
心の中でそんなことを思ったので、それをそのまま口にしました。
そしたらある人が「小野さんは物事を苦労って思わない方なんじゃないですか」と。
そうかもね、と妙に納得。
苦労という言葉を身に纏って生きていきたくはないなと
思っているような気がします。
たかだか二文字の「苦労」という言葉を深掘りしてみたら、
人それぞれの思いが浮かび上がってきました。
この回は「苦労」がキーワードでしたが、
その前の回は先ほど書いたように「尊敬」がキーワードでした。
その回で面白かったのは、「尊敬」という言葉に対して
人それぞれ重みが違うということがわかったことです。
ある人は「尊敬する=神のような存在」でした。
別のある人は「尊敬する=ちょっとした気づきを与えてくれる存在」でした。
「尊敬」という言葉の解釈が、それぞれに違っていて、
言葉の重みも違っているんだね、、、ということが共有できました。
さあ、ここから何を学ぶべきなのでしょうね。
私が思うことは、
辞書的な共通認識は相当にアバウトだと思うべきだということでした。
たった一つの単語に対して、
人は体験から自分の辞書を自分の中に作っているので、
辞書の中身は実は同じではないと理解しておく必要があるということです。
つまり「苦労」も「尊敬」も他の単語もその人なりの意味付けがあるので、
辞書的な意味をもって「当然こういう認識のはず」と思い込むのは
相当に危険だと知っておく必要があります。
ちょっとした言葉でも共通認識はない...。
まずはその前提でコミュニケーションする、
そんな姿勢が大切だと痛感しています。
今週も良い1週間をお過ごしくださ〜い!



