超一流の人のスゴさとは?〜落合博満氏の「采配」を読んで
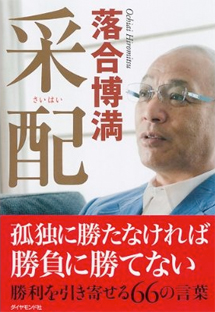 落合博満・前中日ドラゴンズ監督の著書「采配」を読みました。現役時代に三冠王を三回、8年間の監督時代には優勝4回、日本一1回という偉業を成し遂げたことは、ワタシが紹介するまでもなく、皆さんもご存知のことでしょう。そんな落合氏が説くのは「勝負の方程式」はあっても、「勝利の方程式」などないということ。そして、言外にチームのプロ意識の総和がチーム力になる、だからこそ徹底的にプロ意識を育てた、と語っているように思いました。全体的には、ダイヤモンド社から出すだけあって、ビジネス書であり、一種の自己啓発本という印象でした。
落合博満・前中日ドラゴンズ監督の著書「采配」を読みました。現役時代に三冠王を三回、8年間の監督時代には優勝4回、日本一1回という偉業を成し遂げたことは、ワタシが紹介するまでもなく、皆さんもご存知のことでしょう。そんな落合氏が説くのは「勝負の方程式」はあっても、「勝利の方程式」などないということ。そして、言外にチームのプロ意識の総和がチーム力になる、だからこそ徹底的にプロ意識を育てた、と語っているように思いました。全体的には、ダイヤモンド社から出すだけあって、ビジネス書であり、一種の自己啓発本という印象でした。
では、いったい氏の考えるプロ意識というのは、どのようなものなのか、残念ながら、ずばり一言で語っている文章は見当たりませんでしたが、自分で自分のビジョンを描き、何らかの存在感を作り上げるために、自らを成長させようとすることだ…、ワタシはそのように解釈しました。
印象的だったのは、「向上心」を抱く程度ではダメだとして、「野心」を持つことが必要だと語っていた点。人は誰でも年々成長していると実感したいと思っていますが、「日本で一番の○○になる」「社内で一番○○に強いと言われる人になる」などと考えている人は、多くありません。でも、自分でそう思わないことには、なれるものもなれません。その当たり前のことを、改めて認識させてくれました。
氏は、人は誰でも3つの戦う段階があるとし、「自分」「相手」「数字」の順で戦いに直面するとしています。自分と戦う段階で、他責であったり、結果が出ない試合の後に「気持ちを切り替えよう」と考えるだけで、自己分析をしなかったりするようでは、自分との戦いには勝てないと語っていたのも印象的でした。また、数字との戦いで勝つには、『「達成するのは不可能ではないか」という目標を設定すること』が不可欠だと言い、打率3割を達成する選手は3割3分を目指すが、3割を目指す選手は3割に到達することはないとも語っています。
総じて共感することの多い内容でしたが、優れた指導者はこのような意識をメンバーに植え付け、その成長を支援するものだという考えに、賛同はできても、実践は簡単ではないと感じたのも事実です。それでも、超一流と呼ばれている人とそうでない人の違いは、とても真っ当なことをコツコツと地道に継続できるかどうかだけだと思えたので、できることから「真似」してみようと思いました。
模倣とはまさに、一流選手になるための第一歩なのだ。
落合博満著「采配」より
「ファシリテーション」をご存知ですか?
ファシリテーションという言葉をご存知ですか。最近、そんなご依頼やご相談が増えています。問題解決するための議論や合意を形成するための議論を設計し、ナビゲーションしていくような役割の人をファシリテーターと言いますが、私たちはファシリテーターとしてその会議に参加します。
これまで会議といえば、決まった人ばかり発言する、議長役のリーダーの腹の中には結論があるのでは?と参加者が思っている…などの問題があって、そのため結論が出ても、今ひとつ他人事になって実行されないということが起きがちでした。
ファシリテーターはプロジェクトのリーダーではなく、参加者が平等に自分の意見を言えるように、中立的な立場で参加し、効率的かつ最大の成果が出るよう議論の設計と意見の交通整理を行います。ファシリテーターが議論を設計する以上、議論のテーマには精通している必要があり、私たちに依頼されるのは、広報やブランディングといったテーマです。
一般的に、ファシリテーターは、次の3つを担う必要があると言われています。
1)何回の会議で、何を議論するのかを設計する「プロセスデザイン」
2)その会議の参加者がロジカルに考え、見える化してわかりやすく進めるための「プロセスマネジメント」
3)意見が分かれてしまったときにどうやって着地させるかという「コンフリクトマネジメント」
ワタシにとって、「プロセスデザイン」や「プロセスマネジメント」的なことは、社内の企画会議でも行っていることなので、簡単だとは言いませんが、特別なことでもありません。が、しかし…。参加者全員が、ロジカルに話し合うことに慣れているとは限りません。参加者が混乱しないように進めるには、一工夫も二工夫も必要です。特に、話の文脈がわからないと、誰でも混乱しますし、議論のお題の意味がわからないと、意見を言うにも不安になり、モチベーションが下がるものだと思います。
ですから、スキルも大切ですが、一番大切なことは、参加者の気持ちを考えること。先週金曜日に行ったファシリテーションは、「ブランディング」がテーマで、その第1回でしたが、「ブランディング」という言葉を含め、カタカナは極力使わないという方針で臨みました。
そして、もう1点、大切だと思うことは、ファシリテーターであるワタシ自身が楽しんでいることです。眉間にシワを寄せている人が進行していたのでは、会議が楽しいはずがありません。3時間半の会議でしたが、参加された皆さんの意識も高く、ワタシ自身も楽しめたので、まずまずのスタートだったと思います。
3カ月後に、参加者自らが出した答えに納得でき、気持ちが一つになれたらいいですね。これからが楽しみです。
裏ニーズは何ですか?
当社では、現在「サイレントセールス」をコンセプトに内向型営業マン向け研修や本の執筆を行っている渡瀬謙さんにファシリテーション/コンサルテーションをお願いし、月に1〜2回、ディスカッションを行っています。目的は、5秒で自社を語る言葉のあり方や、わかりやすく自社を紹介するツールのあり方を整理するためです。
渡瀬さんのご専門は「営業」なのですが、当社が取り組もうとしているのは「ブランディング」や「事業の再定義」です。それでもお願いしたいと思ったのは、渡瀬さんご自身の活動がエッジが利いていてブランディングされていること、物事の掘り下げ方が私たちの企業文化にあっていると感じられたこと、ワタシ自身と相性が良さそうに思えたことなどが、主な理由です。すでに数回にわたってミーティングを開いていますが、木曜日に行ったのは、ディスカッションではなく、営業研修でした。
商談は4つのプロセスで成り立っているという話や、表ニーズだけでなく、裏ニーズを知る「ヒアリング」が大切という話は、コミュニケーションを体系立てて考える上でとても参考になりました。
さて、裏ニーズを探るというのは、商談に限らず、あらゆる場面で重要だと思います。しかし、これは簡単なようで簡単ではありません。なぜなら、相手の潜在意識を探ることだからです。クルマの商談でいえば、「7人乗りのステップワゴンがほしい」というのが表ニーズだとすれば、その背景を知るのが裏ニーズ。当社に寄せられる「社内報を作りたい」というお問い合わせも、それ自体は表ニーズであり、実はその背景に裏ニーズがあるのです。
ところが、社内報を作りたいと思った背景を普通に尋ねても、「ビジョンを共有し、ベクトルを合わせたい」「部門間コミュニケーションを活性化したい」という紋切り型の答えしか返ってこないこともあります。それだけですと、いったい社内で何が起きていて、どのような現象を問題だと感じているのかまではわかりません。問題を感じているからこそ、「社内報が役に立つのではないか」と考えているはずなのですが、具体的な現象の説明よりも、「どんな社内報を作りたい」という説明に終始してしまうケースや、なぜ役に立つと思ったのか、何が原因だと考えているのか、そこまでは説明していただけないケースが多いと感じます。おそらく、「社内報があれば、何か解決できるのではないか」「やらないより、やった方がいいのではないか」という意識だからなのかもしれません。そこをどう引き出していくかが、ヒアリングの技術であるし、ワタシたちが取り組むべきテーマだと思いました。
渡瀬さんには当社のファシリテーションをお願いしましたが、今週からワタシたちがファシリテーションする側になるクライアント案件がスタートします。ファシリテーションというのは、議論のプロセスや参加意識をマネジメントする技術です。渡瀬さんがファシリテーションしてくださるミーティングは毎回参加するのが楽しみでしょうがないのですが、ワタシも参加者をそんな気持ちにする会議にできたらいいなと思います。今週も、がんばりましょう!
日経ビジネス「社長の発信力ランキング」を読んで
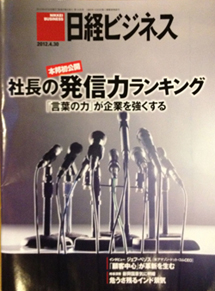 「日経ビジネス」(4月30日号)で「社長の発信力ランキング〜『言葉の力』が企業を強くする」という特集が組まれていました。各社の社長がマスコミやブログなどに登場した回数を調査し、その内容を指数化してランク付けしたようです。ちなみに総合ベスト3は:
「日経ビジネス」(4月30日号)で「社長の発信力ランキング〜『言葉の力』が企業を強くする」という特集が組まれていました。各社の社長がマスコミやブログなどに登場した回数を調査し、その内容を指数化してランク付けしたようです。ちなみに総合ベスト3は:
1位:ソフトバンク社長/孫正義氏
2位:ファーストリテイリング会長兼社長/柳井正氏
3位:日本銀行総裁/白川方明氏
誌面に登場していた著名でカリスマ性のある経営者が広報というものをどのように捉えているのかと、大変興味深く読みました。と、同時に、今回の特集はあくまで外部広報に関するものであり、社内向けの情報発信力は調査の対象外でしたが、仮に社内広報で同じような調査を行ったとしても、概ね似たような結果になったのではないかと思いました。
一般に自社がどれだけマスコミに登場したかについて、その露出度を広告換算しようとする考え方もあり、掲載媒体別に成果報酬を取り決めているPRコンサルタントも存在していますが、本来、自社の考え方に対して、理解を得るための活動が広報の本質だと思います。それをわかっている経営者は、理解を得るためにコミュニケーションを重んじており、その一環として対外広報を位置づけているのではないでしょうか。
現にファーストリテイリングの柳井さんの記事に、次のような件がありました。以下、引用です。
その姿勢は社内外を問わず一貫している。そして、相手が納得するまで何度でも同じ事を発信し続ける。「言う」ことと、「伝わる」ことの違いを理解しているからだ。
「自分が言いたいことを言って終わりでは何の意味もない。相手に納得してもらえない限り、伝えたことにはなりません。
だから僕は、相手が納得して動くまで、同じことを何回でも言うんですよ。1回言って分かるような人間は、100%いない。だから伝わるまで、100回でも1000回でも言い続ける」
まさに、経営コミュニケーションのお手本です。
もう一人、第1位だった孫さんのインタビューも今更ながらにおもしろかった。本音で語り、批判も正面から受け止めることで「裸の王様にならずに済む」し、「ボコボコにされずに済む」と考えているようです。それを読んで、心理学で言われる「ジョハリの窓」を思い出しました。
「ジョハリの窓」では、他の人には見えているのに、自分では気づいていない自己(盲目の窓)や、自分では気づいているけれど、他の人には見せてない自己(隠された窓)を小さくしていくことで、自己成長もできれば、コミュニケーションも円滑になると言われています。さらに、「盲目の窓」を小さくするには、フィードバックを得ることが重要で、「隠された窓」を小さくするには、自己開示が重要なのだそうですが、まさにその両方を積極的に行っているのが孫さんなのですね。
社内・社外にかかわらず、また社長・社員など立場の違いにかかわらず、自分をわかってもらう努力/相手をわかろうとする努力は大切ですね。「『言葉の力』が企業を強くする」というサブタイトルは私の信条でもあります。『言葉の力』でクライアント支援をしていきたいと改めて思ったと同時に、ワタシ自身も自社に向けたコミュニケーションを大切にしなければ…。そんな自戒の念とパッションが同時に湧いてきた記事でした。
「理念浸透」で大切なことは何でしょう?
 こんにちは。
こんにちは。
ゴールデンウィークの谷間ですね。当社も休暇を取っている人が多く、私も明日は休暇をいただき、蓼科に行ってきます。
さて、本日発行の「月刊近代中小企業」(発行:中小企業経営研究会)の「理念浸透力」特集に原稿を執筆しました。題して「社員の気持ちに応えた経営理念〜ブランディング視点で理念浸透を」です。
「理念浸透力」とは何でしょうね? 少なくても、一朝一夕で達成できるものではありませんし、社長が理念を重んじていなければ、浸透することはありえないと思います。今回の執筆では、私自身が経営者として自社の理念を巡って苦労した経験やクライアント案件での体験をご紹介しながら、社内に向けた理念浸透で大切な事柄について紹介しました。
「近代中小企業」は年間購読誌で、経営者や経営幹部が即実践したくなるようなコンテンツを重んじた誌面づくりで定評があります。その他の執筆者の理念浸透に関する記事もおもしろそうですので、ご覧になる機会があったら、読んでみてください。
記事のpdfはこちら



