常識という「刷り込み」のコワさ
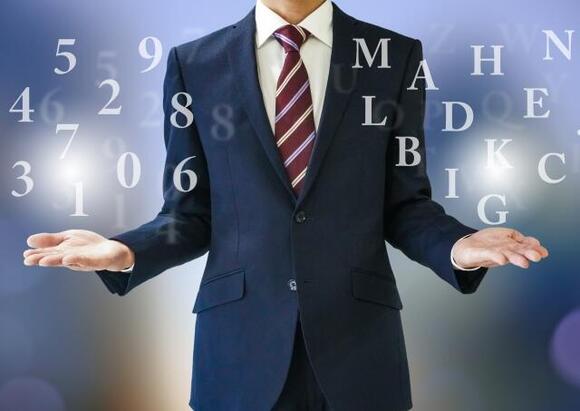
ヤフー知恵袋にこんな書き込みがあるのを見つけました。
ーーー
皆さんが常識を疑うことって、どんなことですか?
夏休みの宿題で「常識を疑う」
このお題が私には難しすぎて全然わかりません。
だから普段、
ぜひ、協力お願いします!!
ーーー
「夏休み」と書かれているので、
これを読んで、最初は、「常識を疑う」
愕然としたものの、よくよく考えてみると、
むしろその感覚の方が健全なのかもしれないなと思い直しました。
というのは、「常識を疑う」
たとえば今週、私の中で1つの常識が覆されました。
何だと思いますか?
実は、私、日本という国は「極東アジアの小さな国」
国土面積が小さい国という意味です。ところが...
日本は意外にも大きかったのです。
知ったきっかけは、「The True Size.com」というサイトを訪れたことでした。
これは、
実際の面積を体感できるサイトです。
たとえば、「Japan」で検索してみてください。
日本がアクティブになり、
日本の国土サイズが感覚的にわかります。
私が最初に驚いたのは、
日本がイギリスやイタリアよりだいぶ大きいのはもちろん、
ドイツよりも大きそうだったこと。
えー!びっくり!という感じでした。
で、さらに調べてみると...
日本の国土面積は377,945,210平方kmです。
東南アジアの中では、
中国 9,600,000
インドネシア 1,910,931
タイ 513,140
に次いで第4位。(単位はいずれも平方kmです)
それどころか、ヨーロッパのこれらの国々よりも大きい。
イギリス 242,495
イタリア 302,068
ノルウェー 323,772
ドイツ 357,581
フィンランド 336,884
ヨーロッパの国は国土面積が狭い国が多いんですね。
では、なぜ私は(もしかしたら、皆さんも)
日本はちっぽけな国だと思い込んでいたのでしょうか?
ここからは推測です。理由は2つあります。
その1。
この地図の特徴は高緯度に向かうにつれ距離や面積が拡大されるこ
日本は、赤道直下ではないにしろ、中緯度にあるので、
地図上の形は実際よりも小さく表示されます。
それが「ちっぽけ日本」
その2。考えられるもう一つの原因は、「日本は小さい島国」
幕末に国内で定着したこと。
どこからどうして定着したのかはわかりませんが、
黒船到来で軍事力のギャップをまざまざと認識させられ、
以来、自国を卑下する意味もあり、
つまり黒船あたりから、「日本は小さい島国」
そのような言語的表現は定着し、
そして、もっともアタマにくることは、(←これ、自分にです)
「日本は小さい島国」という気持ちで生きていなければ、
もっと気持ちも大きくなったような気がすること!
今回、改めて常識は疑わないと、見えてくるものも、
来週は6月も最終週。今年も半分が終わってしまいますね。
暑さに負けずに元気に過ごしましょう!
脱「ついて型」のススメ

例えば、「~について取り上げよう」
あるいは、会議のアジェンダに書かれた「~について」の項目。
日常業務のいろいろなところで、
「~について」という言葉を使って会話がされています。
会議もコンテンツの一種であると考えた場合、
コンテンツの質はコンテンツを作る人のイニシアチブにかかってき
多くの物事で「~について」
本当にそれでいいのかな?とも思います。
というのは、1つの仮説として、この「ついて型」アプローチが、
アウトプットの質や生産性、
そこで、今日は、私が「ついて型」
その「ついて型」にはどんな問題があるのか、
問題があるなら、どうしたらいいのか、考えてみたいと思います。
実際、「~について取り上げよう」
コンテンツは作れますし、会議のアジェンダに「~について」
それなりに会議は成立してしまうものです。
それらのコンテンツでは何かしら言葉的なものが成果物になるので
「はい、これが本日のアウトプットです」
でも、
会議の成果に対し、参加者の納得感はあるでしょうか?
もう一度、たとえば「企画会議」。
当社が提供している企画力養成講座では、
ついて型でもコンテンツは作れるが、
とお伝えしています。
ーーーーーーーーー
~について取り上げよう
↓
だとしたら、誰に出てもらおうかな?
↓
どんなことを聞こうかな?
↓
聞いた話をうまく原稿にまとめなきゃ...
ーーーーーーーーー
確かに、この流れでもコンテンツらしきものは完成しますよね。
ですが、このアプローチはただ「聞いた話をまとめる」
「~について取り上げよう」から始まる企画プロセスでは、
大抵の場合、何をメッセージとするのか、とか、
読み終わった時に、
なので「~について取り上げよう」
「伝えたいこと→伝わること」に執着するなら、
気をつけないといけないなと思います。
会議のあり方もそうです。
日常的に行われる会議こそ、質や生産性、
でも、もしその会議のリーダーがアジェンダを考えるときに、
「1.○○について 2.○○について」というような感じで出していたとします。
そうしたら、
誰にもわかりませんよね。
もちろん、アジェンダと会議設計は別物ですから、
場のリーダーの頭の中に会議設計があるなら、
アジェンダ自体は「1.○○について 2.○○について」で済む場合もあります。
でも、私が一番おすすめしたいことは何かというと、
疑問文でアジェンダを組み立てることです。
(これは企画を立てる時もほぼ同じです)
ところが、
つまり、何を議論する必要があるのか、
場の作り手が「問い」
ですが、慣れていないと、
え? ほんと?と思うかもしれませんが、
考える必要のあることを漏れなく「問い」の形で出せる人は
実はそれほど多くないと思います。
私自身も「問いを立てる」を意識していますが、「漏れなく」
はなはだ心許ないです。
なので、「疑問文として書いてみる」
さて、今年もあっというまに6月。
終われば2024年も半分過ぎてしまいます。トホホ...
と、一瞬背中が丸まってしまいましたが、
その前に、今週を乗り切らないとですね!



