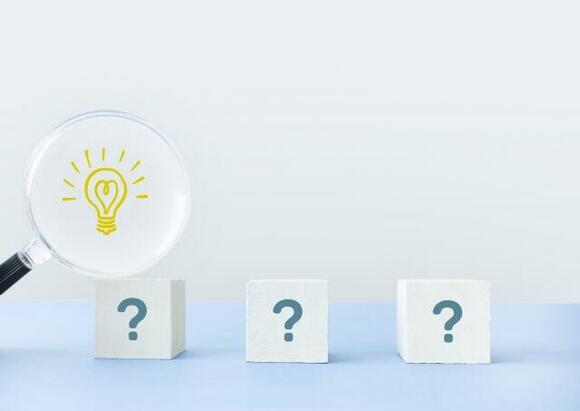Whyは最高の思考エンジン

1カ月ほど前に「仏教」と「日本酒」
観光に行けば、単なる寺巡りをするものの、
仏教や仏像への知識は乏しく、ただ「へ~」「ほ~」
でも、今回の旅では、ずっと疑問に思っていたことを書き出して、
入念に予習をして行きました。
たとえば、釈迦が仏像になるのはわかるけど、
なぜあんなにもたくさんの種類があるのか?
○○如来と○○菩薩はどう違うのか?
不動明王とか、帝釈天も仏なのか?など。
予習ノートは一緒に行った仲間にも大好評でした。
人というのは興味があることには「Why」が出てくるし、
そうするとInputにも身が入る。
「Why」は最高の思考エンジンだと痛感しました。
しかし、
多くの人は質問することを恐れているのではないか、と
4月7日のメルマガで書きましたが、
「こんなことを聞いたらアホと思われる」
「みんなの時間を奪っていると思われる」
疑問を発することを難しくしているように思います。
上司と部下の関係も然り。
「なぜ、これをするのか」と問う部下よりも、
「承知しました」と答える部下の方がラクだと思っている上司も
少なくない気がします。
私自身、若いときにこんな体験をしました。
当時パブリシティ業務を担う部署に異動になったばかり。
外出時の電車の中で、私は上司にたくさん質問しました。
会社に戻った時に言われたのは、「小野さんといると疲れる」
20代前半。正直、傷つきました!
まあ、「なぜ、なぜ、なぜ」
頭でっかちにならずにやってみなさいと言いたかったのかもしれま
今、歳も取り、自分が上司という立場になって思うのは、
やっぱり「なぜ」
成長が早いだけでなく、
どういうことでしょう?
「なぜ」と考えることは、原因や理由、
一方、「なぜ」と考えないということは、
言われたことや今ある情報をそのまま受け入れて対処することです
すると、今回はこうやるという記憶だけが残る。
こういう目的の場合はこうするというのが頭に残らない。
その結果、応用が効かなくなります。
自立して仕事ができるようになるというのは、
応用で対応できることが増えるということでもあるので、
「なぜ」と考えることで応用力がつき、
ところで、ネットの書き込みを見ていると、
疑問が湧いてこない、質問は?と聞かれると困る...
と悩んでいる人も多いようです。
若いときは、
そんな悩みも不思議ではありません。
また、質問をしたときに、親や先生、上司などから
否定的な反応をされた経験があると、
疑問を表明するのは良くないこと、
嫌な思いをしないためには表明しない方が良い、
と刷り込まれてしまうのかもしれません。
疑問を聞くとき(質問を受けるとき)は、
自分の態度が相手に悪い影響を与えないように気をつけたいもので
そして、興味がないと疑問も湧かないのは本当でしょうけれど、
仕事では興味の有無に関わらず、
私自身は、「なぜ~?」「~とは?」「どうしたら~?」の
3つの疑問文だけで思考の7割ぐらいをカバーしているような気が
本質的云々なんて難しい話ではなく、
子どものように素直に疑問を口にすることが大切のではないでしょ
ゴールデンウィークがすぐそこまでやってきました。
素敵な連休をお過ごしください。
「質問」はかっこいい
今週、
何がかっこいいかというと、ミーティング終盤での「質問」が、
どんなミーティングもアジェンダに添って説明や議論が行われたあ
収束段階では疑問点をクリアにしたり、宿題を明確にしたり...
その段階は次のアクションに向けて
理解レベルを一致させる段階でもあるわけですが、
仮にその場がヒアリング/オリエンテーションである場合、
大抵は説明を聞いた側が理解したことについて意思表示します。
その時にどういう意思表示をするか、人それぞれなので、
ある人は、「わかりました。問題ありません」と言います。
別のある人は「わかりました。こういうことですね」
さらに、別のある人は「この点はどうなんですか?」と尋ねます。
今回の例では、クリエイティブのジャンプの幅について、
「この点はどうですか?」という問いかけが出され、
その質問の仕方がとても素敵でした。
さて、ここでこんな問いが湧いてきます。
わかりました VS 質問。
一体どっちがかっこいいと思いますか?
なぜこれを疑問として投げかけるかというと、、、
人は質問することにどれだけ恐れを抱いているのか、いないのか、
私は知りませんが、多くの人は質問することよりも、
わかりましたと言うことの方が良い選択だと思っている気がするか
でも、もし私が説明する側にいて、
「わかりました、問題ありません」とか
「わかりました、OKです」という反応は、
パッと見は安心のような感じですが、
コミュニケーションのキメが荒いように感じてしまうかもしれませ
「本当にわかってくれたの? 大丈夫?」と。
なぜかといえば、そんなに簡単に他人の気持ちや考えなんて
わかるわけがないという前提に立っているからです。
(いや、もちろん、本当にわかってくれての「わかりました」
だからこそ私は、質問が鋭い人を見ると、目が星になりがち(笑)
かっこいいな~と。
では、反対に質問が出ない場では、何が起きているのでしょうか?
質問が出ない主な理由はいくつか考えられますが、
1つは「こんなことを言ったらおかしいと思われるのでは?」
という恐れがあって、そのために質問しないというケース。
もう1つは、そもそも疑問が浮かんでこないケースです。
前者は、心理的安全性を担保できるかが重要で、
これだけでもメルマガ1本書けますが、
今回は後者の方に注目してみました。
なぜ、
これは、なぜ疑問が湧くのか?を考えてみると、理解できます。
人は、自分の想像や直感に反することが起きた時/
疑問が湧いてきます。「え? なんで?」と。
また、人は、
「もし、こうして、ああして、こうなったら、
だから、
ある話を聞いた時、「That's all、ピリオド」で、
それ以上のことを想像しなければ、疑問の湧きようがありません。
なので、「わかりました」で終わってしまうことは、
もしかしたら、聞いたことを理解したことに間違いはないけれど、
それ以上を想像しての理解には至っていないと考えることもできま
ってことは、キーワードは「想像力」ですね。
おや? どこからか「ボーっと生きてんじゃねーよ」という
チコちゃんのお叱りが聞こえてきた(笑)
「いまさら当たり前のことを言ってんじゃねーよ」とも。
はい、ごめんなさーい!
さて、、、
ウクライナ情勢、毎日気にして見ています。
在日ウクライナ人が家族を呼び寄せたくても、
言葉の支援を含む就業の支援や、
断念したケースをニュースで見ました。
自分に何ができるのかを考えても、寄付ぐらいしか思いつかず、
無力感を感じますが、一刻も早い終結を心から祈ります。
国内経済の行方も心配ですが、まずは一人一人が
今日をしっかりと生きることが案外大事なのだと思います。
まずは、今週を精一杯乗り切りましょう!