協調性って、人と和することではない?

桜がきれいですね~ 今週は4月に突入。
新入社員を迎える組織も多いのではないでしょうか。
直近のデータではありませんが、
経団連調査(2018年11月発表)によると、
企業が新卒社員の選考で重視する要素のランキングは
「コミュニケーション能力」が8割で第1位。
2位が「主体性」、3位が「チャレンジ精神」、4位が「協調性」と続きます。
この傾向自体には特に違和感を覚えませんが、
大切なことは、それぞれの言葉をどう定義づけているかですよね。
各社間でも、企業と求職者の間でも幅がありそうな感じがするのが、
「コミュニケーション能力」と「協調性」という言葉です。
そこで、今日はそのうちの「協調性」というものについて考えてみたいと思います。
私が、生まれて初めて「協調性」なる言葉と出会ったのは、
小学校1年生の時でした。
通信簿の通信欄に「協調性があって大変良い」というようなコメントが書かれてあり、
文字は読めないし、これはどういう意味なのか、母に尋ねました。
その時、母がどう答えたのか、うる覚えではありますが、
「お友だちと仲良くやって行けている、ということよ」というように
説明されて納得したような記憶があります。
この機会に改めて「協調性」を辞書で調べてみました。
デジタル大辞泉(小学館)によると、
「協調」とは、「(スル)互いに協力し合うこと。
特に、利害や立場などの異なるものどうしが協力し合うこと。」だそう。
そのような性質を持っている人が、協調性のある人と理解して良さそうです。
ふむふむ。母の説明とはちょっと違いますね。
私自身、調べてみて、そういうニュアンスなんだと知ったのですが、
もしかしたら、割と多くの人が「協調性」の意味を、
私の母の説明のように「人と和する」「人に同調する」「人と足並みを揃える」
と捉えているかもしれません。
では、企業が求める「協調性」のある人材というのは、どんな人材なのでしょう?
特に、これといった確証は見つかりませんでしたが、
デジタル大辞泉の意味に近いのではないでしょうか?
利害や立場が違っても、議論して、収束点を見つけ出し、
最終的には協力し合っていける人材。
つまり、馴れ合いの和ではなく、
切磋琢磨による和をもたらす人材と言えるかもしれません。
仮定に仮定を重ねるのもなんですが(笑
だとしたら、採用面接時や入社後などに、
人と調和して和を乱さないことをアピールをしても、
ダメだということですよね。
さて、「協調性」が重んじられながら、その意味に誤解もあるとしたら、
心配なのは、社会の中で次のような連鎖が起きてしまっているのではないか、
ということです。
「協調性があるのはいいこと」
↓
「和を大切にして、波風立てないことがいいこと」
↓
「空気を読んで、意見を言う/言わないを判断することがいいこと」
↓
「軽々に意見を言うと空気を読まない人と評価されるかもしれないので、
意見を言って損しないようにすることがいいこと」
これはあくまで仮説ですが、あなたはどう思いますか?
実際、発言することに抵抗がある人はどのくらいいるのでしょうか?
2019年、ニュースサイト「しらべぇ」が
相手を選ばず意見をはっきり言える人の割合を調査しています。
それによると、全体の31.2%が
「相手が誰であろうと自分の意見をはっきりと言う」と回答したそうです。
逆に言うと、7割近い人は、はっきり言わないということですね。
意見は意思表示のひとつだと考えると、
グローバル化が進んでいく中で、意見を言わない人が多い状況は少々心配です。
世代別男女別で見た場合、まず男性は?
「はっきりと言う」割合が高いのは10代で、42.0%。
反対に低いのは、20代で、26.9%です。
10代と20代の間の、このギャップの意味を知りたいものです。
女性で「はっきりと言う」割合が高いのは60代で、40.3%。
低いのは30代で、19.9%です。
30代の女性たちはアッチにもコッチにも気を使っているのでしょうか?
職場で「意見」「発言」を世代や立場に関係なく、
言って良い/悪いは、まさに暗黙知。
企業の価値観と、それによって生まれているカルチャーによりますね。
協調性について、あるいは、
「相手が誰であろうと自分の意見をはっきりと言う」ことについて、
あなたはどう思いますか?
むずかしいことをやさしく
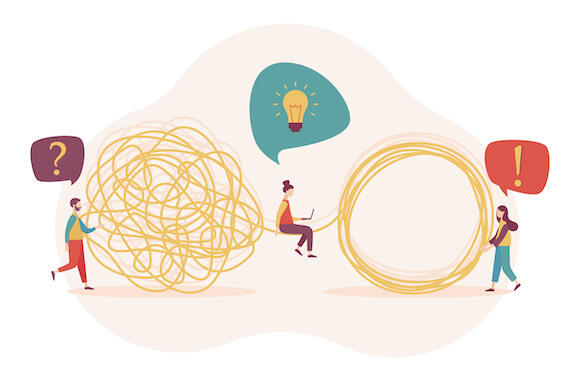
井上ひさしさんの有名な言葉に、こんな言葉があります。
ーーーーー
「むずかしいことをやさしく、
やさしいことをふかく、
ふかいことをおもしろく、
おもしろいことをまじめに、
まじめなことをゆかいに、
そしてゆかいなことはあくまでゆかいに」
ーーーーー
90歳で亡くなった作家の半藤一利さんの遺稿に引用されていたことから、
私はこの言葉の存在を知りました。
難しいことをやさしく書く。
やさしいことを深く書く。
調べてみても、井上さんの言葉には動詞がないようですが、
半藤さんは「書く」と解釈したようです。
どの1行も重みがあって、考えさせられますが、
特に書き出しの1行目に惹きつけられます。
やさしく書くとはどういうことなのでしょう?
「易しい」「優しい」の辞書的な意味から考えると...
「易しい」=理解や習得がしやすい。単純でわかりやすい。平易である。
「優しい」=他人に対して思いやりがあり、情がこまやかである。
文章の話だと思うと、「易しい」の意味の方だと思ってしまいますが、
読み手に対して思いやりのある文章という意味も含んでいるのかもしれません。
ここからは、私の主観になりますが、
第一に、やさしく書くということは、単に難しい言葉を使わないとか、
噛み砕いて書くということ以外に、
「核心を言い切って書く」ということがあるように思います。
私自身もよく陥るのですが、わかりやすく書こうとして、
たくさんのことを書いてしまい、
「これじゃ、何が言いたいんだかわからないな...」と思うこともしばしば。
ダラダラと書いているということは、
結局考えがまとまっていないことの表れなんですよねー
第二に大切なことは、やっぱり「優しい」の字の方ですね。
書くということは、自分の頭の中のことを赤の他人に知ってもらうということです。
そんなものは、相手にとっては「異物」でしかないわけだから、
「異物」に接している相手の気持ちや出てくる疑問をどれだけ想像できたかで、
文章の優しさのレベルが変わるんだろうと思います。
さて、「難しいことはやさしく」「井上ひさし」で検索していたら、
立教大学 経営学部の教授・中原淳先生のブログにたどり着きました。
http://www.nakahara-lab.net/blog/archive/12409
「NHK 100分 de 名著〜ブルデュー『ディスタンクシオン』 」を紹介する内容で、
以下、その本からの引用のようです。
ーーーーー
フランスの学術界で認められるためには、わざと「わからないように書くこと」が重要だ。
(フランスの哲学者の)ミシェル・フーコーは、
自分の文章の「10%」は「わからないように書いている」と述懐している。
一方、(フランスの社会学者の)ピエール・ブルデューは、
「10%」では不足であり、「20%」はわからないように書く
ーーーーー
ほー。わざと人にわからないように難解に書くことに価値があるとは、
理解に苦しみますね(笑)
でも、ふとこんなことを思い出しました。
たまに専門用語を躊躇なく使いながら話す人を見かけますが、
それと同じなのかもしれません。
でも、それこそ「優しさ」を感じませんね。
私自身も無意識にカタカナを使っていることがあるので、
偉そうなことは言えませんが、
ん? 知識をひけらかしたいのかな?と思ってしまうと、
ちょっと辟易するし、そういう人に限って、
この人、自分の話していることを自分で理解しているのかな?
と思うこともあります。
知識ベースでマウンティングしているだけというか、
ただのポジショントークだったりして。。。
本当に素敵な人は、重要なことをシンプルに、
わかりやすく話したり、書いたりしてくれる人ですよね。
そして、本当に重要なことは意外にシンプルなのだと思います。
でも、そのシンプルな本質をつかむのには深く考えて悩まなくてはたどり着けない。
だからこそ、シンプルな言葉には価値があるのかもしれませんね。
あら、またダラダラと書いちゃった...失礼!
花粉が気になる季節ですが、、、素敵な1週間でありますように!



