「書く」といいことあるのかな?
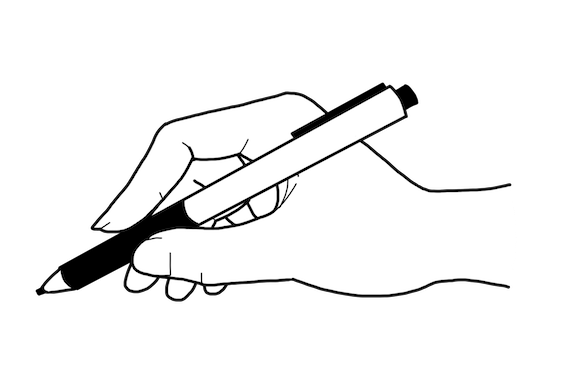
あなたは、どんな時に「書く」という行動を取っていますか?
パッと頭に浮かぶのは、メールや報告書、パワポ資料などでしょうか。
手書きに限った場合は「打ち合わせでメモを取る」かもしれません。
では、それ以外ではどんな時にどんな目的で書いていますか?
今日は、仕事でメモを取る以外のシーンでの「書く」について考えます。
人はどんな目的で書いているか、リストアップしてみました。
・しなくてはならないことを忘れないため
・したことを記録するため
・思いついたアイデアなどを忘れないため
・アイデアを出すため
・なるほどと思った知識を読み返せるようにするため
・感情を鎮めるため
・自分を振り返るため
・計画するため
・自分の考えを整理するため etc.
まだまだあるかもしれません。
また最近は紙に書くというより、
スマホに打つという人が多いような気がします。
人が、どんな時に書くのかをリスト化すると、
上の例のようにいろいろあることがわかりますが、
実は書いている人はそれほど多くない気がします。
さらに、「アイデアを出す」「考えを整理する」という目的で書いている人は、
なおさら少ないのではないでしょうか。
いや、すみません、根拠はありません。
実際、あなたやあなたの周りの方はどうですか?
さて、アイデアを出すことと、考えを整理すること。
前者は思考を発散し、後者は思考を収束させていくので、
ある意味、180度反対の行為です。
それなのに、いずれも「書く」ことでスムーズに出来たりします。
まず、「アイデア」を出すことと「書く」ことはどう関わっているのか、
考えてみましょう。
アイデアを出すための代表的なアプローチとして、
ソクラテスの時代から使われているのが「連想」です。
一つの事柄から、切り口を変えてたくさん連想した言葉を出します。
似たもの、対照的なもの、共通性のあるもの、因果関係にあるもの...
よくマインドマップが使われたりしますよね。
また1つの質問から複数の答えを出す
マンダラートというツールも使われたりします。
最近はアプリを使う人もいますね。
いずれも、思考を「発散」させるために、
たくさん書くのがポイントです。
アイデアというのは異なる要素の組み合わせから生まれるので、
要素が多い方が出てくるアイデアに幅が出ます。
それなのに、もし書かなかったらどうなるでしょう?
たくさんの要素が出てきたとしても、次から次へと忘れてしまいますよね。
脳はそんなにたくさんのことを一度に覚えられないからです。
第一、頭の中だけでやろうとすると、
「たくさん出すぞ!」というスイッチが入りません。
また要素を組み合わせるという段階で、
視覚的に見えている方が組み合わせもしやすいですよね。
だから、アイデアを出す時に、たくさん書くことが有効なのだと思います。
では、「考えを整理する」ことと、「書く」ことは
どう関係しているのでしょうか。
まず、考えを整理するためには、何を書くと良いのでしょうか?
これは、人にもよるかもしれませんね。
私の場合は、考え出す前に、まず「問い」を書きます。
考えるべきことは何かを先に考えるということです。
そして、考えられる答えは1つでない場合もありますが、
それらもまた書きます。
テーマによって、「問い」は違ってきますが、
よく出てくる「問い」もあります。
「ここで言う○○とは何か?」と
「どうなったらうれしいか?」です。
「考えを整理する」ために「書く」ことが有効なのは、
「問い」が見えるようになるからかもしれません。
人間は気まぐれなので、考えはあっちに行ったり、
こっちに行ったりしがちです。
「問い」を書いておくと、戻り地点があるので、
自分が何を考えていたのかが迷子になりません。
スマホ、ノート、白い紙...
ボールペン、シャーペン、フリクション...
ツールはいろいろありますが、
私が一番好きなのはホワイトボードです。
ディスカッションの時はもちろんですが、
一人で考える時も、なぜかホワイトボードを使うのが好きです。
あなたは、どんな時にどんなことを書きますか?
書くようにしていることはありますか?
11月最終週です。
素敵な1週間をお過ごしください。
言葉を変えよう~「発達障害」という呼称から
NHKでは、今、複数の番組で
「発達障害」を取り上げるプロジェクトが行われています。
「発達障害」への理解を広め、
偏見をなくそうという取り組みのようです。
社会に対し、問題提起しようとするNHKの試みは拍手に値しますね。
一方で、私は、ちょっとした違和感のようなものも感じます。
それは、NHKに対してというよりも、社会の動きに対してでしょうか。
そのザラつき感、どんなことなのか、胸に手を当てて考えてみました。
思ったのは、こういうことです。
「発達障害」という概念で人を一括りにすることに対して、
私は微妙に抵抗感を抱きます。
それに加えて、「障害」という言葉のイメージからか、
「病気」だと受け止めがちですが、
厚生省のホームページには、こう書かれています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
生まれつきの特性で、「病気」とは異なります。
発達障害はいくつかのタイプに分類されており、
自閉症、アスペルガー症候群、注意欠如・多動性障害(ADHD)、
学習障害、チック障害、吃音(症)などが含まれます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
とはいえ、ネットで検索すると、
「病気」だとする専門家もいれば、
「特性」だとする専門家もいます。
どっちだったとしても、
言葉の選び方がイマイチな気がするんですけど...。
ところで、NHKの番組の中で、
「発達障害だとわかってむしろ安心した」という親御さんの声や、
「自分が人に馴染めない理由がそこにあると知って、
もっと早く知っていたなら、気持ちが楽だった」との声を聞きました。
彼らは、人と違うがために、
「努力が足りない」「なぜできないのか」と
人からも責められ、結果自分のことも責めてしまうようです。
そんな状況を知ると、
「発達障害」と名付けることも必要かもしれない
と思えてくるのですが...。
でも、、、
誰でも多かれ少なかれ「人と違う変わったところ」がある。
それが人間だと思います。
私自身は発達障害だと言われたことはありませんが、
他の人から見ると、結構「変わったところ」があると自覚しています。
具体的には、、、
集中するがあまり、他の人は気づけることに、
私だけ気づかないとか、
目から入る情報に弱いのか、
なかなか人の顔が覚えられないとか。
「小野さんほどデコボコの激しい人はいない」
と部下からも言われて来ました(笑)
それでも、生きるのに困るほどではない。
一方で、世の中には、自分の特徴によって
生きるのが苦しいと感じている人たちがいるんですよね。
人との「違い」を社会が
ポジティブに認められるようにするには、
「発達障害」という呼称を変えてはどうかと思います。
たとえば、「ユニーク(unique)」という言葉を生かして、
「UC(unique capability)」「UB(unique brain)」
「US(unique sense)」なんてどうでしょう?
イマイチかしら?
あなたは言葉の問題、どう思いますか?
今週も素敵な1週間でありますように!
PS:
こんな情報をお寄せいただきました。
「脳の個性を才能にかえる 子供の発達障害との向き合い方」(NHK出版、トーマス・アームストロング著、中尾ゆかり訳)は私が発した内容と合致するように感じたので、参考までに紹介したい、と。ありがとうございます! 参考情報として、紹介します(まだ読んでいませんが)。
https://www.amazon.co.jp/dp/4140816082/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_ZZcZDbV7W8E1M



