嫌われ者「ノー」のイメージアップ作戦
一緒にメルマガを書いている阿部が
「スウェーデン式アイデア・ブック」という本を手にしていたので、
貸してもらいました。(フレドリック・ヘレーン著、ダイヤモンド社)
本の帯には「ひらめきが生まれる小さなヒントが満載!」とあり、
短いエッセイ30本で構成された気軽に読める本です。
例えば一番目のエッセイのタイトルは「針を探す」です。
アインシュタインの逸話を盛り込みながら、
答えは一つではないのだから、誰かが問題の解決案を提示した時、
別の方法はないかと聞くよう勧めています。
他人のアイデアを認めない偏屈な人物だと思われたとしても、
もう少し粘ることによって、もっといいアイデアが生まれてくるのだ、と。
そうかと思えば、「『イエス』より『ノー!』」というエッセイでは、
批判がアイデアを磨くとして、
アイデアを思いついた時はむしろ批判してくれる人を探して、
批評を得よと語っています。
アイデアにはタフネスが必要だと言わんばかりです。
この本で、私が面白いなと思ったのは、
「ノー」という概念をポジティブに扱っていることでした。
一般的に、アイデアはポジティブに取り扱う方が
膨らんでいくので良いと言われています。
人は否定されたくないし、
否定はモチベーションを下げるというのが通説です。
研修などでイエスアンド話法を教わったりするのも、
そういう前提があるからではないでしょうか。
ま、これ、ある意味正しいかと思いますが...
でも、その考え方にはちょっとした落とし穴もある、
ということをこの本は気づかせてくれました。
というのは、私たちはついつい「イエス」は善玉で、
「ノー」は悪玉と考えてしまいがちです。
擬人化して例えるなら、
背中を押して応援するのが「イエス」君で、
目の前に立ちはだかり妨害するのが「ノー」君です。
キャラクター的に言えば、
「イエス」はキラキラ輝くヒーローのような存在、
「ノー」はダークサイドの悪者というイメージでしょうか。
しかし、もし私たちが「良いアイデアを生み出す人」でありたいなら、
「ノー」とも仲良くしないといけないのですね。
考えてみれば、本当に良いアイデアは
その辺にゴロゴロと転がっているものではなく、
たくさんの「ノー」を克服したその先にある。
ごもっともです。
でも、私たちの心の中にある嫌われ者の「ノー」のイメージは
ちょっとやそっとで良くなりそうにありません。
どうしたら「ノー」と仲良くなれるのか...?
「ノー」と言われることにも、言うことにも恐れがなくなり、
「ノー」を違うイメージで見ることができるのか...?
「スウェーデン式アイデア・ブック」には
メタファーで表現することで視点が変わるとありましたので、
早速やってみました。
「ノー」をダークサイドの悪者ではない
別のキャラクターにできないか、と考えてみたのです。
以下、私がしてみた連想ゲームです。
ノー
↓
難しい問いかけ
↓
禅問答
↓
禅僧
↓
達磨大師
↓
ヨーダ
なるほど。
「ノー」のイメージのネガティブな側面が、
「スター・ウォーズ」に登場するヨーダのイメージになり、
深い知恵を持つ導師のように思えてきました。
私たちの頭の中から浮かんでは消えていくたくさんのアイデア。
「イエス」も「ノー」も味方につけて
アイデアの育て上手になりたいものですね。
どうぞ素敵な1週間をお過ごしください。
「考えない人」を批判する前に考えたいこと
ランチを食べながら、隣の席にいた見知らぬ二人が、こんな会話をしていました。
「仕事を頼んでも、彼女はまったく自分で考えようとしない」
「細いことまで指示しないと、やってくれない」
男性と女性の二人の会話、聞き耳を立てていたわけではないのですが、
すみません、耳に入ってきてしまいました。
主体的に考えない人が組織内にいて、
それに対して悩みや不満を言う先輩/上司。
どんな組織にもありがちなことですよね。
そして大抵の場合、不満を述べている先輩/上司は、
自分たちは主体的に考えていると自認しているだけに、
考えないなんてありえない、理解できないと思っています。
さて、あるあるのこのシーン、
私たちは何をどう考えるべきなのでしょうか。
私はこの会話を聞きながら、何か違和感がありました。
なんとなく上から目線な批判に思えたからです。
気になったことをシェアさせてくださいね。
1つ目は、主体的に自分の考えを述べない人がいたからといって、
必ずしも考えを持っていないとは言えないと言うことです。
ただ単に、考えを言いにくい雰囲気だと感じているから、
考えを発しないだけかもしれません。
聞かれてもいないのに、自分の考えを発言できる人と言うのは、
むしろ少数ではないでしょうか。
多くの人は、水を向けられてもなお、
こんなことを言っておかしくないだろうか...と気にしてしまいます。
あるいは、考えをまとめてからでないと、発言すべきではないと
行動をセーブしてしまったりします。
大抵の場合、過去に嫌な体験があるからです。
笑われたとか、
否定されたとか、
無視されたとか。。。
勇気を出して発言したのに、傷つくような体験があると、
おそらく二度と同じ思いをしたくないと思うのが、
普通の感覚なのではないでしょうか。
どんな意見でも歓迎されると言う前提があるのと、ないのとでは、
当然言いやすさも違いますよね。
言いやすい雰囲気や安心安全の場を作ることは、
リーダーやファシリテーターの重要な役割だと思います。
これが、簡単ではないのですが。
もう1つ気になったことというのは、、、、
筋道立てて考えたり、物事の本質を理解しながら考えるというのは、
実はとても高度で難しいことです。
ですから、これをスラスラできる人というのも、実はとても少数だと思います。
できている風に振る舞う人は大勢いますが、
そういう人に限って、物事の奥深さを甘く見ていたり、
謙虚に考えることをしていないように見えます。
私も、考えることが仕事ですが、
この「考える」行為は、何年やっていても侮れないと感じます。
ということは、逆にいうと、
ただ単に「考えろ」という上司では部下は困ると思うのです。
ただ考えろというだけなら、これほど簡単なことはありませんからね。
で、実際、上司にとって、考えることを部下に教えるのはとても難しい。
教えるスキルを学ぶ機会もあまりありません。
さらにいうと、自分自身が常日頃どのようなプロセスで考えて、
どのように物事を進めているかさえ、上司は整理できていないと思います。
暗黙知だからです。
だから「彼女はまったく自分で考えようとしない」と
批判するだけの上司にはなりたくないなと思いました。
ロジカルシンキングなどのようなコンサル系アプローチとは違う方法で、
考えるコツや考えることを教える方法があるといいですよね。
私のライフワークにしようかな〜笑 ←ちょっと本気。
言いやすい人でいたい
先日、会社のビルの1階にあるコンビニでコーヒーを買って、
フタをしようとしていたら、フタがなかなか閉まらず、
ちょっとあたふたとしていたんです。
そうしたら、同じくコーヒーを待っていた40前後の女性が、
親切にも「閉まりません? ちょっとやってみましょうか?」と言って、
私のカップのフタを閉めてくれました。
閉まらなかった理由は、おそらくキャップが不良品で、
サイズが微妙に小さかったから。
彼女は「あれ、おかしいな」と言って、そのフタを諦め、
別のフタに取り替えて、そうしたらうまくフタが閉まりました。
その間のやりとり、約1分半でしょうか。
私は、最初はあらら、こんなことで手を煩わせてしまって
申し訳ないなと思いましたが、
フタが閉まった瞬間、とっても幸せな気持ちになりました。
と同時に、なぜ彼女は手を差し伸べてくれたのだろうと不思議に思いました。
実は、そのちょっと前に、社内のある人との間でこんな話が出ました。
おせっかいはしない方がいいと思いがちだけれど、
それはもしかしたら間違いかもしれない、
おせっかいかもしれないと思っても、オノさんは、
手助けをしたくなる雰囲気を持っていますよね、というような話だったか、
あるいは、おせっかいという気持ちを抱かせない、というようなことだったかな?
詳細は忘れてしまいました。。。何しろ褒められたみたい〜♪
もし、このコーヒーの例のように、
見ず知らずの人が私を助けたく思ってくれるなら、
これは私のスゴい才能なのかもしれません(笑)
見ず知らずの人は別として、いろいろな人に助けられているという自覚はあります。
でも、なぜ助けてくれるのかはわかりません。
助けてもらうコツは?と聞かれても答えられません。
それでも、もしかしたら関係あるかもしれないと思うことが1つだけあります。
それは、言いにくいことも言いやすい人でいたい、
オープンな心でいたい、そうずっと願ってきたことです。
これは多分、10代か20代か、そのくらい昔から願っていました。
本能的に、直感的に、人が躊躇しないで発言できることが、
自分にとっても、他の人にとって大切だと感じていたのだと思います。
ありのまま、思ったままを発言できること、
自分自身がそうでいられない状況は窮屈だと感じるので、
だからこそ、まず自分は「言いやすい人」でいたいと思ったのでしょうね。
で、私自身が今、どこまでそれを体現できているかどうかとか、
言いやすいことと人が助けてくれることに因果関係があるかどうかはともかく、
言いやすい人/言いやすい関係が増えることは社会にとって良いこと、
これはまんざら間違っていないと思います。
では、いったい「言いやすい人」とはどんな人でしょうか?
「言いやすい人」は「波風立てない、いい人」でしょうか?
「言われたことにそのまま応える人」でしょうか?
そうではないことは、なんとなくわかりますよね。
で、「言いやすい人とは?」のその答えは、
相手の発言自体(言われたこと)をどう位置づけるかで、変わってきますよね。
言われたことを、指摘である、文句である、リクエストである、
期待に応えるべきことである、相談である、受け流せば良いことである、
コミュニケーションの入り口の情報である...。
このように言われたことをどう位置づけるかで、
受け止める時の自分の感情自体が随分変わりますよね。
相手の言葉を文句と位置づけたら、単純に反発したくなりますし(笑
私自身は、言われたことを
・コミュニケーションを深めるための入り口にある情報
・相手が寄り添ってほしいと思っている感情
こんなふうに受け止めるようになり、それによって、
ニュートラルに受け止めることができるようになりました。
(もちろん人間ですから未だに不完全ですが、、、苦笑)
防衛的でなく聞く。
攻撃的でなく言う。
これだけで、社会はもっと快適になると思うんですよね。
そのような考えから、当社では先週から勉強の場として
「育自プロジェクト」を展開中です。
これは、まさに「防衛的でなく聞く」「攻撃的でなく言う」の実践。
社会がそうなってほしいので、まずは自分たちからそうありたいと思います。
そして、私たちは仙人ではないので、実はそんなに簡単にはできません。
それでも、やってみて、軌道修正し...それを組織として繰り返していくことが
とても大切だと思います。
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。
素敵な1週間をお過ごしください!
得意なこと、苦手なこと

最近、私の周りでよく話題に上るのが、苦手なこととどう付き合うか、です。
苦手なことを克服しようとがんばるよりも、
得意なことを伸ばす方がいい、とか
好きなことだけすることに罪悪感を抱く必要はないとか、
がまんして嫌いなことをするよりも、
嫌いなことはやらないと決める方が幸せになれるなど、
自分の活かし方や才能の伸ばし方に関する
ひとつの示唆に富んだ考え方だと思います。
でも、「苦手なことより好きなこと」というのを
「好きなことをすることが幸せ」と短絡的に捉えてしまって、
好きなことがみつからない、
自分のやりたいことがなくて焦る...と悩む人も見かけます。
確かに好きなことだけして食べていけるなら、
いいなあと思いますよね。
もちろん何もかもうまく行くなんてことはありえませんから、
好きなことを始めたものの、経済的には苦しく、
そうこうするうちに、結局立ち行かなくなった...などということも
起きたりします。
それでも、やっぱり一度だけの人生なんだから、
やりたいことや好きなことがあるなら、
やってみる方がいいですよね。
でも、こうも思います。
幸せってそういうことだけではないんじゃないかな、と。
何をしていても、幸せを感じられる人は感じていますから。
さて、、、、
苦手なことを巡っては、こんな考え方もありますね。
苦手意識は単なる思い込みであって、
それを取っ払ってしまうことで、自分の可能性が大きく広がる。
これはこれで、共感できます。
親や先生からこんなことを言われた体験はありませんか?
「歌は上手だけど楽器が下手だね」
「応用問題が苦手だね」
「積極性が足りない」
「絵を描く時に神経質になりすぎる」
こんな経験があると、それをそのまま受け取って大人になってしまい、
未だにそんな自分像を抱いているという話はよくあります。
だからこそ、刷り込まれた決めつけに振り回されず、
自分を白紙で眺めると、新しい可能性が広がるということなのでしょうね。
でも、白紙にするという発想がないままに、
ただ苦手なことを克服しようとすると、
苦しいだけになります。
では、最初の「苦手なことをがんばるよりも、得意なことをする」という考え方と、
「苦手だという思い込みを手放すと可能性が広がる」という考え方、
これらは相反することなのでしょうか。
私はいずれも「自分を大切にする」ということであって、
どちらか一方が正しいというものではないと思っています。
苦手なことは克服しなければならない...
好きなことだけして生きるなど許されない...
自分は〜が苦手だし、できるわけがない...
これらはいずれも自分で自分を制限してしまっていて、
自分で自分を認めていない考え方だと思います。
自己制限をせず、自分を大切にする。
結局、そういうことが自分を生かすことにつながるのかもしれませんね。
私は、自分自身がそう自分を取り扱いたいですし、
当社のスタッフに対してもそういう目線で接したいなと思います。
ここまで読んでくださってありがとうございました。
どうぞ素敵な1週間を!
本当にそう?
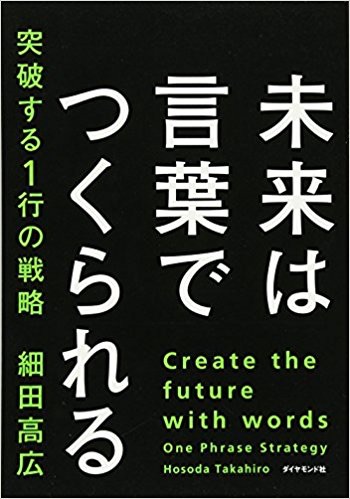
ちょうど今、私は「未来は言葉でつくられる」(著:細田高広、ダイヤモンド社)という本を読んでいるのですが、
あなたは言葉の力を信じますか?
こう聞かれたら、多くの人は「イエス」と答えることでしょう。おそらく過去に感銘を受ける言葉と出会った経験があるからです。
それは、人から言われた言葉かもしれませんし、何かで読んだ言葉かもしれません。
つまり、誰しも言葉には人の気持ちを動かす「力」があることをなんとなく知っています。
でも、結局のところ、言葉の地位は、それ以上でもそれ以下でもない。
少なくてもビジネスにおいて言葉を大切にする経営を行なっている企業は、あまり多くないと感じます。
多くの場合、言葉がどう捉えられているかというと、説明して理解してもらうためのもの、なのではないでしょうか。それはそれで大切ですが、本当にそれだけかといえば疑問です。
私自身は、言葉こそが、自分の人生を変えたり、自分の仕事を変えたり、世の中をより良い方向に変えたりするのだと思っています。何かの始まりには常に向かう先を描く言葉があるのだ、と。
そんな私にとって、言葉は未来をつくるためのものだと語るこの本は、
まさに我が意を得たり!です。
この本では、ソニーやアップル、ディズニーやシャネルなどを例に挙げ、
革新的なことを成し遂げる出発点には
常に「ビジョナリーワード」と呼ぶべき1行の戦略ワードがあったことを紹介。
さらに、どのようにしたらその言葉が作れるのか、
アプローチ方法を紹介しています。
この本には共感することがいろいろと書かれていますが、
中でも一番強く「その通り!」だと思ったのは、
つくりたい未来の入り口を探すには、現状を疑うことが不可欠だという指摘です。
つまり、未来をつくる言葉をいきなり生み出そうとしてもできるものではなく、
現状を疑うことが先である、ということですね。
著者は、そのために有効なのは「本当にそう?」という自問だとしています。
以下の引用は、各社の出発点にあったであろう自問です。
ーーーー
ビジネスは、自然環境の敵である。本当にそう?(パタゴニア)
コンピューターは便利ならそれでいい。本当にそう?(アップル)
クルマは家計と環境の負担になる。本当にそう?(ジップカー)
ーーーー
そうなんですよね。
「疑ってみよ」というのは、身近なことでも言われますよね。
日々の仕事で当たり前のようにやっていることを疑ってみよ、とか。
ところが、疑ってみること自体、結構難しい。
人間は思い込みをする動物だからです。
これはこういうものである、という思い込みで
私たちはがんじがらめになっています。
これでは、未来を変えるどころではありませんね。
しかも、社会常識に対して思い込みを持つだけでなく、
自分自身に対しても思い込みを持っています。
・私は〜が苦手。
・私に〜する時間はない。
・私は〜をしなくてはならない。
思い込みは、言葉の負の力だということもできますね。
だから、仮に目の前のことについて「本当にそう?」と自問して、
「違うかもしれない」と思えても、
今度は「自分の手で現状を変えるなんてムリ。できるわけがない」
という思い込みが働き...などということになりかねません。
でも、、、、
そもそも人間が思い込む習性のある動物であるなら、
常に「本当にそう?」と自問するクセをつけるしかありませんね。
自分の思い込みワードを打ち消し、
自分の未来、社会の未来をより良くするための魔法の言葉、
それが「本当にそう?」なのかもしれません。
さて、10月がスタートし、2017年も最終コーナーです。
どうぞ素敵な1週間を!



