自分が周囲に与えているインパクトに目を向ける

2年前の今頃、私は10カ月に及ぶCTIのリーダーシッププログラムを終了しました。
その中心にあるのが4回(合計22日間)の合宿です。
富士山が見える御殿場の合宿所で修了証をいただいたのが、
2015年の1月25日。
早いものでそこから2年が経ち、
自分の中でいったい何が変わったのか、振り返ってみました。
コンセプトやスキルを学んだからといって、
何かが激変したわけではありませんが、
それでもやっぱり行って良かったと感じることがたくさんあります。
今回は、その中でもその場に与えている自分のインパクトと
それを知ることの大切さについて、シェアさせてください。
インパクトというのは、その場に与える「影響」やその人の「印象」です。
最初の合宿研修の2日目に学んだのが、このインパクトという概念でした。
よく「あの人は〜なオーラを出している。。。。」などと表現したりしますが、
それに近いものと思って良いと思います。
人はただ佇んでいるだけで、いろいろなインパクトを出しているんですよねー!
たとえば、私の場合、、、
(これが結構複雑でちょっと恥ずかしいですが、開示します!)
実直なインテリっぽい印象もありーの、
予測不能な行動をしそうな変わり者っぽい印象もありーの、
とっつきにくく、怖い人っぽい印象もありーの、、、、
というハイブリッドな印象を与えているようです。
少なくても、そこに参加していた23名の参加者とリーダーチーム5名からの
フィードバックをまとめるとそういうものでした。
つまり、よく言えば、場に安定感をもたらしつつ、
時には変化をもたらし、
時には言いにくいことをズバっと言ったりする、
そんな存在感ならしいです。
人によっては、
場を明るくするとか、
場を凛とさせるとか、
場に熱を伝えるとか、いろいろなインパクトの人がいました。
それはいわば自分の力強さの源と言ってもいいのだと思います。
リーダーは場のムード自体を意図的に作り出すことが実はとても大切だ、
ということが、この話の根っこにあります。
自分が持っていて、知らず知らずに出しているインパクトが
場のムードに影響を与えるので、まずそれを自覚して、
それを全開にして活用したり、
自分一人では作れそうにないムードについては、
別のインパクトを持つ人に助けてもらおう、
そんな文脈での話でした。
で、これを知ったことで何が良かったか?
まだ意図的な場づくりがどれだけできているかは心もとない限りですが、
少なくても「自分は今、どんなインパクトを出しているだろうか?」とか、
自分は今、力強くあるだろうかとか、
周りにはどんな印象を与えているだろうかなど、
セルフチェックを頻繁にするようになりました。
それは、自分の態度や素振りがどうかということもありますし、
自分のインパクトを受けている周囲の人の表情や反応がどうか、
ということに今まで以上に目を向けるようになったというのもあります。
さらに言うと、元々初対面の人の反応が「第一印象はとっつきにくかったけど、
話したら話しやすいとわかった」と変化していくことが多かったのですが、
「話しやすい」という関係に
以前よりも短時間で行けるようになった気がしています。
つい先日も、「話しやすくて、聞いてもらうと落ち着く」と言われたり。
これも自分のインパクトを自覚したからなのかな、と。
あなたは、自分にはどんなインパクトがあると思いますか?
どんなインパクトでも悪いということはありません。
いずれもある意味エネルギーの一種であり、
人によってその質感が異なるということだと思います。
予測不能な変わり者という印象と聞くとイメージが悪いですが、
だからこそ場に変化を与える力があったり、、、
とっつきにくく、怖い人という印象の人は、
その場にいるみんなが思っているのに言えないことを
ズバっと言える力を持っていたりします。
ポジの面もネガな面も知っておくと、いいのでしょうね。
他の人に聞くなどして、自分のインパクトに目を向けてみる。
ちょっとオススメです!
今週は早くも2月に突入です。素敵な1週間でありますように!
会話では錦織選手を目指さない
テニスの錦織圭選手。
全豪オープンの4回戦で、残念ながら元世界王者ロジャー・フェデラー選手に
敗退してしまいました。残念でしたね。
テニスでは、相手の手が届かないところにどれだけストロークを打ち返せるか、
それが勝敗を分けます。
打ちにくいところに返すのは、勝負だから当然です。
でも、会話のラリーの場合はちょっと違いますよね。
というわけで、今日は会話の「ストローク」の話です。
で、この「ストローク」という言葉。心理学用語でもあります。
言葉、表情など相手への反応として取る言動のすべてをストロークと言います。
たとえば会話。
テニスのラリーのように言葉を返し合って成り立ちますが、
同じ返しでもポジティブな返し方とネガティブな返し方がありますよね。
肯定的な反応はポジティブストローク、
否定的反応はネガティブストロークと呼ばれます。
「今年こそは英会話をがんばりたい」
「今年こそはダイエットしたい」
相手が発したそんな言葉に対し、
「どうせ三日坊主なんじゃないの?」と返すのはネガティブストローク。
ネガティブストロークに対して、ネガティブストロークで応戦すると、
お互いの気分はどんどん悪化します。たとえば、こんな感じ。
「今年こそは早起きして、毎朝歩こうかな」
「どうせ三日坊主なんじゃないの?」
「人のこと言える? 自分だってダイエットするって言って続いたことがないよね」
テニスの試合と違って、会話は勝負ではないのですから、
打ち返しにくいところに攻め込むようなストロークを打つと、
相手は攻撃されていると感じて、感情が悪化する...というのはよくある話。
私がここで強調して書くまでもなく、
相手と良い関係を育むためには
「ポジティブストロークを心掛けるべし...」とは
一般的によく言われることです。
スマッシュを決めるのではなく、
相手が素直に返せるところにボールを打つ、
気持ちのいいラリーを続けるというイメージでしょうか。
さて、、、、
今日のメインテーマはむしろ素直に受け止められないボールを受けた場合、
つまりネガティブストロークを受けてしまった時、
私たちはどう対処したらいいだろう、という話です。
あなたならどうしますか?
上の例で言えば「どうせ三日坊主なんじゃないの?」と言われた時に、
どう受け止めて、どう反応しますか?
...え、私のこと、そんなふうに思っているんだ。。。
自分のことを棚に上げて、何をエラそうに!
そんなふうにネガティブに決めつけなくてもいいじゃない!...
まあ、生身の人間ですから、こんな心理に陥ったりしますよね。
でも、相手の反応をポジ/ネガで分けて受け止めることを続けていくと、
常に他人の反応で自分の感情が浮き沈みすることになります。
私は、それはバカらしいなと思います。
自分の人生が他人に縛られるからです。
「三日坊主になっちゃうかもね。
『ほら、やっぱり』と言われちゃうかもね。
でも、自分は早起きして歩くと決めたから」
と思ったら、腹も立たない気がします。
相手に同調してみる。
相手が打ち込んできたそのボールは追いかけない。
...というのも、ひとつの知恵なのでしょうね。
「ストローク」について、私自身の経験を振り返ってみると、、、
ネガ/ポジの目盛りも人によって様々だということ。
私にとっては大したことではないつもりだったのに、
部下は否定されたと感じてしまう...ということも起きます。
人は、想像以上に否定に対してデリケートで、
特に、相手が提案、発案、意見、助言などをする状況で、
「でもさ...」とやってしまうと、アウトですね。
私も時々地雷を踏んでいますが、、、、(泣笑
上司と部下、立場が違うと感じることは違うという至極当然なことを
私も含め上司である人間はちゃんと認識すべきなのでしょう。
さて、会話での「ストローク」、
その場に起きているポジ/ネガに意識を向けたらどうなるでしょうか?
少なくても、会話では錦織選手のようなストロークを
目指してはいけないってことですね(笑
どうぞ良い1週間を!
フィードバックを受ける側に必要な「心の準備」
フィードバックのコツって何なのでしょうか?
最近つくづくフィードバックって難しいなと思います。
フィードバックの達人になりたいと思うのですが、なかなかその域には達しません。
それは、公私ともにです。
先日は、友人のマーケティング&コミュニケーションについて
良かれと思ってフィードバックをしたところ、
意に反して、心を傷つける結果となってしまいました。とほほ。。。
そんなことがあったので、今日はフィードバックについて、
自分の考えを整理するためにも、書きたいと思います。
さて、、
あなたは人にフィードバックをする方ですか?
私はスタッフに対してはもちろんですが、
友人に対しても、よけいなお世話的なフィードバックをしますし、
クライアントに対しても必要だと思えばしてしまう、、、
そんなタイプの人間です。
スタッフへのフィードバックも、日常的にありますが、
うまくいくこともあれば、いかないこともあります。
30年間、成長しているんでしょうか(笑
最近思う仮説的なことは、あらゆるケースに共通するのは、
本人がフィードバックがほしいと望んでいない限り、
フィードバックは無効なのではないか、、、
ということです。
多くの人は、ポジティブフィードバックはいつでもウェルカムですが、
ネガティブフィードバックは心の準備ができていいないと、
防衛反応が出ます。
それは当然のことであって、それ自体を責めることはできません。
しかし、大抵のフィードバックは、
良いこと、見直した方がいいこと、ワンセットです。
つまりポジ/ネガ両方を同時に伝えようとする。
(もちろんネガだけの場合もありますが。)
でも、ワンセットで話したとしても、
「聴こう」という気持ちを整える準備がない場合は
ポジしか記憶されなかったり、
反対にネガへの防衛的/反発的な反応で終始し、
実りのない結果になりがちです。
「たとえネガティブフィードバックであっても聞きたい」と
相手が思っている時にだけ、とても吸収される。
フィードバックは言うことが目的ではなく、
相手が何かしら考える材料にしたり、役立ててもらうことが目的ですから、
吸収されないことには目的を達成しないことになります。
だからこそ、そういうマインドセットで
聴いてもらえる状況をつくることが先であって、
それがない状況でするフィードバックは
言いたい人が言いたいことをいうだけの、
自己満足フィードバックなんですよねー
頭ではわかっていることなのに、
気づいていないなら教えてあげるのが親切だ、、、みたいな
おせっかいババア心が働くと、失敗するんだな。
あなたは、フィードバックする時にどんなことを心がけていますか?
どんなフィードバックはウェルカムで、
どんなフィードバックはイヤですか。
この場を使って、時々フィードバック談義、しましょうね。
では、今週も素敵な1週間でありますように!
ウィッシュリスト100を作ってみると?
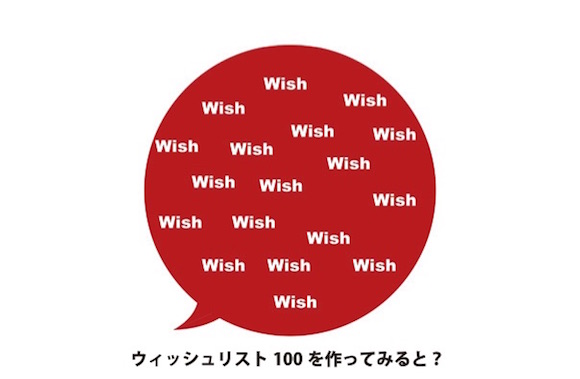
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
新しい年を迎え、初詣に行ったり、
新しいダイアリーやノートを買ったりする機会のあるこの季節、
今年をどんな年にしたいか、やっぱり考えますよね。
その願いは、すごく具体的で計画レベルの人もいるでしょうし、
健康で幸せに暮らしたいなど抽象的な人もいると思います。
私はどちらかというと怠け者なので、
年末年始に目標や計画を立てるのは苦手な方です。
でも、珍しく今年は「ウィッシュリスト100」を考えてみました。
ウィッシュレベルだけでなく、ドリームもです。
夢を書き出すことの大切さについては、
誰がいつから言い出したのか、
調べてもわかりませんでしたが、
自己啓発の世界では、定番的な手法ですよね。
ベストセラーである「7つの習慣」はもとより、
私は読んだことがありませんが、ロバート・ハリスさんも
「人生の100のリスト」という本で、書き出すことの大切さを書いているようです。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんも、あるラジオのトーク番組で、
34歳で引退したときに今後の人生をどう生きようかと戸惑い、
「ウィッシュリスト100」を作ったと語っていました。
そうしたら彼女の中で「結婚」「出産」が上位2位だと自覚したそうです。
その結果、あれよあれよという間に、願いが叶ったのだとか。
具体的には「ゴルフを70台でまわる」をウィッシュリストに入れた杉山さんは、
ある時、ゴルフのプロアマ大会に出ることに。
ゴルフのスキルを上げたくて習ったコーチが今のパートナーだそうです。
こんなふうに、ウィッシュリストはなんとなく有効な気がするものの、
実際なぜ有効なのか、私にも説明はできません。
多分「自覚」と「無自覚」の差なのでしょうね。
人は漠然とした願いでは、願い自体に対し無自覚だから行動しようとしないけれど、
具体的な願いとして自覚すると、脳は行動して達成したくなるのかもしれません。
で、行動するということは、第三者に話すということも含まれていて、
人に話すことによって、いろんな作用が化学反応のように起きて、
実現に近づいていくのではないでしょうか。
あなたは叶えたいことを100件書き出すということ、
やったことはありますか?
私は初めてやってみて、最初はちょっとつまづきました。
100件もスラスラ出てこないのです。
20件ぐらいで、いったん立ち止まります。
でも、あちこち心のボタンを押すと、たくさん出てきますね〜(笑
それも、いろいろなレベルで。
そして、人生で叶えたいことを100件出した後、
2017年にやりたいことを絞ったら、それでも30件!
これは欲張りすぎで、5つもできたら御の字です(笑
100件書いてみると、何が願いの上にあるのかもわかりました。
それが100件書き出すメリットですね。
さて、、、マインドフルネスの世界では「目標」に対し別の視座もあります。
"Zen(禅) Habits"の管理者Leo Babautaは、
今自分が未達成のことを思い描いて、
それが達成できたらハッピー、達成できなかったらアンハッピー...
と思うことは、未来への願望が現在を束縛し、今の幸せに結びつかない。
それを避けるために、まずは毎日を充実させることを大切にしよう、
という考え方を提唱しています。
目標を持つことを否定しているのではありません。
目標を未来の姿に置かず、
日常の中の日々の行いにする、そんなイメージなのでしょうね。
なるほど、と思います。
結論からいうと、私のウィッシュリストには、
未来のこと、日々のこと、両方が混在していたので、
それはそれでいいかなと思いました。
なにしろ100件書いてみるという体験自体が新鮮でしたから!
あなたはどんな一年を願いましたか?
2017年が素敵な1年でありますように!!



