言葉の力を信じていますか?
もうすぐクリスマスですね。
この時期にfacebookを見ていると、
サンタになっているお父さんたちの微笑ましい話をたくさん目にします。
さて、クリスマスだからというわけではありませんが、
「ヨハネによる福音書1:1」に書かれている有名な一節に
次のような言葉があります。
ーーーーーーー
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあり、言葉は神であった。
ーーーーーーー
福音書の原典はギリシア語で書かれており、
「言葉」と訳されている部分の原語は、「ロゴス(logos)」です。
ロゴスとは、概念、意味、論理、説明、理由、理論、思想などの意味だそうです。
私は「はじめに言葉があった」について、勝手にこう解釈しています。
世界や宇宙は、たくさんの概念や意味、事象にあふれていて、
もし言葉がなければ、ただの混沌とした状態でしょう。
その混沌から逃れ、美しい秩序と調和をもたらすためのもの、
それが言葉だ、ということではないかと。
たとえば、もし私たちが「平和」という言葉を知らなければ、
「平和」に向かう努力はできません。
「人権」という言葉が生まれてきたから、
すべての人には「人権」があると理解されるようになりました。
言葉は、人の認識に影響を与えるだけでなく、
行動にも影響を与えています。
ビジネス社会により具体的に影響するのは、
むしろ行動への影響かもしれません。
たとえば、昔は「会社のため」という言葉で人は動きました。
今、その言葉で人が動くことはないと思います。
またこんな例もあります。
この週末、ある人から聞いた話です。
最近よく耳にする「引き寄せの法則」。
最初は「牽引の法則」という言葉で紹介されていたそうですが、
「牽引」を「引き寄せ」に変えたら、ブレイクしたそうです。
(すみません、具体的にどの本の話なのかは未確認です。)
行動につながるかどうかの分かれ道、
それはピンと来る言葉であるかどうかです。
こういうと、広告のキャッチコピーの話なのでは?と
言う人がいますが、そうではありません。
概念の整理選択の問題だからです。
マーケティングやブランディングでは、
この概念とそれに基づく言葉の絞り込みが真剣に行われていますが、
中計の発表やトップメッセージにおいて、
どれだけ多くの企業が言葉の力を信じて、
そこにエネルギーを割いているかは、甚だ疑問です。
私たちグラスルーツの企業理念は
《「言葉」で未来をつくる》です。
言葉の力を信じて、言葉には力があることを
もっと社会に広めていきたいと思います。
年末まであとわずか。今週も素敵な1週間をお過ごしください!
今しかできないこと
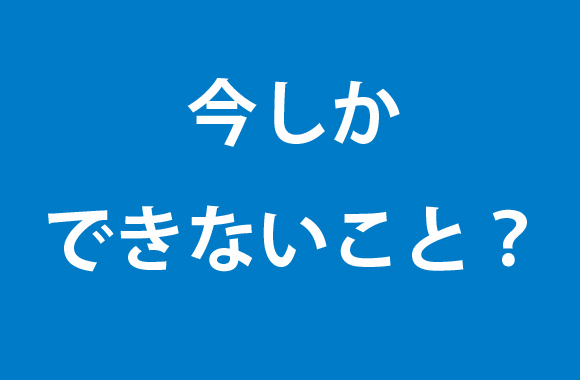
今日は、今、この時代にしかできないことについて、考えたいと思います。
ちょっと前置きが長くなりますが、まずは土曜日の出来事から。
その日、先日行われた高校の同窓会の
幹事が集まって、打ち上げが行われました。
神奈川県立多摩高校が私の母校です。
親子2代で同じ高校という人も少なくなく、
自ずと現在の母校の様子が話題に上ります。
なにやら生徒たちが「反対の署名運動」を行っているのだとか。
何に反対しているのかと聞けば、、、
神奈川県の教育委員会の方針が学校方針に影響し(?)、
学校行事の時間数を減らして授業時間を増やすということが進んでいて、
反対運動はそれに抗議するためのものだそうです。
その方針の背景には、入学時点では偏差値が高いのに、
現役での進学実績が低いという傾向があり、それが問題視されているようです。
偏差値に対して進学実績が低い。
それは、よくも悪くも伝統的に続いてきた傾向でしたが、
そうであってもお釣りが来ると思える校風がありました。
その代償とは何なのか。
それは、主体性や創造性を育むというその一語に尽きます。
たとえば、保護者の立場で各高校の学校説明会に行ったという友人いわく、
「大多数の高校は先生が説明会を仕切っている、
一部の高校は、先生が仕切っている説明会の所々に生徒たちが登場する、
でも多摩高は企画も運営も生徒が行い、内容もユニークだった」。
「社会に出てからではできないこと、
その時代にしかできないことがあるんだよな」。
誰かのそのつぶやきが妙に心にしみました。
さて、、、
高校時代には高校時代にしか、できないことがある、
のであれば、20代には20代にしか、できないことがあり、
30代でも50代でも80代でも、
その時代にしかできないことがあるのではないか、と、
そんなことを考えたわけです。
たとえば、30代の時に持っていなかったものを今は持っているとか、
今は持っているけれど、70代になったら失うかもしれないこととか。
そういうことによって「この時代にしかできないこと」があるのかも、と。
もちろん、それだけでなく社会の進歩なども関係してきますよね。
(あ、何歳になっても始めるのに遅すぎることはない、と反論しないでください。
はい、それも別の意味で、真実ですが)
そして、、、
結局それが何であるのかを決めるのは、
自分次第ですよね。
先ほどの例なら、高校時代は受験勉強よりも、
創造性やリーダーシップ、チームワークを学ぶ方が良いというのも
一つの考え方ですが、
受験勉強に徹し、勉強によって自分の可能性を追求する方が良いとする考え方も
やはり一つの考え方です。
時代背景によっても、いろいろな価値観が出てきて当然です。
何が良い悪いではありません。
ただし、1度しかない人生にどのような願いを持つのか、
その価値観に素直に従うことが大切だということだけは
間違いないのではないでしょうか。
どういう人生を送りたいか、
どういう人間でありたいか。
夢は何か。
今しかできないことは何か。
自分にしかできないことは何か。
とかく歳を重ねると、生活すること自体が目的化しがちですが、
時には、そんな問いとともに立ち止まって考えることも必要ですね。
あなたにとって、今、この時代にしかできないことは何ですか?
私も年末の慌ただしさ、忙しさの中で、
心を亡くさないように。
心の願いを大切にしたいなと思います。
今週も素敵な1週間でありますように!
「もっと○○したい」への妨害者に打ち勝とう!

ここ1カ月ほど、新しい出会いが多く、
また新しいプロジェクトがスタートするなど、外的な刺激の多い時期でした。
しかも、接する方たちに偶然にも共通していたのは、
「もっと○○したい」という強い願いを持っていたことです。
「社員がもっと会社を好きになるようなきっかけを作りたい」
「もっと自社の強みを伝えたい」
「社内をオープンな会話ができるムードにしたい」などなど。
「もっと○○したい」。
とても身近な言葉ですが、
これほど人をパワフルにする言葉はあるでしょうか?
この言葉の力強さに気づいていなかった方は
「え?」と思うかもしれません。
「そんなに力強さがある言葉なの?」と。
でも、この言葉は、未来を変えようとする言葉だと思いませんか?
そもそも人が抱く願いとか、欲求というものには、
高密度なエネルギーがあります。
願いがあると、心の温度が高くなりますよね。
私は、ご相談を受け、仕事を選ぶときに、
その方の「もっと○○したい」が強いかどうかを一つの判断材料にしています。
なぜなら願いが弱い人と仕事をしても、
何の問題解決にもならず、ただの作業になるからです。
書きながら、ふと、レンガを積む男の話を思い出しました。
有名な例えなので紹介するまでもありませんが、
レンガを積む仕事をしている人に「何をしているか」と聞くと、
「人が集まり祈るための教会を建てている」と言える人と、
「見ればわかるだろ、レンガを積んでいるんだ」と言う人がいる。。。
教会を建てていると答える人の心の中には、
社会や人の気持ちなど、何かをより良くしたいという願いが感じられます。
しかし、、、
このパワフルな気持ち「もっと○○したい」対して、
多くの場合、妨害者が現れます。
その妨害者は、上司や同僚、家族や友人の場合もあるでしょうけれど、
もっとも手強い相手は「ああ、もう無理!」と叫ぶ人物、
つまり、自分自身です。
「もう無理!」にもいろいろあります。
*上司を説得するのが無理!
(なぜなら、説得に失敗して惨めな気持ちになりたくないから)
*いろんな意見がありすぎて、みんなを満足させるのは無理!
(なぜなら、みんなから嫌われたくないから)
*そんな難しいことを実行するのは無理!
(なぜなら、今の自分のスキルではできる自信がないから)
*普段より忙しくなりそうだから無理!
(なぜなら、家族と険悪になるのはイヤだから)
さて、、、
多くの場合、人はその無理な原因を状況のせいにしたがります。
( )の理由は自分の中にあるものなのに、
そこに気づかないことも少なくありません。
では、無理と感じ始めたとき、どうしたらいいのでしょう?
お勧めしたいのは、3つのこと。
第1は、そもそもの目的、「なぜやりたかったのか」に立ち返ること。
第2は、熱量のあった最初の身体感覚を思い出すことです。
「え? そんな原始的なこと?」と思われるかもしれませんね(笑)
騙されたと思ってやってみてください。
「グランディング」と言いますが、
姿勢を正し、自分の足が大地を踏みしめて立っている感覚を
意図的に感じることに努めます。
ブレそうになった自分の気持ちが定まって、「無理」が「できる」に変わりますよ。
最後の第3。これは、その妨害者に名前をつけることです。
たとえば私の中にいる妨害者には「ジンジャー」「QT」などの
名前をつけています。他にもいます(笑
そうすると、思考の癖を客体化して見られるんですね。
複雑な社会で人間稼業をやっているわけですから、
そりゃ、誰でもグラグラしますよね〜
大切なことは、今自分がグラついているかどうか、感じ取る力と、
パワフルな自分に立ち戻る力ではないでしょうか。
では今週も良い1週間をお過ごしください!
※今週の動画ブログはお休みです。



