伝わるためのツボは「自分が相手なら...?」
先週8月23日(火)24日(水)の2日間、
宣伝会議様主催の「インナーブランディングのための戦略ロードマップ策定講座」に
講師として登壇しました。
http://www.sendenkaigi.com/class/detail/inner_branding.php
前回のブログにも書いたように、今回初リリースの15時間のコンテンツです。
社内では模擬講座を開いてフィードバックをもらうなど、
時間をかけて練り上げました。
そ、フィードバックをもらっての改善、本当に重要です!
おかげさまで最終日には「実務で役立つと感じたか」のアンケートで
参加者全員から5点満点をいただけたほど、好評でした。
これまでにも良い点を取った経験はありますが、満点は初めてでした。
点数もさることながら、「自信になった」
「実践できる」という感想がとてもうれしかったです。
実は、登壇依頼を受けた当初、2日間でこの内容を行うと、
参加者は情報過多になりすぎて、着いてこられなくなり、
達成感が得られないどころか、不満が出るのではないか...
そんな懸念を抱きました。
なので、私としても、これは結構なチャレンジだったのです。
そうならないために、心掛けたのは;
・本質を極力シンプルに伝えること
・考え方、すること、やり方を整理して伝えること
・理解の度合いを確認しながら、ステップbyステップで進めること
・正論と現実論の両方を伝えること
・難しい専門用語を使わないこと
...などです。
ですが、それ以上にそれらの根底にあったこと、
一言でいうなら、「自分が参加者なら何を求めるか」でした。
何を、どんな順に知りたいか、
どこで、どんな疑問を持つか、
どう教えられるとピンとくるか、
どう教えられるとイヤか、
こんがらかりそうなところはどこか。
参加者の視点で徹底的に考えました。それはもう徹底的に、です。
あくまで「伝える」ではなく、
「伝わる」を目指す。
相手側の感覚でいえば、
「わかった」「やってみよう」となる状態を目指す。
どんなときも、そこにこだわり続けるのが、
私らしくもあり、グラスルーツらしくもあります。
だって、伝えても伝わらなかったら何も残りません。
それは、とっても悲しいですから。
この相手の気持ちを考えるというのは、
コミュニケーションの様々な局面でよく言われることです。
会話のように瞬発力を求められる場合と、
準備して臨める場合がありますが、後者であっても、
それに慣れていない人もいます。
そういう方たちは、大抵の場合、そのコツがわかっていません。
慣れていない人は、いきなり相手の気持ちを考えようとします。
そして、結局つかめないで終わります。
で、私が勧めたいのは、「自分が相手なら」どう感じ、
どう思うかを考えるということ。
「参加者がどう思うか」ではなく、
「自分が参加者ならどう思うか」。
これ、似てますが、まったく違うのです。
そうすると、見えてくることがたくさん出てきます。
それがコツです。
さて、今日の話は、何も自慢したくて書いているわけではありません。
真剣に伝えれば、伝わるということを知ってほしくて書いています。
それは、セミナーというコンテンツに限りません。
あなたが、なんらかの媒体を企画制作しているなら、
そのコンテンツも同様です。
しかも、それだけではありません。
仕事はコンテンツの集合体だとみなすこともできます。
社内会議も商談も、メールもサービスも
言ってみれば、すべてコンテンツです。
分かり合えるコンテンツにする、
そのために、あなたにできることがきっとあります。
そして、繰り返しになりますが、
真剣に伝えるということの本質は、
自分が相手ならと考えるということです。
その真摯で謙虚な気持ち、私たちもずっと大切にしたいと思います。
論理的思考には、想像力が欠かせない
明日、明後日(8/23-24)の2日間、宣伝会議主催の
「インナーブランディングのための戦略ロードマップ策定講座」に登壇します。
約15時間のセミナーコンテンツは、今回書き下ろしました。
さて、戦略といえば論理。
私たちは、論理というと発想や想像、直感とは別のものと考えがちです。
しかし、そうでしょうか?
私は、論理的思考には想像力が欠かせないと考えています。
今日はそんな話を少々。。。
ですが、その前に「戦略」という言葉について。
今回の講座、タイトル名や講座コンセプトは、
宣伝会議様の方で企画されたものです。
それを受けて、「どのように戦略的にインナーブランディング活動を
計画したらいいのか」を学ぶ。それがこの講座の内容です。
「戦略」というのは、元々は軍事用語でした。
ビジネスでもよく使われますが、
どういう意味と捉えたらいいのでしょう。
私は、何をすべきか、進むべき道筋の根幹を決めること...、
と、こんなふうに捉えています。
それに対し、進むべき道筋の中で、
どのようにしたらうまく行くのかを考えるのが戦術。
「戦略=何を」「戦術=どう」。
そんな仕分けをしています。
でも、いろいろなシーンで、この違いが不明瞭なまま、
あるいは「どうやるか=戦略」という使われ方をされている場合も多く、
「戦略」というワードはクセ者だなと思います。
戦略にしても、戦術にしても、
論理的思考が不可欠だと言われています。
論理的思考ができないとビジネスパーソン失格と言わんばかりの勢いで、
ロジカルシンキングが必要スキルとされています。
なんというか、鉄の鎧を来た魔王のように立っているイメージ。
そんなに万能なもんかいな?
「論理的思考」という言葉も、わかっているようで、
実は説明しろと言われても、説明しにくい言葉の一つです。
今や、そんなことを言ったら笑われそうで、
怖くて言えない人も多いのではないでしょうか。
辞書や学術的な意味はともかく、
「論理的思考」というのは、、、
あ、こんなことを書くと叱られちゃうかな〜?
私は「矛盾がなく、概ね間違っていないと思える《脈絡》での思考」で、
「あわよくば最適解に近づけるかもしれない思考」という程度にしか
受け止めていません。
つまり、論理的に考えれば、
必ず正しい答えを導きだせるのかと言えば、
必ずしもそうとは言えない。
にもかかわらず、どうも世の中には論理万能志向がある気がします。
そもそもビジネスで「正しい答」などないのにね〜
ロジカル信仰があるのは、
やっぱり人は間違った選択をしたくないし、
考え抜いた挙げ句の結論であると思いたいからなのでしょうね。
論理的思考をイメージ的に表現すると、
「AだからB。BだからC」というような垂直的な道筋で考えること、
そんなふうに表現することもできます。
だから、論理的思考を垂直思考と呼ぶこともありますね。
しかし、イメージと現実は別で、実際にはもっと複雑です。
たとえば、ある問題の原因を考え、課題を見つける場合、
Aという問題に対して、原因にはa、b、cが考えられ、
aが起きるその原因はa1、a2、a3、
a1のそのまた原因は...となったります。
垂直どころか、タコ足思考です。
ここで行っているのは推論ですが、
このプロセスでは実は「想像力」がものを言います。
推論で想像力が働かないとどうなるか。
たとえば、アンケートに記入する時にこんな経験はありませんか。
自分が選びたい選択肢がない。
あれは調査票の設計者に想像力が足りなかったから起きています。
アンケート調査だけではなく、
あらゆる問題解決で、もし想像力が発揮されないと、
目を向けるべきことに目を向けないまま、
つまりタコ足思考にならないまま、
狭い思考で進めることになってしまいます。
「論理」と「想像」は実は遠い関係どころか、
支え合っているパートナー関係!
推理小説を読むのには想像力が必要だというのと似ていますね。
今週も素敵な1週間でありますように!
フィードバック上手〜福原選手と石川選手の素敵なシーンから
リオ五輪、日本選手は目覚ましい活躍をしていますね。
とても元気をもらいます。
いろいろな競技がある中でも、私は女子の卓球、特に福原愛選手に注目しています。
というのも、子どもの頃から注目された彼女も、今は27歳。
個人シングルでメダルを取ってほしいなと思っていたのですが、残念でした。
団体戦では、4歳下でエース格の石川選手と12歳下の伊藤選手と共に準決勝に進出。
8月15日にドイツと決勝への試合をします。
さて、その団体戦の準々決勝(?)の石川選手の試合で、
面白いシーンを見ました。
それは、ゲームの合間のシーンです。
相手に押されていた石川選手に対し、監督よりも、
むしろ福原選手たちが積極的にフィードバックしていたのです。
内容はわかりません。
でも、ラケットの面を示しながらのものでした。
NHKの解説でも、選手がフィードバックしていることに触れたほど、
それは何かとても良いシーンに見えました。
私は、フィードバックというのは、
上下関係なく必要なものだし、
上下関係なくできる組織こそが強いのだろうなと思っています。
また、理想で言えば、ネガティブフィードバックもポジティブフィードバックも、
コソコソやらず、堂々と愛情込めてできたら素晴らしいと思っています。
でも、実際にはなかなかそうできないのが、人間社会というものですよね。
それに対し、卓球の女子団体戦では、
フィードバックする方もされる方も伸び伸びとしていて、
目的を最優先するからこそお互いにそれを了解し合っているように見えて、
とても好感が持てました。
理想的なフィードバックというのは、
本当に相手のことを思ってするもの。
愛あるフィードバックであることを、
する側もされる側も信頼しているものだと思います。
でも、その信頼基盤がないと、ただの批評や批判にしか聞こえず、
受け止めることができませんよね。
2年前に私が参加した、あるリーダーシップ養成プログラムでも、
お互いにフィードバックし合う場というのがありました。
感情的に受け止めないというのがルールですが、
やっぱり後で聞くと「あのときは感情的に受け止めてしまった」という
声がちらほらと。
その反発心には、
「お前に何がわかるんだ、お前には言われたくない」もあれば、
「え、違うよ、違うよ、そんなつもりはないよ。それ、誤解だから...」もあれば、
「け、また言われた。なんで? 別に普通にしてるだけなのに...」もあるようです。
つまり、フィードバックがうまく機能するかどうかは、
そもそも聞く人が、聞く気持ちになれているかどうかも関係あるんですね〜
で、その聞く気持ちがない人とか、
言ってもスルーする人には、人はなかなかフィードバックしてくれません。
そりゃそうですよね。
良かれと思ってしたフィードバックなのに、
反発されたり、スルーされたら、トホホ...ですからね。
フィードバックするスキルの前に、されるスキル(というか人間力)、
大切ですね。
フィードバックするスキルに関して、最近のマネジメント教育では、
ネガティブフィードバックをするときは、
先に良いことを言ってからにしろ...というのがあるようですが、
私はそれには懐疑的です。その理由は、
・一番いいたいことが、どっちであったのか伝わらない。
中には、良いフィードバックだけを受け止めてしまう人がいる。
・悪いフィードバックをするために、良いフィードバックをしていることを
相手は動物的に察知するので、あざとい印象になり、信頼関係の妨げになる。
相手を傷つけたくないという心理は、言い方を変えると、
自分が悪者になりたくないという心理でもあります。
でも、本当に信頼し合えていれば、悪者にならないと思えるはずです。
もちろん、場とタイミングの問題もありますし、
まだ信頼関係がない段階では、
実際に、良い事柄とワンセットで言われることで、
だからこそ受け入れる気持ちになることもあるから、
一概には言えませんけどね。
福原選手と石川選手は、
憧れる・憧れられる関係から、ライバルへと関係が変貌し、
今でこそ実力的な地位は逆転しつつも、尊敬し合うチームメイト。
そんな関係の中で、フラットにフィードバックする姿が、
とても素敵だと思いました。
私たちも、ビジネスでのフィードバック、上手でありたいものです。
やっぱり信頼関係と素直さだな...。
試合を見ながら、そんなことを考えさせられました。
リオで戦う選手たちを応援しながら、
今週もがんばって行きましょう!
小池百合子さんの当確挨拶で思ったシンプルな言葉の威力
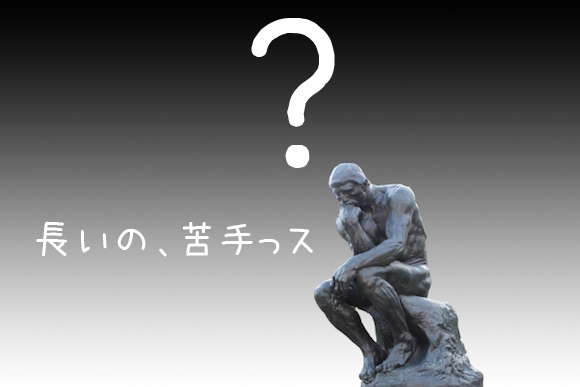
先日の都知事選で、日本初の女性都知事が誕生しました。
先進国の中でも、女性の政治参加率が低いと言われる日本で、
これは一つのエポックメイキングだったと言えるのではないでしょうか。
今度こそスキャンダルは勘弁してほしいですね。。。
さて、当選確実が報道された直後、
選挙事務所で支援者に向かって挨拶した小池百合子さん。
そのシーンをどうご覧になりましたか?
私は、内容とは別の視点で、おや?と感じたことを覚えています。
「〜を申し上げると同時に、〜」
「〜思っていますし、〜」
「〜、そしてまた〜」
口語だから文と呼ぶのも変ですが...。
わかりやすい言葉できっぱり語るいつもの小池さんよりも、
一文が長いなと思ったのです。
小池さんは、かつての「クールビズ」に始まり、
今回の「崖から飛び降りて」や「徴兵制VS志願制」など
言葉の感覚は鋭い人だという印象があります。
けれど、この当確直後の挨拶は、一文が長くてわかりにくかったですね。
恐らく当選し興奮さめやらぬ中での挨拶だったので、
感情が次から次へと湧いてきたためなのでしょう。
ま、小池さんにすれば、話し下手な私から、
そんな指摘を受けたくないでしょうけど(笑
このシーンを通じて思ったのは、
話し言葉も書き言葉も同じだということ。
単語がたくさん続いていくと、
聞いている人、読んでいる人にとっては、
複雑で頭に入りにくくなります。
言葉を短くシンプルにすると、
言葉の威力は反比例して増します。
長くて分かりにくい例を探してみました。
今年6月2日に閣議決定された
「経済財政運営と改革の基本方針 2016について」がその例。
以下、引用です。
ーーーーー
年初来の不安定さは外的要因から来ているとはいえ、
国内経済も個人消費や設備投資といった民需に力強さを欠いた状況となっており、
こうした背景には、人口減少・高齢化社会の下での期待成長率の低下、
IT化などの技術革新を活かしきれていない生産性の低い働き方の継続、
未だ実感に乏しい子育て環境の改善や現役世代の先行き不安等が
根強く存在している。
ーーーーー
いかがでしたか?
私は最初の2行を読むだけでも、意味を噛み砕きながら読まないと、
頭に入ってきませんでした。
まず単純に一文が短いと、言葉が頭に入りやすくなります。
言葉のシンプル化の名人といえば、故スティーブ・ジョブズ。
「今日、アップルが電話を再発明します」や
「1000曲をポケットに」というシンプルなメッセージは
人の心を捉えました。
さて、スティーブ・ジョブズがそうやって言葉を削ぎ落としたのは、
単に才能豊かな人だったからでしょうか。
もちろん、センス溢れる人であったことは間違いないでしょうけれど、
私はそれだけではなく、信念があったのだろうと思っています。
ここからは推測でしかありませんが。。。
それがどのような信念かというと、
「言葉が人を魅する。だから、言葉を大切にすべきだ」、
そんな信念です。
つまり、どんなことをキーメッセージにするか、
どんなワードで表現するか、
どれだけシンプルに表現するか、
単なる思いつきではなく、しっかりそれを考えていた。
彼にとって「設計する」という感覚があったのではないか。
いえ、まあ、あくまで推測ですけど。
最初に話題に挙げた、小池さんにも「クールビズ」の時に、
そういう匂いを感じました。
つまり、ジョブズも小池さんもシンプルな言葉の威力を知っている。
「伝える」ではなく「伝わる」を大切にしている私たちグラスルーツも、
言葉には人の心を動かす力があるという信念を持っています。
人の心を動かす言葉を見いだすのは容易なことではありませんが、
そのためにベストを尽くす、ジョブズのような心意気でありたいと思います。
読んでいただき、ありがとうございました。
どうぞ良い1週間をお過ごしください!
インナーブランディングのロードマップ策定講座 by 宣伝会議様
こんにちは、あっというまに、もう8月です。
2016年も後半戦なんですね、びっくりするほど早いな〜
さて、宣伝会議様からのご依頼で、8月23ー24日の2日にわたって、
「インナーブランディングのための戦略ロードマップ策定講座」というテーマで
て登壇させていただくことになりました。
http://www.sendenkaigi.com/class/detail/inner_branding.php
そして、その体験セミナーが、今週8月3日(水)にあります。
ちなみに、なんとその日は宣伝会議様の別の講座「インナー広報実践講座」でも、講師を務めさせていただきます。
http://www.sendenkaigi.com/class/detail/inner_communication.php
本番も体験セミナーも極力宣伝会議様のご要望にお答えする形で、
コンテンツ開発を行いました。
しかし、これがなかなかむずかしかった〜
内容が難しいわけではありません。
立場の違う方々に、わかりやすく説明するのが難しいのです。
たとえばブランディングに取り組みたいと考えている会社と、
社内広報やインナーコミュミケーションをより良くしたいと思っている会社とで、
ニーズが違うと予想されます。
つまり、両方の方たちにご満足いただくには、どうしたらいいか。
その条件を満たしたコンテンツを作るということが、最大の難関でした。
そして、もう一つの難関は、抽象的な概念を
どうやって実務的なレベルでわかるようにするか。
私自身、昔、何冊も「ブランディング」の本を読んで、
さっぱりわからないと思ったことがあります。
ブランディングというのは、とっても抽象的な概念だからです。
抽象的なことを抽象的なまま語られても、なかなか理解できないんですよね。
また、参加者のテンションを維持するというのも、
講師の重要な役割の一つです。
丸二日、マジシャンになったつもりで、臨まないと...。
そういうことにも配慮しながら、より良いコンテンツ提供のために、
最後まで粘って、バージョンアップを続ける。
そういう姿勢を大切にしたいと思います。
今日は動画はお休み! 髪の毛ボウボウなのに、ヘアサロンに行けてないから(笑)



