つまり、何を伝えたいの?
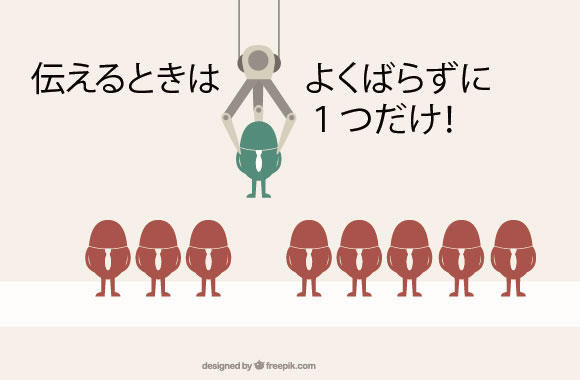
今日は「伝え方の原則は?」という視点から、
「親切なよくばり屋さん」を待ち受ける落とし穴に気をつけろ!
という話です。
当社では毎月2回定期的にセミナーを開催しています。
テーマは企画力と文章力で、いずれもワークショップ形式が特長です。
そこに参加してくださる方たちを見ていると、
一部の人たちがとてもどん欲に伝えようとする傾向のあることがわかります。
彼らは、大抵の場合、頭の回転も速く、
めまぐるしくたくさんのことを考えています。
頭の中は、伝えたい事柄でいっぱいで、
心の中は、伝える情熱に溢れています。
彼らのアウトプットには、惜しみなく与えたいという気持ちがにじみ出ていて、
それは受け手を思う親切心から来るものだと想像されます。
しかし、、、
だから伝わるかというと、話は別です。
企画でも文章でもメッセージの絞り込みが大切なのですが、
絞り込むのが苦手な人、言い切るのが苦手な人がいます。
恐らく惜しみなく伝えることを「是」とする価値観が根底にあるので、
それをしないことは「非」と感じるのでしょう。
そこにあるのは「親切なよくばり屋さんが落ちやすい落とし穴」です。
まず単純に次の3つの文章を比較してみてください。
「伝え方の原則は、これだけです」
「伝え方の原則は、次の3つです」
「伝え方の原則は、次の5つです」
数が多くなればなるほど、その先を読む前から複雑そうな印象を感じます。
そして、その時点で読もうという意欲も失せると思いませんか?
情報が増えれば増えるほど、脳がげんなりしてくるというか...(笑
もちろん、3つでも5つでも、掲げてはいけないわけではありません。
でも、覚えられることを基準に考えるなら、
キーワード化された事柄で3つどまり、
センテンスなら1つがいいところではないでしょうか。
文章でも会話でも、
受け手は「で、一言で言うと、何が言いたいの?」という心境でいる。
相手の記憶に残す発信をするためには、
そんな心理に対応した答えを用意する必要があります。
ところが、この答えを出す時に、どう絞るかの方程式を知らないと、
「つまり」と言いながら、経緯や背景を説明してしまうなど、
相手のニーズに噛み合ない発信をしがちです。
伝えたいことを絞る際の方程式は、
ーーーーーーーー
「つまり、私が伝えたいのは、
(A)については、(B)が大切ということです」
ーーーーーーーー
これだけです。
さらにメッセージ的な表現にすると、こうなります。
ーーーーーーーー
「(A)については、(B)をやろう!」
ーーーーーーーー
もし、あなたが、誰かから、
「つまり、私が伝えたいのは、
(A)については、(B)(C)(D)が大切ということです」
と伝えられたとしたら、どうでしょうか?
きっと複雑な話だと感じますよね。
「二兎を追う者、一兎も得ず」。
人に何かを伝えたい時には、1つに絞り込む。
それが大切という話でした。
6月も最終週です。どうぞ良い1週間を!
リーダーの条件としての「HONESTY」

こんにちは。
Honesty is such a lonely word.
Everyone is so untrue.
Honesty is hardly ever heard.
And mostly what I need from you.
いきなりですが、ビリー・ジョエルの往年のヒット曲、
Honestyの歌詞の一節を引用させていただきました。
誠実... なんてむなしい言葉だろう
誰も誠実じゃない
誠実... 聞いたこともないのに、
私はあなたにそれを求めている
こんな感じの歌詞でしょうか。。。
というわけで、今日は正直である/誠実である、といったことについて、
考えたいと思います。
優秀なリーダーの条件が何であるのか、
その答えに唯一無二の正解はないと思いますが、
「正直である/誠実である」が含まれていることに、
異論を唱える人はいないのではないでしょうか。
リーダーシップの研究者であるクーゼス氏とポズナー氏が行った調査では、
「honest」(誠実・正直である)が第一位となっていますし、
伝説の経営者として知られるジャック・ウェルチなども「誠実さ」を
真のリーダーシップに必要なものとして掲げています。
ですが、、、、
ビジネス社会において、多くの人は鎧を着て仕事をしていると言われています。
鎧を着た状態でいることは、誠実・正直であることとは、
むしろ対極にいることになりますよね。
原因はいろいろと考えられますが、
「会社は、自分の素を出す場所ではない」という思い込みがあったり、
「会社の人に素の自分を見せたくない、何を言われるかわからないし...」とか、
「うかつなことを言って、やり込められたくない」
「周りの人が素を見せていないのだから、同じように振る舞った方が安心」などの
防衛本能が働いているからだと思います。
中には、鎧がカラダに馴染んでしまって、
鎧を着ていると言われても、ピンと来ないという人もいるのではないでしょうか。
自分は自分より上のリーダーたちに正直さや誠実さを求めながら、
リーダーの一員である自分は、実は鎧を着ているという矛盾。
自分では、意外に気づけないものです。
そもそも「誠実さ」「正直さ」をどう定義づけるかで、行動も変わります。
たとえば、発言に裏表のないことは、誠実・正直の条件に含まれるでしょうか?
こう聞かれると、イエスと答える人が多そうですが、
そう答えた人に別の質問をしたとします。
「部下に対し、内心思っていることがあり、
それを言うと気分を害すかもしれない場合、
人間関係を悪くしてまで言う必要はありますか?」
あなたは、どう答えますか?
また、こんな問題もあるのではないでしょうか。
素を出すことに比較的抵抗がない人がリーダーである時、
自分を出せない人の気持ちがわからず、
「もっと自分を出せ」と言ってしまう。
私もやってしまいがちな行動です(汗
もっとデリケートなことだという認識、必要ですよね。
さて、先週16日(木)に宣伝会議様のセミナーで、
講師役を務めさせていただいたのですが、
そのとき興味深い情報を得ましたので、シェアさせていただきますね。
私は、組織の活性化手法として、
「ワールドカフェ」と「ストーリーテリング」を紹介しました。
44名の参加者の中で、両方体験したことがある人が1人いて、
その方に「ストーリーテリング」の体験談伺いました。
「ストーリーテリング」というのは(いろいろなやり方があるようですが)、
車座になって、順番に自分の人生を語っていくというもので、
チームビルディングや組織活性化で使われる手法です。
内容は何でも良く、
離婚したときの辛さを話してもいいし、
子育ての悩みを話してもいいし、
自分が幸福を感じることについて話してもかまいません。
なぜ、そんなことが組織に良い影響を与えるのでしょうか。
それは、それぞれがお互いの人生を知ることで、
一生懸命生きている生身の人間、等身大の人間に思えて、
それが大きなリスペクトを生み、価値観も分かるようになる。
そうなると、ぐっと距離が近く感じられるようになり、
信頼して話ができる関係になるからだと思います。
でも、組織の中でいきなりこれをやれと言われても、
抵抗を抱く人がいるのが普通です。
これをやると距離が近くなって、リスペクトが生まれると説明されても、
そう簡単に鎧を脱ぐ気になれませんよね。
で、なるほどと思ったのは、その方が語ったこんな話です。
「それは幹部向けのチームビルディングの場でした。
みんな慣れていないし、抵抗感はあったのですが、
ストーリーテリングを行う前に、こんな説明がありました。
それは、この方法はオバマ大統領が選挙で圧勝した時に、
チームビルディングに使った方法で、
これを行うことで、自分たちは勝てるチームになれる、と。
みんな勝ちたいと思っているから、やる気になって、
大成功に終わりました」
ただ漠然とチームビルディングを行うと説明しても、
こうはならなかったと思いますが、
オバマ大統領が実践して勝った方法と聞いて、期待感も現実感も持て、
自分たちへのリターンがイメージできたのだと思います。
そうすると人はエッジを超えられるものなんですね。
勉強になりました。
1日8時間も過ごす会社という場所。
そこで自分を飾らず、守らず、ありのままの自分でいられると、
人の幸福度数は上がりますよね。
まずはリーダーが自ら始める。大切なことだと思います。
HONESTな自分でいられますように! 今週も良い1週間を!
自分の影響力に気づく

先々週の金曜日から月曜日にかけて、
急に思い立って北海道に旅行に行ってきました。
小樽に2泊、札幌に1泊のショートトリップです。
小樽で運河沿いの道を散歩していると、1軒のライブハウスがありました。
時間が早かったので、夕食を食べたら来てみようと思い、
夜になって行ったのですが、残念ながら、貸し切りで入れません。
翌日、懲りずにもう一度その店を訪ね、
オーダーをする時に聞きました。
「ライブは何時からですか?」
すると、
「さっきリハーサルをしていたので、
多分やると思うんですが、私は聞かされていないので、
確かなことはわかりません」
え〜!! 考えられますか?
店長と彼は同じ空間で働いているのに、この回答!
結果的に大分待たされた後で演奏が始まりました。
でも、演奏の印象よりも、その時の店員さんの反応の方が
強く心に残っています。
彼はなぜあのように行動したのでしょう?
(1)彼には、自分の対処によって相手がどう感じるかの想像力がない。
(2)自分の応対に対し相手が不審に思おうが、どうでもいいと思っている。
(3)彼は、これまで何度もライブの予定を把握しようとしたのに、
店長が無視するうちに、把握する気がなくなった。
他にもあるかもしれませんし、実際のところはわかりません。
ですが、人の良さそうな印象から、私には原因が(1)であるように見えました。
彼は、自分が人に影響を与えていることに気づいていないのではないか、と。
しかし、、、、
偉そうなことを書いていますが、
じゃあ自分はどうなの?と自問してみると、、、
やっぱり想像できていないし、
あんなところでも、こんなところでも、
人に影響を与えているとは思えていません。
正確に言うと、こんなところで影響を与えているのはわかっていても、
あんなところでも影響を与えているとは気づいていない。そんな感じです。
それは、私や彼だけでなく、きっとあなたもそうなのではないでしょうか。
彼の例は対面ですし、ちょっと極端な例かもしれませんが、
直接接触しなくても、私たちは人に快/不快を感じさせる、
そんな影響力を持っています。
ここでいう影響力というのは、「大きなもの」ではありません。
むしろ「小さなもの」で頻繁に感じるものです。
具体例を挙げると、、、、
誰かが使った会議室のホワイトボードが使いっぱなしだったら、
次に使う人は気分が悪い。
しかし、これは誰もがたやすく理解できるわかりやすい事例です。
ところが、実際には人それぞれ気になることが違います。
それは大抵の場合、価値観の違いや慣習から来るものです。
たとえば、私は、
使い切ったトイレットペーパーがそのまま残っていると気になります。
反対に、カッターの刃を出したまま放置して、社員に叱られます。
また、朝出社して、ゴミ箱のゴミを社員の誰かが捨ててくれていて、
とても気持ちがよくなります。
(毎度、ありがとうと言っていなくて、ごめんなさい to スタッフ)
接触しないつながりの中で、誰かが私のすること、あなたのすることを見て、
気分が良くなったり、悪くなったりしている。
良くなってくれたらうれしいけれど、
知らないうちに不快にさせていたら、イヤですよね。
なので、今日はいつも想像しないことをちょっと想像してみる、
お互いに週の初めだから、そんなことをやってみましょう!
では、素敵な1週間をお過ごしください!
picture (c) Pixabay



