社長就任時、社員の心をつかむスピーチ・原稿の作成のポイント
新年度が近いためか、最近、「社長就任 メッセージ」という検索ワードから当サイトのこのブログを訪れる方たちが多いようです。検索結果に表示されているのは、下記のページ「社長就任時や新年度、社長メッセージでやってはいけない5つのこと」です。
https://www.grassroots.co.jp/blog/monolog/2012/04/120423.html
そこで、今日は、社長就任時のメッセージ発信において、社員の皆さんに対し、何をどう伝えるのが良いのか、社員は何を知りたいのかについて、考えたいと思います。ここでは「メッセージ」という言葉を用いていますが、これはスピーチでも原稿でも同じです。
メッセージとは何か
では、そもそも「メッセージ」とは何か。これを押さえずして、話が前に進まないので、この後を読んでいただくための共通言語、共通理解として、ここでは「メッセージとは、その人がその場で一番伝えたい思い」とさせていただきます。スピーチでも原稿でも、何かを発信する際に一番大切なのが、この「メッセージ」です。
一番伝えたい思いという以上、「メッセージ」はシンプルでなければなりません。人が記憶できるのは、極々短い言葉で言い表された概念です。誰しも、一度にたくさんのことを記憶として保持できません。皆さんも、たとえばセミナーに出て、それがどんなに有益であったとしても、覚えていられるのはせいぜい2割ではないでしょうか。だからまず、その前提に立つ必要があります。
したがって、相手に何を記憶してほしいのかという観点から、極めて短い言葉で整理することから始める必要があります。できればワンセンテンス、ワンフレーズ、ワンキーワードにまで落とし込めるとベストです。それを整理しないまま、あれも伝えよう、これも伝えようとすると、失敗します。どう失敗なのかといえば、何も心に残らない内容になります。
まずは「一番伝えたい思い」をシンプルに言語化する。これが鉄則です。
何をメッセージにすべきか
さて、ではどんなことを「メッセージ」にすべきなのでしょうか。これは必ずしも一概には言えませんが、新社長に対して多くの社員が知りたいのは、「会社をどっちの方向にもっていきたいのか」です。でも、そう捉えるとたくさんの切り口が出てきてしまい、選択しにくくなります。
「会社をどっちの方向にもっていきたいのか」という社員の疑問や興味は、こんなふうに言い換えることもできます。それは、「この人はいったい何を成し遂げたいのか」です。社員は、売上などの業績だとか、課題の克服などの話の前に、もっと骨太の話、どんな世界を築きたいのかを聞きたいのです。「子どもたちから、お父さんの会社、お母さんの会社はすごいねと言われる会社にしたい」でも良いし、「社員満足度ナンバーワンの企業にしたい」でも良いし、「当社がいないと困るという人で世の中をいっぱいにする」でも良いのです。こんな会社にしたい、こんな世の中にしたいという骨太の話をメッセージにする、それを社員は望んでいます。
どのような順で語るのか、気をつけるべき点とは?
その成し遂げたい思いを伝える流れと、そのチェックポイントを7つ挙げてみました。これは、私が考えたというよりも、スピーチ研究をされている方たちの知見を私なりに整理したものです。
流れを大きく言えば、次のようになります。
成し遂げたい思いが誕生するまで
↓
それが成し遂げられた後、どうなるか
↓
それを成し遂げるまでの道のり
7つのチェックポイント
■成し遂げたい思いが誕生するまで
①「なぜ」「なにを」がわかりやすいか
(何を成し遂げたいのか、なぜ成し遂げたいのか)
②「思い」がしっかり語られているか
(自分の人生経験と関連づけて語られていることが大切)
③過去または現在の困難と困難を乗り越えて来た事実
(できるという信念の源として、自社や自身の困難克服の歴史、体験を語る)
■それが成し遂げられた後
④成し遂げたときの情景が「そうなればいいなぁ」とイメージできるか
(シーン自体やシーンが浮かぶような比喩)
⑤現場で何が変わるか、イメージできるように語られているか
(自分たちには何が求められるかという社員の不安に応える)
■それを成し遂げるまでの道のり
⑥困難があるという自覚が織り込まれているか
(単なる夢物語に聞こえないために、覚悟を語る)
⑦強い信念が感じられるか
(何としてもそちらに向かうという強い決意の表明)
最後に、あなたがもし社長のスタッフとしてメッセージ原稿の素案を作る立場にあるのなら、次の3点に配慮することをお勧めします。
・「成し遂げたいこと」というのは実は「ビジョン」と言っても過言ではありません。しかし、ビジョンという言葉を使うと、社長は身構えてしまいます。言葉のイメージに惑わされないようにするためにも、「成し遂げたいこと」「志」というような言葉で会話する方が良いと思います。
・もっともらしくまとめることだけは避ける。それふうにまとめられたものは、社員の皆さんは簡単に察知します。ハートや温度が感じられることが重要です。
・各事業部が柱に掲げていることを、社長の言葉にまとめるというパターンも見受けられますが、これも避けたいものです。
社長就任挨拶は、いってみればデビュー戦です。ここでインパクトのあるデビューを飾れないと、挽回に時間がかかります。「メッセージ」をシンプルに絞り込んで、社員の皆さんが希望を抱けるような発信にしていただきたいと思います。
映画「LIFE!」〜スローガンが言えないボスはナシでしょ?
週末、ベン・スティラー 監督作品、映画「LIFE!」を観ました。映画.comの評価では、星3.8。レビューを読むと、賛否両論です。
内容は、伝統的フォトグラフ雑誌「LIFE」が休刊する時期に、ネガフィルム管理部門という、どちらかといえば縁の下の力持ち的な地味な部門に務める主人公(42歳)が、リストラされながらも、人生を変えていくというようなストーリーです。会社から休刊が告げられた最後の号で、表紙の写真のネガが紛失する…という事態に陥った主人公が写真を撮ったカメラマンを捜すための旅に出る、そんなロードムービー的な色彩のある映画でした。旅する先は、グリーンランド、アイスランド、ヒマラヤなど。しかも、そんなことするわけない!というような突拍子もないことをしながら、映画は半ばコメディタッチに進んでいきました。(けど、主人公が若かりし頃にやっていたスケートボードで壮大な自然の中を進む姿は、本当に壮快でした!)
賛否両論のネットレビューで、評価する人たちの多くは、「平凡で地味な主人公が変わっていく姿に、一歩足を踏み出す勇気をもらった」というようなものが主流を占めている印象でした。一方で、イマイチだと評する人たちのコメントで多いのは、「深みがない」というもの。だから、物足りないという主張です。
どちらの感想にも一理あると思いますが、私のココロに残ったのは、もう少し別のことでした。仕事柄かもしれません。
ネタバレにならないように注意して書きますね。
主人公とカメラマンは、会ったことがない関係です。でも、信頼の絆、無言の絆で結ばれていました。カメラマンは主人公のような裏方の仕事をする人たちがいるから、自分の仕事が成り立っているということをわかっていて、休刊を機に、感謝のメッセージを伝えようとする。(ある意味、それが仇となるのですが…)
でも、映画の中では、主人公は自信のない冴えない感じのオジサンとして描かれていて、本人も、本当はこだわりを持って仕事をしてきたのに、自分の人生なんて大したことはない…と、そんなふうに思い込んでいます。16年も、しかもLIFEが好きで誇りを持って仕事をしてきたのに、本人にその自覚がないんですね。人は、目立たない仕事をし、際立った評価がないと、いつしか「大したことのない自分」という像に甘んじてしまうものなのかもしれません。
現実世界では、仕事の8割9割は目立たない仕事だし、仕事なんだからやるのが当たり前で、いつもいつも誉められるなんてことはありません。だから、自分で自分を誉めてあげないといけないのに、主人公は(その方が普通かもしれませんが)自分を誉めずに気づくと入社から16年が経っていたわけです。
で、カメラマンを捜す旅に出た主人公は、最後には自信を取り戻し、堂々とした人物に変わっています。最後に小気味のいい台詞がありました。それは、リストラ後の新体制におけるリーダー(イヤな感じのやつ!)に向けられた発言でした。「あんたはLIFEのスローガンを言えるか?」と挑発的に聞いたのです。お約束的な展開ではありますけど、悪役リーダーは言えないんですね〜(ま、コメディタッチの映画なので、ボスが答えたスローガンはマクドナルドのものだったりするわけです)。
LIFEのスローガンは、
「世界を見よう、危険でも立ち向かおう。それが人生の目的だから」
でした。それが好きで、主人公は入社していました。
そして、それを思い出して、放浪するカメラマンを探す旅に出かけるのですね。スローガンが好きで入社する。これってスゴくないですか? ワタシはスゴイと思います。しかも、最後にそこに戻ってくる。なぜなら、それが主人公にとっての原点だったからです。それも、スゴイと思います。
人の心を揺さぶる「スローガン」という言葉がある。
それは真実だと思います。
であるからこそ、「スローガン」に関わる責任も重いですね。
その一端を担う仕事をしているんだなと、身を引き締めました。
さて、この映画からワタシが得た教訓は、
・人から誉められるのを待つのではなく、もっと自分で自分を誉めよう!
・きっと誰かが見ている(お天道様かもしれないが…)
・改めて、、、言葉をあなどるな
の3点です。
「LIFE」の休刊の道のりには、経営者として別の学びもあります。「変われないと、淘汰される」と。歴史の貴重な記録を残し、数々の著名カメラマンを輩出した「LIFE」。今は、Googleのイメージ検索で「LIFE」の写真アーカイブが検索可能になっています。
ウソはなぜいけないの?
先月は聴覚障害疑惑とゴーストライター問題で佐村河内氏がウソを謝罪し、今月はSTAP細胞で話題を呼んだ小保方氏に対して疑義が生じています。いずれも実態がどうであったのかはさておき、「倫理」というものに対し、社会の関心が急激に高まったのは事実ではないでしょうか。先週のニュースサイトのランキングでは小保方さん関連のニュースが上位の大半を占めたそうです。
週末、高校時代の部活のOG会があり、久しぶりに集まったのですが、話はあっちに行き、こっちに行きしながら、途中で小保方さんの件が話題に上りました。同情派もいれば、やっぱりマズいよねという人もいれば、理化学研究所の責任問題を語る人も。
それで、ふと「倫理」って、そもそも何だろう? なぜウソをついてはいけないんだろう?という疑問がわいてきました。確かに、子どもの時に、「ウソをついてはいけない」と教わります。ウソをつくと、針千本飲まされるほど、ウソは悪いことだ、と。もちろん、感覚として人を騙すのは悪いことだとわかっていますが、なぜ?と考えたことはありません。
誰もが知っているイソップ童話「狼と羊飼い(オオカミ少年)」にあるように、「オオカミだ!オオカミだ!」と言っていると、やがて信じてもらえなくなるから、と説明するのは簡単ですが、その説明では「別に誰にも信じてもらえなくてもいい」という人には通用しませんよね。
ウソには、「人のため」につくウソと、「自分のため」につくウソがあるそうです。
O・ヘンリーの「最後の一葉」は前者の代表格ですよね。
自分のためにつくウソは、さらに2種類に分かれていて、1つは自分を守るために「自分を騙す」ウソ、もう1つは自分の欲求(利益を得たい、恐れから逃れたい等)を満たすために「人を騙す」ウソだそうです。「別に愛されなくたっていいもん」と自分に思わせるのは前者ですね。反対に、オレオレ詐欺も、佐村河内氏のウソも、食品偽装表示も後者に入りそうです。
ということは、「針千本飲まされる」と教えられてきたウソというのは、「自分のために人を騙すウソ」ですね。そうしたウソはいけないと、モーゼの時代から暗黙裏に社会で合意されているのは、おそらくウソを是とした社会と非とした社会を比べた時に、非とした社会の方が明らかに暮らしやすいから、、、なのかもしれません。騙してもOK、騙される方が悪いという価値観の社会だと、年がら年中、騙されはしないかとびくびくし合ってしまい、暮らしやすいはずはありませんから。疑義が生じると社会から叩かれるのも、そうした暗黙のルールが存在しているからにほかなりません。
一方で、海外旅行などに行った時には、騙し合いは当たり前という文化に接することもありますし、日本でも後からいいがかりをつけてお金を払わない、といった商売をしている企業や、労働条件でウソを言うブラック企業もあると聞きますから、そんなにきれいごとでは済みません。
ところで、自分のために自分を騙すウソは、どうなんでしょう? 誰にも迷惑をかけていないですし、罪はないような気がしますが、よくよく考えてみると、周りの人をがっかりさせたり、さみしい気持ちにさせることはありますね。失恋した親友から「あんな男の一人や二人、こっちから別れてやる」と聞かされたとしたら…? 強がっているのがわかりすぎて、ワタシなら寂しいな。ワタシを信頼してくれていたら、本当の悲しみを話してくれるはず…と思うから。でも、ワタシにもあります。本当は「いいもん」とスネているのに、それに気づけないこと、あるいは気づいているのに言えないことが。
ウソの心理。奥が深そうですね。
メルマガに対する読者の皆さんからの反応は?
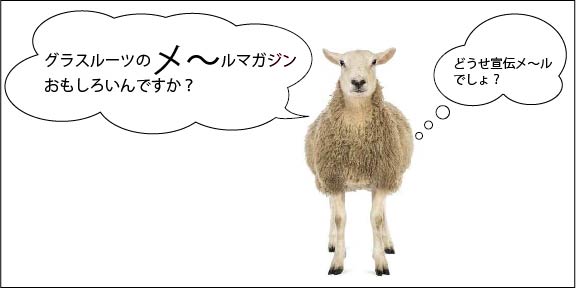
こんにちは。オノです。
グラスーツのメルマガっておもしろいの?
今日は、そんなふうに思っている方のために、どんなメルマガで、どんな反響があるのか、ご紹介します。というのは、現在、当社のメルマガページでは、あまり「どんな」について紹介していないからです。不親切ですみません!
読んでいらっしゃらない方のために、簡単にメルマガの概要を紹介しますと、「組織のベクトル合わせ」「組織内コミュニケーションの活性化」「風土づくり」といったことを考える立場にある方に対して、「視点発見の旅」というコンセプトで日常生活の身近な話題をお届けしています。
メルマガ発行開始からの9カ月を振り返って、ワタシが一番感動したのは、読んでくださっている方たちからコメントを返していただける、ということ。それは、場合によっては、「ですよね!」とか、「読んだよ!」だけの場合もありますし、「こういうことを思い出した」「自分はこうしたいと思った」「勇気をもらった」「我が身を振り返って痛いと感じた」などの感想の場合もあります。
また、当社のメルマガには文章の最後に「読んだよ!」ボタンが付いています。クリックすると、その先に「言葉の贈り物」が書かれています。取り上げているのは、著名人の言葉や名台詞などです。
これまでに取り上げたのは、スティーブ・ジョブズ、田中将大、北野タケシ、マイケル・ジャクソン、ネルソン・マンデラ、アンジェリーナ・ジョリー、ドラえもん、スティーブン・R・コヴィー、ジョン・レノン等々。。。この「言葉の贈り物」は評判が良く、反響の中にはメルマガへの感想と合わせて、このコーナーへの感想も寄せられます。
これまでにいただいた感想の中からピックアップしていくつかをご紹介します。
●言葉のチカラ
HONDAユーザーの私ですが、「負けるもんか」、知りませんでした。とてもいいですね。
●心の中のカメラのピント
私の母も耳が遠くなっているので、他人ごとではありませんでした。ピントを合わせて集中する。人の五感って、そういう風にできているのかもしれませんね。ありがとうございました。
●あなたの発想は言葉で変わる
言葉って本当に大事ですよね。私が影響を受けたのは、下記の言葉です。前職のとある上司から聞いたもので、それ以来ずっとPCのデスクトップにメモの形で置いています。出所はその方もまた聞きでわからないそうです。(略)
●「勝つ」ってなに?
つい映画の「INVICTUS」を思い出しました。ラグビーワールドカップ勝利のシーンは感動的でしたね。ビジネスの場合エンドレスな競争なので、「勝つ」は、私の感覚ですと、「得点」し続ける感覚に近いような気がします。それが「顧客づくり」とか「受注」という言葉だったり。ある時点で勝っても相手は必ず巻き返しにきますので。
●嫌いだと認める
今回の言葉の力も さすがです!!ついつい嫌なことを後回しにしてしまったり・・・。しかし、トライしてみると、思ったほど嫌ではなかったり。今回の言葉通り、まずトライ!!とても日常に共感いたしました。
さらにご覧になりたい方は、こちらのページをご覧ください。
バックナンバーは、そのうちpdfにしてダウンロードできるようにしたいと思いますが、ここでは、タイトルのみ紹介させていただきますね。
- 視点発見の旅へ、ごいっしょに!
- ブラジルサッカーの強さの秘密は「型破り?」
- アイデアマンになる必要はない!
- 逃避する脳、自分の記憶は正しくない
- 「感情」に働きかけると社内報は変わる
- 「〜について紹介します」では人は振り向かない
- 大谷選手のような「できる」発想になったなら?
- 「お笑い係」が組織を救う?
- 「わからない」と言える強さ
- 家政婦の日
- 出戻り率が高いって…?
- ハーバード式ダイエット術の生かし方
- 音が苦(おんがく)
- その色が好きなのはなぜ?
- やっぱり、楽天家?
- その言葉の解釈、一致していますか?
- そのルール、何のため?
- 言葉のチカラ
- 本当に届く「ありがとう」
- 「反応」のモチベート機能
- 花売り娘をレディにするには?
- 塀のペンキ塗りはつまらない?
- みんな自己チュー
- ヤクルトの外国人選手はなぜ活躍できるか?
- 情報発信の達人になるには…?
- 旬の鮮魚一箱は、ぜったいに喜ばれるはず?
- 「やめればいいんですか?」
- 心の中のカメラのピント
- あなたは山羊座ではなく射手座です
- 紙鉄砲を鳴らすと、うまくなるものは?
- 「奥手」だっていいじゃないか! &同志募集!
- あなたの発想は言葉で変わる
- あくび、うつりますよね
- 「見た目」の力
- 論評されているトイレの張り紙
- ブレない力
- 「勝つ」ってなあに?
- マシュマロからビスケットへ
- ロジカルシンキングとギャンブルの不思議な関係
- 負けても相手を褒められますか?
- ハンサムウーマンに憧れていましたが…。
- どう書きますか? 読書感想文
- ズレていてもヨシ! 来年やってみたいこと
- サンタクロースって、いるんでしょうか?
- 「耕」2014年を漢字一文字で表すと?
- 世界一になるには
- アンパンマンのテーマ曲の歌詞、深すぎます
- 嫌いだと認める
- 「本気」と「遊び」のバランス〜決意とのつきあい方
- 荒れた学級を救ったものとは?
- 言わせる力、言う力
- 「友チョコ」世代に期待!
- オリンピックは女子アイスホッケーに注目!
- 最初の一歩
- ありゃりゃ、失敗
- ふとんで寝なさい
- スーパープレーヤー集団の苦悩
- めざせ!「フロー状態」
- ルール? それとも約束事?
- 何事も整理のコツは「選んでから、収める」
- びんた
タイトルを読むだけですと、ビジネスメルマガには思えませんよね。実際に、その中身はビジネスビジネスしたものではありません。日常生活の中から、「でも、これってどこかでビジネスにも通じるな」というようなことを紹介しています。
何より楽しいのは、読んだ方の心の中で化学反応が起きて、その方のフィルターを通じて別のコンセプトが生み出されているような感覚があること。恊働作業をしているわけではないのに、どこかでコラボ感覚があることです。
お読みいただいている皆さん、本当にありがとうございます。
引き続き「視点発見の旅〜【開-CAY】」をよろしくお願いいたします。
* * *
写真© Eric Isselée - Fotolia.com
「軍師官兵衛」を観ながら、「参謀」の本質、考えました
NHKの大河ドラマ「軍師官兵衛」をご覧になっていますか? ソチ五輪も影響してか、視聴率が思うように伸びていないそうですね。でも、ワタシは岡田准一さん扮する官兵衛のドラマ、毎週楽しみに見ています。
ドラマが今どの辺まで進んでいるかといえば、官兵衛が仕える主君・小寺政職に対して織田信長に味方するよう進言し、なおかつ播磨のライバル家と共に信長に拝謁することを勧め、それが実現した。それが昨日の日曜日の内容でした。このあと、恐らくは信長・秀吉ラインで取り立てられ、その後、秀吉の参謀として能力を発揮していく…そんなドラマが待っているのだろうと想像しています。
で、今日のブログでは、まだ始まって2カ月しか経っていないこのドラマを見ながら、ワタシが感じたことを書きます。
それは、「参謀」の本質について。
参謀だから進言したのか、進言したから参謀となったのか、という問いです。
これは、かなり深い問いですよね。皆さんは、どう考えますか? ワタシ意見は、進言したから本物の参謀に上り詰めたのだと思っています。昔も今も、上司に物申すのは勇気がいります。今でこそ、生死がかかることはありませんが、昔は生死がかかっていました。生死をかけて、物申す。今の時代では想像を絶する勇気が必要だったと思います。でも、それをしたから、参謀として信頼されたのもまた事実ではないでしょうか。
戦乱の世も、今の世も、おそらく上司はわかっているのです。自分の顔色を見ている輩か、そうでないか。そして、顔色なんか読まれたくないと思っている。だから、信念に基づき発言する人を信頼する。人間として、自然なことだと思います。
けれど、ここで別の問題があります。
相手が上司であろうと、誰であろうと、考えを整理して意見を言うことに私たちは慣れていないのです。だから、本当は信頼される参謀になりたいと思っていても、それができないという人は多いのではないでしょうか。
つまり、参謀であるためには2つの力が必要です。
1)ヒエラルキーにとらわれず、信念に基づき発言する勇気
2)自分の考えを整理して、意見にまとめる能力
1番は気構えや覚悟で何とかなります。
でも、2番は直感と論理を統合する力と言っても過言ではありません。そして、これはそれほど簡単ではありません。
ところが、「参謀でありたい」という気持ちがあるのに、うまく行かない時、欲求と現実のギャップの間に何があるのかは案外わかりにくいですね。つまり、自分が1番でつまずいているのか、2番でつまずいているのかを把握する必要があります。でないと、間違った方向に頑張ってしまったりしますから。
当社でも、お客様の参謀であろうという心意気を重んじていますし、社内でも思ったことを言い合える風土というのを重んじています。でも、実際にはそれほど単純ではなく、理想の行動をするには壁を乗り越えないといけない場合があります。そして、そのためには、1番と2番のどちらがハードルになっているのか(両方の場合もありますが)、切り分けないことには、次に進めません。
自分の現在地を確認するためにお勧めな方法があります。それは、意見ではなく、感想を率直に言えているかどうか。
意見を言うには、考えをまとめる必要がありますが、感想を言うのは、その必要はありません。ネガティブな感想を抱いた時に、それを言えたか、言えなかったかで、自分の現在地がわかります。感想を言うのに、飲み込んでしまったことがあったなら、恐らくはどこかで反感を買いたくないという心理が働いています。
であるなら、まずはそれと格闘して、取り除かないとね。人に良く思われたいとか、嫌われたくないという心理は誰にもあります。もちろん、ワタシにだって、ありますよ! でも、それに支配されたくはありませんね。だって、それはやっぱり失礼だと思うから。相手を尊重していれば、正面から向き合って逃げないこと、必要ですよね。



