スタッフから薦められた本3冊
こんにちは。先週、宣伝会議主催のインナー広報セミナーが終わって、少し腑抜けな感じのオノです。腑抜けになったには理由があって、コンテンツの準備に結構な時間を費やしたからです。でも、おかげさまで多くの方から「有意義だった」「実務で役立つ」というコメントをいただき、お役に立てたなら…と、ワタシもハッピーな気分です。10月の【開-CAY】セミナーは同じ内容で開催しますので、宣伝会議セミナーに参加できなかった方は、こちらでキャッチアップしてくださいね!
さて、今日は本の紹介です。といっても、読み終わったばかりの本もあれば、これから読む本もあります。どれもみんな、うちのスタッフから薦められた本になります。
 「6分間文章術」(著・中野巧/刊・ダイヤモンド社)
「6分間文章術」(著・中野巧/刊・ダイヤモンド社)
メルマガを共に書いている阿部貢己が薦めてくれた本です。ワタシがセミナーで話している内容とも重なる内容で、共感します。
「文章が苦手な人は、文章の内容を考えながら、文章構成にも気を配り、表現豊かな文章を書くことを、すべて同時にやろうとします。」とあり、そのプロセスを分解した方法論が紹介されています。しかも、相手の気持を考えるということが、さりげなくそのフローに盛り込まれています。6分間でできるかというと、それはちょっと誇張表現だと思いますが、枝葉末節的なことよりも、幹が重要だという観点からすると、幹を理解するのに役立つ本だと言えます。それだけ良いことを伝えようとしている本なのですが、全体的に少しメソッドに偏りすぎている面があり、それが少々残念です。本来の著者の視点である「共感は、相手の気持ちに目を向けてこそ」という思いの部分、もう少し読みたかったかな〜 でも、従来の文章作法の本とは異なり文章を書くという行為をフレームワークに落とし込んだ画期的な本と言っても過言ではないでしょう。これは週末読んだばかりの本で、おすすめできます。
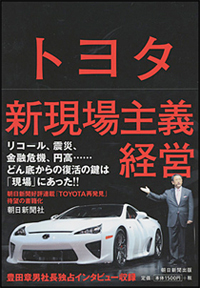 「トヨタ新現場主義経営」(著・朝日新聞/刊・朝日新聞出版)
「トヨタ新現場主義経営」(著・朝日新聞/刊・朝日新聞出版)
これはアサヒビール様の社内報「HOP!」を担当する大吉紗央里が薦めてくれた本。「HOP!」の1コーナーに「あの会社のコレが気になる」というタイトルで該当部門の担当者が他社の同部門を取材するというコーナーがあるのですが、彼女がこの本を読んだのは、最近トヨタ社を取り上げたために、その準備としてだったようです。
実は、ワタシが二十歳で免許取り立ての頃、最初に乗ったクルマはトヨタでしたが、30代の頃に抱いていたトヨタへのイメージというものは、安全への信頼性は高いものの、保守的すぎて今ひとつ面白みのないクルマというものでした。ところが! 今現在どう感じているかといえば、「目指せ、トヨタ!」なのです。保守的どころか、今は、革新的だとさえ思っています。実際に大吉が取材をさせていただいた際に、思想の浸透ぶりが半端じゃないと感じたとか。大吉は、ワタシが今、トヨタ的な経営を目指していることを知っているので、それもあってこの本を薦めてくれたのだと思います。読むのが楽しみです。
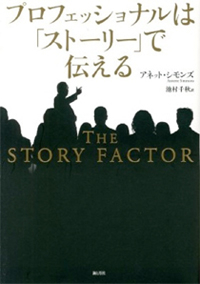 「プロフェッショナルは『ストーリー』で伝える」(著・アネット・シモンズ/刊・海と月社)
「プロフェッショナルは『ストーリー』で伝える」(著・アネット・シモンズ/刊・海と月社)
これは、毎朝カフェで本を読んでいる読書家・薮内久美子がひと月ほど前に薦めてくれた本なのですが、同時に前出阿部貢己からも最近薦められた本です。やっぱり同じ会社で仕事をしていると、志向や関心が似てくるのでしょうか。ある意味、素敵なことです。でも、残念ながら、ワタシはまだ読めていません。だから、詳しい内容やその内容からワタシが考えたことを今はまだ語れません。でも、なぜこの本に興味を持つかと言えば、やっぱり相手の「心」ありきという本に思えるからです。「はじめに」にこんなことが書かれています。「あなたが人を動かせるかどうかは、あなたがなにを言うかではなく、どのように語るか、そして、あなたがどういう人間かにかかっている」と。そして、第1章では、聞き手に心の扉を開いてもらうには、「私は何者か」「私はなぜこの場にいるのか」というストーリーをまずは語らなければいけない、とあります。この本のみならず、実は同様のことをいろいろな専門家が語っています。だからこそ、それをさらに細かく紐解いた本書にワタシは興味を持ち、読みたいと思っています。
以上、ワタシ&スタッフが参考になると思っている本の紹介でした!
私たちの興味は「伝える」ではなく、「いかに『伝わる』コンテンツにするか」です。そういうことに共感していただける方は、ぜひ10月17日(木)【開-CAY】のセミナーへ、どうぞ!
…と、最後に営業! もちろん、シャチョーですから!
では、素敵な1週間を!
宣伝会議セミナーの「メイキング」
こんにちは、オノです。
明日は、いよいよ宣伝会議さん主催の「インナー広報セミナー」に登壇させていただきます。
http://www.sendenkaigi.com/class/detail/inner_communication.php
今日は、その「メイキング」について(といえば聞こえがいいですが)、舞台裏のこんな話、あんな話を少しだけご披露させていただきます!
ワタシの他に登壇するのは、サイボウズ様や「ZOZOTOWN」の株式会社スタートトゥデイ様など、主に企業サイドの事例紹介を行う方たちで、ワタシが受け持つパートは、社内広報の「いろは」的なこと、全体で6時間半の中の4時間を受け持つのですが、改めてこういう時間配分なのかと思うと、責任の重さをより一層ひしひしと感じますね。
セミナー内容の細かいことは、ある意味お任せなのですが、「いろは」っていったいなんだよ?と、神経質に考えれば自問してしまう、そんなお役目。でも、とにかく普段から大切にしたいと思っていること、共感してくれる人を増やしたいと思っていることを話すことにしました。
それは、「組織は感情で動く」ということ。あ、これがセミナーの総タイトルです。サブタイトルは「社内広報の問題解決力は感情分析で決まる!」。
メイキング的な意味で披露したいことが、1点。通常、セミナーコンテンツをつくるのに、模擬までは行わない場合が多いと思うのですが、当社ではそれを行っています。ワークショップも含めて模擬を行ってみて、ダメ出しを受けて、改善する。そんなことを行っています。社長のワタシが、社員からダメ出しされるって、どう思います? いや、正確にいえば、これはネガティブフィードバックであって、ダメ出しではないんですね。どんな声に耳を傾けるかは、ワタシ次第です。必要だから行っているにもかかわらず、でも…。これ、正直案外キツイ。
なぜかといえば、たまたま今回は模擬を行ったのが1週間前でした。そこで、いろんな意見が出るわ出るわ。。。大手術は必要ないという意見もありましたが、もっともな意見もたくさんあって、結局全体の半分近くを見直すことにしました。
で、ここで自問してみました。「大手術は必要なかったかもしれないのに、こんなギリギリになって、なぜあえて大手術を行ったのか」と。
ワタシは実は完璧主義者なのでしょうか? あまりピンときませんが、理想主義者ではあるのかもしれません。
で、いろいろ考えてみた結果…。参加者の表情が「花開く」かのように見える瞬間があって、多分それを求めているんだろうと思います。逆にいえば、その反対の状況がもし起こったとしたら、相当苦痛なのです。反対の状況とは、目がどんよりしていたり、額にクエスチョンマークが見えたり、です。
「花開く」瞬間を求めて、あるいはその反対がイヤで、ギリギリまで粘ろうと思ってしまうんですね。これはもう、サガかな。
さて、リアルセミナーの難しさはコンテンツそれ自体もありますが、ワタシが一番難儀に思うのは、「時間」です。余ってしまってもいけないし、足りなくなってもいけない。で、一方的なレクチャーなら時間もコントロールしやすいのですが、今回のセミナーは、長いうえに、ワークショップがあります。不確定要素、予測不能要素が大きい分、スピーカーとしては緊張感が高いセミナーなのですね。
それでも、こういうセミナーを今後も引き受けたい理由は、あの「花開いた表情」を見たいからなんです。これも、サガですね〜
とにかく…。直前に大手術を行いました。それは、ワタシが理想とするセミナー像があるからです。結果、吉と出るか、凶とでるかはわかりません。もはやそれは神のみぞ知る。ワタシはベストを尽くしたし、今夜はすやすや寝るだけです。
20代30代は「ひよっこ」ではない
こんなことを考えられるようになるなんて、ずいぶん自分が大人になったな〜と思う瞬間があります。そのひとつをご紹介すると…。
最近、自分のために生きるのではなく(イヤ、もちろん人生は自分のために生きるのですが)、若い世代のことを考えられるようになること、そのために生きられるようになること、それができてナンボなのでは? そんな自問としばしば向き合います。「若い世代のことを考える」とは、自分より若い世代(主に20代、30代)に対して、自分に何ができるのか、何を引き継げるかを考えることです。
ワタシがそう考えるのは、自分が26歳で独立し、20〜30代だった頃に、年上の40〜50代の方たちから盛り立てていただいたからです。だから、上の世代への恩返しは、むしろ下の世代に対して「自分に何ができるか」と考えることではないかと。
世の中には、20代30代を「ひよっこ」扱いする大人がいます。でも、20代30代をあなどってはいけません。たとえば、坂本龍馬が船中八策をまとめたのは、31歳です。明治維新を推進した顔ぶれも同様に若かったですよね。まあ、「そんな昔の話をされても…」と思われるかもしれませんが。
現代にも逸話はあります。たとえば…。
伝聞によれば、ソフトバンクの孫さんが起業するか、しないかの頃、マクドナルドの創業社長である故・藤田田さんを訪ねたそうです。なんの縁もゆかりもない無名の若者である孫さんからアポを申し込まれて、会おうと思った藤田さんの懐の深さ。藤田さんに会ってみようと思わせた孫さんのプレゼン能力。両方がかみ合ってのことですが、ワタシが今、ここで話したいのは藤田さんサイドの目線の話です。ワタシが想像するに、藤田さんは若い世代に期待していたのだと思います。おそらくご自身が20代で「藤田商店」を創業したという影響もあるでしょうね。もし、20代30代はまだ「ひよっこ」と藤田さんが決めつけていたら、どんなに孫さんにプレゼン能力があったとしても、恐らく面談は成立しなかったでしょう。
「ひよっこではない!」と思っている20代30代に、ワタシが引き継げることは何なのか? その答えは多分先輩たちがワタシに示してくれたことにあるのだと思います。当時のワタシは、「ワタシを買ってくれた。だから頼まれた」と思っていました。でも、実はそうではなく、チャンスをくれたんですね。クライアントからワタシに向けられた「どうしたらいいだろう?」という問いは、実は相談ではなく「あなたに託すよ、やってみろ」だったんだろうな、と。そして、今にして思えば、20代のワタシに任せた相手は少々心配だったのではないかと想像します。
諸先輩がワタシに与えてくれた機会と同じようなチャンスを、若い世代に与えられるような存在になりたいものです。がんばれ!自分!
祝・東京五輪2020〜プレゼンの素晴らしさ
東京オリンピック2020、決定しましたね! 東京でオリンピックが開催されること自体にとても興奮しましたが、IOCでのオールジャパンのプレゼンテーションの素晴らしさにも本当に感動しました。テレビだけでなく、YouTubeも含めて何度も見てしまいました。また、プレゼンに出なかった方たちのロビー活動にも想像を越えた努力があったはずで、心から敬意を表したいと思います。
プレゼンを見ていて、特に感動したのは次の2点です。
第一は、プレゼンテーションを担う一人一人が、自分の持ち味を生かしながら、しかも、戦略的に役割分担がなされていて、何をメッセージとするべきか、その絞り込みと表現がチームとして素晴らしかった。被災支援への感謝、おもてなし、スポーツの力、オリンピック精神、レガシー(遺産)、インフラ等々。もちろん話す人が個人で考えたのではなく、練り込まれた結果であることは間違いありません。
聞き手の心理を周到に分析し、限られた時間の中で何を語るべきか、どう語るべきか、相当に吟味されたはずです。
第二は、プレゼンに向けて、その裏では血と汗がにじむようなトレーニングがあったはずだということです。それは、当初はあまり上手だとは言えなかった猪瀬知事のプレゼンに代表されます。プレッシャーを乗り越えて、素晴らしいパフォーマンスを見せた彼らの努力に、感謝と拍手を贈りたいと思います。また、日本人が抱いていた自国民へのイメージ、それは「あー、うー、もごもご…」というものであったり、シャイであったり、表情に乏しかったり…。それが、今回のプレゼンを通じて、みごとに払拭されたのではないでしょうか。笑顔で、堂々としていて、それ自体を誇らしく感じた人は多いと思います。
これは、個人でいうところのセルフイメージを変えるのと同じで、日本人の一人一人の「日本人である私」というイメージを変えた画期的な出来事だったのではないかと思います。そして、これはスポーツの世界で日本人が金メダルを取る過程に似ています。誰かががメダルを取ると、萎縮から抜け出し、人が後に続くというような。
これらの2点はビジネスでのコミュニケーションでも役に立つもの。大いに参考にしたい事柄です。
最後に、福島の原発問題について、安倍さんに本当にあそこまで言えるの?と懸念を感じた人も多いのではないでしょうか。実は、率直に言って、ワタシもそう思って、逆に心配になりました。また地震が起きるかもしれない、そうしたらどうなるのか…とか。でも、その後、いろいろ考えてみて、リーダーは「断固やる」という意思を示してこそリーダーであるのかもしれないと思い直しました。ある意味、安倍さんは負ったのです。その真剣さを信じたいと思います。
7年はおそらくあっという間でしょう。東京に暮らす私たち一人一人が、世界の人々に感嘆してもらえるような「お・も・て・な・し」を体現するオリンピックにしたいものですね。
なぜ社内報は「〜ついて型」に陥りやすいのか?
月が明けて、もう9月。。。今年もまもなく4分の3が終わってしまうのかと思うと、時の早さに驚くばかりです。そんな焦るワタシを癒してくれるのは、竹内まりやの「人生の扉」という曲。とても良い詩です。
さて、「ER」という言葉をご存知ですか?
圧倒的に多くの方はテレビドラマ「ER-緊急救命室」を思い浮かべるのではないでしょうか。PR、IR…ときて、ER! これがヒントです。エンプロイー・リレーションズ(Employee Relations)ですね。
元々は、Employer - Employee(経営層-従業員)の間の信頼関係を築くと同時に、従業員のモチベーションを高めるためのコミュニケーション活動を指したのだと思いますが、従業員と部門、部門と部門、従業員と社会の間の関係作り支援を含めた活動を含んでいるととらえる方が、ワタシとしてはしっくり来ます。
でも、残念ながら、「ER」という言葉を知っている人はとても少ない。「ER」以前に、「PR」という言葉の「R」が「Relations」から来ていることを知っている人も、昔より増えたとはいえ、世の中全体を見たら少ないような気がします。
では、日本語で最もよく使われている言葉といえば…? PR→広報、ER→社内広報ではないでしょうか。PRが広報で、ERが社内広報だったとしても、どっちでもいいじゃないかと思われるかもしれません。実際、言葉自体はどっちでも良いのですが、ワタシは、「報」という一文字が含まれているために、広報部や社内広報担当者の皆さんの気持ちを惑わせてしまっているのでは?と考えています。
「報」は、報道の「報」。
goo辞典で「報道」という言葉を調べると、次のように書かれています。
(1)告げ知らせること。また、その内容。
(2)新聞・ラジオ・テレビなどを通して、社会の出来事などを広く一般に知らせること。また、その知らせ。ニュース。
「報」という一文字があるために、多くの社内報コンテンツが「〜について紹介します」「〜について語っていただきます」というパターンに陥っているのではないか、と考えています。ワタシはこれを「ついて型」と呼んでいます。
業界の重鎮である福西七重さんが書かれた「もっと冒険する社内報」のタイトルのように、「〜について紹介します」というパターンから抜け出て、もっと冒険する社内報が増えれば、企業も人も元気になる。そんなふうに思えてなりません。
え? 「〜について紹介します」というパターンではない社内報ってどんなものか? それは、いくらでも考えられます。社内報版プロジェクトX、社内報版自己啓発書、社内報版徹子の部屋…。社内報にはたくさんの可能性がありますよ!
(追伸)
社内報の企画セミナーを定期的に開催しています。ご興味がある方は、こちらをご覧ください。



