変化させるエネルギーと継続させるエネルギー
7月末を境に、ワタシの周りでは、なぜか環境が変わる人、チャレンジを始める人が多いのです。そんな人たちを見ていると、(きっと当人に言わせれば不安はあるのでしょうが)、応援したいなとか、負けずにワタシも進んでいこうとか、そんなことを考えます。
思うのですが、人が充実した人生を送るには、2つのエネルギーが必要なのではないかと思います。一見矛盾するようですが、1つは「変化させるエネルギー」、もう1つは「継続させるエネルギー」です。どちらも、滅茶、パワーが必要ですよね。
「変化させる」を阻む「不安」と「時間のやりくり」
変化させるエネルギーを阻むのは、大抵の場合、「不安」でしょうか。変化させるということは、変化させないのに比べて、明日のことが見えにくくなります。明日が見えないと、人は不安になるものなのでしょう。変化させない方が安心…なんてことは、ないはずなのに、昨日の続きとして見えている道がある方が、安心を抱く生き物のようです。
変化させるには、「時間」のやりくりでもエネルギーを使います。ワタシは、不安耐性はあるのですが、こちらが苦手です。恐らく、優先順位を決めて、割り切ることが苦手なのだと思います。でも、当然ですが、それでも諦めたりしません。たとえ、カメのような歩みだったとしても、駒を進めていこうと思いますし、どうすれば時間が確保できるのか、まだまだ悪あがきを続けるつもりです。
「継続させる」コツは頻度の高さなのかも
もう一方の継続させるエネルギー。これはこれで、変化させるのと同じぐらいパワーが必要です。でも、この場合、継続の定義はいろいろなので、それを明確にすることが先かもしれません。毎日続けると決める、毎週続けると決める等は、わかりやすい継続ですが、頻度を決めなくても続けていける場合もありますよね。
ワタシの場合、たとえばこのブログは「毎週書く」と決めて、2010年から2年近く続いています。先々週も含めて年に数回はパスすることがありますが、限りなく「毎週」書き続けています。それ以前は「月に2−3回書く」と決めたのが2007年7月ですので、そこから数えると、5年続いていることになります。
毎日とか、毎週など、頻繁に行うルールの方が、長続きしやすいのですが、その場合も、「今回だけ」と思ってパスすると、そこから雪崩のように、継続性が崩れ、それっきりということも少なくありません。禁煙やダイエットと同じで、ちょっとしたお休みのつもりでも、そこから立て直すのには倍のエネルギーが必要だからです。
反対に、最初から間隔を長く取ると決めたり、好きな時にやればいいと思ったものは、最初から長続きがしません。やっぱり忘れてしまうのです。旅行に行ったときにスケッチするなど、趣味のものは別ですが。
継続するには、最初に「絶対やめない」と決めることも有効かもしれません。恋愛も結婚も、最初に絶対に別れないと決める。そうすると、覚悟します。会社経営も似たようなものですね。どんなにピンチでも、投げ出さないと覚悟する。やめる選択肢が最初からないのですから、継続するしかありません。だからグラスルーツは28年も続いたのかな。他のことにも、当てはまるような気がします。
変えていくための時間づくり。目下、これがワタシの課題です。
8月から新しい環境に身を置いたり、新たなチャレンジをしようとしているワタシの周りの皆さん。くじけそうになったら、飲みに行きましょう! ハッパ、かけますので(笑)
ただの備忘録〜『8』と『0』
「びぼうろく」と打ったら、なぜか「美貌録」と最初に出てきて、ちょっと悪い気がしなかった小野です。こんにちは。
なんだかありがたいことに、忙しいです。先週に続いて、今週もこのブログを書くのをさぼってしまおうかと思ったのですが、せめて「つぶやく」ぐらいしておこうかと思い、手短に書きますね。
一生、伸びたいと思っている人は、素敵だな、カッコいいな。。という話について。
先週お会いした取引先の社長の「好きな数字は『8』と『0』」だそうです。8は一般的に末広がりという意味があるので、そういうことかと思いきや、理由はまったく違っていました。『8』と『0』は閉じていて、終わりがない形だからなのだとか。それ以外の数字は、始まりがあって、終わりがあるのに、『8』と『0』だけは、始まりも終わりもない。自分は、一生成長していきたいので、そのイメージと一致するから好きなのだ。そんな話を聞いて、カッコいいと思いましたし、私もそうありたいなと思いました。
さて、今週もがんばっていきましょう!
いろいろな既成概念にとらわれず、素直な気持ちで物事を受け入れ、人の話を聞き、一日一日、あらゆることを吸収できるように。
忙しいからといって、傲慢な気持ちになりませんように。おまじない、おまじない。。。
ありがとう、多摩高!
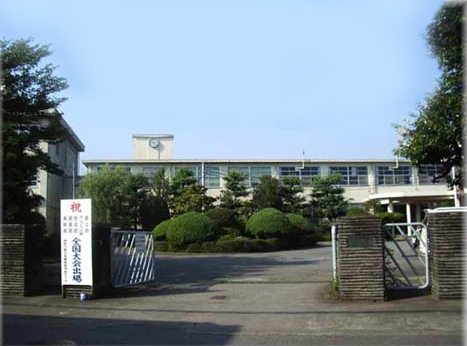
こんにちは。
昨日、ワタシが卒業した高校から、同窓会報が届きました。モノクロ16ページのその会報、普段はあまり読まないのですが、昨日は日曜日だったので、ふとパラパラとページをめくりました。その中に、今年の秋から校舎の立て替えが始まるとありました。3月に行われた同期会でも、その話は聞いていたので、それ自体は驚きませんでしたし、むしろ、この時代になっても、当時のまま2階建ての校舎が4棟並んで立っているということの方が、不思議なくらいです。
ワタシの母校は神奈川県立多摩高校。湘南高校などに比べると、全国的な知名度は低いものの、県内ではそれなりに知られた高校です(俳優の三上博史さんも卒業生です)。会報に寄せられている卒業生の寄稿を読みながら、なんだかふと、自分自身のアイデンティティを再確認させられました。
最近卒業した寄稿者も含め、みんなが口を揃えて「生徒の自主性を重んじる校風」について書いていたからです。実際のところ、まったくもってその通りで、進学校にありがちな緊張感は、良くも悪くもなく、お祭り好きな校風でした。体育祭や文化祭はもちろんのこと、合唱コンクールや大師競歩(川崎大師まで約20kmの道のりを多摩川沿いに歩くというイベント)など、伝統的なイベントが多く、それに熱中するあまりに現役での合格率が低いなどと揶揄されてもいました。中でも体育祭は、1年生から3年生までの全生徒が生まれた月によって、春組、夏組、秋組、冬組に分かれて戦い、各組ごとに巨大なマスコットを作ることで知られています。「お祭り好き」と書くと、軟派な高校のような誤解を与えるかもしれませんが、スポーツも盛んで、ワタシの期は、いろいろな部が県大会優勝をしていました。当時は、校訓に関心を払うことなどありませんでしたが、今、改めてホームページを見ると、次のように書かれています。
校訓
○質実剛健
集団の規則に従い、社会的な諸条件の中にあって、必要最小限度の質素な素材を持って、不撓不屈、勤勉力行、堅忍不抜、もって最大限の効果を挙げるようつねに努力する。
○自重自恃
生命の貴重なことを自覚して、自他を敬愛し、明朗闊達、礼儀を重んじ、自由と責任をわきまえ、自主独立の精神に徹し、つねに自らを恃みとできるように自己の昂揚に努める。
自主独立の精神。自由と責任。
無謀なくらい(笑)、随分高い理想だと思います。在学中には思いませんでしたけどね。それを、高校時代にカラダで味わえたことは、ワタシの財産になっています。
最近になって聞いたのですが、当時も、先生たちの間では意見が分かれていたのだとか。自由闊達路線か、現役合格者を増やす路線か。自主性を重んじる精神は、先生方の努力によっても、守られてきたのですね。そのために知名度競争では負けているのかもしれませんが、知名度以上の価値を生徒には与えてくれたような気がします。
ワタシよりずっと年下の卒業生が、行事や部活が自主的に行われていることについて、書いていました。このような運営は「先輩の仕事を見たり引き継ぎされたりしない限り、ほどんど不可能」であり、「『生徒主体』『自由』は先輩たちから受け継がれた伝統」であると。
さて、企業の社風や伝統も同じようなものかもしれません。
グラスルーツの社風や伝統は、ワタシと創業期を共にした多摩高の友人田中英理子によって、多摩高文化の影響を受けながら、グラスルーツにもたらされ、グラスルーツを支えてくれた先輩たちのエッセンスがミックスされ、今のような文化・社風になっているような気がしています。
会社の社風や伝統というものは、創業者が一人で作るものではなく、先輩たちが残していったものなのですね。企業では、「DNA」という言葉がよく使われますが、伝播の不思議、継承の不思議を改めて感じました。
ま、それはそれとして、ワタシを育ててくれた多摩高、ありがとう! 今年は忘れずに、同窓会費を払います!
『自分の小さな「箱」から脱出する方法』
 表題の本を、友人の経営者が知り合いの経営者から勧められたというので、ワタシも読んでみました。アマゾンでは、星が4つ半。全米でベストセラーになったと言われるのが本書『自分の小さな「箱」から脱出する方法』(著:アービンジャー・インスティチュート、刊:大和書房)です。
表題の本を、友人の経営者が知り合いの経営者から勧められたというので、ワタシも読んでみました。アマゾンでは、星が4つ半。全米でベストセラーになったと言われるのが本書『自分の小さな「箱」から脱出する方法』(著:アービンジャー・インスティチュート、刊:大和書房)です。
この本は、自分の中のウソに気づかず、自分を正当化し、相手を責める(あるいはその気持ちを抱く)ことによって、人間関係の何が損なわれてしまうのか、どんな悪循環に陥るのか、「自己欺瞞」という心理学的な事柄をわかりやすくストーリー仕立てで紹介していますが、家族関係などの例を挙げながらも、最終的には組織論として書かれており、経営者が着目する理由もそこにあるようです。
本書では、自己欺瞞という言葉を「箱」に入った心理状態という言葉に置き換えて説明しています。自己欺瞞に冒されている人ほど、自分に問題があることが見えなくなる、と。そして、その自己欺瞞は、自分が他人のためにすべきだと感じながらも、その行動を取らなかった時にしてしまいがちな、自分を正当化することから始まるとしています。自己正当化のために、相手を必要以上に非難し、やがてはその正当化された自己イメージを持ち歩くようになるのだとか。自分がこんな状況に陥っているのは、ダメな夫/妻、能力のない部下が悪いからであって、自分はこんなにやっている等々です。
ワタシは、どちらかといえば、常々プライドを持つことよりも素直であること、やましいことをせずフェアであること等を価値観の上の方に置いている人間なのですが、この本に書かれている通り、どんなに箱の外にいようとしている人間でも、箱の中に入ったり出たりするというのは本当のことだと思います。ワタシも例外ではありません。大筋では、自己欺瞞に陥らないようにとは思っていても、日常のこまごまとした生活の中には、自己欺瞞的なことが潜んでいます。
本当に優れたリーダーは箱の外に居続けようとする人である、本当に強い組織はみんなが箱の外に出ている状態にある、という著者の主張は、耳を傾けるに値すると思いました。ストーリーは、幹部候補としてザクラム社に入社したトムが、入社1カ月にして早くも「君には問題がある」と言われるところから始まり、経営者のバドによってコーチング的な手法でリーダーのあるべき姿を理解していく物語になっており、コーチングに興味のある人にもおすすめの1冊です。お時間があれば、読んでみてください。ではまた。



